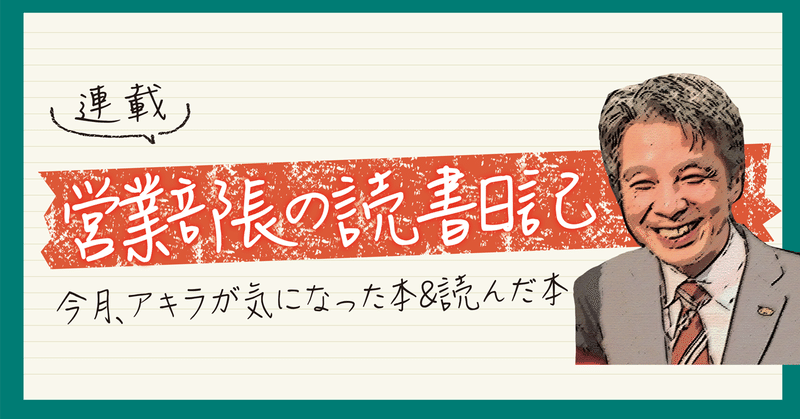
■読書日記〈第12回〉おろかな争いをしている余裕はない
春はさまざまな変化がありますね。私もご多分に漏れず、PHP研究所の京都本部から東京本部へと転勤しました。幸い仕事は変わらず、これからも読者や書店さんに本をお届けしてまいります。閉塞感の増す世の中で、弊社の書籍や雑誌が、みなさまのお役に立てれば幸いです。
《今月の購入リスト》
『ナターシャの踊り(上・下)』オーランドー・ファイジズ(白水社)
『生きることとしてのダイアローグ』桑野 隆(岩波書店)
※大垣書店烏丸三条店にて購入。昨年の刊行時から気になっていた高額本です。
『プリズン・ブック・クラブ~コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年』アン・ウォームズリー(紀伊國屋書店)
『現代思想入門』千葉雅也(講談社現代新書)
『女のいない男たち』村上春樹(文春文庫)
※紀伊國屋書店あらおシティモール店のグランドオープン時に購入
『終わりと始まり』ヴィスワヴァ・シンボルスカ(未知谷)
※丸善博多店のウクライナ事変関連コーナーにて購入
『人生の決算書』曽野綾子(文藝春秋)
※福岡金文堂本店にて曽野綾子さんの愛読者である店長のお勧めで購入
『戦争プロパガンダ10の法則』アンヌ・モレリ(草思社文庫)
※自宅近くの住吉書房保土ヶ谷店にて購入
■3月26日
『生きることとしてのダイアローグ』⇒人も世界も〈対話〉で発展する
『生きることとしてのダイアローグ』は、ロシア人思想家のミハイル・バフチンが唱えた「対話論」にフォーカスを当てた解説書です。バフチンは、ドストエフスキーの評論に「ポリフォニー」や「カーニバル」といった概念を持ち込んだ人物。じつは近年、教育や精神医療、ケア、介護、異文化交流など、さまざまな分野でバフチンの対話論が実践されているようです。どういうことでしょうか。
バフチンのいう<対話>とは、相手に呼びかけ、相手がそれに応答するような関係性一般を指します。たんに向かい合って話す、ということだけではないのです。生きていくにあたっての姿勢のようですね。
これは、自分が一個人としてあるのに先立って、個人と個人の相互関係があるという考え方です。生きるということは、対話を働きかけること、つまり相手に問いかけ、注目する、応答する、同意することになります。こうした対話に、人は生涯にわたり全身全霊をもって参画しているのです。
バフチンは本書で、対話の重要性を強調します。たとえば、次のような一文があります。
***
対話では、人間は外部に自分自身をあきらかにするだけでなく、あるがままの自分にはじめてなるのである―――くりかえすが、それは他者にたいしてだけでなく、自分自身にとってもである。(バフチン『ドストエフスキーの創作の問題』平凡社ライブラリー)
***
対話の欠けた社会でさまざまな問題が発生することは、誰しも納得できるでしょう。ところが、対話不足を不自由や不自然に感じないあり方こそ個人主義の弊害だ、と著者は控えめに主張します。私もまさにそのとおりだと思います。これについて、まず、バフチンはドストエフスキーの言葉をひき、資本主義は「出口なき孤独」という「幻想」をつくりあげたとしました。そして、この「幻想」、すなわち、人間はひとりで生きていける、あるいはひとりで生きていくしかないとの錯誤は、ドストエフスキーが生きた19世紀よりも、むしろ今日のほうがいっそう蔓延しているのではないかと問題を提起します。
では、対話の効用はどこにあるのでしょうか? バフチンは、自分自身を語る言葉を見つけられずにいる人、――あるいは葛藤しており、自分自身との対話という<内的対話>の悪循環のなかにいる人――に、他者がもうひとつの声を――助けの手を差し伸べるように――加えると説きます。じつにダイナミックなものです。その例として、ドストエフスキーの『白痴』より、他人から「あばずれ女」扱いされている女性ナスターシャ・フィリッポヴナに向けて、主人公のムィシュキン公爵が語りかける場面を挙げています。
***
「あなたも恥ずかしくないんですか! いったいあなたは、今ご自分が演じてみせていられるような、そんな人でしょうか? まさかそんなはずがあるでしょうか!」突然公爵が、しみじみと心から咎めるような口調で叫んだ。
ナスターシャ・フィリッポヴナははっと驚いてにやりと笑ったが、しかし何かその笑いの下に隠しているような様子で、いくぶん当惑気味にガヴリーラを振り向き、それから客間を出ていった。だがまだ玄関まで行きつかぬうちにふいに引き返すと、速足でニーナ夫人のもとへ歩み寄り、その手を取って自分の唇へと引き寄せたのである。
「私は本当にこんな女ではありません。あの人が言ったとおりです」彼女は口早に熱を込めてそうつぶやくと、突如見る見るうちに顔を真っ赤に染め、そのままくるりと振り向いてすたすたと出ていった。(望月哲男訳『白痴1』河出文庫)
***
バフチンのいう対話は、あくまでもダイナミックな弁証法的なものを指します。決して、お互いが言いたいことをぶつけ合うだけで、未来に対して何の発展性のないものではないのです。これを受けて私は、人を一方的に決めつけず、<対話>を通して話題を深め、拡大していく能動的な姿勢は重要だと思いました。バフチンは、対話の終焉は人類の滅亡にも等しい、とまで言い切っています。
こうした姿勢を踏まえ、著者は「みんなちがって、みんないい」「ナンバーワンでなくオンリーワン」という主張に疑問を投げかけます。集団主義からの脱却としてはいい考え方でしょうが、いまの私たちにとって消極的な相対主義こそ、独裁的な教条主義以上に恐ろしいものだということです。そして、人それぞれの事情や個性を認めたふり(実際は無関心)をする一方で、自分自身への介入をいっさい拒否する閉じられた姿勢は、決して個人一人ひとりの声が価値を持ち、独立して存在しているとは言えないとしました。
さらに、教育の場が、与えられた真理に代わる新たな真理を主体的・対話的に生み出せるような、伸びやかな場であることを願います。もっともです。
本書の最後には「補 沈黙」という章が設けられています。そこで著者は、評論家・若松英輔さんが環境学者・宇井純さんについて語る言葉を引用しています。
***
水俣病は、人から語ることを奪うことがある。身体機能として語ることができないということだけでなく、語ることができない苦しみと悲痛を強いる。そのことを深く認識することからはじめなくてはならない。語りえないものに遭遇し、語ることの意味が、消えそうになったところから語り出さなくてはならない。自分は語り得ないものに出会っている、という認識から出発しなくてはならない。
現代は、さまざまなところで意見が求められる時代です。人は、考える前に語ってしまう。宇井さんはそこに「否」を突きつけている。宇井さんは、沈黙のはたらきをよみがえらせようとしているのかもしれません。語られざる苦しみの声を沈黙のうちに聞き取ろうとすること、また、沈黙と向き合うことなく、意見を語り続けることで、人は過ちを繰り返す、と警鐘を鳴らすのです。(水俣フォーラム編『水俣へ 受け継いで語る』岩波書店)
***
ここで著者が言いたいことは、<対話>を問題にする以上、沈黙と向き合うべきだということです。私たちはつい目の前にいる人のことだけを考えて対話をしてしまいがちです。ですが、著者はどのような対話も、眼では見えず声も聞こえない「高次の超・受け手(神や絶対的真理、民衆、公平な人間的良心の裁きといった第三者)」を前提にしていると指摘し、私たちは目の前にいる話し相手がすべてを言い尽くしている訳でもなく、沈黙している第三者に訴えている部分にこそ核心があるかもしれないと言います。
そして、状況はどうでも、私たちとしては、さまざまな種類の沈黙(とりわけ強いられている沈黙)に耳を澄まし、応答できる心構えだけはつねに持っておきたいものだと説きます。厳しい要請だと思います。
■4月9日
『現代思想入門』⇒日本の「思想市場」に浅田彰以来の衝撃
次に、『現代思想入門』です。現在の新書ジャンルでは、ウクライナ紛争関連本や和田秀樹さんの高齢者の生き方本とともに、ベストセラー・ランキング上位に挙がっています。帯に書いてある「人生が変わる哲学」として、フランス現代思想(もはや古典?)のデリダ、ドゥルーズ、フーコーの思想を、平易な言葉で図式的に説いた、たいへんわかりやすい新書です。
著者の千葉雅也さんは、日々の生活や仕事につぶされない考え方を、現代思想からアクロバチックに取り出します。45歳の学者として円熟してきたからでしょうか。著者は、ポスト・モダンの構造主義は、二項対立から弁証法による止揚をめざさず、脱構築を希求します。あくまでも対立のグレーゾーンに留まる覚悟をするというのが、著者の説く現代における処世術の結論かもしれません。
本書が扱っている哲学の対象から、私は1983年に発刊された浅田彰『構造と力』(勁草書房)を思い出しました。こちらも日本の出版界に一世風靡の「思想市場」をつくり出した、15万部突破のベストセラーです。
この本も『現代思想入門』と同じく、当時、蓮實重彦さんしか紹介していなかったフランス現代思想を、「チャート式」という学習参考書のノリで紹介したものでした。私が大学生の頃に発刊され、バブルに向かう日本の消費社会を「差異化」という概念でタイムリーに後押ししたと言われます。
『構造と力』とその翌年に発刊された『逃走論』(ちくま文庫)は、著者の浅田彰さんが24歳のときの著述です。この2冊とも、80年代の「思想市場」にたいへん大きな影響を与えました。『構造と力』は、「差異化」というタームを一気に「生き方」のモードへ、いわば「処世術」へと変換します。そして、そこから「差異」の「過剰」を肯定しつつ、メディアの現在と戯れる『逃走論』へと一足跳びに飛躍したものでした。
その後の浅田彰さんや同時代に脚光を浴びた中沢新一、一世代上にあたる、蓮實重彦、柄谷行人といった1970年代の論客から連なる、20世紀末の日本「思想市場」論壇の系譜(福田和也、大塚英司、宮台真司、東浩紀)も、また時間を見つけて辿り直してみたいものです。そこから端折りますが、今の千葉雅也さん、齋藤幸平さん(『人新世の「資本論」』集英社新書、なんと45万部!)の活躍に続くものがあるのかないのか、もう少し考えてみる必要がありますね。
■4月16日
『コザック ハジ・ムラート』⇒紛争の歴史にピリオドを打て
トルストイ『コザック ハジ・ムラート』(中央公論新社)を読了。ウクライナ紛争が長引くなかで読むには、なかなかにしんどい読書でした。
19世紀のロシア文学を代表する文豪・トルストイは、ナイチンゲールの活躍で有名なクリミア戦争(1853年)に、志願兵として従軍していました。クリミア半島は、まさに160年後のロシアが併合し、いまも蹂躙し続けるウクライナの領土です。日本と違って、地政学的脅威にさらされ続けてきた中欧の歴史を思うと、ほんとうにつらいものがあります。
本書はトルストイが晩年、1900年ごろに執筆した小説です。ただし、話の舞台は、トルストイが20代後半に着想した青春小説『コザック』と同じ、1850年ごろのカフカーズ(英語読みでコーカサス)地方となります。主人公はハジ・ムラート(?―1852年)。1817年ごろから続くコーカサス戦争で、ロシア軍に抵抗する側に立った実在の英雄的人物です。
コーカサス戦争は、北カフカーズ地方を領有しようとするロシア帝国とそこに住むチェチェン人やタゲスタン人たちの間で起きた戦争です。軍事指導者としてロシア帝国と対峙していたハジ・ムラートは、内ゲバによりタゲスタン人の王を名乗ったシャミール(第三代イマーム)に暗殺されそうになります。そこで、ハジ・ムラートはロシア軍に帰順し、因縁のあるシャミールを打倒しようと図りますが、ロシア軍の協力を得られません。
結果、敵方に囚われた家族(妻や息子、母)のために、シャミールの奸計とわかっていながらアゼルバイジャンから逃亡しようとして、ロシア軍に無残に討たれる物語です。じつは、トルストイは彼のロシア軍への投降事件の場に居合わせていたといわれています。
本書に描かれたハジ・ムラートは、自分の幸福を信じてやまず、自分の成功を確信する子供らしい善良さを持つ戦士として、貴族的なロシア社会でも毅然とした存在感をしめします。そのハジ・ムラートの無残な最後は仲間とともにありました。ひげだるまの従僕ハネーフィ、銃火の下でも悠々と歌うクルバン、快活なハン・マゴーマ、チェチェン人ガムザーロと魅力的な仲間とともにロシア軍に立ち向かい、英雄そのままの最後を迎えます。
ハジ・ムラートの生首の描写が克明に記されますが、最後の一文が胸を打ちます。「頭の無数の傷にもかかわらず、紫色をおびた口辺のひだには、子供らしい善良な表情が浮かんでいた」。旧約聖書のような、叙述詩のような小説でした。
トルストイは随筆『人生論』で、「幸福とは、どのような形の愛を得られるか次第であり、われわれはほかの人びとと交流し、絆をつくることによってのみ自身の幸せを見つけることができる」と説きます。ハジ・ムラートが一人で死んだのではないというのが救いです。また、トルストイが文学作品として昇華したのも幸いでした。
コーカサス戦争により、カフカーズ地方はロシア帝国に併合されました。その後、チェチェン共和国として独立しようとする独立武装派とロシア連邦軍とのあいだで、チェチェン紛争が勃発します。1991年から始まった紛争は2009年に終決しましたが、実際は残党による「北コーカサスの乱」と呼ばれる戦争が2017年まで続いたそうです。歴史は繰り返しますが、ウクライナ紛争による人類の流血沙汰が、一日も早く終わることを心より祈ります(関係各国の思惑があるにせよ、19世紀と何ら状況は変わっていないように思えます)。
トルストイの生涯を辿るには、ロマン・ロランの『トルストイの生涯』(旺文社文庫)が参考になりました。大正期の白樺派に影響を与えた日本のトルストイ受容の歴史では嚆矢となるものです。著者のロマン・ロランは本作の翌年、ノーベル賞に輝く名作『ジャン・クリストフ』という小説を書き、評伝として無抵抗主義を貫いた『マハトマ・ガンジー』をトルストイの次に取り上げました。
さらに日本のトルストイ関連の評伝では、藤沼貴『トルストイの生涯』(第三文明選書16)が決定版だと思います。私は本書で、トルストイ晩年の謎だといわれる「家出と死」について、詳細に知ることができました。
なお、トルストイは、1910年10月28日の朝6時に発作的に家出をします。妹マリアの暮らすロシア正教の権威的でない民衆的な修道院に立ち寄ったあと、行先の定まらぬまま出発。同月31日の夕方に38.5度の発熱をして、列車での旅行途上のアスターポヴァ駅で途中下車しました。その後、寒さと疲れから肺炎を発症。駅長の宿舎で病床についたあと、11月7日の朝6時5分に逝去します。享年82歳。臨終の床の周囲には、旅の最初から付き添っていた主治医マコヴィツキーをはじめ、たくさんの人が居並んでいたといいます(駆けつけたソフィア夫人とは会っていなかったそうです)。
これは、はたして正宗白鳥がいう、「野垂れ死に」なのでしょうか(小林秀雄との有名な1936年「思想と実生活論争」があります。理想と現実の相克を問う論争)。藤沼版『トルストイの生涯』では、常軌を逸した、老齢のための錯乱状態・うつ状態だったともいわれますが、私にはトルストイは青春の地であるカフカーズ地方に向かうことで、人生幾度目かの再起を図ろうとしたのだと思いたいです。
■4月23日
『Wedge』5月号⇒「忍耐力」こそ、AIが不得手な人間の能力
仕事のため東京と京都を行ったり来たりしています。新幹線の車中、『Wedge』5月号の論考でメディア論の佐藤卓己さん(京都大学教授)の「真実分からぬ報道のジレンマ“あいまいさ”に耐える力を」を読みました。
少しだけ引用します。
***
いま誰もが納得できる形でウクライナ戦争の真実の姿を示すことは、政治家にもジャーナリストにもできない。おそらく後世の歴史家の仕事となる。明快な真実を早急に追い求めれば巷(ちまた)に溢れる陰謀論の罠にはまることになりかねない。戦争宣伝と表裏一体の戦争報道において、証言や映像の真贋を判断することは容易なことではない。つまるところ、情報構築モデルのメディアリテラシーとは「あいまい情報」をすぐに理解しようとする誘惑に耐える力である。この耐える力こそ、真偽を見分けることがほとんど不可能な「あいまい情報」への正しい向き合い方を可能にする。
***
この耐える力こそ、白/黒を瞬時に識別するAIが不得意とする人間の能力であり、ネガティブ・リテラシー(消極的読解力)と呼ぶべきだと、著者は主張します本連載の第1回で採り上げたネガティブ・ケイパビリティと同様の発想法です。つまり、何事においても「あいまいさ」に耐える力を持つべきだとのことです。
まず敵味方を識別して安心することを求めるのは止めましょう、というのはわかりました。冷静にひと息つこう。OKです。では、しばらく(いつまで?)耐えてからは、どうしたらいいのでしょうか。そこからが主体的な各自の言動が問われる問題ですね。日本中のメディアが騒ぐコロナ禍についてもそうだと思われます。
4月発売の5月号で、弊社の月刊誌『PHP』は記念すべき創刊75周年を迎えました。本誌3月号裏表紙記載の「風景」という文章を、私はロシア語に翻訳して、かの国の大統領プーチンに読ませてやりたいものだと、つい思ってしまいました。最後の部分だけ引用します。
***
世界の大国の指導者が同じ宇宙船のクルーとなって、宇宙から国境のない地球を眺めたらどんなに痛快だろう。「これ以上の風景は、ほかにはない。おろかな争いをしている余裕はない」と思うに違いないのだ。
***
かつて本誌の裏表紙の文章は、弊社の『道をひらく』としてまとめられました。その後、創刊75周年となる今に至るまで連綿と継続しています。書店店頭で、ぜひお手に取って表紙 の特集タイトル、装画だけでなく裏返してご覧になってみてください。これもまた、思わぬ新たな邂逅となるに違いありません。最新刊の6月号は、5月10日発売です。

