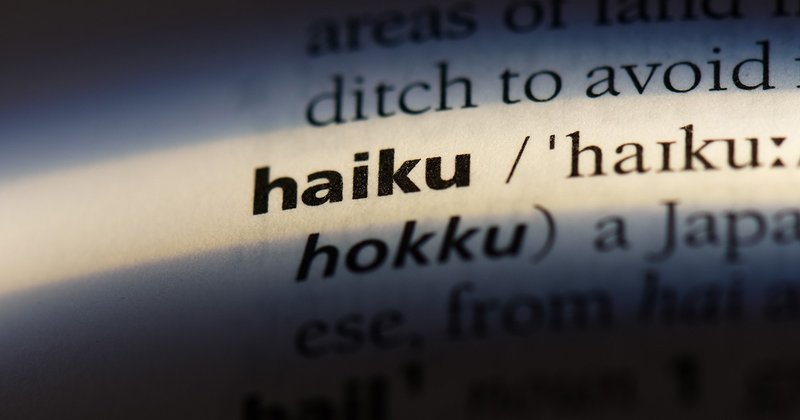
歌人・紀貫之と近代俳句論
執筆:ラボラトリオ研究員 七沢 嶺
貫之は下手な歌よみにて、古今集はくだらぬ集に之有り候。
正岡子規著「再び歌よみに与ふる書」より
正岡子規は俳句の生みの親といって過言ではない。俳句のみならず、歌人としての実績もある。歌壇における、氏の発する言葉の影響力は極めて大きい。私も、俳句を学習し始めた頃は、鵜呑みにし、紀貫之に対し「誤解」を抱いてしまった。しかし、それは子規が詭弁を弄しているのではなく、真の俳句論を打ち立てるための言葉なのであった。
現代、幾らか改善されたかもしれないが、両者の「誤解」は依然として流布しており、少しでも真実に近づきたいと考えている。
国文学者である目崎徳衛氏の著書「人物叢書・紀貫之」をもとに、正岡子規の俳論とあわせて私なりの考察を述べたいと思う。平安時代の歌に対する考え方と近代俳句の考え方を比較し、読者の皆様が何らかの洞察を得ることにつながれば幸いである。また、俳句と短歌を同列に考察することは必ずしも真実へ導くとは限らない点と、初学者である私の考え等に笑うべき蒙失があることはお詫び申し上げたい。
まず、正岡子規の主張する俳句の考え方において最も重要な点は、客観写生であると私は考えている。客観写生とは風景の一瞬間を切り取り、むやみに装飾を加えずに、表現することである。
鶏頭の十四五本もありぬべし 子規
氏の有名な一句である。鶏頭(ケイトウ:花の一種類)が十四、五本程度あるだろうか、と述べただけである。句会で発表した際は、低評価であったそうだ。後世に再評価された句である。良さがわからない方も多くいると思うが、何ら技巧的で装飾された様子がないことはわかっていただけるだろうか。
甘草の芽のとびとびのひとならび 高野素十
大榾をかへせば裏は一面火 同
参考に客観写生を最も実践した俳人、高野素十(子規、虚子系列の門人)の句も引用する。
どの句も、みな淡白であり、侘び寂びをおし出すこともない。そのことが、かえって季語の情趣を響かせているのではないだろうか。俳句とは、季語という言葉の力を最大限に引き出すことであると私は考えている。例えとして不適切かもしれないが、料理の世界における和食の技術に近い。無駄なものを削ぎ落としていく考え方は和食の基本である。素材(つまり俳句では季語)の味を最大限に引き出すことが肝要である。
ただし、客観写生とは以上のように一面的な単純なことではなく、専門的にはより複雑な考え方であるため、それは応用としてまたの機会に述べたいと思う。次に、子規の最も有名な短歌を一首引用する。
くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる 子規
こちらは、俳句ではなく、短歌であるが、客観写生に忠実に詠まれていることがわかるだろう。
一方、平安時代の紀貫之の歌はどうであろうか。
朱雀院女郎花合にて
小倉山峯たちならし鳴く鹿の経にけん秋を知る人ぞなき 紀貫之
句の頭を一文字ずつみていくと、「をみなへし」である。歌合わせの場が、朱雀院女郎花(をみなへし)花合であるから、その五文字を短歌に織り込んだのである。
宇多院物名合にて
むねのひを緒しも貫かねば乱れ落つる涙の珠にかつぞ消ちぬる 同
初句と二句目に「子(ね)の日を惜しむ」という長い題が詠み込まれている。極めて高度な技である。
霞たちこの芽もはるの雪ふれば花なき里も花ぞ散りける
「古今和歌集」紀貫之
二句目の「はる」が「春」「張る」の両方の意味で詠まれている。季節の春のみならず、木の芽が張るとしているのである。大意は、霞が立ち込め、木の芽も張り、春の雪が降るので、花のない里でも花は散るのであった、というところであろう。
いずれの歌も、技巧的・機智的である。それは、必ずしも、紀貫之自らが望む結果ではなかったが、時代的な制約もあり、そのような歌風になったと考えられる。その時代の要請に応えることのできる才能を有していたからこそであり、紀貫之の歌人としての能力の高さは驚くべきものがある。
歌というものは「古今集」序で貫之がいっているように「人の心を種として」これを言葉に真直に表現すべきもので、純粋に内的な衝動を作因としなければならない。ところが、当時の実状としては、「代々の御門、春の花の朝、秋の月の夜ごとに、侍ふ人々を召して、事につけつゝ歌を奉らしめ給」うたり、また殿上人たちが「酒たうべけるに召して」歌を作らせたりするような外的動機によって歌を作る場合がむしろ多かった。それは歌が隠遁の孤独なすさびから宮廷の表面へ進出したことによる避けがたい代償であった。そうした場合業平的なひたむきな抒情はどうにもふさわしくないので、歌人より身分は高いが本質的には文雅を解せぬ俗人である「殿上のおのこたち」の低俗な鑑賞力に無理なく受け入れられるためには、なるべく表面的な技巧を凝らした、つまり読者に一読ポンと膝を叩かせるような機智的傾向がお誂え向きなわけであった。
(目崎徳衛著「人物叢書・紀貫之」より引用)
以上のように、正岡子規らの提唱した客観写生と、平安時代に求められていた歌風は大きく異なる。私の主張は、どちらが良い悪いということではなく、紀貫之と正岡子規に対する誤解を少しでも解きたいという一点である。
私にとって、先人は皆、慕ふべき師である。師の主張の一切を肯定し、日本文化のために最大限活用していきたい思いである。われわれの生きる令和という時代の要請を見極め、真の文学のあり方を探求していく決意である。
・・・・・・・・・・
【七沢 嶺 プロフィール】
祖父が脚本を手掛けていた甲府放送児童劇団にて、兄・畑野慶とともに小学二年からの六年間、週末は演劇に親しむ。
地元山梨の工学部を卒業後、農業、重機操縦者、運転手、看護師、調理師、技術者と様々な仕事を経験する。
現在、neten株式会社の技術屋事務として業務を行う傍ら文学の道を志す。専攻は短詩型文学(俳句・短歌)。
この記事は素晴らしい!面白い!と感じましたら、サポートをいただけますと幸いです。いただいたサポートはParoleの活動費に充てさせていただきます。
