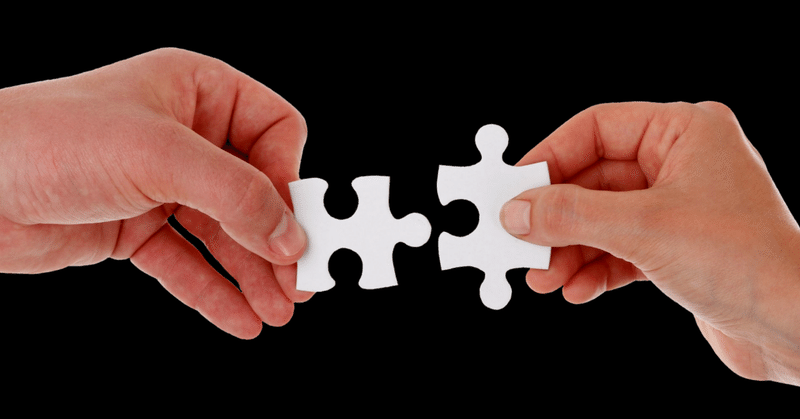
言葉の二面性、文学と政治
執筆:ラボラトリオ研究員 七沢 嶺
“文化が去勢されることにより、将来、民族の精神、倫理面での能力がどれほど深刻に失われることになるか。
現在の権力の利益のために、民族の精神の未来を犠牲にした人々の歴史的な罪は、その分、重いものとなる。”
(公開書簡『グスターフ・フサーク大統領への手紙』ヴァーツラフ・ハヴェル)
戯曲家でありチェコスロバキア(当時)大統領であったヴァーツラフ・ハヴェル氏の言葉である。
1989年、チェコスロバキアの首都プラハではビロード革命と呼ばれる体制転換が起こった。ソ連のペレストロイカ政策の波を受け、非共産党政権が発足し、社会主義体制が終わりを告げた瞬間であった。この時、ヴァーツラフ・ハヴェルという戯曲家が大統領に選出された。
私は政治や経済の専門家ではないため、共産主義、資本主義のどちらが正しいかに対する明確な解を得ることはできない。そして、文学・芸術といった文化についても同様である。
もし文化に社会的制限があり、海外とも鎖国状態であった場合は、一体どのような文化になるだろうか。しかし、ハヴェル氏を引用して論じるということは、その主張は、反社会主義体制派であり、文化は一切の制限を受けないことを賛成する立場にあることと同義であろう。
予め申し上げると、私はどちらにも偏らない中道をいく立場である。ただし、ソ連のペレストロイカに始まり、プラハの春、ビロード革命の一連の流れを学習する限り、「その時代」においては、ハヴェル氏の立場が正しいのではないかと思うのである。それは、全体主義の力により、人の純粋な意志が阻害され、文学・芸術が著しく貶められたという歴史的事実があったからである。
この全体主義という言葉は深く考察すべきであり、ドイツやイタリアにおけるファシズム体制つまり古典的全体主義とは異なることには留意する必要がある。その全体主義の力は、知らぬ間に人々の「拠り所」になってしまうのである。
“人間という存在の奥深くまで介入してくる。形而上的、実存的な確実性が危機に瀕している時代にあって寄る辺なさや疎外を感じ、世界の意味が喪失されている時代にあって、このイデオロギーは、人々に催眠をかけるような特殊な魅力を必然的にもっている。”
(『力なき者たちの力』ヴァーツラフ・ハヴェル著、阿部賢一訳)
われわれの住む日本はどうだろうか。
例えば、「社会の目」という目に見えない力がある。自己の意志ではないが、皆がおこなっているから私も同様にしたほうが良いはずだ、と盲目的に行動することはないだろうか。また、出る杭は打たれるため、目立った行動は取らないほうが良いと考えたことはないだろうか。
チェコスロバキアの場合は、計画経済により特に深刻であり、皆と異なることを行うと仕事さえ失う可能性があったのである。今の「幸福」を維持するためには、自己の純粋な意志を偽らなければならなかったのである。
政治は時に人の心を操作するために、言葉を巧みに利用することがある。その言葉は、社会に浸透し、いつの間にか人の奥深くまで介入し、盲目にしてしまう恐れがある。
その果てには、自己の偽りが「異常」ではなく「普通」になってしまう恐ろしさがある。つまり、反旗を翻す意志すらも生まれないのである。
“あらゆるものの初めに言葉があります。それは奇蹟で、われわれが人間であるのはそのおかげです。しかしそれは、同時に、わな、試練、まやかし、そして試金石でもあります。”
(『言葉についての言葉』ヴァーツラフ・ハヴェル著、飯島周訳)
ハヴェル氏がいうように、言葉はヒトを人たらしめる力を有している一方で、使い方によっては、人を真実から遠ざけるまやかしにもなってしまうのである。ラボラトリオ代表・七沢賢治氏の講話における、「生かす言葉もあれば、殺す言葉もある」と述べたことを思い出す。
表現の自由がおよそ保証されている昨今、文学や芸術、政治のあり方を再度問われていると感じる。われわれの使う言葉は文化をつくり、国をつくる。政治の真贋を見極め、真の言葉をつかうことが、この国の明るい未来をつくるもとになるのではないだろうか。
・・・・・・・・・・
【七沢 嶺 プロフィール】
祖父が脚本を手掛けていた甲府放送児童劇団にて、兄・畑野慶とともに小学二年からの六年間、週末は演劇に親しむ。
地元山梨の工学部を卒業後、農業、重機操縦者、運転手、看護師、調理師、技術者と様々な仕事を経験する。
現在、neten株式会社の技術屋事務として業務を行う傍ら文学の道を志す。専攻は短詩型文学(俳句・短歌)。
この記事は素晴らしい!面白い!と感じましたら、サポートをいただけますと幸いです。いただいたサポートはParoleの活動費に充てさせていただきます。
