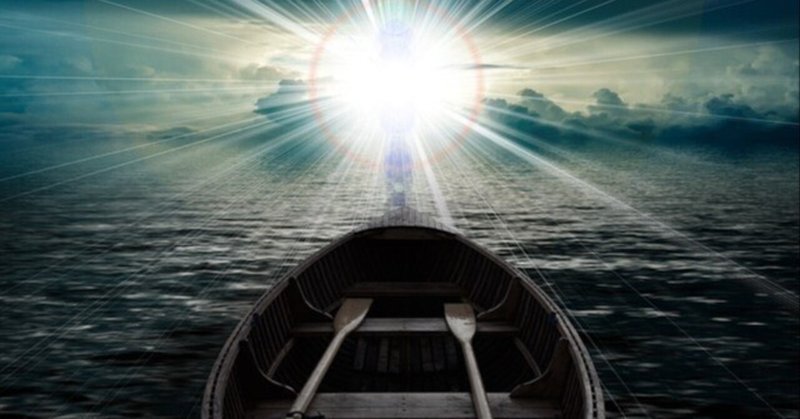
抑えがたい信仰の心とスロー思考
人は本質的に「他人に言われたことを信じやすい」傾向があり、これには進化論的背景がある、ということが分かってきました。
数百万年に及ぶ狩猟と採集の時代を経た人類は、その過程でその時代での生活に適した認知機能や性質を遺伝情報として保持するようになりました。
この時代人類は血縁関係に基づく、数十人程度、多くても150人くらいまでの集団で、移動しながら生活していたらしい。
太古の昔に養われた信仰心
厳しい自然環境と慢性的な食糧難の中でこの集団は、性別・能力別に役割分担をし協力関係を築き、助け合いながら暮らしていたようです。
この社会では、知識の共有が重要視されました。
繁殖期の動物は危険だとか、この一帯はオオカミの生息地であるとか、この川には近づかない方が良いとか、もちろん口にしてはいけない植物の情報なども含まれていたでしょう。
中には「この森に入ると森の神の祟りに合う」などの迷信じみた教えもありました。
でもそれは、例えばその森がとなりの部族の領地であり、無用な争いを避けるために「神の祟り」を持ち出して恐怖心をあおり、仲間を近づけさせないようにするための、部族に伝わる知恵だったりします。
要は、集団を成り立たせ安全を確保するための「使える知識」であれば、前提の部分はどうでも良い。
集団がチームワークを発揮するには、知識の共有が第一で、耳にした知識をそのまま信じ行動する方が生存に有利に作用したのでした。
このようにして人類は、他者の言うこと、決まり事を信じやすい傾向、「信奉欲求」を遺伝により身につけてきた。
現代生活に必要な科学リテラシーとの齟齬
自然や環境について情報の少ない(そして体系だった学問も存在しない)太古の昔はそれでもよかったのでしょうが、現代は逆に情報化社会。
耳にする情報が過大になり処理しきれなくなった今、逆にその情報の「前提条件」について思いを馳せる必要が出て来ています。
これは、長い狩猟と採集の時代で培われた信奉欲求を持つ人類にとっては中々のストレス。
しかし情報化社会などと言われる時代は、どう長く見積もっても高々数十年。
数千年前の昔でも、文明が築かれた社会であれば太古の昔に比べ接する情報量は増えたと言えるかもしれません。
それでも生物進化という観点からすると、時間が全然足りません。
数千年~一万年という時間スケールでは、遺伝子は書き換わらない。
現代人でも信奉欲求は厳然として存在するのです。
信奉欲求がより強い人の中で、特に自尊心が低くて落ち込みやすく、不安な心が強い人(一般的にはうつ傾向にある人)が超常現象を信じる傾向にあるということが、研究で明らかになっています。
有効な「スロー思考」を導く五回の「なぜ」
ある情報が得られたとして、ではその前提条件をいかに洗い出すのか?
その方法の一つとして、デザインマネージメント会社アイデオの共同経営者トム・ケリーは、「ヴジャデの目で見ることが重要」と言います。
「ヴジャデ」とは?
「デジャヴ」はご存じですね?
初めてきた場所なのに、なぜか既視感があり、場合によっては懐かしかったりもするあの感覚。
ヴジャデはその逆。
何かを観察するとき、何かの情報を得た時、たとえそれがかつて見聞きし当たり前だと思える内容だとしても、あたかも初心者あるいは部外者であるかのように接する、ということ。
そういう目で見ると、「なぜ」という素朴な疑問がわいてきます。
寝る前に歯を磨く習慣。
幼いころ親に言われ、盲目的に長年従っていたルール。
これを改めて、耳新しく受け取ってみる。
すると、「なぜ寝る前に歯を磨かねばならないのか?」という疑問がわいてきませんか?
日本最大の車メーカー・トヨタの生産方式に「5回のなぜ」というのがあります。
問題に対し1回でなく5回「なぜ」と問いかけ、根拠なく前提としていた知識に捉われない、事の本質を見定める手法です。
例えば「なぜこの商品は売れなくなったのか」という問いに対し「顧客が商品を理解していないから」と。
1回の「なぜ」だとここで終わるから、「ではより理解してもらうために広告をもっと打とう」といった結論になるかも知れません。
それでも良いかもしれなのだけど、あえて更に4回、「なぜ」と問い続けてみましょう。
「なぜ顧客の理解が進まないのか?」⇒「商品に触れる機会が少ないから」
「なぜ商品に触れる機会が少ないのか?」⇒「手軽に手に取れる場がないから」
「なぜ手軽に手に取れる場がないのか?」⇒「流通経路が百貨店中心だから」
「なぜ百貨店中心の流通なのか?」⇒「今使っている卸業者が百貨店に強い業者だから」
(「デザイン思考でゼロから1をつくり出す」中野明、Gakken(2020)より)
こう考えると、「では卸業者を改めて選定しよう」となります。
このように5回繰り返してみると、当初思いもよらなかった問題の核心に迫ることがあります。
情報があふれる現代、複数回の「なぜ」で核心に迫り、見えない「前提条件」を洗い出してみると、目からうろこの新たな方策にたどり着けるかもしれません。
○Kindle本
「再会 -最新物理学説で読み解く『あの世』の科学」
○身近な科学ネタを優しく紐解く‥
ネコ動画ほど癒されずEテレほど勉強にもならない「お茶菓子動画」
見えない世界を科学する「見えない世界の科学研究会」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
