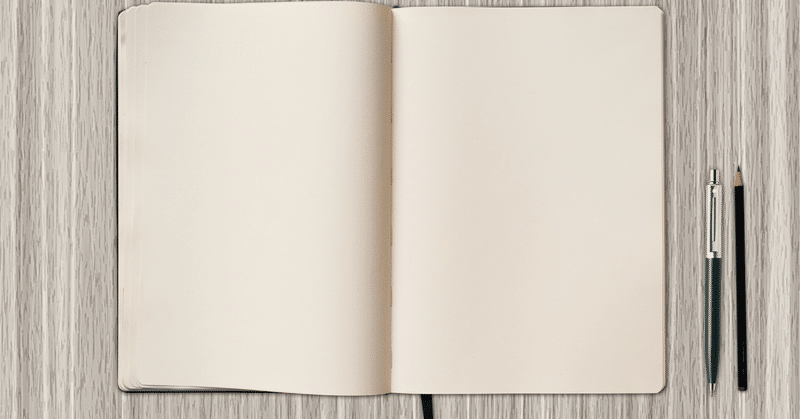
長い文章を書くのが苦手な人へ
文章を効率的かつ確実に書き上げる方法
読了時間:約11分(約5,500字)
書きたいことがあるはずなのに、まとめられない!
短文投稿サービスを飛び出して、自分の趣味や推しについて長文でガッツリと語りたい・・・と思ったのもつかの間、いざ書こうとすると全然書けない。書きたいことは山ほどあるはずなのに。これほどもどかしいことはないだろう。
あるいは一向に着地点が見えずダラダラと書き続けてしまうというパターンもある。せっかく想いを詰め込んだのに、文章が読みにくいせいで誰も読んでくれない。これもまた、もどかしい限りである。
この記事では「書きたいことはあるが、まとめられない人」「書くのに時間がかかる人」「読みやすい文章を書きたい人」などを対象として、文章を効率的かつ確実に書き上げる方法を示したい。発表資料やレポート、小論文試験対策にも使えるかもしれない。
逆に対象としないのは「面白い文章を書きたい人」「小説を書きたい人」などである。読みやすい文章は読みやすい・読まれやすいだけであって、面白いかどうかは別の問題である。ただし読まれてこそ初めて面白さが伝わるのだ、とは言えるだろう。
お察しの通り、この記事はいわゆる「文章の書き方」を扱うものなので「この記事自体は読みやすいのか?」という大問題がある。実はこの記事自体があとで紹介する手順で作成されているので、もし読みにくいと感じたら退出してもらっても構わない。ただしその手順はごく一般的なものである。
なぜ書き上げられないのか
ハッキリ言えば「飽きちゃうから」である。長い文章を書くのが苦手なあなたは、本文を何度も書き直していて一向に完成させられずにいる。自分でも何を言いたいのかわからなくなり、次第に文章の説得力も失われてきた。ダラダラと関係ないことも書いてしまったが、もったいないので残しておき、余計に収拾がつかなくなっていく。
それでも書き続けている限りいつかは完成するはずだが、どれだけ忍耐力があったとしてもそんなことを続けていれば飽きて当然である。実のところ、あなたはただ方法が間違っていただけなのだが、具体的にはどこが間違いだったのだろう?
いきなり本文を書き始めないで
文章を書き上げられない人の最初の失敗は「いきなり本文を書き始めること」である。それがなぜいけないのか分からないという人にこそ、この記事を最後まで読んでほしい。
140字のつぶやきであればその方法でも書き上げられるだろうが、もっと長い文章を書こうとする場合は難しい。家を建てるとき設計図が必要なのと同じで、ある程度まとまった文章を書くときは構成から考える必要がある。構成という言葉がピンと来なければ、目次を先に作ると考えてもらってもいい。構成は文章の設計図なので、本文を書き始めた後はいじらないというのがポイントである。
構成から考えるメリットのひとつは、書き直しのロスが圧倒的に少ないことだ。文章の流れが固まるまでは本文を書き始めないので、文脈を整理したいときは見出しを並べ替えるだけで済む。またどこにも置くところが無い話題はあらかじめ「よけておく」ことが出来るので、書いたあとでボツにするような事態も未然に防げる。
このように文章の流れが分かりやすくなると、読者にとっても読みやすい文章になっていく。書きやすい文章は読みやすい文章でもあるのだ。
・・・とはいえ、実際にやったことがない人にはピンと来ないだろうから、あとで例を示しながら具体的な手順を説明するつもりである。
読みやすいとはどういうことか
「タイトルと見出しだけ見れば大体わかる文章」なんてものがあるとすれば、それこそが読みやすい文章だろう。適当に流し読みしていても意味が分かるのだから、まさに読みやすい。読者が助かるような工夫を凝らせば凝らすほど、その文章は読みやすくなっていく。
読みやすさとは読者に対する思いやりである。読者は作者の考えを分かりたいと思って読んでいるのだから「結論と根拠が明示されている」というのも読みやすさの条件になる。また「読む前から大体どんな内容か想像がつく」ことも読者にとってはありがたい、というのは知っての通りだ。
逆に「よく分からないまま最後まで読んだが結局期待した内容ではなかった」というのが読者にとっては最も腹立たしいことだから、それを避けるために冒頭で概要を簡潔に伝えて退出してもらうというのもある意味で思いやりだと言える。そしてもちろん概要が期待通りだった人には安心して続きを読んでもらうことができる。
手順1:テーマを決める
ここまでの議論をもとに、実際に文章を構成から組み立てる手順を考える。くどいようだが、面白い文章にするためではなく「確実に書き上げる」ための、いわば書きやすい手順である。書きやすい手順で組み立てれば、読みやすさは後からついてくる。ちなみにこの記事自体がその手順に従って書かれていることはすでに明かした通りだ。
何はともあれテーマを決めなくてはならない。この記事のテーマは冒頭で述べた通り「文章を効率的かつ確実に書き上げる方法」だが、いきなりそんなふうに具体的に決められないというなら、まずは「文章の書き方」程度にざっくりと話題を決めるだけでもいい。そこからより具体的な話題を列挙し、階層を分けて整理する。
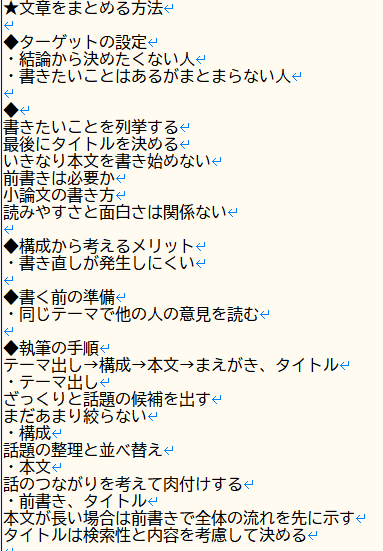
関連する話題をいくつも思いつくような話題は自分にとって関心の高い話題だから、つまりは書きやすい話題だと言える。
先ほど、読みやすい文章の条件のひとつとして「結論が明示されていること」を挙げた。テーマに対する答えが結論となるので、テーマは問いかけの形をしていることが望ましい。つまり「文章について」ではまずいことが分かるだろう。「文章の書き方(=文章はどう書くか?)」ならまだマシだが、範囲が広すぎていかにも答えにくそうだ。
結局のところ、ある程度せまい範囲の問いかけがテーマとして適していることになる。話題を限定することで書くべきことがはっきりするし、文章に独自性も生まれる。
余談:実際に小論文の試験などで「○○について、あなたの意見を述べなさい」という類の出題はよくあるが、そういうときはまず自分で話題を限定してから書き始めたほうが書きやすい。
手順2:構成を考える
テーマが決まったら、次の手順は構成である。先ほど書き出した話題の階層図を、文脈を意識して並べ替えよう。この記事の実際の下書きを例として示す。階層図と言うと大げさに聞こえるが、要はただ思いついた話題を整理して並べた文書に過ぎない。

このときどこにも置くところがない話題は脇によけておく。「消す」のではなく「よけておく」理由は、あとで構成を見直した結果「やっぱり使える」ことになったり、そうでなくても別の記事で使える可能性もあるからだ。
本文を書き始めてしまったあとでこのような構成の変更をしようとすると、とんでもない手間がかかる。しかし本文を書く前であれば大した負担にならない。これまで構成を考えずに書いてきた人がこの方法を経験したら、二度と本文をいきなり書こうとはしないだろう。
手順3:本文を書く
構成が出来たらようやく本文を書き始めるが、実のところ、この時点で執筆の終盤に入っていると言っても過言ではない。あとは点と点をつなぐように書くだけの仕上げ作業である。
タイトルとまえがきは本文が出来てから決める。タイトルはテーマそのものでも構わないが、想定する読者や検索性も考慮して決めるのが望ましい。まえがきは無くてもいいが、先述した読者への思いやりの一環として、文章全体の流れを先んじて示すために書いてもいい。
余談:動画の場合、前置きを省略して即座に本題に入るほうが好まれる印象がある。文章のまえがきも丁寧に書けば書くほどいいというわけではなさそうだが、いずれにせよ読者にとっての快適さを考えるのが大事だろう。
これで完成、というのが理想的だが、実際には本文を書いたあとで加筆修正することも多い。構成を変えるのではなく補強するために、説明不足な部分を加筆したり冗長な部分をカットする。本筋に関係ないことはそもそも書かないか、書くとしてもそれが余談であることを明示する。
このように。
さらに書きやすくする方法
構成から考えることで、文章は自然と書きやすくなる。なぜなら明確にすべき論理の流れは本文を書く前からすでに出来あがっているのだから。しかしそれでも書けないという場合は、構成を考え始めるよりも前の段階で、まず他人の意見を参照するのが有効である。
具体的には、「○○について」レベルのテーマまで定めたあたりで、そのテーマに関する他人の意見を読むのだ。noteで検索してもいいし、動画サイトやSNSなどでもいい。必ず誰かが何らかのことを語っているだろう。
他人の意見を読むことのメリットは大きく二つある。第一のメリットは、事実の確認である。つまり自分の勘違いや見落としに気づけるということだ。実際には記事を公開した後で気づいたり指摘されたりすることもあるのだが、事前に確認するに越したことはない。
二つ目のメリットは、テーマの発見である。あなたにとっては当たり前のことでも、他人にとってはそうではないということはよくある。つまりそれはあなたが他人に向けて説明する価値のある知識だということだ。
ちなみに他人の意見を読むときは、その意見があなたの意見と一致している必要は全くない。むしろ反対のことを言われているほうが、それに対するあなたの意見を述べる価値が出てくるというものだし、結局これもテーマの発見につながる。
長い文章は読みにくいか
テーマが見つからない人とは逆に、書くことがありすぎる人もいるだろう。構成から考えて書くことによって長い文章も効率的に書き上げられるようになる。すると今度は、文章が長すぎて読みにくくならないかと心配されるかもしれない。
その答えは基本的にはノーだと考える。文章が長くても構成さえしっかりしていれば読みやすさは保てるし、逆に文章が短くても構成が悪ければ読みにくくなる。文章の長さと読みやすさは直接的には関係ない。
長くて読みにくい文章が世の中に多く見えるのは、文章の長さが悪いのではなく、構成が悪いのである。一般に文章が長いほど構成をまとめるのは難しくなるので、結果的に長くて読みにくい文章が多いというだけだろう。
話題が整理されていて見出しも分かりやすいものが付いていれば、読者は興味のある部分だけ読むことができるので、文章の長さは問題にならない。作者の立場から言えば自分が書いたものは全部読んでほしいに決まっているが、読みやすい文章を目指すなら、読者の「読み飛ばす自由」にも寛容であるべきだろう。
文章の長さが問題となるのは話題が整理されていないときである。読者はどこが興味のある部分か分からないので、全部読み通すしかなくなってしまう。そしてそのとき文章が長いことに気づいた読者は読むのをやめるだろう。つまり読者にやさしくない=読みにくい、ということになる。
扱う話題の数が多くなると、しっかり構成から組み立てていても、その構成自体が長くなってくるので、まとめるのは難しくなる。そのせいであなた自身が飽きてしまっては本末転倒だし、出来るだけ話題を絞り込む努力はすべきである。読者は読み飛ばせばいいが、作者は「書き飛ばす」わけにはいかないので。
しかし、そこに並んでいる話題がすべて必要なものであり、簡潔にまとめる努力を尽くしてなお、省略できないとあなた自身が判断していて、書き上げる自信もあるのだとすれば、遠慮なく書くべきだ。むしろ変に遠慮して必要な情報を省略してしまうと、かえって読みにくい文章になりかねない。
あなたの文章に興味を持った人にしてみれば、文章が長いことはむしろ歓迎できる。そもそも動画サイト全盛の現代でテキストを読みに来る人というのは長文を読むことにある程度耐性があるので、内容を削ろうとするより充実させる努力をしたほうが有意義だ。
「文章力」は必要か
ありがたいことに何人かの方から過去の記事が読みやすかったとのお声を頂いていたので、いずれこのような記事を書いてみようという構想は以前からあった。
構成から考える書き方というのは、私が発明したものでも何でもなく、一般的に知られているものである。英語でパラグラフ・ライティングなどと呼ばれたりもする。知っていれば誰でも真似できる「型」のようなものだが、これに従ったからと言って文章の個性が減るものでもない。
心配な人のための補足:その型はあくまで「書き方」を教えるものであって「何を書くか」はあなた次第だからである。同じお弁当箱に入れた料理は全部同じ味になるか?という話。
書きたい思いはあるのに「文章力がない」ことを理由に書かずにいる人も多そうだと感じている。ここまで述べてきた通り、実際には「書き方を知らない」だけだと思っている。近年では動画配信が一般化してきたとはいえ、まだまだインターネットは文字の世界であり、文章での表現が苦手なために発信の機会を失っている人も多いのではないか。
同じ文字数を書くのでも、短文を100回書くのと長文を1回書くのとでは全く異なる。言葉を多く知っていることや人の心をつかむ言い回しが出来ることは短文向きの能力である。それに対し、長文を書くために必要なのは全体を見る視野の広さであり、これは短文だけをいくら書いていても決して身につかない。
美しい文章表現をするには神秘的な才能も要求されるのかもしれないが、「読みやすさ」を求めるだけなら、それは習得可能な技術に過ぎないだろう。しかし気づいていない人が多そうでもある。(終)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
