
◆読書日記.《ハワード・フィリップス・ラヴクラフト『ラヴクラフト全集2』》
※本稿は某SNSに2020年12月9日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
ハワード・フィリップス・ラヴクラフト『ラヴクラフト全集2』読了。
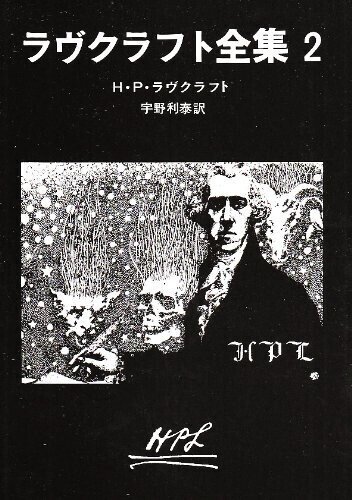
アメリカ怪奇幻想小説の大家にしてコズミック・ホラーのシェア・ワールド「クルゥルー神話」の創始者として有名なラヴクラフトの文庫版全集の2巻目。
本書はその「クルゥルー神話」の始まりを告げる短編「クトゥルフの呼び声」を収録した作品集です!
◆◆◆
本書は短編「クトゥルフの呼び声」の他にラヴクラフトの三大長編の内の一つ「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」、そして掌編「エーリッヒ・ツァンの音楽」の三篇を収録した作品集。
ゴシック的な怪奇幻想小説の背景に地球規模、宇宙規模の巨大な背景を持たせた途方もないスケールの恐怖を描くのが特徴のラヴクラフト。
その特徴を余すところなく伝える一編が「クトゥルフの呼び声」だ。この短編より後が「後期ラヴクラフト」としてクトゥルー神話体系を構築していく事となる。
――20世紀初頭、亡くなった大叔父の遺品整理をしていた「ぼく」が発見したものは、象形文字と奇怪な怪物を描いた粘土板や様々な書類等であった。
それら書類の中心と見られるものは「クトゥルフ教のこと」と題された分厚いノートだった。そのノートには、太古の昔に地球を支配していた邪悪な神が海底の巨大な石の都にひっそりと眠り、再び地球の支配を目論んでいる……そして、その神の復活に手を貸そうという邪教徒の存在が記されているのだった……。
そして、更に驚くべきは、あるとき発見された謎の難破船から救助された船員から、その「眠れる邪神」を実際に目撃したという衝撃の証言が記録されている事だったのだ……というお話。
ぼく的には怪異についてはけっこう仄めかしが多いという印象だったラヴクラフトの作品の中では珍しくストレートに怪異そのものが、姿を人目に晒す物語となっていてなかなかの迫力がある。
現代では既にゴジラやガメラなど「巨大なスケールの異形のもの」という存在を具体的な映像として見慣れてしまっているという部分があるのでこの作品に出て来るクトゥルフのイメージは、さほど物珍しさは感じられないかもしれない。
だが、20世紀までのゴシック・ホラーの傾向から言えば、これほどのスケールの異形のものを登場させて自然災害クラスの巨大な暴力イメージを読者に提示する、というのはなかなかなかったのではなかろうか。
この短編はそういったイメージをしっかり表現していて、その描写の迫力も説得力があって優れている。
ラヴクラフトの提示する「恐怖」の形式というのは、そういう所に特徴があると思っていて「こんなの絶対に人類の手には負えないだろ」「こいつが暴れたらもう人類はお終いだ」というレベルの巨大な「意志を持った存在」が人類に巨大な超暴力を振るい始める、という絶望的なイメージが魅力なのだと思うのだ。
それに比べると、他の二編はややスケールは小さい。
だが「途方もない背景を仄めかして怖ろしい」というラヴクラフト的なイマジネーションは健在である。
掌編「エーリッヒ・ツァンの音楽」は、主人公が学生時代に住んでいた「オーゼイユ街」のアパートの、ある奇妙な隣人の音楽家について回想する物語。
その隣人は主人公の部屋の上にある屋根裏の部屋を借りていて、喋る事ができないあるヴィオル(六弦の擦弦楽器)弾きだった。
彼の部屋からは毎晩のように不気味なほど暗澹たる調子の音楽が漏れ聞こえてきて、主人公はその音にすっかり魅了されていた。
あるとき主人公はそのヴィオル引きの部屋を訪ねてみる事にした。
主人公はそのヴィオル弾きに演奏を聞かせてもらうよう頼むが、この演奏家はいつまで経ってもあの暗い旋律を弾いてはくれない。主人公は弾いて欲しいあの音を口笛で吹いて見せると、奇妙な事に彼は急に主人公の口を押え、恐れたようにおどおどと部屋の窓のほうに目を向けた。
それは何故かというと……というお話。
気になるフリではあるが、この短編でははっきり何がどうなっているのかという事を説明しない。
これがラヴクラフトの「遠まわしに仄めかす演出」と相まって、サラリとした結末であるにもかかわらず妙に気になる小品となっている。
そして本書のラストを飾るのがラヴクラフト三大長編の内の一つ「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」である。
――ある日、ロード・アイランドのある精神病院から、極めて特殊な症状を示していた25歳の患者が脱走する。
彼は好古趣味が高じて系譜学の研究を行っていたのだが、彼の三代前の先祖である、ジョゼフ・カーウィンという男に関する古文書を調べ始めてから、どうやら彼の精神は異常をきたし始めていたという。
ジョゼフ・カーウィン、彼は調べれば調べるほどに妖しい過去が掘り出される、怪奇と謎に包まれた人物であった。
元々はセイレムに住んでいたものの、有名な魔女狩りの騒ぎが始まると、この男はいちはやくプロヴィデンスへ逃れて行った。
――彼は好んで化学や錬金術を行っていたのではないかと言われていた。
彼は逃れた先のプロヴィデンスの街に住居を構え、彼の農場には実験室を建てて、そこで怪しげな実験を行っていた。
このカーウィンの周囲に、徐々に恐ろしい噂や奇妙な事件が発生し始める。
彼の実験室からは夜な夜な奇妙な悲鳴や物音があがり、しばしば異臭が発生していた。
また、彼が移住してきてからというもの、街の墓地にたびたび墓荒らしが出没するようになる。
その上、奇妙な事にカーウィンは、外国から頻繁に複数のミイラや奇妙な物を輸入しているという噂が立つようになったのだ。
チャールズ・ウォードの先祖である、このジョゼフ・カーウィンという男はいったい、どんな人物だったのか?
――チャールズ・ウォードは遂にカーウィンが昔住んでいたと言われる住居にて、彼の肖像画を発見する。ジョゼフ・カーウィン、彼は――チャールズ・ウォードと瓜二つの容姿をしていたのだ!……というお話。
長編だというのに、あっけにとられるほど中身の薄い話ではあったが、それだけ細かい経緯を省かず、修辞が念入りだという事だろう。
たぶんこういう書き方だと、現代日本のエンタメ文学に慣れてしまった若い読者からしてみれば、ねちっこくてテンポが悪いという印象になってしまうだろう。
だが、ラヴクラフトがねちっこいほど修辞を重ねるのは、ストーリーではなくこの「雰囲気」を構築する事に重きを置いていたからではないかと思う。
実際、中盤で出て来るジョゼフ・カーウィン邸襲撃作戦なんかの顛末は、作戦の現場を直接書かない手法が妙に気持ち悪さを刺激して逆に新鮮な印象を受けた。
また、チャールズ・ウォードの秘密の実験室をウィレット医師が探索するくだり等はまさしくゴシック的なぞくぞくする怪異冒険譚として面白い。
ここら辺は定番のブラム・ストーカー『ドラキュラ』を思い出したほどだった。
ただ、本作のラストについては、あらゆる怪異がテレビや映画で溢れ返っている現代人の肥えた目からしてみれば、じらしてじらして、やっと出てきた「怪異の正体」が「あれ」だというのはあまりに想像の範囲内なので、あっけない結末に感じてしまった。
これは時代的な事もあり、仕方ない事なのだろうが。
という事で、全体的に言えば「クトゥルフの呼び声」は王道のクトゥルー神話ものを楽しめる名作、「エーリッヒ・ツァンの音楽」はラヴクラフトの「雰囲気を構築する演出」の冴えが光る小品、「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」はやや古典的ながらもゴシック的な雰囲気が楽しめる佳品といった印象であった。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
