
◆読書日記.《日影丈吉『多角形』》
※本稿は某SNSに2022年5月28日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
日影丈吉『多角形』読了。
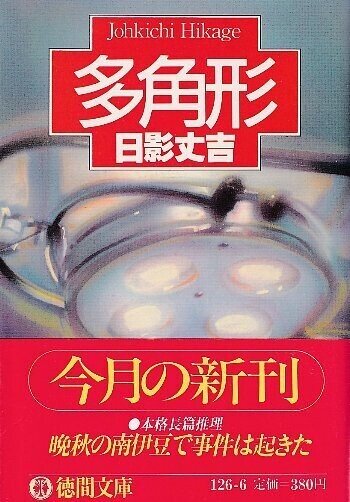
ご存じ60~70年代にかけての異端文学ブームの中で小栗虫太郎や夢野久作、久生十蘭、橘外男、香山滋、山田風太郎、国枝史郎といった作家らと共に再評価されたのが日影丈吉である。
元々ぼくは近年、年が始まる時期にまだ未読の日影丈吉の本を一冊読むという習慣を続けていたのだが、本年は正月からサルトルという厄介な課題と取り組んだために後回しにしてしまっていたら、この時期までお預けになってしまっていたのだ。
日影丈吉という作家はよく知られている通り、推理作家離れしていると言われるほどの名文家としても有名だ。
最近、文章のおかしなラノベに次々当たってしまったという事もあり、いったん自分の中の「正しい文章感覚」をオーバーホールしようという意味でもこのタイミングで本書を読んだわけだ。
しかし、本書の場合は日影丈吉の、いつもの名文を意識した作品とはちょっと毛色が違っていたようだ。
<あらすじ>
《この物語は複数の人物らの証言を繋ぎ合わせた形で再現されている》
《一つは、推理小説誌の編集者の落合捨巳が、精神分析医神近昇の診断の参考に話した話の記録》
《もう一つは、落合捨巳が自分の雑誌に投稿されてきた新人のデビュー前の原稿の一部を読み聞かせた部分など》
《もう一つは、神近昇による落合捨巳の診断に関する意見》
《もう一つは、この物語で発生する事件を取材する新聞記者・酸本の証言》
《この物語はこれらの意見や証言、話などを交互に配置して、ある殺人事件の輪郭を素描するという試みである……》
雑誌「木星<ジュピター>」の編集者・落合捨巳は、自分の所の雑誌に投稿されてきた無名の新人・月野景好の推理小説の原稿の内容にどこか惹かれるものを感じていたものの、それが未完成であるという事もあって、いまいち判断をつけられずにいた。
落合は静養もかねて、この小説の舞台となっている南伊豆の蘭生にあるホテルに宿泊していた。
彼がこの蘭生の住民らと交流していくうち、この蘭生の状況が、月野景好の原稿とそっくり同じものである事に気が付く。
地元の病院を継いだまだ若い医師の秀真兄弟。彼らは最近になって地元で人気が上がってきているようである。
そして、その兄弟と対立しているかに見える宇佐医師は、地元の大手の病院を経営し、今度秀真と公開討論会をしようとしているという。
この南伊豆の蘭生で起こっている事や人物配置はほぼ月野景好の原稿のままだというのに、彼の原稿には、具体的な殺人方法も、そのトリックもまだ書かれていなかった。
原稿と同封された手紙で月野は――メイントリックには自信があるのだが、もう少し検討したいのでそれは追ってまた連絡する――等と書いているのである。
メイントリックが分からない状態だと、まだ何とも意見する段階ではないのだが、落語「死神」に着想を得て<秀真医師は「死」を予見する事ができる能力を持っている>というアイデアは面白いと思うのだ。
そんな中、宇佐医師が運転を誤って自動車ごと崖から落下し死亡するという事故が発生する。
警察が調べた所、どうやらこれは事故に偽装した殺人事件であるという事が判明する。
未完成の推理小説の内容を埋めていくように事件は進展していく――落合は、警察とはまた別に自ら独自にこの事件の真相を追い始める。
このような事件が起こったのである、社の方針とは違うが、まだデビュー前の新人ではあるが事情を聴くために月野景好と連絡を取ろうとするのだが――彼のアパートは長い事、留守にされており、同アパートの住人らも彼の顔を良く知らなかった。――月野景好とはいったい何者なのか? そしてこの事件は何のために、誰によって起こされたものなのか?
<感想>
本作は上にも書いたように、いつもの名文を意識した作品とはちょっと毛色が違っているように感じた。
舞台の情景や登場人物の内面などをしっかりと書き込むよりも、大量の登場人物(メインの人物だけでも10人以上はいる)を巧く捌き、推理小説としての<ある仕掛け>を成立させ、その<仕掛け>を支える<思想>の説明する事……といった事のほうに意を注いでいると言った感じ。
もしかしたら、本作の分量は、あらかじめ決められていたのではないかとも思う。
というのも、けっこう登場人物も多いし、複数の証言や文章を繋ぎ合わせて小説を成り立たせるというこの作品の工夫についても、ある程度の分量が必要と思われるからだ。
この作品を『応家の人々』のように情景をしっかり書き込んだり、『女の家』のように心理描写をしっかりと書き込んだりしていると、たちまち原稿の分量が倍以上に膨れ上がってしまっていただろう。
逆に言えば、そういった文学的な側面を排除してでも、この小説の「推理小説的なテーマ」や「推理小説的な思想」「(当時としては)斬新な手法」のほうを優先したかったのではないかと思うのである。
それくらい、当時(1965年)この推理小説の内容は先進的であった。
本作のメイン・トリックはさすがに今では手垢に塗れたものになってしまっているが、この手のトリックが日本の推理文壇で盛んに使われ始めたのは1990年代になってからである。
しかし、この斬新な工夫についても、著者があまりに派手な演出を好まず、抑えた筆致でごく控えめに書くクセがあったからこそ、内容の割には派手な効果は与えていないのではないかとさえ思う。おそらく●●●●よりも先にこのネタを使っていたというのにもかかわらず。
だが、本書の特徴は何もそのメイン・トリックだけに限らないのが、この作品を未だに読むに値すると思わせられるような、一種異様な個性となっていて、ぼくとしてはそこが非常に楽しめた所であった。
その個性とは、本書のある「推理小説的なテーマ/推理小説的な思想」である。
さすが「異端作家」の面目躍如といった所か。
『一丁倫敦殺人事件』でも、『応家の人々』でも、「この人はヘンだ」と思った。
普通の推理作家がやらない事を、好んでやるのである。
あまりに大人の文章であり、抑制的な名文を書く人なので分かりにくいのだが、――彼の長編作品は、しばしば非常に挑戦的、野心的になるのである。
本作の思想性も先進的だし、「あのトリック」を使っていてなお「あんな結末」にしてしまうという所が、何より日陰丈吉の挑戦的な個性が現れていると思える。
さて、本作のその「挑戦的な個性」や「推理小説的な思想」を説明するためには、ここからネタバレの解説をしなければならない。
◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆
《注:以下、日影丈吉『多角形』の中核的なアイデアに触れるレビューとなっています。本書を未読の方、またネタバレをされたくないと思っている方は、以下文章を読む際はその点をご考慮の上ご覧頂ければと思います》
◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆
さて、という事でここからは本作のトリック面、そしてテーマ面に関して記していこうと思う。
本書の中核となるトリックは勿論、リチャード・ニーリイが最も得意とした多重人格を利用した叙述トリックである。
多重人格ものの叙述トリックというのは、一見して非常に奇妙な現象を引き起こす事ができ、トリックが判明した時の衝撃は、世界の見方が180度ひっくり返ったようなものとなるので、トリックに拘る推理作家ほどこのトリックは真似たがるだろう。
実際、90年代にはこの手法は広く知れ渡り、まずはニーリイをお手本とした叙述トリック職人の折原一が使い始め、その後多くの作家があれこれと工夫してこのトリックを利用している。
しかし、本書『多角形』が書かれた年代は1965年である。
ニーリイのデビュー年は1969年。
日影丈吉のほうが圧倒的に早いのである。
日本でハッキリした叙述トリックを使った作品にしても、中町信の乱歩賞候補作で有名な『新人賞殺人事件』でさえ1971年である。
この年代の推理小説を調べれば調べるほど、本書『多角形』がいかに「ヘン」だったか分かる。
しかし、それにしても面白いと思うのは、この先進的なトリックを、必ずしも前面に押し出して「だましてやろう」という見せ方をしていないという所である。
ぼくが思うに、本作での「多重人格ものの叙述トリック」は、あくまで本書の「推理小説的なテーマ」を成立させるための一つの駒でしかないのである。
本署の「推理小説的なテーマ」の一つは、秀真遷吾医師の婚約者・頼母木説江の次のセリフに現れている。
「動機だのアリバイだのって、規格のきちんとした状況を設定しないと、人を殺せないような紳士淑女の時代はもう過ぎたわ。完全犯罪なんてのは、もうアナクロニズムだわ。実際に起る犯罪を見ても、そうでしょう。計画的な犯罪ほど、簡単に割れてるわね。学校の先生なんかが悪いことすると、すぐつかまっちゃうじゃない」
「はあ、あなたは推理小説通だけじゃなくて、犯罪研究家でもあるんですか」
「いつだったか、東京のある刑事さんに聞いたんですけど、放火犯人なんかは、現行犯をつかまえなければ、絶対といっていいくらい、わからないものですってね。意味もない犯罪の比率が、実際には莫大に大きいのに、一方で動機やアリバイに拘泥しなければならない古典的な法律があるおかげで、それが黙殺されてしまう。だから、手のこんだ完全犯罪は、検察官にはお得意さまみたいなもので、気持ちよくあばけるけれども、できるだけ不完全な犯罪ほど、わかりにくい。なんの意志も怨恨もない、風が立木をたおすような、突発的な力を用いた、天衣無縫の犯罪とでもいうものが、これからの完全犯罪なのね」(本書P.182-183より引用)
まとめると、頼母木説江は以下のような主張をしているのである。
1)現実の世界では、練りに練った計画殺人よりも、突発的な殺人のほうが多い。
2)警察捜査は、アリバイ捜査や怨恨関係の捜査など、計画的な殺人事件に対応しやすい捜査方法を得意としているが、突発的に行われる意味もない犯罪などには弱い。
3)故に、これからの時代の「完全犯罪」とは、推理小説で良く見るような計画的犯罪ではなく、突発的に行われる、意味や動機のない犯罪こそが、真に「完全犯罪」と呼ばれるにふさわしい。
――と言っているのである。この思想性だけでも、じゅうぶん面白い。
本作では、この思想を踏まえた結末を迎える。
しかも、――これが面白い事に――この思想を反映させるために、日陰丈吉はラストの展開に三重底の真相を用意していた。
【1】まず、主人公の落合捨巳が、非常に「推理小説的な真相」を、オーソドックスな推理小説に出てくる名探偵の語る大団円のように解説する。
――これは後に否定される。
【2】次に、「突発的な殺人」としての容疑者として、永宗医師が逮捕されて自白して殺人罪として起訴される。
――しかし後に永宗医師は「警察の誘導尋問で昏迷におちいり、不利なことを喋った」といって犯行を否定。彼が上告している最中で物語は終わる。
【3】最後に、精神分析医の神近氏の分析として、落合捨巳は多重人格者であり、彼こそが「月野景好」となり替わって犯罪を行ったのではないかと推測する。
――しかしこれは状況証拠のみで決定的な証拠はなく、彼が犯人だとしても動機も分からないまま、それらを含めて精神科医として落合捨巳を追求がこれから始まる……と宣言されて物語は閉じる。
この三重底の結末というのはなかなか凝った構成だ。
【1】で「推理小説らしい真相」が語られる。
【2】で「突発的な殺人=衝動的殺人」としての、小説的ではない、より「リアルな/現実的な」結末が提示される。
【3】で「突発的な/動機も意味も分からない/未知の」殺人という結末が仄めかされる。
つまり、それぞれの結末は、それぞれの位相を全く異にしているのである。
頼母木説江の主張どおりに、【1】の「推理小説的な真相」はこの物語の結末でも完全に否定されるのである。「フィクション」の位相は、否定されるのである。
そして、永宗医師による【2】の「突発的な殺人=衝動的殺人」は、「現実の、リアルな位相」を表している。
永宗医師は警察官によって虚偽の自白をさせられたとして上告するという、現実の裁判でもいかにもありそうな展開を見せる事となる。――現実的な犯罪ほど、「推理小説的な真相」のような完璧な犯罪の証明などできず、そこにはただ「裁判の結果」があるだけである。
落合捨巳による【3】の「突発的な/動機も意味も分からない/未知の」殺人は、当時の精神医学の分野でも(おそらく当時では)「未開拓=人類の未知の領域」を表す位相なのである。
そして、このような「動機が判明しない」犯罪については、警察は全く手が出せない。
そもそも、このような精神状態であれば裁判では責任能力が問われる事となるだろうが「多重人格の殺人」が(当時は)未知のものである限り、司法は手が出せない領域に入ってしまうという事になる。
このように並べると日影丈吉のやりたかった事が見えてくるようでもある。
本作の三重底の真相というものは、【1】から【3】に進むにつれて、だんだんと推理小説の理想とする「理知的で精緻に考えられた犯罪=完全犯罪」が崩れていき、推理小説的ではない「非知性的な犯罪=不完全な犯罪」に変化していく過程なのである。
そして、このプロセスが進むほどに、事件の真相はどんどん藪の中へと消えて行ってしまうのである。
この展開というのが、まさしく頼母木説江が主張していた「不完全な犯罪ほど、わかりにくい」という説を表現しているのである。
推理小説が理想としている「完全犯罪」を否定し、現代のリアルな犯罪というのは推理小説からしてみれば「不完全な犯罪」こそが重要性を増してきている――そういう著者の思想性が、本作では見事に小説として結実している。
今では手垢に塗れてしまったリチャード・ニーリイ流の「多重人格ものの叙述トリック」を使いながらも、本作はこの「思想性」にこそ、主眼があったのではなかっただろうか。
日影丈吉にとって「多重人格もの」というトリックは、「読者を騙す」ためではなく、このテーマを成立させるためだけにあった。だから本書には叙述トリックにある外連味が全く感じられなかったのではないか。
いわば本作は、作家で言うなら麻耶雄嵩が得意としているような、推理小説という文学形式そのものを批判的に解体した、メタ・ミステリだったのである。
このようなミステリが、後にも先にも、本作以外にあっただろうか?「多重人格ものの叙述トリック」でさえ、当時はまだ誰も手につけていないような時代にである。
日影丈吉は、「ヘン」なのだ。
ぼくが冒頭にそのように言ったのには、このような理由がある。そして、その「ヘン」さが、ぼくが日影丈吉をこよなく愛する理由の一つでもある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
