
◆読書日記.《塚本邦雄『秀吟百趣』》
※本稿は昨年2021年9月3日に呟きの形式で投稿したレビューを日記形式にまとめて加筆修正したものを掲載しています。
今年の頭から毎日1~2作ずつ読み進めてきた塚本邦雄による近現代作家の短歌・俳句の秀歌絶唱を100集めて鑑賞するアンソロジー『秀吟百趣』読了。
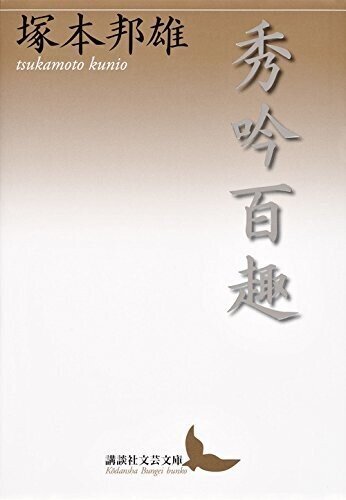
ああ、遂に読了してしまった。毎日のささやかな楽しみ。毎日のように確保されていた、厳選された美を味わう癒しの時間。それが遂に終わってしまった。
現代短歌を先導してきた塚本邦雄は、短歌については初期のものほど秀逸なものが濃縮されているが、晩年については、評論や小説など短歌以外にも様々な分野に進出して、そちらの分野に秀逸な作品が多い。
塚本は歌作でも膨大な量の作品を残しているが、評論についても精力的な研究と著述を残している。
既にぼくは去年、よく「凡作が多い」と指摘される定家の『小倉百人一首』を、塚本邦雄が同じ歌人の中から定家の選んだものよりも優れた作品を同数集めて編みなおした『新選・小倉百人一首』をご紹介している。
その他にも塚本には『王朝百首』や『定家百首』等、古典を吟味する著作も多い。
『王朝百首』や『定家百首』といった古典を論評した本を出した後、塚本はある時『サンデー毎日』の編集長より「現代においてなお朗々誦すべき秀歌絶唱ありや」と尋ねられた。
近現代の短歌を吟味して論評しようとしたのはそれがきっかけとなったという。
今度は明治以降の近現代における短歌・俳句における秀歌・絶唱を吟味に次ぐ吟味によって100作+3作を選び抜き、それを鑑賞するアンソロジーを編んだのが本書となったのである。
類稀なる審美眼を持つ塚本が選びに選んだ103作、それぞれに詳細な解説と、取り上げた作者の作のうち塚本の愛誦する作品を最低5つ以上取り上げ、その作家の持つ個性を示す。
俳句も短歌も、その作品の内容をどう解釈し、どう読むかという事にははっきりとした正解はない。
はっきりとした正解はないからこそ詩歌というものは面白いのだが、塚本のように類稀なるセンスを持った実作者が、近現代の作家の作品をどう読み、どのように味わっているのかというその「実力者の鑑賞の具体例」を提示してくれるというのが非常にありがたいのである。
ぼくは常々言っているように、自分は詩や短歌、俳句についてはド素人だと思っている。
だからこそこういう「読み方」の一例を示してくれるのがありがたい。
本書に取り上げられている作品については、改めて一つ一つピックアップして述べる事まではしない。
ただ、本書を読んだ事で今回、いくつか理解した事があったのでそれを述べるにとどめておこう。
「やはり」と言うか「当たり前だけど」と言うか、本書に取り上げられている近現代の秀歌の数々は、「読めばそのまま意味が分かる」ものは一つもなく、必ず鑑賞者それぞれの「読み」が必要となる作品ばかりであった。
つまり、誰でも読めば理解できるような簡単な作りの作品などはなく、誰でも全く同じ意味を読み取れるような作品もないという事なのだ。
分かり易い作品は「薄っぺらい」のである。
たいていの秀歌というのは「読み」の多様性がある。だからこそ奥深いし、人それぞれに様々な楽しみ方ができるようになっている。
、また、もう一つ本書を読んで気付いた事は、そういった秀作を残している作家というのは「語彙」を疎かにしていないという点である。
作品を鑑賞するにも、作るにも、やはり「語彙力」は必須なのだ。平易な言葉や平易な表現であればあるほど、表現の幅は狭いからである。
例えば「曼殊沙華」をテーマに一句作ろうと考えたとしても、それにも彼岸花、死人花、天蓋花、幽霊花、捨子花……等という様々な別名があって、ご覧の通り、それぞれの言い方でニュアンスが非常に大きく変わってしまう。
同じ5音でも「曼殊沙華」と言った場合と「死人花」と言った場合では、17音しかない俳句の世界では、読者に与えるニュアンスの差は圧倒的に違ってしまうのだ。
おそらく曼殊沙華であったらよく知られた「曼殊沙華」という言葉を使ったほうが分かり易いだろう。だが、句のニュアンスによってそれ以外の別の言葉をチョイスできないようでは、句意もその作風も狭まってしまうだろう。
俳句や短歌を作る人というのは、少ない文字数に思いを詰め込むからこそ、様々な語彙の中から最も適した言葉を選んでニュアンスを整えねばならないのだ。
そういう厳しいルールが課せられたポエムだからこそ、語彙力がなければ表現の幅は広がる事はない。
つまり、語彙力はスポーツ選手で言う所の体力や筋力のようなもので、鍛える事はできるが、なければ圧倒的に不利なのだ。
だから、優れた作者というものは言葉をよく知っているし、語彙力だけでも実力と言うのは大体想像できる。
逆に言えば、読者についても、秀歌絶唱を味わうためには語彙力を高めなければならないのだ。
解釈がわからない、意味がよく呑み込めない、といった短歌があった場合、まず「分からない単語はないか?」というのをチェックしてみる事をお勧めする。
また「その言葉の他の意味/裏の意味はあるか?」などというものも調べてみると、今まで理解できなかった作品の印象が突然判明したりもする。
俳句・短歌は17音、31音という、非常に限られた、短い音数の中で一つの世界観を作り上げなければならないものだ。
だからこそ各作家は様々な単語や名称や表現を吟味し、その中で最も自らの感覚にマッチしたものを選んでいるのである。書くも、読むも、吟味、吟味である。
それだけ厳しい条件の中で作られるからこそ、磨かれた言葉が作り出す詩の中に、ギラリと光る奇跡のような秀歌絶唱が出来上がるのである。
「きらめくは歌の玉匣眠る夜の海こそ千尋やすらはぬかも」――塚本邦雄
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
