
◆読書日記.《ルネ・ネリ『エロティックと文明』》
<2021年2月11日>
いま読んでいるのはルネ・ネリ『エロティックと文明』です♪
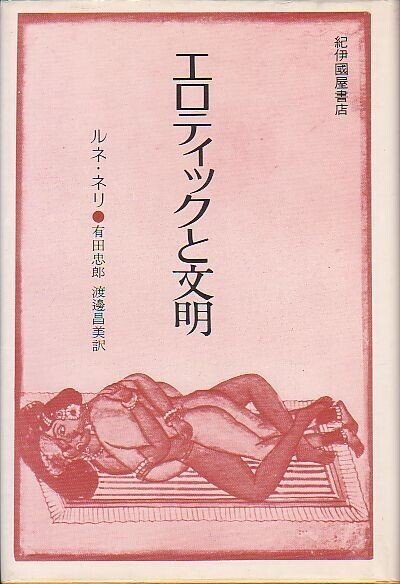
フランスの碩学・ルネ・ネリが「エロティック」を文化現象として思い切りよく論じた論考。
バタイユの『エロティシズム』を読んだときも思ったが、フランス人のエロティシズム論はぼく的にはどこか違和感が拭いきれない。
この違和感は、いったい何に由来するものなのだろう?とずっと疑問に思っていた。
ルネ・ネリはちゃんと東洋のエロティシズムも知悉しているようで、しばしば西洋的エロティシズムと、中国やインド等の東洋のエロティシズムを比較している。
自己を知るには他者を知らねばならない。評価は大抵の場合、他者との比較でしか決まらない所があるからだ。
文化現象の評価も同じである。
だからぼくはしばしば「外国からの視点というのが、自国を理解するのには重要だ」と言っているのである。
西洋的な文明を「狩猟民族文明」と東洋的な文明を「農耕民族文明」と評価するのはあまりに単純化が過ぎるとは思うが、エロティシズムについては、どこかそういう枠組みに当てはめたくなる部分が見える。
というのも、このルネ・ネリの論考を読んでいて気づくのは、西洋的なエロティシズムにはどこか「性急さ」が底流に存在しているように思えるからだ。
ルネ・ネリは「中国や日本では間接的愛撫の手練はきわめて高度の域に達していて、このように迂遠な形で事を始めるのに習熟していない西洋の人間は、乗り組まないうちに目的地へ入港したり、時には巧妙な玄人女と男の間には性的接触すら必要としないのを見て驚嘆するほかない。これは、西洋の人間がひたすら目的をとげようとし、目的を重視しすぎ、その結果、先行する拡散した快感を見過ごして、これを余計な段階としか見ない野蛮人だという事を意味する」――と、東洋のエロティックに対する「迂遠さ」と、エロティックに関して目的を遂げる事を優先させる西洋の「性急さ」の差を強調している。
西洋の伝統的性道徳がしばしばエロティックを否定し、あまつさえそれに対する憎悪のようなものまで抱いているのは何故なのかというのは、ぼくにはずっと疑問だった。
東洋のエロティックに対する「迂遠さ」というのは、エロティックだけではなく恋愛についてもやたらと様々なプロセスを経てからでないと恋愛が成立しないような「迂遠さ」と相同的なものにも感じるし、それはアメリカ的な「好きだ」で済ませる「性急さ」にも表れている東西との差なのではないかとも思える。
トマス・アクィナスが「主として欲情が結合行為へと追いやる時、常に大罪あり」と言った通り、キリスト教的性道徳は「生殖行為」から「性的快楽」を引き剥がそうと努力してきた。
前者を聖なるものと、そして後者を「大罪」としてきたのである。無茶な努力だが、これも「目的」のみを重視したものであろう。
そのための「禁欲的なセックスの方法」というのは、例えばキリスト教キュニコス派やエピクロス派等が実践している方法があるという。
「欲求がどうにもならなくまで待って、自分だけで、あるいは二人で疲労を避けるために立ったまま、あるいは窮屈な姿勢で、能う限り速やかに欲求を満たすべきであり~(以下略)」
このように、西洋の伝統的性道徳は性交に伴う快楽を「罪」と捉えてきた。
この理由をルネ・ネリは次ように推測している。
「なぜ快楽が悪であるのか。なぜ快楽を禁じねばならぬのか。快楽が意志と自由を滅ぼす眠りに似ているからである。死の如きもの、積極的な生活に対する脅威であるからである」
「冷静な性欲の享楽」というものは語義矛盾のように思える。
冷静な理性の下において快楽をコントロールする事はできない。
ある種の没我状態にあらねば性的快楽は成立しないのである。
さもなくば、キュニコス派のように「性急な処理」によってその時間をできうる限り短縮してしまわなければ、没我状態は克服できない。
西洋の性道徳が生殖行為から性的快楽という癌を厳しく摘出してきたのは、この「没我状態」を警戒しているというニュアンスを強く感じるのである。
性交時の没我状態が何故警戒に値するかと言えば、それが意志の安定、冷静な感情のコントロールを失った状態が持続する「危険な時間」だったからではなかろうか。
西洋のエロティックがしばしば「性急さ」を感じさせるのには、やはりそのような性交に伴う快楽への憎悪、もしくは嫌悪感が元になっているのではないかと思わせられる。
周囲の危機を回避するための冷静な判断力、周囲の災厄の予兆を察知する緊張感――それを消失させる「危険な時間」が性的没我状態にあったのではないのか。
ルネ・ネリは指摘する。
「人類の原始時代には、快感は緊張――おそらく「異様な状態」に感じられた――の消去の中に存したのであって、消去する快い方法の中に存したのではないと、言えるであろう」
「性的快楽」というものは、日常生活では性交時以外には感じられない、非常に特別な感覚なのである。
苦痛でもない、掻痒感でもない――更に言えば局部的な快感でもない、「没我」を伴う"異常な"高揚感。この特別な感覚を「危機」と感じるか、それとも「素晴らしきもの」と捉えるのか。
東西でエロティックの捉え方がここまで逆転しているというのは、非常に興味深い現象なのではないだろうか。
そういう「感情のコントロールの失った"没我状態"の時間」に対する感覚の差というものを感じるからこそ、――いささか単純化しすぎる分類ではあるものの――西洋的な文明を「狩猟民族文明」と東洋的な文明を「農耕民族文明」と評価する見方を取りたくなってしまうのである。
<2021年2月13日>
ルネ・ネリ『エロティックと文明』読了。
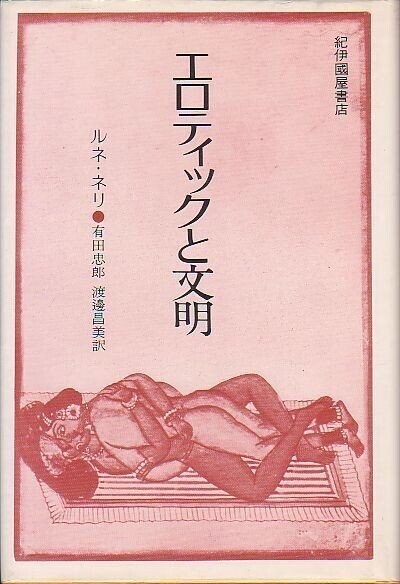
フランスの碩学、民俗学が専門の学者ルネ・ネリが民俗学、人類学、文学、心理学などの該博な知識を駆使して愛と愛欲の発展の歴史とその謎について思い切りよく語る。
実証的な文章ではないが、西洋人の「愛の謎」を歴史を通貫して語るダイナミックな論考。
ただ、本書で論考の対象となっているのはあくまで西洋の文化的な階層の人々がメインのようである。
庶民や、東洋についても論究されてはいるが、あくまで西洋人との比較においてその事例が上がっているだけといった感じであった。
それだけに西洋人の愛の意識、性意識の歴史は興味深いものがあった。
先日も呟いたが、ぼくは以前から西洋人が学術的に語る性の話に、どうにも素直に頷けない違和感を抱いていた。
これについては先日の呟きにもあったように、その東西の性意識の差というのはおぼろげながら分かってきたように思える。
西洋人の性意識の源流にどこか、セックスに対する好悪相反する感情が見えるのだ。
「膣口」に対する奇妙な不安感も、しばしば西洋人が性を語る一つの特徴となっていると思われる。
「男は、自分の出生に関わる時間の夜を思えば、直ちに、子宮の夜が今も自分を待ち受け、再びその暗闇に捉えようと脅かしているのを感じる。女の眼は、彼を見つめる闇なのである(本書より引用)」
女性器は、原始時代に狩猟民がシェルター兼住居として利用した、あの暗い洞穴の闇を思い起こさせ、それが性交時の暗闇にリンクしているのである……男性の性感機能をほぼ独占する器官である陰茎を飲み込み、男をあの"危険な"没我状態に落とし込む闇。去勢不安を思い起こさせるキバの付いた男を飲み込む口。
ポリネシア神話に出て来る死後世界の神「ヒネヌイテポ」は、膣口に黒曜石の歯を持って男を飲み込むという、男性の去勢不安を精神分析的にキャラクター化したような性質を持っている。
古代の男性は、女性器を楽しみながらも、同時に「それ」に曰く言い難い不安や恐れを抱いていたのである。
……といった女性器に対する奇妙な不安感というものは、割と西洋人の性意識の論考に出て来るロジックなのだが、ぼく的にはどうにも「実感」としてピンとこない。
そもそもエディプス・コンプレックス的な「去勢不安」というものを感じた事が全くないので、どうにも共感できないのである。
友人らとの会話で「去勢不安」等といったものについて、今まで話題に挙がった事も一度としてない。
西洋人の話に良く出てくる、自慰をしている事を母親にバレた時に「そんな事をしていると、オチンチンをちょん切ってしまいますよ」といったような(フロイト思想にも良く出てくる例え話だ)叱り方など、日本人の母親はしないのではないだろうか?
もしかしたら日本人には「去勢不安」を感じさせないような、西洋人との何かしらの「差」があるのではないか。
それが、西洋人的な男性優位的性意識よりも、昔から「女性を楽しませる」事を意図したあらゆる性技に長けた東洋の鷹揚な性意識に繋がっているのではないかとも思えるのである。
西洋人の性意識は、古代にあっては女性を「敵」と見做す傾向があったようである。
著者のルネ・ネリは西洋の歴史を通して、原始社会にあってかつて「敵」であった女が徐々に「友」となり、「恋人」となり、やがて自らの両性具有的な「分身」の存在となる「エロティックの意識」の歴史を仮説として紹介している。
これらを見ていると西洋の女性解放の歴史は、男性による女性嫌悪の意識――つまりは「敵」とみなしていた意識――を緩和させ、社会的にその意識から解放されていく歴史だったように思える。
男性は自分の意識が緩和している「没我状態」にあって、何者か正体の知れない「女」という存在に、かつて恐怖していたのだ。
最も油断している状況の中で、己の急所をガッチリと飲み込んでいる存在に、古代の男性は暗闇の中、言い知れぬ不安を抱いていたのかもしれない。
だからこそ古代西洋人は、女性と交わるときほとんど強姦に近い交わり方をしていたのではないかと著者は想像している。
確かに、生物界の中でも無理やりメスを犯す「強制交尾」はしばしば見られて、例えば南オーストラリアの熱く乾いた地方の塩湖に住むエア湖トカゲの雄などは、厳しい環境の中、いやがる雌を脅して無理やり強姦する種である。
その厳しい交尾はときとして交尾中に雌を殺してしまうこともあると言われる。
西洋人の女性抑圧的なキリスト教道徳というものは、こういった昔からの女性への敵対心に由来しているのではないかと思われる部分がある。
キリスト教道徳が、女性抑圧的な性関係を強要したというよりも、西洋人の性意識が、そういった女性を抑圧する道徳を要請したのではなかろうか。
西洋人の性交は古代と地続きの動物的な「苦痛」を伴う強制的性行為の敵対意識を緩和させ、徐々に相互交流的な「快感」に変化させていくという、男女の敵対関係を和解させていく歴史を辿って行ったのではないかと思うのである。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
