
◆読書日記.《アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ『ボマルツォの怪物』》
<2022年12月10日>
アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ『ボマルツォの怪物』読了。

20世紀フランス作家・マンディアルグのエッセー、批評、小説を集めた文集。澁澤龍彦の訳。
この本は大和書房で出された箱付きハードカバー版と河出書房の文庫版「澁澤龍彦コレクション」の2ヴァージョン持っていたのだが、今回は外出時にも持ち歩いていたので文庫版のほうを読んだ。
実はマンディアルグは初めて読む作家なのだが、澁澤の紹介だけあって澁澤好みの残酷、幻想、怪奇趣味の文章家といった感じであった。
本書でもマンディアルグはサドを高く評価し(本書収録の「ジュリエット」)『O嬢の物語』について言及し(本書収録の「黒いエロス」)シュルレアスムを愛する、澁澤龍彦の趣味的近親者といった所か。
しかし、本書で言及されているテーマのほとんどが凡そ澁澤の書籍でじっくりと紹介されているものが多く、学生時代から澁澤のエッセイに親しんできた自分としては、マンディアルグのエッセーは「澁澤のエッセンスを薄めた感じ」という印象がぬぐえなかった。
本書の末尾に収録されているのは本作品集の中で唯一の小説作品。
この作品はマンディアルグが「ピエール・モリオン」名義で発表した小説『イギリス人』である。これはまさにマルキ・ド・サドの『ソドム百二十日』を連想させる、世間から隔絶された閉鎖環境で行われる、残酷な性の饗宴を描いたポルノ小説であった。
しかし、これもどこか『ソドム百二十日』の規模をいくぶん縮小して行われる性的残酷劇といった内容になっている。
それでも面白そうではあったのだが、冒頭三分の一で「これから盛り上がってくるのに」といった所で終わってしまう「抄訳」版なのである。
このようにラストを締めくくるこの一編さえも、斯様に中途半端な形での収録というのが、本書の中途半端さを引き立てていて何とも食い足りない気分になってしまう。
うーん、趣味は悪くて好みなんだけどなァ。
◆◆◆
本書は、表題作のエッセー「ボマルツォの怪物」が分量、内容共に本書の代表作と言えるだろう。
このエッセーで取り上げられているのは、中部イタリアの「ヴィテルボ県のオルテから遠からぬところにある」、ボマルツォ村の郊外のやや寂れた場所にある奇妙な彫刻群である。
その彫像群は、この一編が書かれた当時は既に作られてから四百年以上経ってすっかり忘れら去られ、廃墟のように放置されていたようである。
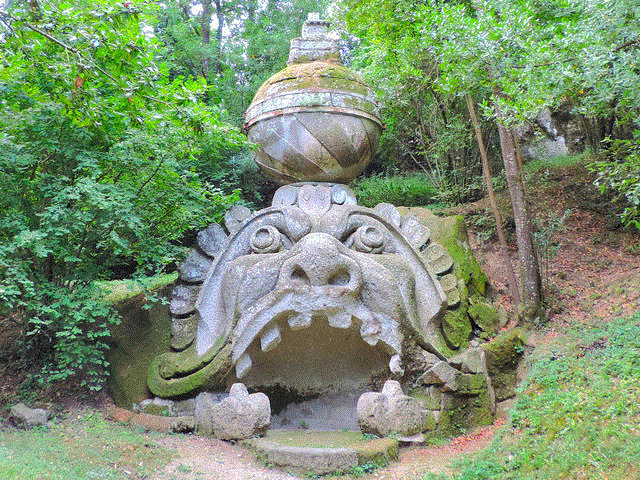
写真を見ても分かる通りのインパクトある巨大な彫刻群が、茫々たる下草に半ば覆われて放置されている、ある種「廃墟」的な美しさを湛えていたようだ。
あるいはマンディアルグ自身も例えているように、ジャングルをかき分けかき分けやっとたどり着いた秘境に、誰からも忘れ去られたアンコール・ワットを見たようなインパクトがあったのかもしれない。
たとえばアンコール・ワットとか、パレンケとか、(それ以上列挙するのはペダンティックであろうが)世界のほとんどあらゆる地方に散在する、忘れさられた、あるいは有名な、同じような種類の場所を思い起こしていただきたい。そして人間的であると同時に獣的で、しかも魁偉で、あまりに現実離れしているので観察者が呆然自失するほどの大きさと表情をもった、あれらの彫像を頭の中に思い描いていただきたい。
数百年放置され、誰もが忘れ去ってしまった秘密の場所にある怪奇的な彫像群。
こういう「世間に秘された怪奇趣味」という所に、マンディアルグの興味を引く点があったのかもしれない。
「世間から隔絶された秘された場所に設定される怪奇・残酷・幻想」という意味では、この「ボマルツォの怪物」らも、本書の末尾に収録されている小説『イギリス人』の趣向と通底する所があるのだろう。
『イギリス人』では、満ち潮になると道路が海に沈んで孤島となる城砦で繰り広げられる残酷な饗宴が描かれる。
世間の目を逃れた秘密の場所で繰り広げられている怪奇と残酷とエロティシズムの饗宴という意味で、『ボマルツォの怪物』と『イギリス人』は同じ趣向なのだ(因みに、このボマルツォの怪物群の中にも「一種の残酷なエロティシズムで見る者をぎょっとさせる」彫像や「ボードレールの『巨大なる女』もかくやとばかりの彫像」などと言ったように、「黒いエロス」を感じさせる彫像がある事が紹介されている)。
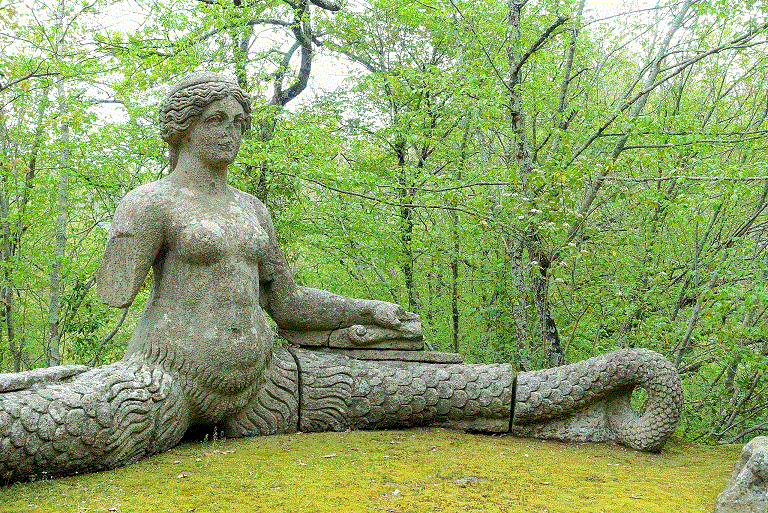
それは、極端に楽しみが少なかった中世ヨーロッパの時代の百姓女の多くが熱中した淫靡なサバトのような神秘主義、オカルト趣味とも共通した「秘された享楽」であったのであろう。
その趣向は「秘されている」からこそ意味がある。秘されているからこそ、余計に淫靡な雰囲気が強まる。
少なくともマンディアルグはそう考えていたに違いない。
そうでなければ「まだ怪物たちがそこに無事でいるあいだに、早く彼らを見に行かなければならない」と警告し、「まことにありがたいことに、彼らは現在、小牧場と野原と森のあいだで自由を楽しんでいる」等とは言わないだろう。
まして下草をすっかり綺麗に刈り取られ白日の下にさらされ、にぎにぎしく大勢の観光客に見物される「怪物群」の姿など、許容範囲外だったであろう。
かといってこのまま人々に忘れ去られたまま、風雨にさらされ、牧人の気まぐれで破壊され、緑に呑まれて覆滅してしまうという運命も「怪物」達にとっては悲劇だ。
もし諸君がボマルツォの将来について、ほったらかしにしておくべきであるか、それともきびしい管理のもとに置くべきであるか、二者択一をしなければならない場合に立ち至ったとしたならば、いったい、どんな決定をすることができるだろうか? それというのも、この二者択一はどうしても必要だからであり、過去の偉大な作品の運命は、この悲しむべき解決方法のいずれかを避けることは不可能だからである。
マンディアルグはこの彫像群を「モニュメント」と称しているが、これら彫像群は半「建築」的な要素もある(実際、ボマルツォにある巨大な怪物の顔の彫像は、人が数人入る事のできるほどの巨大な口を開けていて、その中にはテーブルとベンチが置いてあり、まさに建築的作品となっている)。

こういうタイプの作品は、絵画のような作品とは違って「体験的」なのである。
観客はただ単にその彫像を「外から眺めている」だけなのではない。
「その彫像がある空間」自体を、観客は「体験的に感じている」のである。ある種のインスタレーション作品と同じようなものだと思って良いだろう。
マンディアルグが「ボマルツォの怪物」の美を褒める時、そこでは明らかに、朽ちかけた彫像群が熱帯アジアの植物群もかくやという緑に半ば呑み込まれている、その状況そのものを含めて「作品」として褒めているのである。
植物群とモニュメントとの結婚(不釣合な)、人間の手で加工された石あるいは青銅と、木質、樹液、ならびに腐植土からたえず吐き出される葉緑素の全体との、結婚ということなのである。それはかまきりの結婚におけるように、もし気高い犠牲者たる男性の役割を「芸術品」に振りあてるならば、雄が雌によって喰われてしまう結婚である。
……この「異質な結婚」というものは、勿論マンディアルグも本エッセーで触れているロートレアモンが「解剖台の上のミシンと蝙蝠傘の偶然の邂逅のように美しい」と形容した、そういうタイプの「美」であっただろう。
だからこそ、これら怪物群は、人目を忍んでほうっておかれるべきであった。例え朽ちるに任せて物理的にも文化的にも風化してしまったとしても。
ぼうぼうと繁殖する緑に侵食された状態で、ジャングルのような森の奥地へと進む者だけにその姿を開陳する秘境として、破滅を約束されたサバト的な秘密の、残酷な饗宴を続けていればよかったのだ。
◆◆◆
因みに、マンディアルグが紹介したこの「ボマルツォの怪物」群は、現在イタリアはウンブリア州のボマルツォで「怪物公園」と呼ばれる観光地となり、その怪異な彫刻群をヨーロッパ中のひとびとが観光しにやってくるようになっている。

入り口で入館料を払って入場し、鉄柵に押し込まれた「怪物」たちを眺め、記念にお土産物屋で買い物をする事もできる。
今では「Parco dei Mostri」で画像検索すれば、世界中の誰もがその様子の一端を見る事ができる。
……という事で、マンディアルグが衝撃を受けた「ボマルツォの怪物」も、今では博物館に陳列される「お上品な美術品」に腰を落ち着けてしまったようだ。
マンディアルグはそれも人間の創作物が美術に推移する当然のプロセスだと考えていたようだが、恐らく「公園=アミューズメント」化したこれらの「怪物」たちは、以前の野性的なジャングルの奥地に隠された「秘境」である事をやめ、人間に飼いならされる家畜に変化し、以前の野性はもう見られないだろう。
こういった「展示問題」というものは、過去の作品を展示する場合に付いて回る問題でもある。
現代アートは製作段階で「美術館に展示される事」は念頭に置かれて作られているものだが、オールド・マスターと呼ばれる過去の作品群というものは、現代的な美術館の照明設備の下で鑑賞される事を前提に作られてはいない。
例えば、ゴシック期のキリスト教絵画などは、窓の小さい薄暗いゴシック建築の礼拝堂の中に掲げられて、蝋燭の揺らめく弱々しい光源にぼんやりと浮かび上がる事を想定して描かれている。聖壇の上に掲げられ、信者は祈りをささげる時にその絵を見上げるような角度で鑑賞する。
そういった環境等の条件にマッチした表現によって彫像や絵画は作られているものなので、個々の作品の条件を無視し、皆一様に現代の照明設備の元に隅々まではっきりと鑑賞できる状態で展示するのは、当初の製作意図とは違っているのではないだろうか?という事になるのである(この問題は以前、フレデリック・ワイズマン監督のドキュメンタリー映画『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』のレビューでも触れた問題だ)。
勿論「ボマルツォの怪物」たちも、マンディアルグが称賛していた「朽ちた状態」では、制作された当初の意図とは違っていたかもしれない。
だが、この場合は当初の意図とは違った環境に変化していたからこその「異質な結婚」であったはずだ。そこを、マンディアルグは称賛したのである。
しかし、この彫像群は現在のように「美術品」に収まり大衆に開かれる事でアウラは消失し、その稀有な秘境的「体験的価値」を貶めてしまったのかもしれない。
ボマルツォの秘境にかけられていた饗宴の魔術も、光に照らされ、もうその効果は切れてしまった。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
