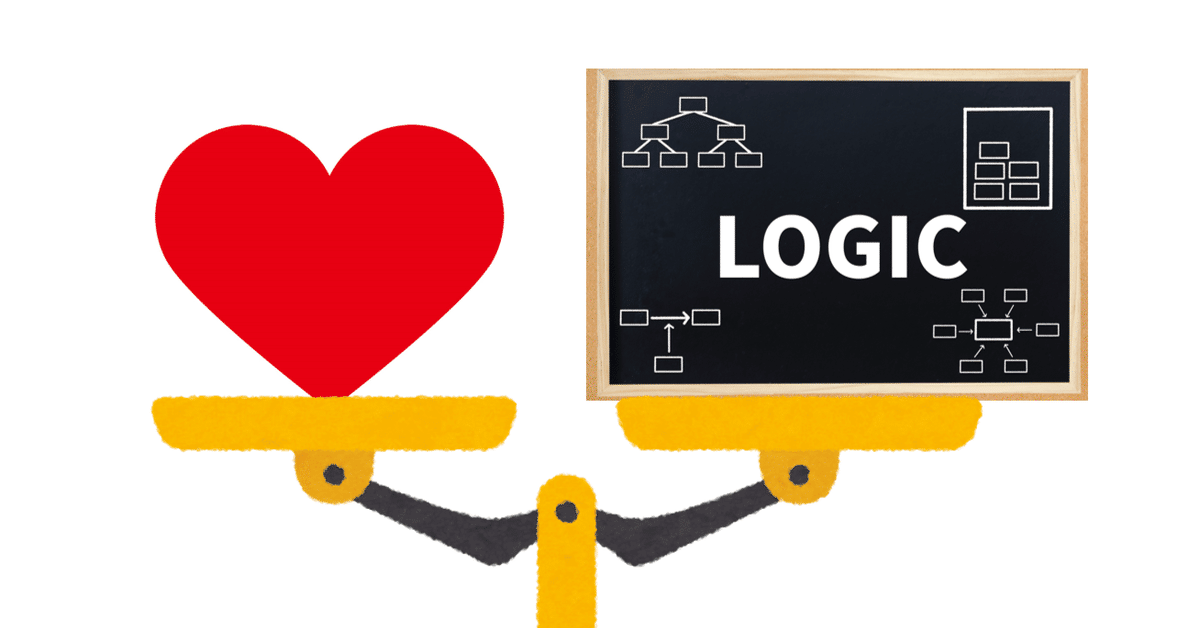
今までに読んだ本の中で一番好きな「あとがき」 『大人のための国語ゼミ』(野矢茂樹著)
今日は、文章を読むあるいは文章を書くうえで、自分にとって一押しの本をご紹介。
日本語の「ことば」の使い方についての本で、何が良いかと聞かれたら、迷わずこの本をあげます。
※Amazon のアソシエイトによる広告を含みます。
野矢先生の本は、むかし初めて「論理トレーニング」を読んだとき、論述式のテスト対策でめちゃくちゃ役に立ったのを覚えています(マスターはできてませんが…)。
※Amazon のアソシエイトによる広告を含みます。
単語や言い回しは自体はすべて知っているはずの「ことば」なのに、うまく解けない。問題が骨太。日本語って簡単そうな言葉でも難しい。
普段着の文章をきちんと読み取り、きちんと伝えるのがいかに難しいかに気づかされ、それをわかりやすく解説してくれます。
そんな中、大人になってから買ったのが、「大人のための国語ゼミ」です。
この本も、問題があって解く形式です。読むだけでもとても勉強になりますが、ちゃんと問題に取り組んだ方が絶対にいいです。
ちゃんとやるとまあまあ時間がかかります。noteを書く時に参考になる問いがたくさんあるとおもいます。
帯には、この本を読むのにおすすめの人が書いてあります。以下のような人。
■ 相手にきちんと伝わるように話せない
■ 文章を読んでも、素早く的確にその内容が捉えられない。
■ わかりやすい文章が書けない
■ 質問に対して的確にこたえられない
■ 議論をしていても話があちこちに飛んで進まない
■ 言われたことに納得できないのだけれどうまく反論できない
*
実は今回、久しぶりに再読しようかなと思い、改めて増補版を買いました。
例えば、昔、私がまんまと間違えたこんな問題があります。
問 次の文章中で不適切な接続表現を一か所指摘し、適切な言い方に訂正せよ。
①肖像画を見ると、モーツァルトは髪をカールさせている。②だが、あの髪はかつらである。③では、どうしてモーツァルトはかつらをかぶっていたのか。④禿げていたからではない。⑤フランス革命以前のヨーロッパでは、かつらが貴族の社交における正装だったのである。⑥そして、フランス革命によって貴族の力が失われてからはかつらもすたれていった。⑦例えば、バッハやモーツァルトはかつらをつけているが、フランス革命以後のシューベルトやショパンはかつらをつけていない。
何番に違和感があるか?だと・・・やっぱり骨太だ。
(ちなみに私はまた間違えました・・・回答はコメントに)
*
そんななか、今回触れたいのは、最後のあとがきである「おわりに」です。
数年ぶりにこの「おわりに」を読み返しましたが、やっぱり、好きな「あとがき」だ、こういう文章が書けるようになりたいというのは、同じ感想でした笑
そのあと、追加されていた付録も良かったです。
本書には、「本書は名文ではない、普段使っている文章の解説だ」という趣旨の記載があります。実際のところ、本書は芸術的な名文ではなく、実生活で伝わるようにするにはどうしたらいいかという意識で書かれている本です。
「ある文章を名文かそうでないかを見分ける自信」は、私にはありません。が、この「おわりに」は間違いなく名文だといいたい。
別に難しいことばが使われているわけでもありません。書いてある内容がすごい意外な内容というわけでもありません。しかし、この本を通して伝えようとしていることについて、無駄な文が一つもなく洗練され、お手本のように綴られています。
わずか4ページの文章ですが、noteを書くときは、この「おわりに」のような文章がかけるようになりたい…(道は遠い…)。
この「おわりに」には何が書いてあるのか?思わず、言いたくなってしまうのですが、中身を言ってしまうわけにもいかない。
そこで、「おわりに」の最初の2文だけ引用します。
私たちは完全には分かりあえない。それはあたりまえのことだ。
このあと、どう文章を展開させますか。
「おわりに」は、この問いに対する見事なお手本です。
より良い文章が書けるようにトレーニングをとおして、論理力と相手の気持ちを考える想像力をさらに働かせて、大人の国語力を高めてみよう、そんな感じです。
ということでちょいと頭を働かせて、「今日一日を最高の一日に」
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
