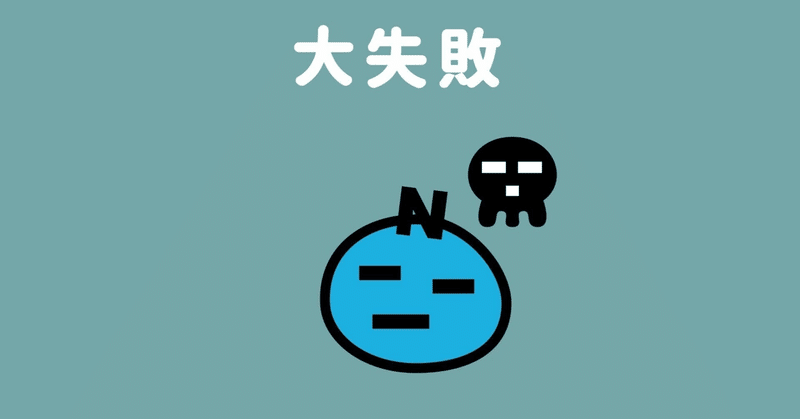
【寺子屋いなふ資料公開】テストの振り返りのお手本公開
テストの振り返りをしろと教師は言うが、実際にどうするのかはおしえてくれないので、
僕が実際にやってることを公開します。
是非参考にしてみて下さい。
大前提 テストの振り返りはかなりエネルギーを使う作業であることを忘れてはいけない。
先生は簡単に口にするし、簡単に生徒に指示を出しますが、
そもそもテストの振り返りは難しいです。
やるべきことが多すぎます。
それを簡単に箇条書きにすると
1 そもそも今回のテストの課題や目標、作戦は何だったかを確認
2 テストの点数を確認
3 自分の試験中のメモを確認
4 ミスの種類を特定(大変)
5 今回のテストの理論値は何点だったのか計算する
6 元々の作戦はうまく機能していたか(点数以上に価値のある結果であるか)
7 ミスの根本的な原因
8 その原因の解決方法
9 次のテストの日程確認
10 次のテストの作戦を立てる
実際の添削を見ながらこれらについてどんなことを話すのか
どんなコメントを先生がしているのかを公開します。
実際の添削したものがこちら。

計算ミスはどれくらいあるのか、落としてはいけない問題をいくつ落としているのか
これらをまずは確認をしています。
そして通常の授業で解説して、練習していた戦略や作戦を試験本番でも正しく使えているのかを確認します。
右下の変化の割合の問題はもともとの授業で解説して練習していた公式を使えてなかったので、
正解したとしても本来の目的を見失っています。
僕は基本的には「1回授業でやったから本番もできるよね」
という指導はせず、この公式についても授業2回か3回で取り扱った問題でもあるので、
作戦をしっかり遂行できれば、それだけで称賛に値しますね。
残念ながらその公式は使ってなかったので、練習不足ですね。
途中式をサボっている場合はしっかり指摘する必要があります。
手抜きで点数を落とすのはテストでは最も避けたい失点なので、
これを「次から気にしましょう」で済ませるのはNGです。
自分で振り返りをする場合も、決して忘れてはいけないミスの一つなので、
可能なら印刷して勉強するときの視界や勉強机の見えるところに置いておきたいですね。
ダイヤのAの小野という控え捕手(わからない人ごめんなさい)のように
自分を戒めるためのものを机に飾るのは大事ですね。
2枚目 半分を残して時間切れになっていたことについて

今回のテストにおいては、「公式を使えば一発でできるネタ」を複数用意して、
それを試験本番で正解させて、平均点を目指すことを狙っていました。
仮に今回テストの点数が前回よりもあがっていて、平均点を取れていたとしても、
なぜうまくいったのかが明確になっていないままなので、
再現性がなく、偶然うまくいった1勝で終わってしまうことが多いのです。
じゃあ前回から点数はどうなったのか
成績推移を簡単にメモしたものがこちらになります。

3年の第1回のテストでは数学は因数分解と展開の基本公式を素早く使って解くためだけに3回か4回の授業を使いました。
その結果しっかりそこで満点を取れたので、点数がかなりあがりました。
しかし、第2回のテストにおいては、その練習のための授業を行わず、
いわゆる広く浅く簡単に点数にできる問題を多く解説しました。
結果戦略は噛み合わず、大問1と2だけで試験時間を全て使ってしまい、
大きく点数を落とす事になりました。
試験前の取り組みとしては学校のワークを数学以外しっかり試験前の土日で終わらせることはできたので、
テストに向けての準備については第1回から大きく成長しています。
ただ、過程よりも結果が重視されるのがテスト。
試験期間にしっかりワークが終わった、というレベルでは
受験シーズンで受験生と戦う上では思うように点数は伸びないということです_(:3 」∠)_
全体的な反省点 先生と生徒の戦略のすり合わせが不十分だと、お互いの狙いが噛み合わない。
そもそも毎回目標点数を決めさせられる生徒は多いのですが、
点数だけ決めてもそのあとの
どうやってその点数を取りに行くのかが決められない限りうまくいきません。
また、今回は平均を狙う上で必要なテクニックに重きを置きましたが、
それ以前の土台や計算力については今回は宿題でカバーするという戦略をとりました。
その宿題をこなすこと、計算力をつけることが土台となっていることが
先生と生徒での温度差がありましたね。
実際の家庭での勉強や宿題の状況というのは基本お祈りゲーでしかない
そこでスタディサプリを活用して管理はしていたのですが、
いかんせんこちらでは演習量が足りず、
予習復習には最適でも、練習をするには問題が足りない、
ということがあげられました。
実際この問題をどのように解決するのかは来年度の寺子屋いなふの課題にはなりますが、
家での演習の宿題もしっかりこちらで確認、把握する仕組みを作るか
そういう管理をするための人材を確保するのか
準備することは多くなりそうです。
このノートがテストの振り返りの参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
このnoteが面白いと思っていただけたなら、
もう一個noteを読んでいただけると幸いです。
今年度指導中の生徒の逆転合格への道
多くの人に読んでほしい
成績の上げ方note
連絡先はこちら
人となりはこんな感じ
https://note.com/online_teacher/n/na105fb032cc4
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
