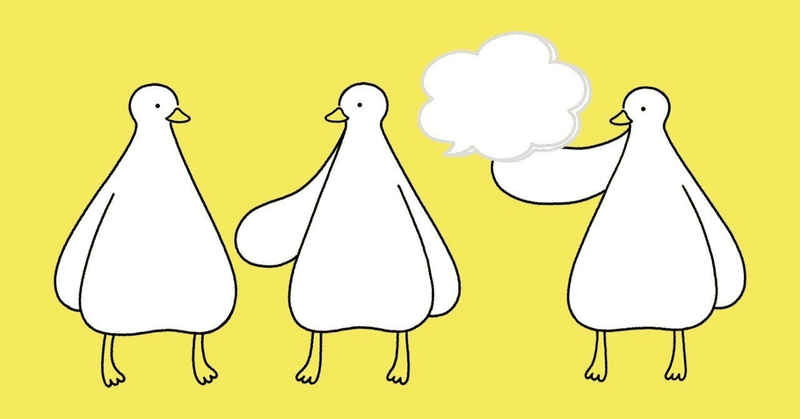
地方では下拵えコミュニケーションが特に欠かせない。てか、そうしないとそもそも動かせないし、動いても食い違うだけ。
前提の「あたりまえ」がズレていると、同じ日本語を使っているはずなのに、食い違うことが死ぬほど起こる。
地方でしごとをしはじめてから、この前提の擦り合わせに凄まじくエネルギーいるよねと気づいた。むしろこの前提を整えることができないと何もできずに、ただただ重なることのない平行線をたどるだけで、その状態だとしごとのクオリティうんぬんすらどうでも良くなってしまう瞬間がある。
たとえば、デザイン。「そもそもデザインって?」「なんで必要なの?」という前提条件をしなければ前に進めないことが多く、「まあデザインって大事だよね」という共通認識があって進んでいく都会のような世界線であれば、スッと業務に進むことができる。それがそうもいかないのが、地方であり、田舎である。
この事業(プロジェクト)において、どんなものがデザインとするのかイメージを丁寧に多世代・多業種の人に共有しながら、はじめるための下拵えのためのコミュニケーションに苦労を要する。わからないものに対して、人は否定し、拒絶しようとしてくるのが常である。ことばの闘い、ここに負けてはいけない。
また、しょうもない定義で「デザイン」がすでに位置付けられており、その前提でよくない方向に進むものがあれば、いったんその前提の修正からはじめなくてはいけない。
都会からきて、地方で「はぁ?」とやたら言ってる人は、ここの下拵えをすっ飛ばして、「なぜ伝わらないのか?」と異文化に悶々として、激昂して、ときにはその地を去る人も少なくない。なまじ日本語が通じるからつらいのだろう。これが違った言語を使う外国であれば、沸き起こる感情も変わったかもしれない。
ちなみに、地方のクリエイティブの単価が低くなりがちなのは、その下拵えコミュニケーションと、その成果による地域全体での共通言語の蓄積がうすいからなんじゃないかとぼくは思っている。
山崎まさよし『セロリ』の冒頭の「育ってきた環境が違うから」ではないが、そりゃあそうだ、地域によって必要とされてきたものの優先順位は違うわけで、「なんで常識が通じないんだ!ふざんけんな」と怒り狂ってもしかたがないわけで、相手の現状の理解から探りながら、今求める意味と現象をいっしょにつくっていくしかない。そうなった場合、「デザイン」という言葉は手放してしまってもいいかもしれない。
自分の「あたりまえ」あるいは自分の物事の判断するときの「前提」を一度疑ってみる。どんなにロジックとして正しいことであっても、相手に噛み合わなければ、視野が狭くなった囚われ野郎であり、価値観の押し付けにしかならない。そうならないためには、相手の関心に関心を持ち「聴く」耳を持つこと、その気遣いひとつがあればいいだけの話ではないか。
都会から来たからといって、偉いわけではない、文化が高いわけでもない。地域や人から学ぼうとしない輩は、相性が良くないんだから、べつに来なくてもいいとすら思う。ちゃんちゃん。
もしも投げ銭もらったら、もっとnoteをつくったり、他の人のnoteを購入するために使わせてもらいます。
