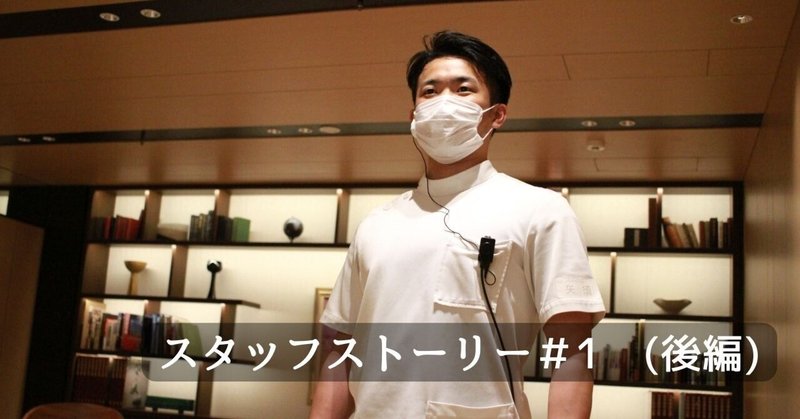
スタッフストーリー#1(後編) / 大切なのは「高級」ではなく「本物」であること
インターンで青梅慶友病院の介護クオリティとホスピタリティに感銘を受けた矢須さんは、大学3年の2月には入職を決意したという。
でも、不安や迷いはなかったのだろうか。
「東京」と「女性ばかり」への不安
入職を決めたあとも不安や迷いはもちろんありました。
まず一つ目は「東京」に馴染めるのかということ。
二つ目は「女性ばかりの職場」でうまくやっていけるだろうかという心配でした。
なにしろ男3兄弟で、ずっと野球部の中で育ってきたので。

でも一つ目の不安は、結果的には余計な心配でした。
青梅はたしかに東京都ですが、熊谷や高崎と変わらないというか、
むしろもっとのんびりしていて。
最初に借りた部屋は2DKで4万3千円、職場まで徒歩5分。
生活環境には何の不満もありません。
では「女性ばかりの職場」についてはどう感じたのだろう。
いまの職場でうまくやれているか、を自分で評価することは難しいですが、可愛がってもらっていると感じることは多いです。
チームにはあらゆる世代のスタッフがいて、年齢も人生経験も本当にさまざまですが、性別や世代の違いがあるから難しい、と感じることはありません。
むしろ温かく見守っていただきながら、のびのびと働かせてもらっています。
それに、同じリビングサポーターの仲間は全員が男性で、決して
「女性ばかりの職場」
ではありませんでした。

どんな企業や組織であっても、その一員となって働きだして初めて知ることもあるというもの。
インタビューでは、青梅慶友病院は高級な病院という世間でのイメージについても言及があった。
矢須さんが入職してから知った青梅慶友病院の姿とはどんなものだろう。
青梅慶友病院は「高級」な病院ではなかった。そうではない。
「高級」ではなく「本物」にこだわるんだ、と。
今日の「コーヒーの会」もまさにその考えがベースにあります。
「高価」なコーヒーを提供することが大切なのではなく、「本物」を提供すること。
香りや音、目に映る光景も含めた本物の雰囲気を楽しんでもらうんだ、と。
そのために手間をかけることを、この病院は「それでいい」と認めてくれるし、どんどんやりなさいと背中を押してくれる。
逆に安易な「この程度でいいだろう」という発想には、本当に?それでいいの?と問いただされます。
この点は甘くないです。

同世代の仲間が増えてくれたら嬉しい
どんな職場であっても、良いところばかりではない。
これはちょっと大変だなとか、これはつらいな、という面は必ずある。
それを聞かせてほしいと質問をすると、矢須さんはしばし悩んだ末に答えてくれた。
例えば私たちの仕事というのは日曜祝日でも出勤の日があります。
シフト勤務なので、年末年始やゴールデンウィークでも交代しながらの勤務になったりします。
もちろん休日に働いた分は平日に休みが取れるので、リズムに慣れてしまえばなんてことないのですが、日曜日や祝日は必ず休みたい、年末年始やゴールデンウィークは全て休みたい、という人には難しい仕事だと思います。
逆に平日休みが好きな人、空いている時にスノーボードを楽しみたいとか、平日の安い時期に旅行へ行きたいという人にはピッタリだと思います。
連続休暇制度もありますし、育休を取得する男性職員もいる。
当たり前かもしれませんが、「休暇制度」が存在するだけでなく、きちんと
利用できるというのは、青梅慶友病院の「働きやすい」理由の一つだと思います。

もうひとつ私にとってのマイナスポイントをあげるなら、同世代のスタッフがあまり多くない、ということ。
先輩のサポートは十分すぎるくらいもらっていますが、もう少し同世代や後輩が増えたら、さらに楽しいかなと思います。
確かに病院のような職場では休日だからみんなで休む、という訳にはいかない。
シフト勤務はこの業界の宿命でもある。
それでも「働きやすい」と感じることの方が圧倒的に多いと矢須さんは言う。
些細なことですが、勤務時間がきっちり決まっているというのは気に入っています。
ムダに早く出勤したり、終業後もダラダラ残ったり、そういう文化がまったくないので。
希望すれば朝や夕方の食事介助に入らせてもらうこともできますが、それがなければ9時から17時30分が勤務時間。
自由に使える時間がたくさんあるというのは嬉しいです。
朝、出勤前にジムへ行ってトレーニングすることもありますよ。

自分のまま働ける
青梅慶友病院の良さは「自分のままでいい」ということです。
この病院はすごいところ、というイメージが先行して、最初は自分もそれに合わせて生まれ変わらないと、なんて考えてしまいそうになりましたが、そういうことではないんですよね。
自分の人格を変えて、別の誰かになって働く必要はない。
自分を磨く意識はもちろん大切ですが、無理難題を押し付けられて人格が変わってしまうようなことはありません。
自分のできることの中から、青梅慶友病院に貢献できるものを探せばいい、
と考えています。
矢須さんは姿勢がいい。
人と話すときには背筋を伸ばし、しっかり相手の顔を見てハキハキ言葉を発する。
小学3年生のころから介護の仕事を目指していた、というエピソードも含め、これは採用面接じゃないからリラックスして正直に本音を話してくれていいと水を向けても、「自分はこういう人間なんです」と笑顔で答えてくれた。
そんな矢須さんに、最後は少し意地悪な質問をしてみた。
ここで働いて一番の失敗談は?と
すると矢須さんの顔が少しだけ曇ったのちに、恥ずかしい話ですがと前置きをして口を開いてくれた。
勘違いをしていたことですかね。
自分は介護の仕事に対して、誰よりも熱い思いを持っていると。
正直に告白しますが、入職して間もない頃、周りのスタッフに対して介護への熱量が低いと感じる場面があったんです。
自分は小学生の頃からの夢をかなえて高揚していたのでしょう。
「そんなんじゃだめだ」と心の中で思っていました。
自分のやり方が正しいんだ、と。
いま振り返ると、独りよがりで恥ずかしい限りですけど、当たり前のことを淡々とこなす強さ、地に足をつけて働くことの価値を理解していなかったんだと思います。
青梅慶友病院ではさまざまな職員が働いている。
就職直前まで「自分が病院で働くとは思っていなかった」
「介護には縁がないと思っていた」というスタッフも多い。
一方で矢須さんのように、ずっと介護の仕事がしたかったというケースもある。
その熱量やスタンスは人それぞれ。
でも、その一人一人思いが違う職員が青梅慶友病院という一つの船に乗り
それぞれのやり方で船を動かす、そのおもしろさに「ようやく気づけました」と矢須さんは語った。


