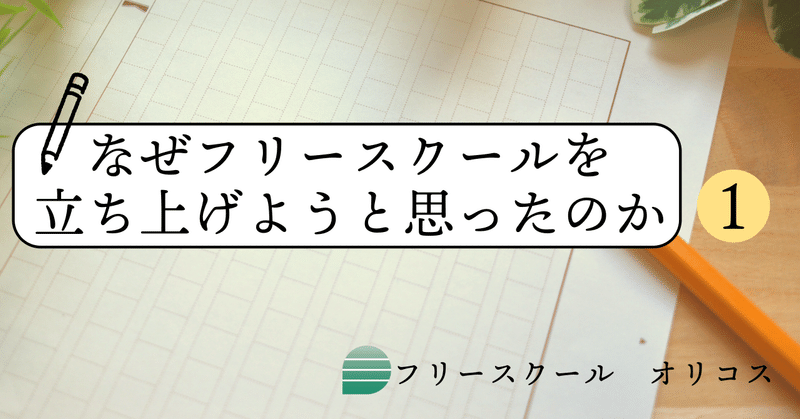
フリースクールを立ち上げようと思ったきっかけ(1)
フリースクールを作ろうと思ったきっかけがいくつかあります。
そのことを知ってもらうことで、より私やオリコスのことを理解いただけると思い、noteに書いてみることにしました。
今回はその一つです。
教員時代に出会ったある親子
教員時代に不登校のある女の子を担任することになりました。
(個人が特定出来ないように、創作した部分があります)
この家庭は、母、女の子(小3)、祖母の3人暮らしでした。
元夫のDVなどが原因で離婚し、実家に帰ってきたようです。
世帯の収入の多くは祖母の収入でした。
元夫からの養育費は支払われていなかったようです。
母は離婚のこともあり、診断があったかはわかりませんが、鬱の症状があったのではないかと思います。
そのため定職についておらず、バイトをしても長く続かずに転々としていました。
そんなとき女の子が不登校となり、母は仕事をあきらめ、経済面は本格的に祖母頼みになりました。
私がこの子を担任したときはすでに不登校で、学校には来ていませんでした。
適応指導教室に行ったことはあるものの、初回のみで、以後行くことができなかったようです。
このときにはすでに、文科省から
不登校児童生徒への支援は,「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。また,児童生徒によっては,不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で,学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。
といった見解を示していて、学校としても一昔前までの無理矢理学校に連れてくるような指導はしていませんでした。
私としても家庭への事務連絡はするものの、自分の子ども(2人います。1人は医療的ケアと障がいがあります)のこともあり、「放課後にその子と遊ぶなりして信頼関係を作る時間はとるべき」などと思っていても実行しませんでした。(この時の罪悪感もフリースクール立ち上げのきっかけの一つかもしれません)
そんな日々が続いていたある日、その子の祖母が他界します。
「この家庭は生活していけるのか?」
そんなことが頭によぎりました。
配慮に欠けていたかもしれませんが、遺族年金のことや生活保護のことなど調べたことを情報提供しつつ、様子を見に家庭訪問をするようにしていました。
母は、生活保護は絶対嫌だと言い、仕事をしなければならないと考えていたそうです。
しかし、娘が家にいることで仕事ができないと話してくれました。
結局、不登校をそのままにしていいはずがないことに私はやっと気づくことになったのです。
そこからは、家庭訪問や楽しんでもらえそうな学級イベントなどを積極的に行うなどして、学校に来てもらえるように努力しました。
公教育への疑問
結果として、何とか学年の終盤に学校に来るようになったのでよかったのですが、ここから公教育全体としての不登校に対する姿勢に疑問を抱くようになります。
先の通知で
「不登校児童・生徒への支援は〜児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要がある」
と言いながら、不登校を毎年確実に作り出す学校の在り方や年齢とともに自動的に学年が上がってしまい、やり直しが実質的にできない構造など、そもそも社会的に自立することを阻害しているのは公教育ではないか、ということ。
「不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある」
などと言って、不登校の子どもがいる家庭の状況を半ば放置することで、休養どころか、先に挙げた構造的な問題から、時間とともに追い詰められてしまう場合があること。
これら以外にも疑問に思うことはありますが、簡単に言えば、「不登校にしておいて無責任」だと感じるようになったのです。
そして、結局自分もそうではないか、という自責の念とも不甲斐なさともいえる感情を抱くようになりました。
他にもきっかけとなったことがあります。
それはまたの機会に投稿しようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
