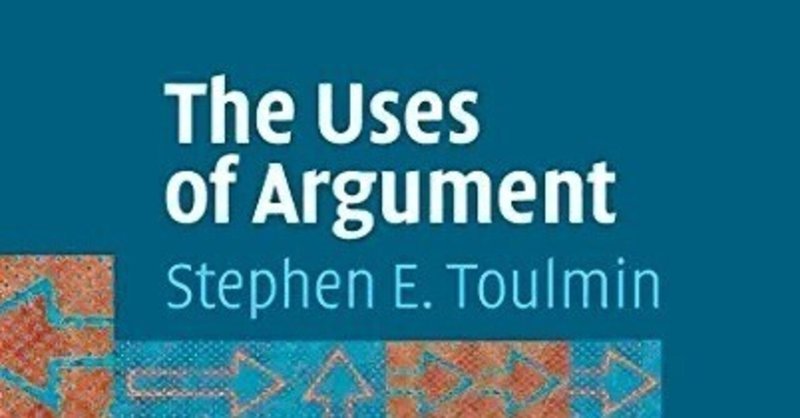
Reflections on The Uses of Argument『論述の技法』省察録(4)
第4回
Preface to the Updated Edition vii頁より
さて、2002年に『論述の技法』がアップデートされたときに、トゥールミンが書いた前書きをこれから読んでいく。これはいわゆる達意の英文で書かれているので、じっくりと楽しんで読解をすすめていきたい。
厳密な形式的論理学の方法でなくても主張claimの正しさを読み手に説得出来るとするトゥールミンの方法は、有効性基準(validity)の分野依存性(field-dependent)の提案と言われることは前回説明したが、これは状況限定的に理性的に自分の主張の正しさを相手に対して説得する文章を書く作業と言い換えることが出来る。なんだかすごく大げさな表現になったが、論述を駆使して語るとは、こういうことなのだ。そして、そのときには、自分が文章を通して読者に語るディスコースを生み出すことが出来ている。自分の文章によって他者に対して自己の主張の正しさを説得できる。これが論述であり、アリストテレスが「修辞学の目的は説得である」と呼ぶところのものだ。議論を先取りしておくと、アリストテレスの論文術の目的「説得」は良いがそのために用いる方法である演繹的モデルの三段論法はいかがなものか、というのが『論述の技法』の大きなテーマであり、それに変わる方法をトゥールミンは考え出していて、それを活用して論述をおこなうディスコース つくることが、論文を書くための第一歩となる。
この態度もつ文章を新たに作り出すことは、なれないとちょっと難しいので、トゥールミン自身の考え方をディスコースとして英語で今回は分析してみたい。The Uses of Argument Updated Edition はこう始まる。
Books are like children. They leave home, make new friends, but rarely call home, even collect. You find out what they have been up to only by chance. A man at a party turns out to be one of those new friends. ‘So you are George’s father?- Imagine that!’
So has been the relation between The Uses of Argument and its author. When I wrote it, my aim was strictly philosophical: to criticize the assumption, made by most Anglo-American academic philosophers, that any significant argument can be put in formal terms: not just as a syllogism, since for Aristotle himself any inference can be call a ‘syllogism’ or ‘linking of statements’, but a rigidly demonstrative deduction of the kind to be found in Euclidean geometry. Thus was created the Platonic tradition that, some two millennia later, was revived by Rene Descartes. Readers of Cosmopolis, or my more recent Return to Reason, will be familiar with this general view of mine.
ここには語り得なかったことnon discursive(ディスコースにならなかったこと)をdiscursive(語り得るものにする)にするdiscourseがある。つまりトゥールミン モデルを使って普遍主義に向かってしまっている学術研究論文の閉塞状態をのりこえることができるようにこの本を書いたとある。語り得ないものを語り得るものとして読み取り、それを文章として構成できるか、が実は論述の仕組みで文章を書くことができるか、であり、ここに、現代の学術論文を書くときに技法として覚えなくてはいけないことがある。これを覚えれば、自分の視点からディスコースを組み立てていく、つまりは自分の文体を獲得するという論文の書き方を学ぶことが出来る。そうなれるかどうかが、プロとしての思索家になれるかどうかの分水嶺になるのだ。この文章を細かく見ていこう。トゥールミンディスコースはこうである。
Books are like children. They leave home, make new friends, but rarely call home, even collect.
本とは子供のようなものであり、家をでて、新しい友達をつくるが、家には電話をすることはない。コレクトでいいといっても電話をかけてこない。
You find out what they have been up to only by chance. A man at a party turns out to be one of those new friends. ‘So you are George’s father?- Imagine that!’
(そんなわけで)本がどのような読者(友達)を得ていたかは偶然にしかわからない。パーティであった男がたまたま僕の本の読者(子供としての本が自分の知らないところで作った友達)だったりする。そして「あなたがジョージ(息子つまりは僕が書いた本)のお父さん(著者)ですか、なるほど」となるわけである。
So has been the relation between The Uses of Argument and its author.
僕が書いた本である『論述の技法』と著者である私の関係も同じだ。
When I wrote it, my aim was strictly philosophical
この本を書いたときに、私の(執筆の)狙いは厳密に哲学的なものであった。
to criticize the assumption, made by most Anglo-American academic philosophers,
つまり、アングロサクソンのアカデミックな哲学者(大学で教えている哲学者)のほとんどが共有している仮定(assumption)を批判しようとした
that any significant argument can be put in formal terms:
その仮説とは意味のある論述は形式的な言葉で表現できる、というものであり、
not just as a syllogism,
それは三段論法としてだけではない。
since for Aristotle himself any inference can be call a ‘syllogism’ or ‘linking of statements’,
なぜならアリストテレスにとって、意味のある推論 inferenceはすべて三段論法つまり言明statementの連鎖と説明されているが、
but a rigidly demonstrative deduction of the kind to be found in Euclidean geometry.
とはいっても、厳密に演繹が出来る事例としてはユークリッド幾何学のようなものしかなかった。
Thus was created the Platonic tradition that,
そして(このようなちんけな理屈が)、これがプラトン的伝統(意味のあることは演繹的思考で生み出せる)をつくった。
ちょっと英語の説明。このThusの意味は websterをみると、
because of this or that : HENCE, CONSEQUENTLY
である。つまりこのため、またはそのために: HENCE, CONSEQUENTLY
という意味で、三角定規の理屈(ユークリッド幾何学)みたいなものがプラトンの演繹思考の背後にはあるんだよ、えらいめいわくだなあ、
という感じのディスコースである。
some two millennia later, was revived by Rene Descartes.
そして二千年後にデカルトがプラトン的伝統を復活させた。
Readers of Cosmopolis, or my more recent Return to Reason, will be familiar with this general view of mine.
僕の本であるCosmopolisとかReturn to Reasonの読者であれば僕のこの見方は知っていると思う。
しかし現状では・・・と続いていく。
哲学者としてのトゥールミンの仕事は前にも紹介したが、翻訳があり、それなりに読まれている。
これが、ここでのディスコースである。自分の息子ジョージ(レイアウト論述図)の話からアリストテレスに飛びプラトンを批判して、自分の本の狙いをかたる。ここを理解すると、『論述の技法』The Uses of Argumentのなかでトゥールミンが語っている論述という方法への思いがわかるだろう。このように自分の視点を語ることでディスコースを作る。それはここでみるようにトゥールミンの文体でもある。何かを語るときにかたりえるためにはディスコースが必要で、そして自分のディスコースは「自分の文体」によってのみ語りうることが出来る。このように論述とディスコースは深くかかわりあい、一つの文体を形成する。つまりディスコースを確立して、論述の仕組みを使って自己の文体を確立していく。これが論文を書く時に必要な最初の能力であり、論文を完成させるための最後の能力でもあるのだ。論述とディスコースが交錯するとこで自分の文体が生まれる。トゥールミンはこれを応用論理学と呼んだ。文体が生まれるときだからだ。
さて、このディスコースから解ることは、トゥールミンの『論述の技法』は作文の方法として広く世の中に行き渡った。英語圏のみならず日本でも作文の方法としてのトゥールミンの方法は広く知られている。練習本が日本語でもある。claim:主、grounds:根拠、warrant:ワラント、qualifier:クオリファイヤ, rebuttal:反論, backing:裏付け の空欄ボックスがあり、それをうめて論理的な文章を書こう、とやさしく表現される。critical writingとかcritical thinkingとか呼ばれたりする。これがアップデート版の前書きに登場する「息子のジョージ」である。彼が「レイアウト論述」君だが、それだけではトゥールミンの考えていた新しい論理学にはならない。
たしかに、現在、学術論文を書くときにはトゥールミン論述レイアウトモデル(the “layout arguments”)を理解して、書き始める。だが、論文は論述の図式だけでは書けない。さまざまな事柄を記述しながら自分の論述が読者に受け入れられるように工夫する必要がある。そのためには、レイアウト論述図式を形式的に従うのではなく、主張を巡る様々な事柄を丁寧に説明する必要がある。そしてそれはディスコースとしてあらわれる。
ここで注目するのは文体である。argumentと、それ以外の修辞学の技法を組み合わせて、文章をそれでね、それでね、という語り口でつなぐ中で文体が生まれてくる。論文を指導していて、データの少なさを指摘すると「もっと具体的に書くのですか」となるし、warrantの欠如を指摘すると「抽象的に書くのですか」となる。そして「証拠はこれです」といきなり提示をする。このような書き方をやめよう、というのがトゥールミンの主張である。確かに、サイエンスやエンジニアリングの勉強をして論文を書く場合、どのような形で論文を書くべきなのかの形式がきちんと決まっている。そしてそれは、一応論述の形をとっている。たとえば、木下 是雄氏の『理科系の作文技術』を始めとする一連の著作で展開している方法にしたがって作文すれば「いい論文」となる。だが、これでは現代の学術論文を書くことは出来ない。こうした演繹的思考ではそもそも学問は出来ない、とトゥールミンは主張しているのだ。
現在の学問は論理実証主義科学哲学と仮説演繹法、そして反証性の影響の強い考え方つまり認識論に縛られており、学術論文を狭く捉えているからである。科学哲学ではそもそも論文において何をどのように論じたら正しいのだろうかの問題を考える時に基本となるのは論理学としてきた。特に記号論理学において「真である」とされればその論述は正しいとする、という考えを確立した。だが、論理的に正しく考える手順を守って文章を書いたところで、つまり演繹的に文章をかいたところで、自分の主張が正しいと相手を説得できるのか、の問題は解決しない。普通に考えれば論理的でなければ議論の場から退場である。だがclaimの正しさは論理学的な判断だけだろうか? 論理的に詰め切ってもそこにはなにも語ることはないと退場してしまった前期ウィトゲンシュタインのあと、論理学者はどの様に思考すればいいのか。
記号論理学を構築して捨て去ったウィトゲンシュタインの影が見えている我々はどうか? 不変な真実への懐疑はあるが、それでも普遍的真実をもとめるという視点で文章を書こうとしているのではないか。また世の中の流れもどこかで普遍的真実をもとめている。だが話は簡単ではない。
トゥールミン の議論は発表された当初はまったく評判にならなかったが、1970年代後半くらいから人文科学社会科学で使われ始めてまた作文術としても高校中学のみならず小学校高学年の授業でも使われるほど普及した。彼のThe Uses of Argumentが述べたことは、claimを正しいとする仕組みは論理学あるいは記号論理学が述べている真偽を決定する分析的な方法ではないということである。思弁を駆使した(つまり、データと論理で状況を理解し説明する作業を何度も繰り返した)論文を書くことに挑戦した人間であれば、科学的な論文執筆方法が現代の複雑な学問領域では上手に適応できないと感じているはずだ。このようなときに、トゥールミン モデルという非形式的な論理「学」を使えばargumentが可能になる瞬間を見つけることが出来る。そして、そこが分かると、論文はデータを整理して論理的にならべればいい、という自然科学的なそして社会科学でも主流になっているようにみえる仮説演繹法とその背後の抽象的で行動に形式的な論理学に依存する議論には納得がいかなくなるはずだ。そこから魅力ある研究は始まる。
トゥールミンが主張したのは日常的に行われる議論を評価するのは論理学が示すような演繹的思考ではない、ということである。評価されるのは データがwarrantを構成できたときだとするのだ。それは与えられた状況の中で議論を正当化(justification)するという方法である。それほど複雑な論理的な構造を持っているわけではない。warrantとは論理学が物事を正しいとする演繹とは別の普遍的真実を保証する論理学に代わる方法ではないのだ。非常にささいな状況に依存した、しかし整理された考え方なのである。ウィトゲンシュタインは思索を停止して、普遍的論理の構築から撤退した。この先がトゥールミンの行ったことである。デカルトやガリレオにはじまる近代科学だけが科学ではない。現在の科学が立脚する形式的な論理学でディスコースが構築できなければ、沈黙し、ほかの方法でディスコースが成立するなら、そこにwarrantを構成する。それに成功すれば、claimを正しいと評価する論述が成立する、と考えたのだ。さすがに1950年代にこの主張をしたら、当時のイギリス経験論から出発した科学主義をよしとする論理学者は、これを無視するな、と筆者でも思う。だが、その後時代はこうした科学主義の限界に直面していく。
次回は、演繹的推論を否定して新しいワラント型推論を提唱することを意気込んだ『論述の技法』出版の1958年に書いたトゥールミンの前書きを読んでみよう。なかなか声高に激しい主張を述べている。
まとめ
論述の技法はレイアウト論述法ともう一つあり、その新しい推論についてちまたの論述の方法を議論するハウツゥ本は紹介していない。なので現代の論文執筆には役立たない。「応用論理学」が必要となる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
