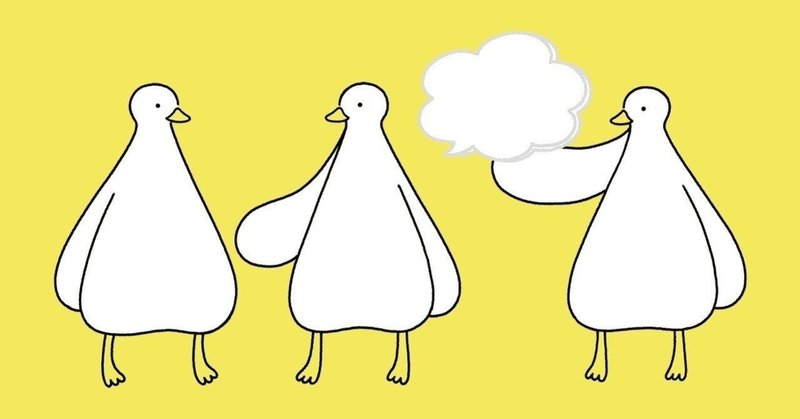
「話を引き出す」は怖くて使えない
話を引き出す、という言い回しはよく聞きます。でも私はこの言葉をあまり使わないというか、自分に当てはめて使うのはちょっと怖いと感じます。
なぜ使わないかというと、たぶん自分が使われる立場になるのが嫌だから。たとえば自分が話を聞かれる側になっていろいろ話した後、相手のライターさんが記事を掲げて「この話は私が引き出しました」と言われたら、まあかなり嫌な気持ちになるんじゃないかと想像します。
なぜなら、取材の現場では話し手のほうも「ちゃんと話せるかな」とか「こんな答えで大丈夫かな」というのを絶対に一生懸命考えながら答えています。聞きに来る人ができるだけ答えを持ち帰ることができるように気を遣っている人がほとんどです。
場合によっては聞き方が下手くそなライターの意図を忖度して、「ああこういうことを聞きたいのかな」と先回りして答えていることだってあります。そういったお互いの工夫で成り立った話やエピソードのはずなのに「私が引き出しました」と言っていいのかどうかはいつも疑問なんですよね。
* * *
辛辣な言い方をしましたが、この下手くそなライターが自分自身である可能性も大いにあります。うまくいった現場は決して自分だけの力で作り上げたわけではない。
人が話をしてくれるプロセスを分解すると、気持ちや行為にはステップがあります。まず相手がそこに関係する話を思い出してくれること、話そうという気持ちになってくれること、実際に話してくれること。これらのいくつかのステップで協力というかご厚意がないと実現しません。
話し手は別に話したくなければ話さなくていいし、質問をスルーしても構わない。話そうと思ってもらえたのであれば、それは相手のご厚意以外の何物でもないです。
取材はもともと私たちが持っていない情報を勝手にくださいと頼みに言っているようなもので、相手が「シェアしよう」と思ってもらわなければ話にならない。だから「引き出す」というのではなくて、どちらかというと「教えてもらう、思い出してもらう」という言葉のほうが近いと思います。
それを無しにして「自分が引き出しました」とか「私には話を引き出す力があります」と言い切るのは結構勇気が要ると思うんですよねえ。
* * *
もちろん能力がある人は、文字通り引き出せる確率が高いとは思います。でも理論上、相手の協力がゼロで自分の力が100という現場はあり得ません。
ライターの経歴などで「人の話を引き出すのが得意です」という言い回しはよく見かけるし、もう一般的なので特定の誰かという話では全然ないのですが、これまで自分が取材する話し手の方が親切だった、という視点は忘れちゃいけないんじゃないか。引き出したのではなくて、あたかも引き出したように相手が気遣って花を持たせてくれた現場も実はたくさんあるんじゃないか。
それを無視して聞き手のスキルや手柄のように扱うのはとても危険だし、私にはその勇気はないです。やっぱり怖い。
よろしければサポートお願いします!いただいたお金はnote内での記事購入やクリエイターとしての活動費にあてさせていただきます。
