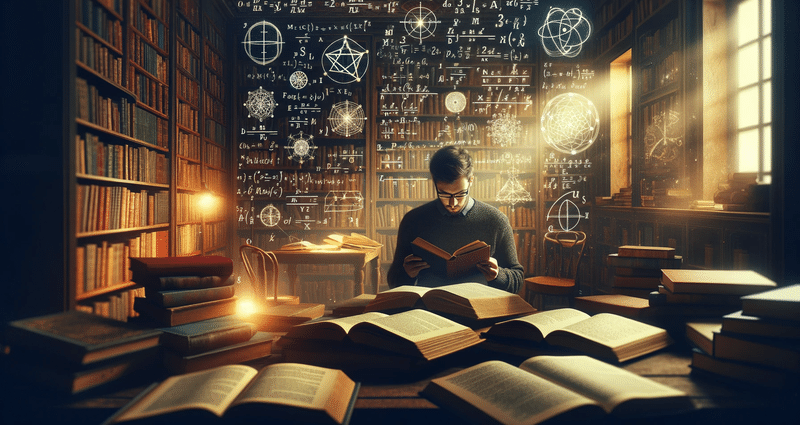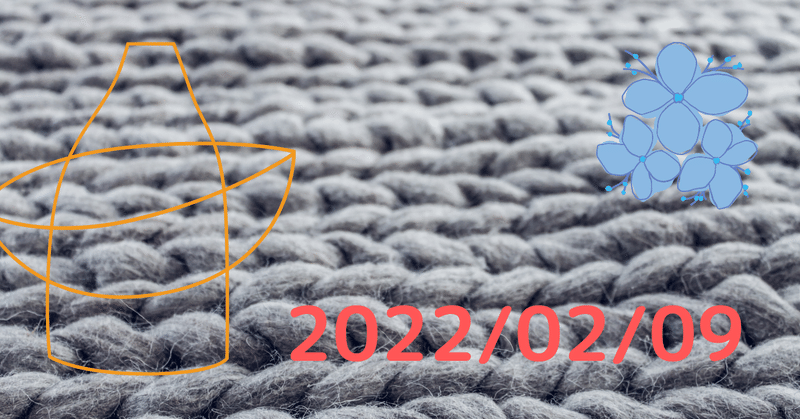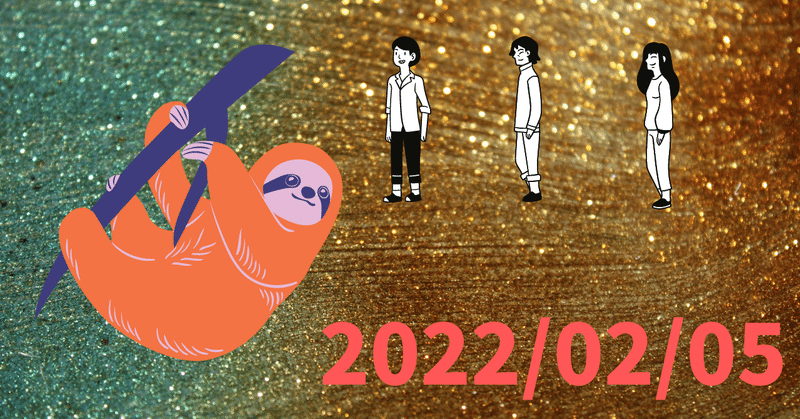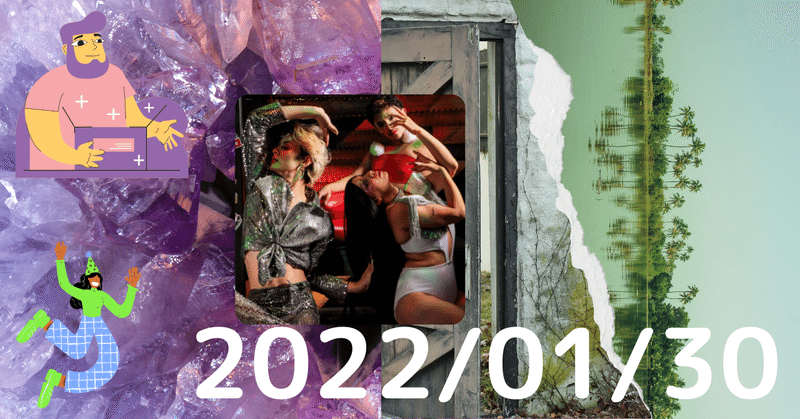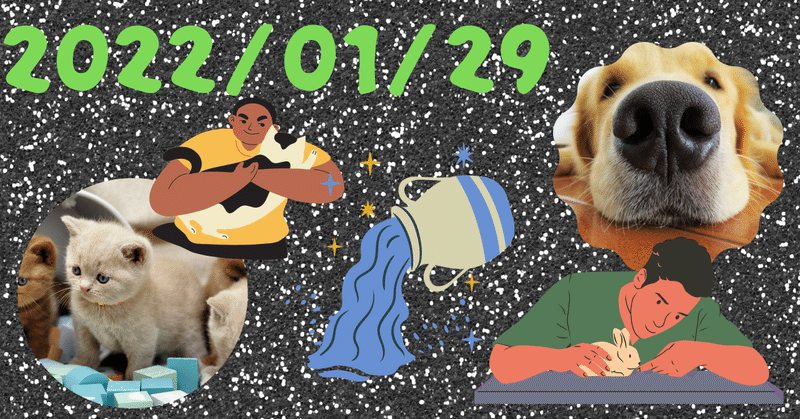#おじさん小学生
おじさん小学生の読書メモ35回目
久々に「森の生活」を読むと、面白い感想を抱くことができる。
ソローは俗世の人々の無駄と非効率を嘆いて、その根拠を理路整然と述べているが、実は恐るべきことに、その大衆の愚かさ、間違い、放蕩こそが、人類により巨大な豊穣をもたらすものであるのだ。ということを見抜いていない(意図的に無視しているにしては感情的すぎる)
こういうことは、自分もまた陥りやすい罠を表している。他人の愚かさには、それなりの由来
おじさん小学生の読書メモ34回目
最近は絵を描くことについて考える時間が増えている
だいぶ前に地元の本屋で見つけたハウツー本を、ちゃんと読み始めた。著者が自分の作品についての苦悩や逡巡を、技法の解説と並列して内容として提示していたことが興味深く、ひとつ自分の中で確信しつつあることがある。
言語、論理、あるいはそのように呼ばれるものの使役は「鍵」そのものではない。でありながら「錠」を開けることができる場合がある。つまり「鍵開け道
おじさん小学生の読書メモ32回目
今日はちょっと番外編というか、図書館の本じゃなくて人に教えてもらった論文みたいのを読んでいます。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshuppan/38/0/38_107/_pdf
「メディア倫理学」というものを提唱したクリフォード・クリスチャンという人について書かれたもので、国際的に多様化しているはずの、国家というコミュニティそれぞれにおけるメディア
おじさん小学生の読書メモ31回目
ひさしぶりに万葉集鑑賞事典を読む。「久にあらなくに(そんなに時間が経ってもいないのに)」は普段使いしたい古語だなと思った。
以前にも同じことを思った表現がなかったか?たしか「よくもまあそんなに無神経に質問することができますよね!?」みたいな古語…
と思って、鑑賞事典をパラパラめくっても見つからない。手元の読書メモはゴチャゴチャしてて見返す気にもならない。それでnoteに書いた記憶を手がかりに、
おじさん小学生の読書メモ29回目
「武器としての資本論」を読んで、とにかく同じことについて色んな人の話を聞くというのはいいなと思った。佐藤優の対談シリーズや「超入門」、「父が娘に語る経済の話」の中で共通して語られる資本主義社会の起源やフランシス・フクヤマの「歴史の終わり」議論、冷戦の終結、そういう話を「思い出す」ことができることの嬉しさがある(こういうのって俺だけなんですか?)
哲学人文系を読むことの快楽もそこにあって、たとえば
おじさん小学生の読書メモ27回目
最近はドゥルーズに関する二つの本を読んでいるよ
ヒュームについて論じるところから始まったドゥルーズの哲学は、次々と先人の哲学の「襞」を開いていく。その危うさと狂気の肯定(あるいは前提)、カント以降の超越論が問題にしなかった部分に一貫して取り組む超越論的経験論というあり方…ムズいわ!!!
読んでいる時はなるほどと思っても、どういう本なのかを説明しようとするとできないということは、理解を司る6要素
おじさん小学生の読書メモ26回目
図書館がまた始まったので、さっそく毎月恒例の「10冊借りて読めずに返す」をやることにした。今回から借りた本を記録しておく。
また借りた。例のごとく期間が空いてしまったので最初から読む。
こういう副読本ばかりが読み進んでしまう。とはいえ、今回のこの本や、前回借りたコレみたいに、「思想としてではなく、現代資本主義社会を生き抜くための資本論」みたいなアプローチは、自分向けではないな。と思ってしまう。
おじさん小学生の読書メモ25回目
今日はバテてます昨日色々と根詰めて作業した反動で、今日はほとんど本を読めず「世界文学全集48伊藤整 編 世界近代詩十人集」を最初から眺める程度だった。
ハイネから始まるこの全集は伊藤整の編集によるもので、元々は文学全集だったものが、地元のBOOK OFFに1冊だけで105円で売っていた。
それがなかなかどうして面白い。当時の言葉づかいなのか、異国の詩を日本語らしく七五調に翻訳している様子からは
おじさん小学生の読書メモ23回目
遅く起きたが、当初の予定通り読書からルーチンを始めた。読書メモを投稿できそうな感じになるまで読む。
哲学を存在論から価値(倫理)論に転換させようとしたレヴィナスどうやらそういうことらしい。他なるものとの関わり合いについて「享受」と「労働」、「所有」という言葉を使って語っている。「道具」におけるハイデガーとの対比、昨日のエレメントと合わせて簡単な図示ができそうな気がしつつ、もうちょっとちゃんと理解
おじさん小学生の読書メモ21回目
今日は読む本をあらかじめ決めてみたが、まあ案の定、就寝前にパラパラと見る程度である。
「熊楠原論」面白すぎて、逆に警戒してしまう。この在野の人(著者)は、どうしてこれだけの著作を出して、その分野に大きく取り上げられていないのだろう?アカデミックの精査(きっとありますよね?)に耐えられない内容なのか?そのあたりの知識がまったくない。
同様に「儀式論」も、学徒によるものではなくて社長さんの書いた本
おじさん小学生の読書メモ19回目
やっと本を読める感じになってきた。
「シリーズ哲学のエッセンス ベルクソン」読んだことがあるような気がする瞬間が何度もあったので、たぶん読んだことがあるのだろう。西田幾多郎や現象学の本を読んだあとだと、フック(意識に引っかかる部分)が増えていた気がする。同じ本を何度でも読んでもいいという気持ちになってきたのは、最近のことかもしれない。
帯広図書館のおすすめコーナーにあった「熊楠原論」かなり良さ
おじさん小学生の読書メモ18回目
やっと躁転したぞ〜
前回のnoteに書いた贈与論の内容紹介企画は、休み休みではあるけど続いている。
資本論(佐々木隆治)も週一の発表があるのでなんとか読んでいる。読書はそれくらいだな。
本が読めると嬉しい。人生において、たびたび「匂いを嗅ぎ分ける」ことができない場面がある。人の書いたものに心を動かされた経験は、その手がかりになることが多い。
行動することを後押しするものは、行動ではない。行