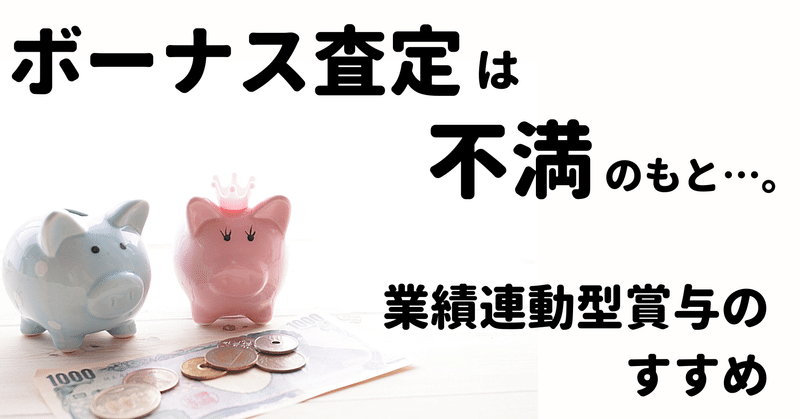
ボーナス査定は不満のもと…?人事評価と連動した賞与査定のすすめ
年末が近づくにつれ、話題になるのが「ボーナス(賞与)」の話。
あなたの企業では、ボーナス査定をどのようにして行っていますか?
給与の〇〇ヶ月分の賞与支給といった、定額支給を約束している企業もあれば、業績や成果に応じて賞与額に変動がある企業もあります。
一見、〇〇ヶ月もらえるといったボーナスの定額化は、従業員にとって安定をもたらし、モチベーションの向上に繋がるように思われがちです。
しかし、実際はこのボーナス定額化が、従業員の不満を生み出してしまう恐れもあるということをご存知ですか?
今回は、このボーナス(賞与)査定と従業員のモチベーション管理について説明していきます。
給与連動型賞与とは
まず、賞与支給額の選定方法には大きく分けて2種類あります。
その一つが、「給与連動型賞与」です。
給与連動型賞与とは、基本給をベースに、全従業員に対して一律で〇〇ヶ月分を支給するといった形で支給額を決定する方法です。
では、給与連動型賞与にはどのようなメリット・デメリットがあるのか整理していきましょう。
メリット
・従業員は毎回安定した賞与を獲得できる。
・賞与額が一定であることから、査定の手間が省ける。
デメリット
・個人の業務貢献度が賞与額に反映されない。
・賞与が従業員のモチベーションを引き上げる役目をもたない。
・業績が芳しくないときでも、全従業員に一定額の賞与支給をする必要がある。
従業員としては、毎回ある一定額は支給されるという安心感は得られるでしょう。
その一方で、普段から人一倍熱心に業務に取り組み、成果を出している従業員にとっては、その頑張りを賞与では還元してもらえません。
どれだけ成果を出そうが出さまいが、賞与額に変動がないことは、頑張っている従業員にとってはマイナスになりうるということが、注意点です。
業績連動型賞与とは
もう一つの賞与査定方法は、「業績連動型賞与」です。
業績連動型賞与では、企業業績や個人業績に連動させて賞与額を算出していきます。賞与原資が確定後、各個人の業績や成果に合わせて賞与を割り振っていきますが、このときの個人業績と賞与を連動させる基準は明確にしておく必要があります。
では、業績連動型賞与におけるメリット・デメリットについて整理していきます。
メリット
・個人の業績が賞与に反映されるため、モチベーション向上につながる。
・従業員に対して、経営状況や業績、賞与査定基準の透明化が図れる。
・全ての従業員に一定額支給する必要がなくなるので、無駄な人件費の削減につながる。
デメリット
・業績が下がった場合、賞与ゼロになってしまう恐れがある。
・賞与額の変動が大きくなると、従業員に不安感をもたせてしまう。
・一定額の安定した収入を求める従業員が離脱する危険性がある。
業績連動型賞与において一番のメリットは、やはり個人業績の反映ができるという点です。
会社に貢献し、結果を残している従業員に対しては、きちんとその貢献度合いを賞与という形で還元することができます。
優秀なメンバーを公正・公平に評価できるため、そのようなメンバーの離脱を防ぐ効果も期待できるでしょう。
一方で、どうしても会社としての業績が下がってしまうと、賞与原資を確保することが難しくなり、結果として賞与を渡せないという場合も出てきてしまいます。その際に、従業員から不平不満が募らないようにするために、業績や賞与配分の基準などは、見える化させておくことが非常に大切だと思います。

事業成長のためには業績連動型賞与を
賞与査定に関して、どちらの方法もそれぞれのメリット・デメリットは存在します。しかし、メンバーに納得感を持ってモチベーション高く業務に取り組んでもらうためには、OGSとしては「業績連動型賞与」の導入を推奨しています。
個人業績を反映する仕組みを取り入れることで、メンバー同士が切磋琢磨し、成果を出すための主体性や相互成長のカルチャーづくりも期待できます。
個々人の成果に対する対価をきちんと還元できれば、結果として優秀なメンバーの離脱阻止にもつながりますし、このような主体的な動きは、必然的に事業成長のスピードを加速させることにも繋がります。
モチベーションの維持・向上は、チームや組織としていかにそのようなプラスの空気を作り出せるかにも関わってくると思いますので、個人業績ならびに部署業績も査定項目に入れておくのも良いかもしれません。
業績連動型賞与を導入する際の注意点
業績連動型賞与を導入するにあたり、その評価基準が曖昧なものになっていては、余計にメンバーからの不平不満は生まれてしまいます。
ですので、査定項目や基準が適正かどうかを今一度冷静に判断する必要があります。
注意点としては、
・メンバーの組織貢献度合いや成果を定量化すること
・査定項目や基準を公開して、被評価者であるメンバーに納得感をもたせること
以上の2点を特に重要視してください。

成果の定量化に関しては、いくら一生懸命業務に携わっているからといっても、そもそも評価者が求めている成果が定量化できていなければ、評価にブレが出てしまいます。
何をどの基準で求めているのか、そして、どれくらい貢献できているのかを数値で示すことによって、自他ともに納得のいく評価をすることができます。
また、その査定項目や基準はきちんと公開するようにしてください。
何を評価されているのかが明確になっていないと、メンバーは結局納得感を得られなくなります。そして、項目や基準が明確になることで、自分は何をどれくらい頑張れば良いのかが分かるので、メンバーを正しい方向に育成することにも繋がります。
評価する側にもされる側にも、納得感がないと事業成長はいつまでたっても加速しません!
正しい人事評価設計こそが事業成長につながる
今回は、ボーナス(賞与)についての設計方法についてまとめてみました。
賞与設計の重要性を今一度ご理解いただくとともに、ぜひ「業績連動型賞与」の導入を検討してみてください。
そして、「どんな評価を下されているのか分からない」といったメンバーの声が出ないように、必ず自社の人事評価が正しく透明性のあるものかどうかを見直してくださいね。
「じゃあ、具体的にどんな風に設計をすればいいのか分からない」
といった方に向けて、OGSでは人事評価の無料サンプルシートをプレゼントしています。
賞与査定には人事評価の設計はマストとなります。弊社が実際に使用している人事評価の項目も掲載されたサンプルとなっていますので、参考にしていただけるかと思います。
無料サンプルシートは下のバナーからダウンロードください!

