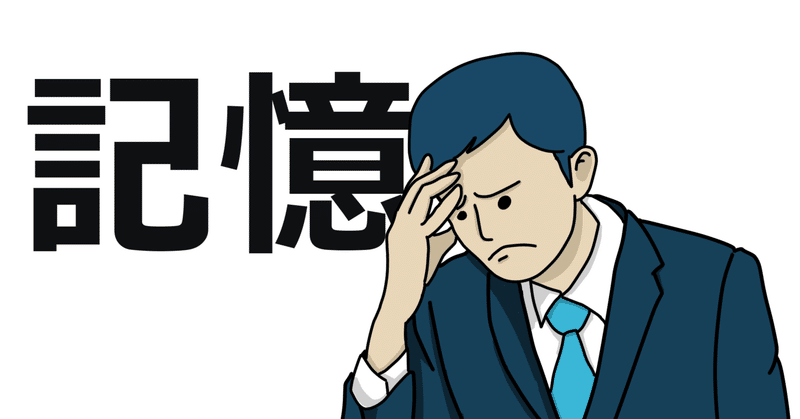
“人の記憶はあてにならない” のはけっこう怖いことかも
テレビ番組を観ていると、時々、過去のテレビ番組や映画などの一場面が流れることがある。
特に自分にとって印象的な場面だとつい見入ってしまう。そして、たまに、懐かしさとともに、「あれ、こんな内容だっけ?」という違和感のようなものを覚えることがある。
自分の頭の中にあったまさにその通りのものが再現されれば懐かしく思うだけだが、自分の記憶と違う部分があると頭の中に疑問符が浮かんでしまう。
違和感を覚える場合は、テレビに流れる再現映像が間違っているのかな?とふと思ってしまう。しかしそんなはずはない。古い映像をわざわざ改変して流すことは考えられないからだ。
つまりそういう場合、自分の記憶の方が間違っていたということになる。
記憶とは何か?人はどこまで詳細にかつ正確に物事を記憶できるのか?というのは心理学的に重要な問いだと思うが、中でも「記憶は上書きされるのか?」とか「記憶は書き換えられるのか?」という問いも興味深い。
過去の印象的な、いや場合によっては何ということもないような平凡な一場面を何十年経っても繰り返し思い出すことがある。たいてい、なぜその場面なのかは分からないのだが。
ただ、考えてみれば、自分では同じ場面を繰り返し思い出していると思っていても、実際に経験したものを正確に再現しているとは言えないのかもしれない。
人の記憶は上書きされ得る、というのは学問的に定説になっているようだ。
自分では覚えているつもりでも時間の経過とともに記憶が上書きされ、その内容が徐々に変わっていく。日常生活では特に不都合はないだろう。例えば、同窓会などで昔話をしているときに互いの記憶が違っていることが判明して、かえって場が盛り上がることすらある。
自分は経験がないが、警察や検察の取り調べは、この “人の記憶は上書きされ得る” ということをあえて無視しなければ成り立たない。
伝聞にしかすぎないのだが、取り調べの現場では核心的な事柄について、少しずつ表現を変えて繰り返し同じような質問を重ねていくのが基本的な手法になっているようだ。
繰り返し繰り返し、同じことを聞かれても、デジタル機器でもない人間は、一瞬一瞬の出来事を正確に呼び起こすのは難しい。
「信号は青だったと思います。」
「思います?さっきは青でした、と言ってたよね?もう一度しっかり思い出してみて。信号の色は何だった?」
「青だったはずです。」
「はずです?」....
といったやり取りを延々と続けられると自分の記憶に自信がなくなってくるのが普通だろう。そして相手の見立てに沿って供述が誘導されていく。見立てにあった自分の発言が文字として記録されていく。記憶が上書きされてしまったら、裁判での証言もその上書きされた記憶に基づいたものになる。
人の記憶はあてにならないということから、冤罪事案へと話を広げてしまったが、かなり奥深いテーマではありそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
