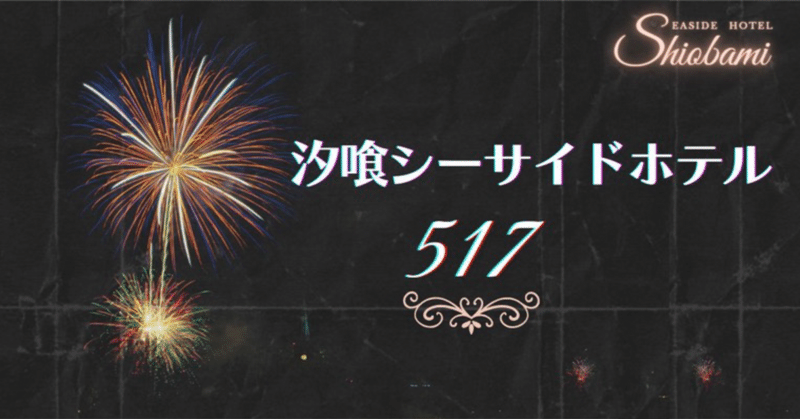
小説/汐喰シーサイドホテル517号室
歳を重ねるにつれて、夢と現実の距離が近くなった。目覚めながら夢を見ている。夢を見ながら目覚めている。ホテルの窓から見えるのは、白い空と灰色の海だった。
涸れたプールの向こうにある砂浜を、ホテルの宿泊客と思われる家族が歩いている。痩せた母親とせむし男。その後ろを歩く二人の男の子は合成獣で、顔は人間なのだが、その体は蜘蛛だった。
男の子たちは八本の節足を動かし、大きく膨らんだお腹を引きずって歩いていた。私は覚醒した頭の半分で、それが嘘だということもわかっていた。その正体は極度な近視だ。それに乱視が加わり、遠くに見える像が分裂し、ある部分で密接し、重なり合い、ぼやけた視界にありもしない輪郭を描く。
といって、それが視力だけの問題ではなく、自律神経のささやかな抵抗ではないかと気づく。車に撥ねられ、ぺしゃんこになった猫がネズミを追いかけている。古いアニメーションを観ている感覚で、残酷な描写を残酷と感じないことに安らぎを覚える。そうした気持ちが視覚に作用し、敢えて目に映る現実を捻じ曲げているのではないか?
現実はこうだ。
汐喰シーサイドホテルの517号室のテーブルには、降霊術で使用するウィジャボードや動物の骨がならべられ、いたるところで焚かれている香の煙で視界が霞む。単三電池二本で稼働するブッダマシンからは高名な僧侶の読経が響き、妻は「カーテン、閉めてくれない?」と私を睨みつけ、「聞こえてる? 光が邪魔なんだけど」
揺蕩う香の煙は、東南アジアの男娼が路上に吐いた檳榔の臭いがする。
ホテルの部屋に備え付けられた机には、一枚の写真が立てられている。おそらくは四、五年前に撮影された写真だ。場所は、住んでいるマンションの近くにある公園。前髪を切り過ぎた女の子が矯正中の歯を気にしながら笑っている。写真立てのまわりには花びらが撒かれ、インドの寺院の祭壇を思わせる。
カーテンを閉める前、最後に砂浜に目をやると、男の子二人が共喰いをはじめるところだった。
福岡県の犬鳴トンネル。香川県の根香寺。兵庫県のゼロ戦墓地。
私と妻が旅しているのは、全国の心霊スポットと呼ばれる場所だ。蝋燭が灯り、室内の暗がりに薄明が滲むように広がっていく。燃え立つ火が写真立てのガラスに反射して、女の子の笑顔が光の裏側に消える。娘のちひろを交通事故で亡くしてからというもの、私と妻は行方不明になった霊魂の情報提供を呼びかけている。
身長一四〇センチぐらい。痩せ型。肩までの黒髪。
登校中、ワンボックス車に轢かれて死にました。どんな形であれ、娘との再会を願っています。
妻が言うにはこうだ。
あちらの世界には、あちらのネットワークがあるかもしれない。あちらの人なら、もしかしたら娘のことを知っているかもしれない。
夜店の籤引き、そのハズレ玩具のようなブッダマシンには、およそ六十のお経が収録されているらしいが、デジタル表示がなぜ三桁あるのかは謎のままだ。
妻が行っているのは、恐山のイタコと同じく、自分の体を憑代にして霊を降ろす方法だ。娘がどこにいるのかと霊に訊ね、娘がどこにいるのか自分が答える。妻が言うには、死んだからといって消えて無くなるわけではなく、それらは形を変えただけで、永い年月をかけて塵となり芥となり、火葬場の煙突から降り積もる。いつしか新しい土地に運ばれて、もしかしたら子どもたちが遊んでいる砂場の砂は、元はご先祖様だったかもしれないといった論法だ。
つまり、それらは確実に存在しているが、どこに潜んでいるのかわからない。
「全地全霊の神よ、わたしの声よ、火星になれ」
お祓い棒を振り乱し、妻が祈祷の言葉を口にする。
永い目で見れば、目に映るすべてが死を宿している。
汐喰シーサイドホテルには、首無しサーファーの霊が出るという。
12/31 23:00 汐喰シーサイドホテル砂浜
夜の砂浜にあるのは二つの足跡だった。一つは、ホテルの玄関からほぼ一直線に続き、もう一つはホテルの敷地を右に左に折れ曲がり、最終的に涸れたプールを一周してから現れる。
「最初に確認させて頂きたいのですが」とホテル従業員は言った。
「どうぞ」と私は応えた。
「YouTuberとかではないんですよね?」
「違う」
「SNSにあげたりは?」
「しない」
ホテル従業員の身丈は二メートル近くあって、私の視線は彼の首元のあたりを彷徨っていた。彼と目を合わせるためには見上げなくてはならず、たとえ見上げたとしても、彼が手にしている懐中電灯の光が明暗を濃くして、彼の顔は黒いベールの向こうにある。
ホテル廊下で見かけたとき、彼の顔はマネキンを模したラテックス製のマスクだった。高い背丈に似つかわしくない童顔という意味で。
私は訊きたいことがあると言い、それだけで彼は何を知りたいのか、私が何を見たのか察したようだった。
「申し訳ありません」と彼は応じた。「夜の見廻りのときにでしたら」
心霊体験をまとめたネットサイトによれば、K(匿名希望)は強烈な喉の渇きで目を覚ました。社員旅行で汐喰シーサイドホテルを訪れていたときのことだ。先輩にビールやウイスキーをしこたま飲まされ、そのときはアルコールのせいだと思ったが、海水を飲み込んだときに似た、喉が焼けるような渇きだったという。
Kは自販機を求めて部屋を出た。正確な時刻はわからない。午前二時は過ぎていたと思う。ホテルの廊下には海鳴りが響いていた。汐喰シーサイドホテルはその名の通り、海に面して建てられている。海鳴りが聞こえても不思議ではない。それにしては近くから聞こえる。それはホテルの壁を震わせて、落雷のように轟く。
と、廊下の奥に灰色の波が弾けているのが見えた。Kはそれだけでも驚いたが、その波間からサーフボードが突き出してくる。
首の無い人間が波乗りしている。
ホテル従業員の制服らしいネクタイは臙脂だった。ただし、ここでは黒に見える。
羽織っているベンチコートが波風を受けて、有刺鉄線に結びつけられたコンビニ袋のようにはためいた。それがバタバタと慌ただしい音をたてて鳴った。
ホテル従業員は大谷と名乗った。
「お一人ですか?」
「いや、妻と二人で泊まっているんだが、妻は部屋で休んでいるよ」
「歩きながらでも?」
頷いた。
「1986年のことらしいです」と歩きながら、大谷は話しはじめた。
台風の夜だった。無謀な若者がサーフボードを手にして海に出る。激しい雨が降っていた。砂浜に立ち、荒れ狂う海を見つめる。翌朝発見されたのが若者の首無し死体だ。寄せては返す波に洗われて、独りでに揺れる。
どうして首が切断されたのか?
足首とサーフボードをつなぐリーシュが首に巻きついたのか、サーフボードそのものが鋭利な凶器と化したのか、顛末は解明されていない。いずれにしても事件性はなく、故人の命知らずな行為による水難事故として処理された。若者の頭部は未だ発見されていない。
「それがどうしてホテルのなかに出るんだろう?」
「わかりません。何かを探している、とかでしょうか?」
「首無しサーファーが探すとしたら自分の頭だろう。それがホテルに?」
「さあ」
私は質問を変えた。
「きみは怖くないのかい?」
「何がでしょう?」
「職場に幽霊がいるなんて、普通は嫌がると思うが」
「僕はお客様を差別しません。様々な事情を抱えたお客様がいて当然ですから」
「なんだかね、わかったような気がするよ」
「何がです?」
「ここは幽霊にとって居心地がいいホテルって意味だよ。このホテルに来てから考えていたんだ。妻が言っていることが本当に正しくて、娘のちひろはまだ生きていて、死んでいるのは私たちのほうかもしれないって」
旅立つ前に見た、私と妻が住んでいる部屋の様子を思い返してみる。物音しないダイニング。対面式の台所カウンターにはシンゴニウムが飾られている。埃をかぶった枯れない造花。台所カウンターの内側には冷蔵庫と食器棚。その脇にはテーブルと椅子。子供用の椅子が一脚。フローリングの床——この場面のどこか、男女の青褪めた足が横たわってなかったか?
「娘さんは?」
「死んだよ」と私はできるだけそっけなく応えた。「交通事故だった」
だからどうなるというわけでもない。もしも娘のちひろが生きていて、本当は私たちのほうが死んでいるとして、それで誰が幸福なのか? ちひろか? 妻か? 私は?
「少なくとも、僕にはお客様が見えています」
「見えているからって、生きているとは限らないだろう? 現に首無しサーファーだって見ることができるんだから」
「それはそうですが」
「きみだって死んでいるかもしれない。知らないのは自分だけ。自分が生きているのか死んでいるのかさえ、我々は認知できていないのかもしれないよ」
12/31 18:30 汐喰シーサイドホテル 5階廊下
汐喰シーサイドホテルが建てられたのは1971年。昭和のリゾート開発から時代は流れ、増改築とリニューアルを繰り返し、もしかしたら床のカーペットは新しく敷き直されているのかもしれないが、それでも蓄積された古さは否めない。
照明は黄色だった。
客室が多く、視界の奥先まで続いている。
ここが霊障イベントの発生現場。
首無しサーファーの目撃証言は、汐喰シーサイドホテルの五階廊下に集中している。
歩いていても、これはどこのホテルでも言えることだが、人の気配がしなかった。誰もが息を殺して部屋のなかに潜んでいるのか、そもそも宿泊客が少ないのか、物音ひとつしない。耳を澄ますと、巨大な空調が稼働しているのがわかる。それは地底深くの洞穴に生じた風のように遠くから聞こえる。
富山県の坪野鉱泉。山梨県のおいらん淵。京都府の首塚大明神。
レンタカーで大量殺人が発生した廃村を訪れ、古びたフェリーで怨霊伝説が残る島に渡ったとしても、そこは蛻の殻だ。誰もいない。移住したのか、成仏されたのか、そもそも最初から何事もなかったのか?
もしかしたらと期待が膨らむ現象さえ、終わってみれば、ただの不在連絡に過ぎない。
降霊から二時間、白目を剥いた妻が泣き叫び、青く血管が浮いた自分の首を掻きむしる。娘のちひろを撮した写真立てがカタカタと震え、妻は剥がれた皮脂がこびりつく指先でテーブルの上のコインを動かしはじめる。
い、ま、せ、ん。
骨折り損が当然のごとく、ネットから書き起こした心霊スポット一覧に×印が増えていく。
「ねえ、包帯もらってきてくれない?」と妻が言う。「喉が地獄」
合わせ鏡のように同じ景色が延々と続く。
汐喰シーサイドホテルの五階廊下には、客室と客室の間の壁に一号サイズの絵が掛けられている。そのどれも肉筆画らしく、風景、静物、動物と画題は統一されていないが、筆のタッチや色使いから同一人物の作品と思われた。
見るでなく横目で眺めながら歩く。
正直なところ、鑑賞するに値しない。衣料品を取り扱うスーパーマーケットのワゴンに積まれたスウェットやパーカーと同じだ。自己主張の強いロゴとキャラクター。無地ならまだしも可能性を秘めている。あれは機能性に優れた商品が、不要なデザインによってどれだけ価値が下がるかという実験をしているとしか思えない。
それにしてもこの画家は、いったい何枚の絵を描かされたのだろう?
点数とサイズ、ホテルのコンセプトとして肉筆画を飾るという発注だけで、その内容は画家まかせだったのかもしれない。
自販機や製氷機が置かれたコーナーを過ぎたあたりから、画家の絵は少しずつ変わりはじめた。
海水浴を楽しむ家族の背景には、遠くの水平線から顔だけ突き出した怪物が描き足されている。
水差しと果物の静物画は一見しただけではわからないが、死んだ鳩の頭を筆にして描かれている。
あんなに愛らしかった猿は自分の目を穿り返し、血の涙を流しながら天に向かって赦しを乞う。
そのころには精神に異常をきたしていたのかもしれない。
最後に見た絵は、色彩を失った誰もいない部屋だった。
と、私は立ち止まった。
ひとつ客室のドアが開いている。覗くつもりはなかったが、前を通るときに視界の片隅が何かを捉えた。
引き返して覗くと、はたして子どもの足だった。
ベッドの端に座って、床に届かない足をぶらぶらと遊ばせている子どもの足だ。位置的にはテレビを観ているのかもしれない。しかし室内は薄暗く、テレビが点いている感じはしない。
ドア枠の壁が視界を妨げて、全身は見えない。楽しげに揺れる足だけが見える。
娘のちひろが死んでから、四十九日が過ぎて自分たちの心を整理する——はずが、私と妻はそれができないまま、娘のちひろや、自分たちの将来を口にしないことでかろうじて生き延びている双頭の亀だった。ひとつの体に暮らしながら、お互いが何によって壊れてしまうのかわからない。時おり、甲羅の奥から首を伸ばして生存を確認し合う。お腹は空きましたか? もう寝ますか? 藻に翳る水槽から朧げな陽射しに目を細めるような。望んだ生活ではないが、ただし痛みは感じない。
ふと真夜中に目を覚ますと、寝室が明るかった。閉じた瞼を透かした光に反応して、予定外の時間に覚醒してしまったらしい。
隣からは妻の鼾が聞こえた。電気スタンドは妻側のサイドテーブルに置かれている。眠りにつくまでスマホを操作している妻が消し忘れて眠ったのだと思った。
灯りを消そうとして、体の向きを変えた。そして、なぜかこちらを見ている妻と目が合った。
私が気づくのを待っていたのかもしれない。しかし、どうして鼾を真似てまで寝たふりをする必要があるのか? そもそも、いつから私を待っていた? もしも私が目を覚まさなかったら?
それらの疑問に応えることなく、妻は、もしかしたら、と言った。
その夜、妻は初めてその想念を口にしたのだと思う。
ちひろは生きているかもしれない。私たちに見えないだけで。
貧血の予兆か、視界の四隅が昏くなる。
ベッドの端に座っているのは、ちひろの足だった。違うかもしれない。正しくは、娘のちひろと同年代と思われる女の子の足だ。
さっ、と冷たいものを感じて視線を床に移すと、廊下に敷かれたカーペットの上を水が走っていた。驚いて顔を戻すと、部屋のドアが閉まりつつある。
狭まっていく室内に、女の子が立ち上がるのが見えた。私の視線に気づいたのか、顔をこちらに向ける。
〈537〉
ドアに記されていた部屋番号だ。
その間にも水嵩は増していた。今では私の膝にまで達しており、廊下全体を海水が満たしていた。泡立つ小波が私の足を押し流そうとしている。
「どうかされましたか?」
気づき、振り返ると背の高いホテル従業員が立っている。
「いや、水が」
「水ですか?」
背の高いホテル従業員の背後で、灰色が渦巻いていた。それがそそり立つ大波だとわかったとき、まずは寝息は自然か? 瞼は閉じられているか? レム睡眠時には瞼の裏側で眼球が小刻みに動く。もしもこれが悪夢なら、どうか私の頬を叩いてほしい。目が覚めるまでなら遠慮はいらない。胸から下に定規で測ったように三ミリずつ包丁を這わせてほしい。
皮膚がふやけて溶け出し、醜い禿頭をさらした溺死体が私の足に喰らいつく。あわてて蹴飛ばした足が空振りして幻覚と知る。磯臭い死がホテルの廊下を水飛沫あげながら迫ってくる。
「自動販売機でしたら、まっすぐ進んでもらえたら」
ホテル従業員はそう言うと、自分の作業に戻る。537号室の前に飾られた、誰もいない部屋の絵を掛け替える。ホテル従業員が新しく掛け直した絵は、色彩も構図も同じだが、ベッドの端にはひとりの少女が腰かけている。
「エレベーターでしたら、その奥の通路を右に進んでもらえたら」
いまにも崩れそうな波の腹からサーフボードの先端が突き出してくる。
首の無い人影が舞台下からせり出してくるように、その姿を現す。
「お客様?」ホテル従業員が言う。
その後すぐ、塩辛い濁流が私を呑みこむ。
12/31 19:30 汐喰シーサイドホテル 夕食会場
不釣り合いに豪華なシャンデリアの下で死者たちは、さして旨くもない焼きそばを貪り食べ、張り切れそうな胃袋を押し拡げては、自分だけが損をしたくない一心で、再び席を立つ。
「ここには絶対いると思う」と妻が言う。
異論はない。ここにはいると思う。
「あれは居留守だよ、わざわざ『いません』なんて言う必要がある?」
それは人それぞれの考え方次第かもしれない。やむ得ぬ事情で今は対応できないが、知らず待ち続ける相手の時間を無為にするのも申し訳ないという誠意の顕れかもしれない。もしくは、妻が接続したのはあちらの世界に通じるSNSだったのかもしれない。
神はいません。あるのはこのページに記載した祝詞だけです。唱えることで言語空間を介して新たなエネルギーを供給します。RT/いいね、により、さらなるエネルギー支援を行います。
それらの呟きには必ずと言っていいほど青字のリンク先が貼り付けられているが、怖くて押したことがない。
正直なところ、それらの怪しげなリンク先に飛ぶことなく、汐喰シーサイドホテルの宿泊客が全員死んでいると想像できるのは、私にとって唯一の救いだ。そう思うだけで、煩わしい騒音も我慢できる。
「考えたんだけどね」と蒸し鶏を小さく切り刻みながら、妻が言う。「首無しサーファーには耳も口もないわけじゃない?」
「首無しだからね」
「聴こえないし、喋れないわけよね」
「そうだね」
「ちひろのこと、問いかけても無駄じゃない?」
私たちが座っているテーブルには、ちひろの遺影が飾られている。これは推しのアクリルスタンドと同じだ。妻はいつでも持ち歩き、食事に同席させる。これはある種の魔除けと同じ効果を発揮する。誰もが目を背けて、私たちのテーブルに寄りつかない。
「案外いけるわよ」と言って、妻が蒸し鶏を口に運ぶ。
私の脳裏を巣食っているのは、537号室の住人だ。
537号室にひとり佇む女の子。ドアが閉まるとき、一瞬だけこちらを向いた。
ちひろだった。
いや、ちひろではなかった。
正しくは、剥がしたちひろの顔を自分の顔面に縫いつけた女の子だ。
「もう少し食べようかな」と言って妻が席を立つ。
537号室の女の子は、その両手にひとつずつ頭を掴んでいた。ひとつは見知らぬ男。首無しサーファーの頭がこれかもしれない。もうひとつがおそらくちひろ。おそらくというのは、顔の皮を剥がされて解剖されたカエルの腹にしか見えない。それがたとえ、実の娘であったとしても。
僅かだが、娘のいない世界を望んだことがある疚しさが、私にグロテスクな妄想を抱かせるのかもしれない。目を閉じて、ややもすれば、残酷なイメージを作り出す思考を掻き消すように自分の頬を撫でる。魔法が解けかけている。残酷なイメージを残酷だと感じている自分に気づく。夕食会場の霊魂たちは喋るか、笑うか、食べるか、飲むか。必要以上に食器をガチャガチャと鳴らし、テーブルと料理を往復する足音が止むことはない。
「ありがとうぐらい言えよ、クソガキ」
目を開くと、戻ってきた妻が不機嫌そうに目配せしている。
妻の視線の先には一組の家族がいる。父親と母親、男の子が二人。おそらく部屋の窓から見かけた、砂浜を歩いていた家族だ。
「どうしてだろうね?」と妻が言う。「子どもって、たとえば見て。あの人の子宮から産まれたんだと思うと、なんだか気持ち悪いでしょう?」
痩せこけた母親が鶏ガラのような喉を伸ばしてスープを啜っている。大量のお皿を積みあげた男の子と視線がぶつかって、あわてて目を逸らす。
「でも、きっとあれだよ」と妻は新しく取ってきた蒸し鶏を再び細切れにしながら言う。「血のつながりとか、セックスとか出産とか、愛の結晶とか? が悪臭を放つんだよ」
鶏の、かつて鶏だったことがある蒸し肉を口にして咀嚼する。
「たぶん、そんなものに依存してる家族って、もう古いんだよ」
12/31 22:30 汐喰シーサイドホテル砂浜
浴室から娘のはしゃぐ声が聞こえる夢とも記憶ともつかない。私の手元には開けたばかりの缶ビールがある夏の夕刻、という情景が克明に思い出せるから記憶かもしれない。しかし以前に見た夢をもう一度見て、記憶と勘違いしているのかもしれない。
ちひろの髪を洗っているらしく、妻の陽気な鼻歌が浴室から洩れてくる。
蒸し暑く、昼間の冷めやらぬ熱が頭の芯にこびりついている。それは次第に大きく膨らんでいく。
ダイニングテーブルには、ちひろが大切にしている人形が置かれていた。手垢がついたフェルトの人形だ。私は衝動的にその人形を掴み、マンションのベランダから投げ捨てた。
お風呂から出てきたちひろが人形がなくなっていることに気づき大泣きし、濡れた髪をタオルで拭っている妻が、蔑むような目で私を睨みつけたことも覚えているのだから、やはり実際の出来事かもしれない。
夜の砂浜は凍りついたように硬く、靴の下でざりざりと音をたてた。遠近感を失ったひたすらに大きな闇から波の音が響いている。ホテル従業員の大谷が手にしている懐中電灯の光が私たちの歩く足元を照らし、光のなかに浮かび上がる砂の陰影を濃くする。
「首無しサーファーについて知っているのはこれだけです」と大谷は言った。
私はうなずき、
「もうひとつ訊いてもいいかい?」
「何でしょう?」
「537号室」
大谷が舌打ちした。唾を含んだ唇を手の甲で拭く仕草をした。私はそれを横目で見ながら次のキーワードを繋ぐ。
「あの絵」
思い返してみる。あのとき、537号室のグロテスクな女の子を見かけ、首無しサーファーと遭遇した廊下で彼が何をしていたのか?
絵だ。
彼は絵を掛け替えていた。誰もいない部屋の絵から、少女がいる絵に。それが何を意味しているのかわからない。わからないが、あの絵が憑代になって、汐喰シーサイドホテルに霊障をもたらしているという仮説が成り立ちはしないか?
「理由は知りません」と大谷は応えた。「理由は知らないのですが、一日に一度、絵を掛け替える決まりになっているんです」
「掛け替えたらどうなるんだい?」
「特別、何かが起こるわけではありません」
「537号室は?」
「開かずの間みたいなものです。宿泊のお客様も入れていません」
「今は使っていないのかい?」
「使っていません。今、というか僕が働きはじめたときにはすでに。もしかしたら開業当初から」
「しかし、私が見たときには部屋のドアが開いていたが」
「毎日、清掃には入っているんです。ベッドシーツが乱れていたり、お菓子の袋が落ちていたりするので」
「537号室には女の子がいるよね?」
「誰なのかわかりません。少なくとも、幼い子どもが亡くなったとか、そういった事件や事故の記録は当ホテルにはありません」
私の推測が正しければ、汐喰シーサイドホテルで起こっている心霊現象の元凶は、537号室の女の子だ。首無しサーファーがホテルのなかに出現するもの、537号室の霊力に引き寄せられているに違いない。
「たとえば」
と次の言葉を発しかけたとき、大谷が手で制して私の歩みを止めた。自身も立ち止まって、懐中電灯の光を海に向ける。黒一色だった海に波模様があり、白波が立っているのがわかる。懐中電灯の光を左右に動かす。
大谷が何を探しているのかわからなかった。わからなかったが、私の視線も自然と懐中電灯の光に吸い寄せられる。一瞬、本来そこにあるべきではないものが映った気がする。大谷もそれに気づき、懐中電灯の光を戻す。
それは浅瀬を漂う一艘のボートだった。
毛布から顔だけ出した家族が体を寄せ合っている。こちらが何かをしたわけでもないのに、なぜか被害者顔をしている。懐中電灯の光を浴びて、詳細が白く飛んだ顔というのは誰しもそうなるものなのか。密航者という言葉が脳裏を過ったが、そうではないとわかったのは、夕食会場でも見かけたあの家族だからだった。
「すみません」と言いながら大谷が一歩足を踏み出した。家族に声をかける。「何をされているんですか?」
家族は顔を見合わせて、自分たちが置かれている状況を考えあぐねているようだった。怯えているようで、開き直っているようで、彼らの態度にはわからない部分が多かった。
「花火を」と父親がようやく応えた。
「ああ、新年の打ち上げ花火ですね」
「花火を見たいと思いまして」
「ホテルの部屋からでも綺麗に見えますよ」
「海から見たいんです」
「しかし、夜の海は危険ですので」
「何がです?」
「夜の海です」
私は黙って大谷と父親のやりとりを聞いていたが、それは片方はボートの上から、片方は砂浜からとはいえ、距離にすれば五メートルにも満たず、それにしては二人の会話には隔たりがある気がした。複数の中継地点を介したタイムラグがあるような。
母親と二人の男の子は、父親の背中に隠れるようにしていた。不躾な視線を向けているのはこちら、という気分にさせられる。
やがて父親が「お願いが」と言い出した。
「ボートを押してもらえませんか?」
「ボートを?」
「櫂を流してしまって」と下卑た笑顔で言ってから「少し押してもらえませんか? 押してもらえたら、あとは勢いで沖まで出れると思うんです」
櫂のないボートでどうするつもりなのだろう?
ここで初めて、この家族が死ぬつもりなのだと気づいたが、大谷は変わらぬ朗々とした声で「わかりました」と応じた。
「ちょっと」とさすがに口を挟んだ。「本気かい?」
「お客様の要望ですので」
「いや、あの人たちは」と私は言い淀んだ。一家心中という言葉を呑みこんで「逃げようとしてるんだよ」と言い換えた。
「宿泊費は前払いで頂いてますので」
「あの男はビールを飲んでいたよ、夕食のとき。あれは別料金だろ? 随分と飲んでいるようだったよ」
「お金なんて関係ありません。あなたはお金で……いえ、いいです」
彼が先に宿泊費のことを持ち出したのでビールの件を口にしたに過ぎないのだが、大谷の言い方に少し腹が立った。
そうしている間にも、大谷は靴を脱いで、スラックスの裾をたくし上げていた。
「手伝おう」と言って、私も靴を脱ぎはじめた。
いま思い返してみても、この夜の出来事はレンズの屈折が織りなす実在のない虚像という気がする。投射された光が登場人物を照らして、ありもしない影が話し、思いつくままに勝手な行動をとりはじめる。それは私自身にも言えることで、どうして手伝おうなんて言ったのか、普段の自分なら考えられない。
結局、夜の海に消えた家族がその後どうなったのか——翌日に汐喰シーサイドホテルを後にし、その日から新聞に目を凝らしているが、消息を伝える記事は今のところ掲載されていない。事件性なく何処かの浜辺に漂着した可能性もある。もしくは泥舟のごとく海に沈んだのか、いまもなお航海を続けているのか。
大谷についてなら知っていることがある。
汐喰シーサイドホテルを後にしてから数週間後、私宛に一通の手紙が届いた。そこには彼がホテルを辞めたこと、あの夜のことは深く印象に残っていることが丁寧に綴られていた。それから、あの夜には話せなかった汐喰シーサイドホテルの秘密について——
開業当初のことらしい。
従業員が廊下を走る女の子を見たという。追いかけると、霧のように消えていった。その従業員はそれから一週間後、ゴミ収集車に頭を突っ込んで死んだ。
宿泊客からは眠れなかったと苦情が入る。一晩中ドアをノックされ続けたという。その宿泊客も一週間後に死んだ。通勤中のバスが横転し、乗客十三人の首が切断される大事故だった。
当時のホテル支配人は、ある霊媒師に霊視を依頼することにした。
それがあの鳴海砂月である。
「ちょっとね、これはわたしにも無理」と彼女は言った。「ずっとこの土地にいる怨霊というより、神に近い存在。昔は本当に崇める人がいたと思う。国家を滅ぼすぐらい強力」
鳴海砂月なら私も知っていた。眼球坂の神隠し、腹赤峠の爪剥ぎ地蔵、四十八人連続飛び降り自殺ビル、といった数々の怪事件を解決したのは、この人ではなかったか。それだけの人が無理だと言うのだから、よほど強力な霊なのだろう。
「でも、その力を抑えることはできる」と彼女は言った。「二枚の絵を準備してください。それから霊専用の部屋を」
物語の結末はこうだ。
マンションの浴室から妻の声が聞こえる。楽しげな笑い声。聞こえる声は妻ひとり。曇りガラスの向こうには、妻と対面する小さな影がゆらめいている。
冬の海は想像を絶する冷たさだった。
「もしもなんだが」とボートを押しながら言った。「537号室の女の子が幸せになる方法があるとしたら?」あまりの寒さに自然と声が大きくなる。
「どういう意味です?」
「あの子にも幸せになる権利があると思うんだよ」
「でも、あの子は存在していませんよ」
「でも、存在している」
私たちの声は、ボートに乗っている家族にも聞こえているはずだった。しかし、敢えて聞こえないふりをしていた。
「生きたいとか死にたいとか、嘘臭く感じることはないかい?」
「人間の真摯な感情だと思いますが」
「私はあるよ。生きたいとか死にたいとか呟いている声が、とても遠くに感じること」
大谷は黙った。
「だからね、考えるのをやめようと思うんだ。生きているとか死んでいるとか、いつまでもそんなことを囚われていたら逃げ遅れてしまう」
「どうするんです?」
「あの子と暮らせないかと思うんだ。もちろん、あの子が望めばだが」
全身が悴みはじめた。体の感覚が遠ざかり、心臓の音さえ聞こえない。
「僕はですね」と大谷が話しはじめた。「正直、お客様の言われていることがわかりません。それでも、逃げ遅れてしまうっていう感覚はわかります。いつもはですね、ひとりで見廻りをしているんです。毎晩、この砂浜を歩きながら夜の海を眺めています。そうすると、あれって。億年単位の地球の歴史のなかで自分が逃げ……」
「このあたりでどうだろう?」と私は話を遮った。
大谷はしばらく黙っていた。やがて「そうですね」と応え、ボートから手を離した。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
