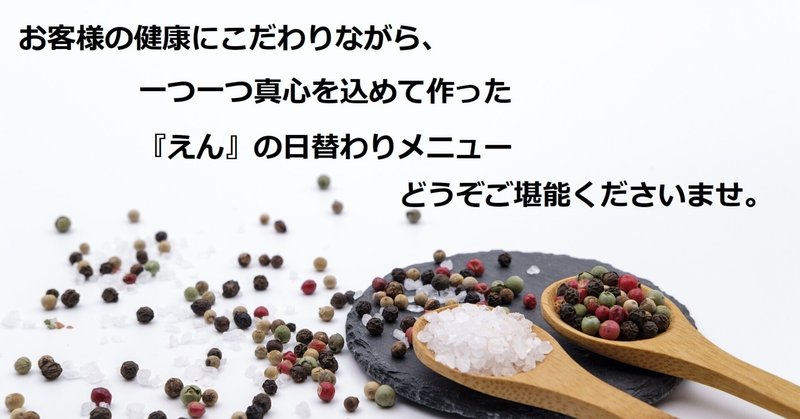
[短編小説]創作料理店えん
――Menu1――
東京のビル街から外れた細道にひっそりと佇み、ほんのりと淡い照明でもって客を出迎えてくれる、創作料理店『えん』。
ビル街や駅前に行けば、多くの仕事終わりの会社員たちによって賑わっているけれど、『えん』はそういうチェーン店のような場所とは違って、落ち着いた雰囲気を醸し出していた。なんと言えばいいのだろう、実家に帰った時の安心感と言えば伝わるだろうか。店内に足を踏み入れた瞬間、都会の喧騒とは異なる空気感を敏感に察した。
この独特な雰囲気は、恐らく立地的な条件もあるだろうけど、多分それだけじゃない。
「いらっしゃいませ」
人当たりの良い笑みと人の心を穏やかにさせる柔らかな口調でもって、来客を出迎えるのは、この『えん』を切り盛りしているひぃさんだった。ちなみに、ひぃさんの本名は分からない。今日『えん』まで連れて来てくれた上司の高野課長も、本名を知らないらしい。
ひぃさんの姿を見るや否や、高野さんは破顔をさせながら手を上げた。
「やぁ、ひぃさん。真護、この人がさっき話していたひぃさんだ」
「あ、こんばんは」
「あら、はじめまして。ゆっくりくつろいでいってくださいね。お話し好きな高野さんを相手にしてたら、気持ちは休まらないかもしれないけど」
「ははは、それはひどいぜ、ひぃさん」
ひぃさんの口元を抑える上品な笑い方、それに混ざるように僕と高野さんも笑う。すると、更に店の中が朗らかで温かい空気に包まれた。
五人ほどが座れるカウンター席と、二人が対面に座れるテーブル席が二つ。高野さんは迷いなくカウンターの方に腰を掛けたから、僕も続いて高野さんの隣に座る。
カウンターとひとつなぎになっているキッチンを見ると、驚くほど綺麗に片付けられていた。「綺麗にしておいて良かったぁ」、僕の視線に気付いたひぃさんは、少しだけ頬を赤らめた。「何言ってるんだよ、ひぃさんが水回りを汚しているところなんて、見たことがないぜ」と、高野さんは常連らしく言った。
「変わったお店ですね」
いつの間にかカウンターの上に置かれていたお通しを食べながら、店舗の内装に目を向ける。壁には、白い紙に『日替わりメニュー』と書かれたものが貼ってあった。その他のメニューはどこにもない。変わっているところは、食事に関してだけでなく、飲み物に関してのメニューもないということだ。当然、酒やつまみもなく、ジュースやお茶などといった類もない。今、僕と高野さんが飲んでいるのも、水一択だった。
「ははっ。最初来た時は、俺も驚いたよ。酒好きからしたら、困るかもなぁ。でもま、真護って、確か酒とか飲めないよな」
「ええ。だから、困ることは全くないんですよ。ただ珍しいなって思っただけで。逆に、高野さんはお酒飲まれましたよね?」
「少しだから、別になくても構わん。てかな、『えん』で酒を飲んで、ひぃさんに負担を掛けるくらいならなくていい」
「あはは、いつもお気遣いありがとうございます」
先ほどから、ひぃさん以外の従業員の姿は見かけなかった。あまり人が来ない立地と、一品限定のメニュー、加えて営業時間も平日の十七時から二十二時と限られているからこそ、ひぃさん一人だけでも経営が成り立っているのだろう。
「ひぃさん、今日のメニューは?」
「作り終わってからの内緒。これも『えん』の醍醐味にしてるんですから」
「ちぇっ。今日は真護がいるから、教えてもらえると思ったんだけどな」
高野さんは大袈裟に指を鳴らして悔しがる。だけど、その表情は言葉とは正反対で、子供らしく嬉しそうにしていた。
僕の中で高野さんのイメージは、リーダーシップを遺憾なく発揮させて、要領よく仕事をこなす人だった。こんな子供らしくお茶らける一面があるとは、初めて知った。
「ところで、真護さ――」
高野さんは、僕の方へ体ごと向けながら話を始めた。高野さんの話に相槌を打ったり、僕からも話を広げたりもした。
その傍ら、ひぃさんは聞き役に徹しながら、日替わりメニューを作る手は止まらない。
高野さんと一緒に働くようになってから長い時間が経つけれど、今まで過ごした中で、一番楽しく話が出来たような気がした。
他愛のない世間話で高野さんと盛り上がっていると、「そろそろ出せますからね」とひぃさんが声を掛けてくれた。
「お、待ってました。真護、楽しみにしてろよ」
高野さんから言われる前から、ずっと楽しみにしていた。
鼻腔を通して食欲を駆り立てる香り、一つ一つの工程に丁寧に向き合っていることが伝わって来る音。
これから提供される料理への期待度は、これでもかというほど上がって来るものだ。そもそもの話、最初のお通しを食べた時点で、僕の胃袋はすでに掴まれている。
「おまたせしました」
そして、ひぃさんは高野さんと僕の前に料理を置いてくれた。
「――豚の生姜焼きよ」
一口で食べやすそうなサイズに切られた豚肉に、絶妙にタレが絡んでいる。備え付けのキャベツも美味しそうだった。先ほどから感じていた香りも、前にしたことでより強く僕の食欲を刺激する。
見た目は至ってシンプル。けれど、味は――。
「うわ、美味しい」
たったの一言で終わらせてしまう自分が悔やまれた。ただの生姜焼きのはずなのに、今まで食べたことのない味が口の中で広がった。
「だろ! ひぃさんの作る料理は素材からこだわってるからな。美味くて、健康的なんて、まさに最高だろ!」
喋ることで口の中から味がなくなってしまうことを恐れて、僕は租借しながら頷いた。説明してくれた高野さんには申し訳ないけど、同じ料理を食べているんだから、この気持ちは伝わっているはずだ。
互いに料理を黙々と、しかし豪快に食べていく。美味しくて箸が止まらない、という経験は年々減って来る。けれど、ひぃさんが振る舞ってくれた料理は、僕の食欲を止めてくれない。
「この生姜焼きはね、食材に拘ったのもあるんだけど、実はタレによりをかけてみたの。豚の良さを引き出すために、試行錯誤を重ねたんだけど、美味しく出来上がってよかった」
残り数口といったタイミングで、ひぃさんが料理の説明をさらりとしてくれた。説明を聞く前から美味しかったのだけど、説明を聞いた後は、タレに強く意識が向くから不思議だ。
「で、例の話は前向きに捉えられたか?」
「あ、いえ」
「ああ、急かしたわけじゃないんだ。真護の今後に関わる話なんだ。ゆっくり考えて、真護の意志が固まったタイミングで言ってくれればいい」
お茶を濁すような反応をした僕に、高野さんは詰め寄ることもなく、笑って受け入れてくれた。
たったそれだけでこの話は終わり、高野さんはくだらない話に花を咲かせてくれた。ひぃさんも笑って、場を盛り上げてくれる。僕も口角を上げるけれど、先ほどのように楽しむことは出来なかった。
例の話――、それは僕の昇進に関わる話だ。
高野さんが課長から部長へと昇進することで、空いたポジションを務めてはどうかと僕は打診されている。この話を聞いたのは、半月前。しかし、僕はまだ決めきれずにいた。
ありがたい話だと思う。けれど、僕には高野さんのように、人をまとめる力はない。誰かの陰に隠れて、ひっそりと仕事をするのがお似合いだ。
要するに、僕は自信がないだけだった。
――Menu2――
「――肉じゃがよ」
ボルダリング仲間の岩上と一緒に行った創作料理店『えん』で出された日替わりメニューは、ひぃさんという店主が言った通り、何の変哲もない肉じゃがだった。
味にうるさい岩上がオススメだというから、楽しみにして来たというのに、これじゃ期待外れだ。肉じゃがなんてどこでだって食える。何なら俺にだって作れる。
「いっただきまーす」
岩上は目の前に広がった肉じゃがに嬉しそうに箸を伸ばした。で、「うっめー!」と反射的に口にする。おい、今の速すぎだろ。絶対に食う前から言うって決めてた奴の台詞だよな。本当に味分かって言ってるのか。
だけど、岩上が食うと、何でも美味そうに見えるから不思議なんだよな。
「功志くんも冷めないうちに食べてくださいね」
ひぃさんが手の平を向けて催促してくる。今日初めて来た俺に対しても、ひぃさんは一度で俺の名前をしっかりと憶え、まるで常連のように親しく接してくれる。
俺は箸を手にして、肉じゃがを口に運ぶと、「あ、うま」と反射的に言ってしまった。「だろ!」と岩上は返す。
ひぃさんは一瞬ほっと息を吐くと、すぐさま「口に合ってよかったぁ」と破顔させた。
「ただの肉じゃがだと思って食べたら、全然違ってたわ。これ、肉じゃがじゃない」
「ははっ、肉じゃがは肉じゃがだって。そうですよね、ひぃさん」
「ええ、お肉にもジャガイモにも、にんじんにもネギにも、ダシにも、この肉じゃがを作る上で必要な全てのものに拘って腕によりをかけた、とっておきの肉じゃがよ」
あまりにも肉じゃがという単語が飛び交い過ぎて、肉じゃがの概念が分からなくなって来る。だから、「肉じゃがのゲシュタルト崩壊だな」とつい言ってしまった。言ってすぐに後悔する。脈絡がなさ過ぎて、意味分からなかったかも。
けれど、「なんだそれ。相変わらず面白れぇな、功志」と岩上はゲラゲラと笑ってくれ、ひぃさんは口元を抑えながら控えめに笑ってくれた。
よかった。俺には時々こういうところがある。言うべきことと言わなくてもいいことの判別を付けないまま、考えと同時に、言葉が口を出ていく。
何度か嚥下を繰り返した後、
「でも、マジで初めて食べる感じの肉じゃがです。こんな複雑な味にするには、色々な調味料とか食材を入れてるんでしょうね」
この肉じゃがの美味さがどこにあるのか気になって、俺はひぃさんに問いかけた。すると、ひぃさんは「ふふっ」と意味深く笑みを零した。
「あ、すみません。もしかして、俺間違ってました?」
「あら、ごめんなさい。間違ってたとかじゃなくてね、確かに食材はたくさん使っているの。でもね、調味料は多く入れてないんですよ」
「え、そうなんですか?」
純粋に驚きの声を上げたのは、岩上だった。
「ええ。調味料を多く入れて、味を濃くすれば、新しい味覚に触れる機会を作れるかもしれない。でもね、『えん』で食べてもらうからには、健康にも気を遣って頂きたいし、食材そのものも楽しんで頂きたいの。だから、今日の肉じゃがも、不必要な要素を取り除いて作ってみたんです」
「じゃあ、今日食べてる味って、食材本来の味……ってことですか?」
岩上の質問に、ひぃさんは嬉しそうに首肯した。
「なるほどなぁ。俺が普段食べるのって、味が濃いものばっかだから、逆に珍しく感じたのか」
「だな。一人暮らししながら社会人してると、外食ばっかになるから、『えん』での料理は本当に体に染みるんだよ」
「まぁ、ここにいる時点で、外食には変わりないけどな」
肉じゃがの味を口に広がらせながら、岩上の言葉にツッコミを入れる。一瞬、岩上の箸が止まったのを、横目で捉えた。――気がした。
気がした、というのも、すぐに岩上は「ほんと、何を除くかって大事ですね。ね、ひぃさん」と話しかけたからだ。ひぃさんはどう反応するべきか困ったように苦笑いを浮かべながら、肉じゃがを作るために使用していた調理器具を片付ける手を止めなかった。
「そういえば、最近ジムの他に、近所でランニングを始めてさ」
気まずくなりかけた空気を変えるように、俺は新たに話題を振った。
社会人になってから趣味で始めたボルダリングを介して、俺と岩上は知り合った。お互い体を動かすことが好きなのだ。だから、岩上と話す時は自然とスポーツ系の話題で盛り上がる。
一瞬岩上がホッと一息吐くと、先ほどの空気が嘘のように、嬉々と話を広げ始めた。『えん』に来る客がスポーツなどの話題を出すことが多いのか、ひぃさんも楽しそうに、俺と岩上の話に相槌を打ってくれた。
ひぃさんには、不思議な魅力があった。人の話を引き出す力というか、小さな話題にも大袈裟な反応にしてくれるから、もっと話したいという気持ちが湧いて来る。従業員はひぃさん一人で、メニューも一つしかない、ひっそりとした店だったが、なるほど、これは常連が出来るはずだ。
「じゃあ、そろそろ帰るとするか」
岩上が立ち上がりかけたのを見て、俺は反射的に壁に掛けてある時計に目を向けた。時間はまだ二十一時四十分だ。『えん』に来てから、二時間強は経とうとしているが、それでも帰るには早い。
「おいおい、まだ夜は長いだろ。もう少し話そうぜ」
せっかく気分も盛り上がっているところだった。全然話足りない。それだけでなく、もっとひぃさんの話も聞いてみたかった。
だけど、岩上は困ったように眉根を下げるだけだった。
「ごめんなさい。私の体力のことを考えて、早めにお店を閉めさせてもらってるんです。ほら」
店の名刺を渡されると、確かに営業時間は十七時から二十二時と記載されていた。
「へー、そうだったんですね。でも、こんな短時間で、経営とか成り立つんですか?」
「お前な、そういうところだぞ」
頭に浮かんだ疑問を、単純に興味本位で聞いただけだったのだけど、岩上はあからさまに溜め息を漏らした。ひぃさんも苦笑いを浮かべている。
「すんません、こいつ。良い奴なんですけど、言葉が過ぎるところがあって……」
「いいのよ。功志くんは、気になったことが放っておけないだけですものね」
二人の言い方には少しだけ引っかかるものがあったが、ここで話を広げても、話がややこしくなるだけだ。こういう時に話を広げてしまうと、「おい鹿野、いい加減にしろ」と昔から多く詰め寄られた。そんなことを繰り返す内、そこだけは深堀をしてはいけないと察することが出来た俺は、「ええ、まぁ」と曖昧に頷くだけに留まらせた。
「けどね、料理でもそうなんだけど、あえて引くものを引いたら美味しくなるっていうのは、よくあることなんですよ」
ひぃさんは手を洗いながら、何でもないように言った。そして、毛の立ったタオルで手を拭くと、そのままレジへと立つ。俺と岩上は、それぞれの財布から千円札を出した。
「このクオリティで千円ピッタリって、めっちゃお得ですよね」
「あはは、ありがとうございます。もし良かったら、また食べに来てくださいね」
恭しく腰を折るひぃさんに見送られて、俺と岩上は『えん』を後にした。時間は、まだ二十二時になっていない。いつもなら二軒目に行っていたかもしれない。
けれど、なんとなしに俺と岩上はそのまま別れることにして、それぞれ家路へと着くことにした。
――裏Menu1――
創作料理店『えん』で、ひぃさんが振る舞ってくれた料理を食べてから、僕の身辺はすっかり変わってしまった。
まずは、僕がひぃさんの味の虜となったこと。
高野さんに誘われなくても、仕事が終わるや否や僕は一人で訪れて、ひぃさんの料理のお世話になった。多い時は週三で訪れるほどで、すっかり常連になってしまった。だけど、あまり長居しても迷惑になるかもしれないと危惧して、日替わりメニューを食べて、ひぃさんと他愛のない世間話を少し交わして帰るようにしていた。
ひぃさんの話は面白くて、何度話しても飽きることはなかった。
多くの雑談を交わしたけれど、ひぃさんの本名と年齢だけは分からないままだった。だけど、ひぃさんの人柄に惹かれているのだから、そんなのは些細なことだ。
ひぃさんと話した中で一番興味深かったのは、やはり料理に関する知識だ。
毎回異なる日替わりメニューを提供してくれるのだが、どこに拘りを入れているのか必ず教えてくれた。
料理の中で共通していることは、余計な味付けを減らすということだった。『えん』を立ち上げる前からずっと、いつか健康に気を遣った料理を作りたいと思っていたそうなのだが、その夢を『えん』で実現しているらしい。
――「メインは素材そのものを楽しんでもらうことで、あくまでも味付けは引き立たせるための脇役」
――「そしてね。大事なのは、塩の匙加減なの。この塩梅が少し異なるだけで、人の感じる味覚はとても変わってしまうんですよ」
ひぃさんはよく楽しそうに目じりに皺を寄せながら教えてくれた。
その僕に向けたでもないアドバイスが、僕にとっては突破口にもなっていた。
今までの僕は、自分のことを些細な人間だと思っていた。あえて料理にたとえるとするなら、たとえられないくらい微々たる調味料の一部だと思い込んでいた。
そんな僕には、課長なんて荷が重すぎて務まるはずがない。
だからこそ、高野さんから打診されていた昇進の話を、考えるフリをしていつまでも渋っていた。
だけど、ひぃさんの話を聞いて、そうではないと思った。
昔から人の懐に潜り込むのが上手だと言われていた。とにかく波風立てないようにしようと思っていただけで、自分の中ではそこまで大きな取り柄ではないと感じていたのだけど。
しかし、料理にも人にも適材適所がある。
一見するとマイナスなようにも思える僕の個性を活かすことが出来たなら。
高野さんのようにリーダーシップを発揮して纏める課長ではなくても、一緒に働く人を支えることなら出来る――、そう考えを転換させることが出来た。
昇進の話を受け入れる旨を高野さんに伝えると、
「真護なら安心して任せられるよ」
と満面の笑みで受け入れてくれた。
それが、僕の身辺が変わった二つ目の出来事。
それから、高野さんから課長業務を引き継ぐと、僕は新しい役職で仕事をすることになった。
最初は慣れない業務で手一杯になった。お得意先への挨拶、僕の後について仕事をしてくれる人のフォロー、書類の作成などなど。現場を支えるために、ここまでやるべきことがあるのかと驚きを隠せなかった。泣き言一つ漏らすことも、顔色一つ変えることもせず、こんな多くの業務を高野さんはこなしていたのか。改めて僕との違いを痛感させられた。
けれど、高野さんにしか出来ないことがあるように、僕にしか出来ないこともある。
課長としての業務の傍ら、現場への声かけも忘れなかった。また、現場時代の自分がされて嬉しかったことを、僕は精一杯行なった。
そのおかげかは分からないが、上長が変わるという出来事が生じたにも関わらず、現場が混沌とすることはなかった。みんな楽しそうに働いてくれている。むしろ、課長らしくない僕をいじってくる始末だ。
部長席に座る高野さんは、微笑まし気に僕達のことを見つめていた。
どうやら自分の中で重く考えすぎてしまっていたようだ。僕の悩みや心配は、杞憂に終わった。
もちろん、全てが上手く行ったわけではない。どうしようもない失敗を犯し、落ち込むことだってあった。
そんな時は、『えん』に行って、ひぃさんが振る舞ってくれる料理を食べて、ひぃさんと話せば、疲れも吹っ飛んでくれた。
これも全て、『えん』に行ったおかげだと思う。『えん』に行って、ひぃさんと出会わなければ、僕の凝り固まった思考は変わらなかったはずだ。
課長としての業務に慣れたある日、僕は一つの可能性に思い至った。
高野さんは僕自身の価値を認めさせるために、あえて『えん』に連れて来てくれたのではないか。
そう思ったことを高野さんに言うと、「考えすぎだ。俺はな、ひぃさんと美味いメシを誰かに薦めたかっただけさ」と笑って一蹴された。僕は一種の照れ隠しだと思ってるけど、高野さんの前で掘り下げることはしなかった。ひぃさんの前で言った時の高野さんを考えると、楽しみで仕方なかった。
僕も高野さんもお互いに忙しくなってしまって、ゆっくりと語らう時間を取れなくなっていた。それは仕事をする上では嬉しい悩みだとは分かっていたけれど、少しだけ寂しいことだった。
僕自身、最後に一人で『えん』に行ったのは、もう二か月とか三か月くらい前の話だ。ひぃさんの人柄がそのまま味になったような、優しい料理に恋焦がれている。
「……また行きたいな」
小さな呟きは、忙しい職場の中では誰にも聞かれることなく、溶けて消える。
「馬場課長。相談があるんですけど、今お時間いいですか?」
むしろ追い打ちを掛けるように仕事が降りかかる始末だ。僕は笑顔を作ると、
「うん、もちろんいいよ」
今では新たな案件が舞い込んでも、冷静に対処して周りの人も気にかける余裕は出来た。
あともう少しで、今取り組んでいる案件にも一区切りが付けられる。そうしたら、『えん』に行く時間も取れるだろう。よし、と頬を叩いて気合を入れ直すと、パソコンに向き直って資料を纏め始めた。
――僕は素材になって、誰かの目を惹くことは出来ない。だけど、塩のようにさりげなく、食材を支えることが出来る。
それが僕に任された仕事だと、今日も一日を頑張っていく。
――裏Menu2――
「こんばんは、ひぃさん」
扉を開くと、ひぃさんがカウンターの拭き掃除をしているところだった。来客の訪れにひぃさんは顔を上げると、「あら、功志くん」と親しみが込められた笑みを浮かべた。
「今日は一人ですか?」
「後から合流するんです。オススメの店を紹介するって言っておきました」
「嬉しいな。テーブル使います? それともカウンター?」
「カウンターで」
俺は迷わず答えた。あいつと二人きりで料理を楽しんでもいいけど、『えん』で食べる食事はひぃさんの人柄があってこそ味も倍増する、気がする。
カウンターに座ると、ひぃさんは慣れた手つきで水を前に置いてくれた。
「連れの方はいつ来られるの?」
「仕事が終わってから、って言ってました。なんか最近不調を乗り越えたみたいで、仕事をバリバリ任されるようになったらしくて。悔しいから、仕事が終わったって連絡が来るまで、『えん』の名前は出さないでやりました。あいつの驚く顔が楽しみですよ」
「あはは、初めて来た時の功志くんが嘘みたい」
ひぃさんは楽しそうにコロコロと笑ってくれた。そして、話の流れを遮らないようにさり気なく、
「はい、今日のお通し」
小鉢に入ったお通しを、すっと俺の前に置いた。今日のお通しは、小松菜のおひたし。ただの小松菜のおひたしなのに、なんでこんな美味そうに見えるんだろうなぁ。
単純な料理にこそ、その人の実力が垣間見える。だから、ひぃさんの料理の腕は、相当に確かなんだろう。
俺は「いただきます」と手を合わせてから、箸を伸ばした。
「どう?」
「すっげー美味いです」
口をもごもごさせながら言ったところ、「いつもお上手なんだから」と、ひぃさんは笑みを零した。
岩上に紹介されてから、何度か一人で足を運んでいるが、ひぃさんが振る舞う『えん』の料理はいつも美味しい。
最初はどこでも食えるような料理に辟易してしまったけれど、どの料理も平凡な名前に反して、通常では食べれない奥深い味だった。そして、味覚を刺激するだけでなく、俺の心までも刺激してくれた。
漠然として抽象的な話になるが、ひぃさんが作る料理を食べながら話を聞いていると、今まで気付かなかった自分の内面を見つめ直すことが出来た。まるで今まで慣れ親しんでいた料理でも、ひぃさんの手にかかれば、まるで違う料理になるかのように――、だ。
たとえば、初めて『えん』で肉じゃがを食べた日だって、俺の口数が多いことを再認識させられた。思ったことをすぐ言葉にする減らず口によって、昔から余計なトラブルが発生していたが、これも俺の性格の内だと割り切っていた。
けれど、この日は違った。何故か、この肉じゃがのように取捨選択しなければいけないのではないかと痛感してしまった。しかも一度だけではなく、ひぃさんの料理を食べると、似たような経験を多々した。
このままではいけないと察した俺は、自分の言葉を意識することにした。
すると、自分がどれだけ余計な言葉を口にしていたのかが分かった。そして、余計な言葉は、会話の質を下げる要因となる。
だから、まずは言わなくてもいいことを口にしないことから始めた。
気になって聞いたことだとしても、不躾で真っ直ぐな俺の言い方は誰かを傷つけている可能性がある。
そして、言わなくてもいいいことを抑えることが出来るようになったら、言ってあげたら嬉しいだろうことを言えるようにしていこう。
そうやって、段階を踏んで変わっていくことにした。
「お連れの方は、いつ頃来られそうなんですか?」
「さっき仕事が終わったらしくて、『えん』の場所を伝えたところなので、もう少しで着くと思います。真護、あ、そいつの名前なんですけど、割と近いらしくて……」
「真護……?」
この後合流する連れの名前を口にすると、ひぃさんは料理の手を止めて、俺の方を向いた。
「真護って、もしかして……」
ひぃさんの言葉は最後まで紡がれることもなく、ガラガラと引き戸が開けられる音によって遮られた。
ひぃさんは「いらっしゃいませ」と入口に向けて言った。俺もひぃさんの視線を追うように、入口を見ると、
「オススメしたい店って、『えん』のことだったのか」
旧友である真護が、息を切らした姿で立っていた。課長という役職を得たせいか、前に会った時よりも顔つきが変わったように思う。
真護は慣れたように、ひぃさんに会釈をすると、俺の隣に腰を下ろした。
「あら。やっぱり、功志くんの連れって真護くんだったんだ。お久し振りです」
「はい、ご無沙汰してました」
ひぃさんの接し方は、常連に対するそれと同じだった。真護は嬉しそうに挨拶を交わす。
「え、もしかして既に知ってた?」
「うん。一年くらい前に、一度上司に連れて来てもらったんだ。そしたら激ハマりして、常連になっちゃって。まぁ、ここ二、三か月くらいは、仕事が忙しくて来れなかったんだけどさ」
「で、その真護くんがいない間で常連さんになったのが、功志くんなの」
「なんだ、驚かせようと思ったのに、俺が一番驚かされてるじゃん」
「いやいや、僕も十分に驚いてるって。でも、本当に早く『えん』に来たかったから、今日来れてすごく嬉しいよ」
「相変わらず、真護くんは言葉が上手ですね。高野さんは元気?」
「はい、元気ですよ。部長の席で、めっちゃ大声で笑ってます」
「あはは、すごく想像出来ちゃう」
どうやら真護は『えん』にかなり通う常連だったようで、俺の知らない人物の名前を、ひぃさんと楽し気に語り合っている。何だか置いてけぼりになった気分になって、隣に座る真護に肩をぶつけた。
「なんだよ、俺と来るの不満みたいじゃんか」
「いやいや、そんなことないって。久し振りに幼馴染の近況を聞けるのは、すっげー嬉しいよ」
「なら良いけどさ」
そう言うと、俺は水を一口飲んだ。水を飲む間、ずっと視線を感じていた。隣を見ると、まるで肩透かしを喰らったかのような素っ頓狂な顔を浮かべる真護がいた。
「どした?」
「いや、今までの功志なら、もう一言か二言言ってたよなって思ってさ」
「……ああ」
真護の指摘に、合点がいった。
それもそうだ。『えん』に通うようになってから、言葉を吟味して、無意識で誰かを傷つけないように言葉遣いに気を付けている。
俺は反射的にひぃさんに目を向けた。全てを分かっているかのような穏やかな目を、俺に注いでくれていた。
俺が変わることが出来たのは、『えん』でひぃさんと話をしたおかげだ。直接的には関係ないことばかりかもしれないけど、素材に味が染み渡るように、俺の腑に落ちて来た。
俺が変わることが出来た話を、真護に話してみよう。
「不必要なものを取り除いた方が、上手くいくって気が付いたんだよ。料理のようにな」
「へぇ、その話聞かせてよ。僕にも似たような話があるんだ」
真護は目を輝かせながら、俺に続きを催促してくれた。
それから、ひぃさんの日替わりメニューが振る舞われるまで、お互いの話に花を咲かせた。
――Original Menu――
「光莉の料理って、特徴がないよね」
夫の突然の容赦のない言葉に、洗っていた皿を落としそうになった。「おいっ」という声に、ハッと我に返り、自分でも驚くような反射神経で皿をキャッチした。食器を一つ無駄にしなかったことに安堵すると、「危なかったぁ」と互いにホッと息を吐いた。
皿洗いを再開させると、
「で、特徴がないってどういうこと?」
「あ、ごめん。ないというよりも、なくなっているっていうべきなのかな。なんていうか、どこでも食べれる味っていうか……、昔はもっと光莉らしさがあったような気がしたんだけど」
「だって、しょうがないじゃない。私が勤めてるのは、ファミレス。求められているのは、変わらない味なんだもん」
料理の道を突き進もうと決意した当初は、有名な料理店に弟子入りもした。けれど、求められるクオリティの高さに、昼夜問わず働く忙しさに、私は音を上げてしまった。七年ほど勤めた料理店を後にした。
それからファミレスの厨房スタッフとして働くことになり、この時点で十年近く経とうとしていた。有名料理店で働いた腕前は、ファミレスの中では十分すぎるほどに発揮されて、私はパートリーダーとして生き生きと働かせてもらっていた。
私の言い分に、夫は渋々と頷きながらも「でも、昔食べた光莉の料理は、もっと特別だった気がするんだよな」と、まだ納得していないように呟いている。
「はい、この話は終わりね」
「あ、それと。最近の料理、濃い味付けで誤魔化そうとしていない?」
ふいに口をついた夫の指摘は、ずばりと私の内心を見抜いていく。
夫と出会ったのは、まだ私が有名料理店に勤める前のこと。つまり、私が自分だけの料理の道を突き詰めようと、躍起になって行動していた時のことだ。
当時の私は、料理を食べてくれた人が健康的になることを願っていた。そのためには、濃い味付けをしたら体を害してしまうと考え、薄く優しい味付けになるようなメニューを心がけていた。
だけど、社会人として料理の道に進むと、私の考えは夢物語だということを痛感させられた。
社会で求められるのは、万人受けする味だった。そのために、味を濃くすることを強いられた。
自分の拘りを貫けるほど、料理の世界は甘くなく、私の志は次第に折れていった。そして、無難に万人受けする味付けが、私の手には染み付いてしまっている。
「だって、楽なんだもん。慣れちゃったし」
「そうなんだけどさぁ」
夫は文句を言いながら、私の料理に箸を伸ばしていく。そういえば、私の料理を夫が美味しいと言ってくれたのは、いつだっただろう。久しく聞いていない。
私自身、家で振る舞う料理をなおざりにしてしまったことも原因だ。
薄味で美味しいと感じてもらうためには、絶妙な塩加減が必要となる。少しでも塩が足りなければ味が感じられないと言われるし、逆の場合は塩味が強すぎて受け入れてもらえなくなる。要するに、紙一重の業が求められる。
日々働く中で、そこまで家での料理に求めることは容易ではないし、合理的でもない。
だけど、悔しかった。あそこまで言う必要ないじゃない。
そう思い至ったら、私の闘争心に火が付いた。
その日の夜、夫を起こさないように、私は昔のレシピを棚の奥からこっそりと探し出した。十数年ぶりに手に取ったレシピノートは古びていた。よく残っていたな、と我ながら感心した。
レシピを開いた。
そこには、とうに忘れてしまっていた情熱とともに、事細かに食材や調味料が記載されていた。改めて見ると、すごい薄く感じられてしまうのは、私の思考が一般的なものに染みてしまった証拠だ。
だけど、そこには若々しさがある。
ああまで言うなら、やってやる。私の料理に文句を言ったことを後悔させて、そして、絶対に美味いという言葉を引き出してやる。
次の日、さっそく私は忠実にレシピを再現した。絶妙な塩加減をした、鯖の塩焼きだ。
「そうそう、これこれ。昔食べた光莉の料理の味そのものだ」
美味しい美味しいと、大皿に盛り付けた料理が夫の口の中へとなくなっていくのを見て、私は心底満たされていた。
こうやって純粋に私の料理を食べてもらえて、目の前で反応してもらえる経験って、いったいいつ以来かな。
有名料理店に勤めてからは、いつも裏に回って仕込んでいたし、今のファミレスだってキッチンにしかいない。夫だって、私の濃い味に慣れてしまって、何も言わなかった。
って、あれ。そう考えると、料理の道を決意してから、本当に見てなかったんじゃない? そもそも反応を見たくて、料理人の夢を志していたというのに?
「なぁ、光莉。この味なら自分の店だって持つことが出来るんじゃないか」
すっかり平らげてくれた夫は、お腹を擦りながら言った。「なにそれ」、と私は夫の冗談を笑って一蹴する。
実のところ、今日料理を作っている中で感じていたことでもある。
昔のレシピを忠実に再現していると、当時に思い描いていた理想を叶えてみたいと思うようになった。私の料理を食べてくれる人が、身も心も元気になる姿を、間近で見ることが出来たらどれほど嬉しいことだろう。
けれど、とうに四十を迎えてしまった。なのに今更になって、自分の店を持とうとするなんて、非現実的だ。
そう思って、私自身諦めかけていたのに。
しかし、夫は笑わない。終始、真剣な面持ちを貫いていた。
「……もしかして本気で言ってる?」
「もちろん。だって、こんなに美味しい味を独り占めするなんて、もったいなくて出来ないよ。それに、ずっと自分の店を持ちたいって言っていたじゃないか」
「けど、今の私の体力じゃ、お店を持つなんてこと出来ないよ」
「いいじゃないか、光莉のペースでやれば。気軽に訪れられない隠れ家的な店になって、一定のファンもつくと思う。それに、最近になって、そういう小さな建物を売り出している不動産と知り合ったんだ」
「私、人の雇い方なんて分からないし」
「無理して雇う必要もないよ。一人でこっそり始めて、厳しそうだったら雇えばいいんだ」
「でも、やっぱり……。私が作ってる料理って、塩加減も最低限にしてるから、印象に残らない味なのよ?」
やらない理由は、いくらでも口から飛び出して来る。その中でも、一番ネックなのは最後に言葉にした理由だ。
世間一般的には、味を濃くしてこそ、という風潮がある。もしくは、写真に取りたくなるような見栄えのいい料理が人気になることも多い。
私の料理は、真逆だ。
問題は料理自体だけじゃない。私の潜在意識には、一般論が染み渡っている。きっと私の味は受け入れられない。どこかでそう思い込んでいた。
「だからこそ、いいんじゃないか」
踏み出さない私を、夫が一蹴した。
「塩分は入れすぎれば体に毒になるけど、だからと言って入れなければ、味気はない。塩は加減が重要だ。その絶妙な采配を、光莉は心得ているんだ。光莉の料理は、誰かにとって必要不可欠なものだと、俺は思っている」
「店を開いても、その誰かに巡り合わなかったら……」
「もう俺がいるじゃん」
さも当然のことを言うかのように、夫は笑いながら言った。
「だから、一人も巡り合わないってことは、絶対にあり得ないよ。光莉の味を待っていて、食べた瞬間に好きになってくれる人は、必ずいるんだ」
夫は昔から確信のないことを、堂々と宣言してしまう節があった。そして、何故だか分からないけれど、その宣言はだいたい当たる。
「やってみなよ。応援してるし、俺に出来ることなら何でもする」
そこまで言われたら、突拍子もないように思えた提案を受け入れない訳には行かなかった。
それから私はファミレスの調理スタッフを辞め、店を開くための準備をした。
最初は分からないことだらけの連続だったが、慣れたら何とかなるものだ。
夫や周りの人のサポートを受け、私は『えん』を始めるに至った。
――これが私が『えん』を始めるきっかけだった。
私が願いを籠めた通りに、『えん』。
店に名付けた『えん』という言葉には、様々な意味が込められている。縁、円、宴、援、塩。他にも意味が込められている。ありきたりかもしれないけど、私が思い描く理想にピッタリだった。
そして、実際に『えん』を開店すると、今回もまた夫の言ったことが当たった。私は多くの縁に恵まれて、たくさんの人に料理を食べてもらうことが出来た。それだけではなく、何度も何度も足を運んでくれる人まで現れた。
私の拘りをとことん貫いた『えん』に、大声で文句を言われることもなかった。
まさか十数年前に描いた理想が、この年になって実現するようになるとは、夢にも思わなかった。
なんとなく過去を回想してしまったのは、今日の日替わりメニューが、夫に振る舞った時と同じだったからかもしれない。香りには、記憶を掘り起こす力がある。
私は日替わりメニューを丁寧に皿に盛り付けると、
「――今日は鯖の塩焼きよ」
常連になってくれた真護くんと功志くんの前に置いた。
「シンプルで最高じゃないですか」
「一人暮らしだと、普段魚なんて食べないから嬉しいです」
二人はいつも子供みたいに顔を輝かせてくれる。そして、「いただきます」と手を合わせてから、箸を動かし始めた。
「美味っ」
「久し振りのひぃさんの料理、ほんと生き返ります」
真護くんと功志くんが、それぞれ感想を口にする。
私が作った料理を食べてくれて、美味しいと口元を綻ばせてくれる姿は、私にとって何よりのご褒美だ。「よかった」、と思わず安堵の声を漏らす。
そして、二人が箸を進めていく内、ふと話したいことが脳裏に過った。
「ねぇ、料理でも何でもそうだと思うんですけど」
あえて言葉を区切ると、真護くんと功志くんが興味深そうに耳を傾けてくれている。
「人に何かを振る舞う上で肝心なことって、何だと思いますか?」
<――終わり>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
