
高橋睦郎+藤井貞和 対談「日本語詩歌の深層から」
☆mediopos-2359 2021.5.2
高橋睦郎が示唆しているように
「現代詩のなかに現代自由詩と現代定型詩があって、
現代定型詩のなかに現代短歌と現代俳句がある」
そうとらえたほうがいい
そして「詩」とされるものの奥行きには
<うた>われてきた言の葉の大海がある
それを古典と表現してもいいのかもしれない
「詩」として表出されているのは
その広く深い言の葉の
海面上の波のようなものなのだろう
波の形しか見えない者は
そして波の形を見て
奥にある言の葉をとらえ得ない者は
海を知らずに海を語ろうとする者である
そして知らずその海に呑み込まれて
みずからの言の葉を死んだものとしてしまう
現代自由詩
現代定型詩
現代短歌
現代俳句
そうしたジャンル分けがあるとして
それらのジャンルの
そのまたさまざまな派だけで表現される
「波」しか見ないでいることは
ほんらいあり得ないことだろう
しかも「現代」ということについても
それをどう意識するかが不可欠になる
時代が過ぎれば「現代」は
「前代」になりえるからである
「現代」という以上
その時代に見えている言の葉と
ともに歩まねばならないだろうが
それが流行語のように「前代」と化さないためには
そこに古典という言の葉の大海への視線が不可欠になる
しかもその古典と称されるものは
たんなるアーカイブなのではない
それはまさに「冥界の聲」でもあり
現在まさに言の葉に起こり続けている
変容そのものの根源にある力でもあるからだ
高橋睦郎が歌人・詩人たちの「二十七の聲」を
召喚しようとした試みも
まさにそうした古典そのものである「聲」を
「日本語詩歌の深層」である「冥府」という伝統から
生きたかたちでとらえなおそうとしたものなのだろう
■高橋睦郎+藤井貞和 対談「日本語詩歌の深層から」
■江田浩司「<うた>の羽音、冥界の聲」
※上記/『現代詩手帖5月号』(思潮社 2021.5)所収
■藤井貞和『<うた>起源考』(青土社 2020.7)
■高橋睦郎『深きより 二十七の聲』(思潮社 2020.10)
(江田浩司「<うた>の羽音、冥界の聲」より)
「藤井貞和の大著『<うた>起源考』の刊行が、二〇二〇年七月十日であることに、私は運命的なものを感じる。この日付に、心動かされないわけにはゆかないのである。この日、短歌の可能性を極限まで追求しゆづけた岡井隆が、静かに息を引き取っている。
折口信夫は「歌の円寂する時」の冒頭に、島木赤彦の死を滅びゆく歌のように記していた。藤井の書に岡井の死が記されることはない。が、藤井が本書で示唆した短歌の命運は、折口が島木の死によって感じた以上に、私には切実な問題であると思われてならない。岡井という現代短歌のリーダーを失った今、歌人は、それぞれがそれぞれの短歌観にもとづいて、アクチュアルな歌の状況に直に向き合ってゆかなかればならない。本書で藤井が考究した、<うた>の起源と現代短歌に至る変容の様態に、実作上の希望を受け取るのか、滅びゆく歌の危機を自覚するのか、歌人の創作への姿勢と覚悟が問われているだろう。」
「藤井は<うた>の起源と<うた>の本質を、深く、広く見渡し、その分析を通した上で、現代短歌に言及するとき、現代短歌と現代詩の協働が、喫緊の問題であることを示唆している。<うた>の内在する「詩」の本質の観点からは、詩と短歌は切り離しえない。藤井のいう「真の文法」は、「詩」表現としての短歌を支えると共に、現代詩を支えている。思えば、現代短歌と現代詩の協働は、岡井隆の願いでもあった。だが、現歌壇の中心に位置を占める、文語定型派の歌人の多くは、現代短歌と現代詩の協働から目を背け、むしろ、そのような働きを意識的に断とうとしている。本書の画期的な論考は、創作者、研究者を問わず、詩歌表現と詩歌研究に意識的な人々に多大な影響を与えるだろう。それと同時に、現代短歌と現代詩の協働かた目を背ける者を、潜在的に告発する書でもある。
さて『<うた>起源考』の刊行から二ヶ月後の十月下旬に、高橋睦郎の新詩集『深きより 二十七の聲』が上梓された。本書は、第一の聲の稗田阿禮「深きより」から始まり、第二十七の聲、河竹黙阿彌
「悪の華くらべ」に終わる。二十七人の先人に成り代わり、彼らの聲を現在の詩の場に甦らせた詩集である。本書の最後には、跋に代えた、三島由紀夫との創造的な対話「半世紀ののちに」が配されている。この対話の虚無的な結末には旋律を覚える。この対話の結末から、二十七の聲すべてが照り返されてゆく。
高橋は「伝統という冥界下り/重ねての代跋」と題する「栞」に、自分が三島と対話ができたのは、生前の三島が「広い意味での詩を求める者だったからだろう」と記している。その上で、「古代からの自国語の詩歌の先人たちの降霊の真似事を試みたのも同じ理由からだ」と説明する。その降霊も自己の発明ではなく、例えば芭蕉の「おくのほそ道」の旅は、宗祇に加えて西行の旅のまねびであり、芭蕉の先人への追体験は、「言い換えれば彼らの霊との交流、冥界下りだった、といえよう」と記す。先人たちの「詩」との対話を通して、高橋が浮かび上がらせた「聲」は、伝統という名の冥界の、豊穣な海の波音であるのかもしれない。」
(高橋睦郎+藤井貞和「日本語詩歌の深層から」より)
「高橋/「現代詩」という言い方でぼくが気になるのは、現代詩に対して短歌、俳句という言い方をして、現代詩だけが現代性をもっていて、短歌、俳句は現代性をもっていないかのように言うのはどうか。現代詩のなかに現代自由詩と現代定型詩があって、現代定型詩のなかに現代短歌と現代俳句がある。
藤井/睦郎さんが現代詩という言い方に対して、チェックポイントをきちんと立てられているのはだいじなことで、安易に現代詩と言ってはいけない。現代が前代になったら現代詩は前代詩になるじゃないかと、睦郎さんが言っていたけれども、逆に現代が現代でありつづけるために、短歌や俳句も含めて現代を考えつづけようと。」
「藤井/詩と、それから短歌、俳句という広がりは睦郎さんの他にいない。その睦郎さんが俳句に希望を持ちつづけるというのは目の醒める思いがしまう。短歌は解体しろと(笑)。
高橋/そんなことはないですよ。いまや解体が不可抗力なら、解体は再生のための解体であってほしいというところでしょうか。ぼくは昨年岡井さんが亡くなったことと関係があるのかどうか、亡くなって一ヶ月くらいから、へんに短歌ができていて、ほとんど毎日作っているんです。塚本邦雄、岡井隆、そのあいだに玉城徹。この三人が亡くなって、古典という縦軸と世界文学という横軸を考えながら作る人がいなくなった、と感じる。短歌だけでなく、俳句、それから自由詩にも以外にないんじゃないか。これはゆゆしい事態で、もはや自分がその器であるとかないよか考えていられるような場合ではないので、とにかく作らなきゃと思って作っているんですけどね。
藤井/睦郎さんのなかから歌と俳句が湧いて出てきている。とてもいい光景だと思っています。若き俳句詩人、短歌詩人も含めて、定型詩人たちに睦郎さんが希望をつないでいく。いま光景と言ったけど、それを目の当たりにして、自由詩でだいじなことを言い残していらっしゃる。
高橋/いろいろ勝手なことを言いましたけど、自由詩も含めてこの国の<うた>は現在、大きく変わろうとする苦しみのなかにあるのでしょう。その先端にあって身をもって苦しんでいるのが若い人たちですが、ぼくも彼ら、彼女らの驥尾に付けて、よたよたとでも苦しみつづけたいものです。苦しむ力が少しでも残っている限りはね。」

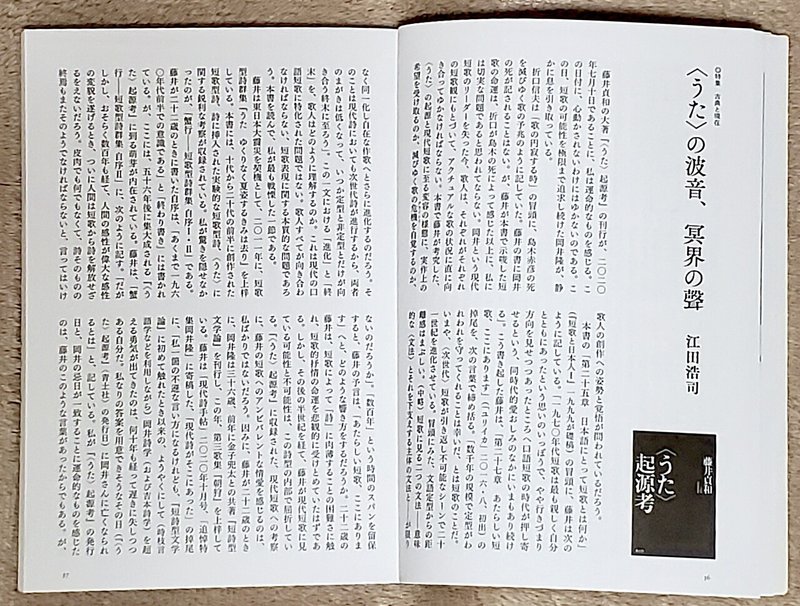
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
