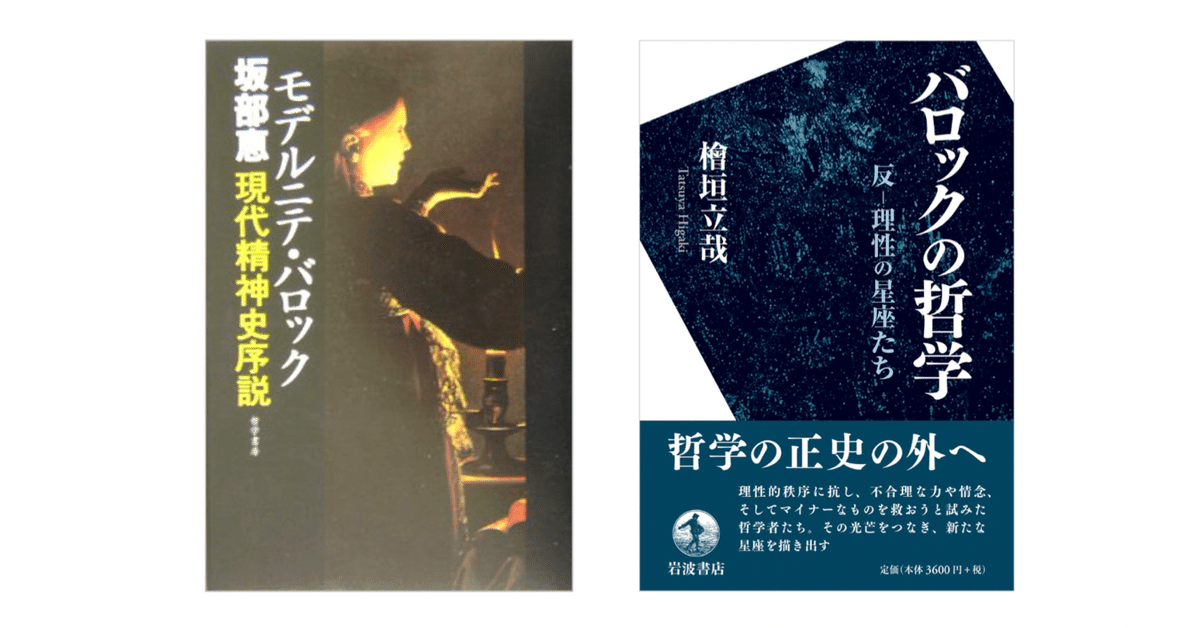
檜垣 立哉『バロックの哲学/反-理性の星座たち』/坂部 恵『モデルニテ・バロック』
☆mediopos2775 2022.6.23
「バロックの哲学」といえば
本書の最初の章で論じられているように
坂部恵の「モデルニテ・バロック」である
「バロック」とは「歪んだ真珠」を意味する
ポルトガルの言葉から由来するように
「バロックの哲学」は哲学の「正史」からみれば
歪んだ哲学とみなされるかもしれない
檜垣立哉が本書で試みた「バロックの哲学」は
いわゆる理性的な秩序や合理主義に抗するように
坂部恵が灯した不合理な力や情念を解放し
非調和的な世界をこそ哲学しようとした試みを
ドゥルーズ・ベンヤミン・ホワイトヘッド・オルテガ
ベルクソン・ジェイムズ・パース
そして西田幾多郎・九鬼周造・レヴィ=ストロースといった
「反−理性の星座たち」のなかに見出そうとする
それは二〇一三年から昨年二〇二一年までのあいだに
書きつづけられてきた論考であり
今回少しだけとりあげてみたのは
その最初に書かれた
「坂部恵とモデルニテ・バロック」についてである
坂部恵は「バロックの復権は哲学史をどう書き換えるか」
において若き日のベンヤミンの
『ドイツ悲劇の根源』を重要視している
坂部恵はベンヤミンの示唆している
アレゴリーを「バロック哲学」を支える「方法」とみなす
アレゴリーは「理念的なものを他のものによって
語ったり描いたりするもの」だが
「具体的で感性的な個物こそが、
抽象的な普遍を提示する可能性をはらんでいる」とし
断片としての「個」を
そのまま「全体」と連関させていく
ベンヤミンは「個」と「普遍」という問題に
「両極端の合致」という仕方で応答しているというのだ
「個」は「個」だけで存在するわけではないが
決して「普遍」や「理念」に回収されたりはしない
断片としての「個」である「モナド」は
それらの「星座」や「布置」において
「普遍」や「理念」と「両極端の合致」をなしている
「「個」の感性性を重視しながら、
同時に「理念」のレアリスムを手放さず、
「個」が成立するシステムをそのまま肯定する」ということ
「個」と「理念」
「個」と「全体」は
一方から片方が演繹されるものではないが
調和的でではないとしても
対立しているわけでもない
そのありようを近代的時間である
「時間−歴史的な進歩性」を破棄する
つまり垂直的な時間によって
「個」を「全体」や「理念」の桎梏から解放しようとする
「バロックの哲学」はその意味で
「近代主義的でありながら同時に脱近代的なもの」であり
カント主義を淵源にもつ現象学や
論理的合理性を事とする分析的学といった
二〇世紀の「二大潮流」によって
マイナーにされてしまった哲学の系譜の断片
それらを「星座」として描きだそうとしている
それらのそれぞれがどんな星座なのか
今後機会をみてとりあげてみることにしたい
■檜垣 立哉『バロックの哲学/反-理性の星座たち』
(岩波書店 2022/6)
■坂部 恵『モデルニテ・バロック―現代精神史序説』
(哲学書房 2005/4)
(檜垣 立哉『バロックの哲学/反-理性の星座たち』〜「第1章 坂部恵とモデルニテ・バロック」より)
「『モデルニテ・バロック』では、その各章の題目からも窺えるように、小林秀雄とキルケゴール(モーツアルトをめぐって)、九鬼周造と萩原朔太郎、和辻哲郎とヨハン。ゴットフリートヘルダー、岡倉天心とフリードリッヒ・シェリング、メルロ=ポンティた多彩な思想家のテクストが縦横矛盾に論じられ、相当に逸脱気味な記述も含みながら広域的な議論が展開されていくのだが(・・・)この小論考(「バロックの復権は哲学史をどう書き換えるか————二十世紀の哲学の回顧と二十一世紀の展望」)では、あつかうべき材料を大幅に限定している。そこで重要視される人物は、何はともあれヴァルター・ベンヤミンなのである。
(・・・)
ここで具体的に論究されるのは、『ドイツ悲劇の根源』(一九二八)を著した若き日のベンヤミンである。(・・・)
ここでのベンヤミン評価のポイントは三つある。
まずは、まさにベンヤミンが、『ドイツ悲劇の根源』において、バロック悲劇とギリシア悲劇を対比しつつ、バロック悲劇の根幹をなすものとして、断片としての「個」をそのまま「全体」と連関させていく「アレゴリー」の概念をとりだしてくることにある。アレゴリーとは、(・・・)「バロック哲学」を支える「方法」とみなすことができる。(・・・)
ついで、『ドイツ悲劇の根源』の序論をなす「認識批判論序説」で論じられる「個」と「理念」の「モナド」的な関係性そのものにある。これは、もちろん上述のアレゴリーの方法と呼応しながら、哲学的概念としての「バロック」をとりだすときの鍵になるものである。「モナド」という概念は、この言葉を編みだしたライプニッツとの関連をどうとらえるのかは別としても、「バロック哲学」を規定するときの根幹的なタームといえる。「モナド」の概念をもちいることによってみいだされる、断片としての「個」と、その彼方に「星座」として描かれる「理念」との捻れた関連が、バロック哲学を展開する軸になるのである。
そして最後に、「モナド」とともに提示される時間や歴史の概念についてである。ベンヤミンは、アレゴリーをもちいた叙述によって、モナドとしての実在を描き出すのであるが、こうした議論が向かうひとつのテーマは、まさにその時間性や歴史性そのものにある。こうした発想は、最晩年の「歴史の概念について」(一九四〇)に直接むすびつく。だが坂部は、初期ベンヤミンのアレゴリー的な発想自身が、垂直の時間性を織りこむことによって、はじめから現代における時間意識の解体に強く関連しているととらえていく。」
「アレゴリーとは、抽象物を具体的なものによって、理念的なものを他のものによって語ったり描いたりするものであった。そこでは具体的で感性的な個物こそが、抽象的な普遍を提示する可能性をはらんでいることになる。一般的にいえばこれは、具体的である個が、どのようにして普遍である全体を指示しうるのかという「喩」の問題として解釈されがちである。だが、より着目されるべきは、中世哲学以来の広い射程をもつ「個」と「普遍」というきわめて広大な問題に、ベンヤミンは「両極端の合致」という仕方によってひとつの応答をなしていると、坂部がとらえていることの方にある。
そこでは「個」は「個」としてありつづけ、合理的で理性的な「普遍」によって「蹂躙」されることのないその「感性的」な位相が重視されている。(・・・)それはドゥルーズが「出来事」や「特異性」という言葉によって表現しようとしていることにきわめて近いといえるだろう。
だがベンヤミンは、こうした「個」がただそれだけで存在すると考えるのでもない。「個」はいつでも、普遍や全体を「星座」や「布置」として描きだすのである。むしろこうした「理念」が叙述されることによって、「個」が「個」としても「救済」されるとのべうることになるのである。これはレアリスムとイデアリスムの、「個」と「全体」の、ベンヤミンによる「両極端の一致」にほかならない。」
「「個」の感性性を重視しながら、同時に「理念」のレアリスムを手放さず、「個」が成立するシステムをそのまま肯定すること。そこで「個」と「理念」、「個」と「全体」の関係が提示する、けっして調和的ではない(一方が他方から演繹されるものではない)が、対立的でも闘争的なわけでもない側面をきわだたせること。そしてそれを、近代的時間の極限としての、時間−歴史的な進歩性の破棄することによってひきたてること。
バロック哲学とは、近代主義的でありながら同時に脱近代的なものである。それはフーコーが評価するカント、ベンヤミンが協調するボードレール、そしてドゥルーズが随所で引用する一九世紀的思考をひきついだ「近代的思考」なのである・それは、イデアのレアリスムを肯定するという意味で、まったき近代性の思考である。しかしそこには、近代にお決まりの、合理主義的な普遍主義、概念の抽象運動、言語の分析にすべてをゆだねる姿勢はみうけられない。
自然の実在をイデアのレアリスムにかさねあわせること。それは近代という時代を、そこからすべてが等しくみとおすことが可能になった頂点=終焉として描いていくものである(フーコーやドゥルーズの時間や歴史にかんする議論は、この発想にたたないと理解できない)。そして、本当のことをいえば、こうした地平から時間をとらえることは、すべての人類はなしてきたことでもある。そうした意味で、バロックのモデルニテは、あらゆる時間=時代のなかに偏在する。
そうであるがゆえにこの思想は、進歩という発想をとらないことにより、徹底してマイナーなものを救済する。それは、ベンヤミンののべる歴史の塵屑、ドゥルーズの提示するあらゆる分類を逃れる微細でマイナーなもの、これらを意識と言語からひき離しながら救いだすものである。マイナーなものは、ドゥルーズがのべるように、けっして少数なのではない。マイナーなものは、つねにメジャーなものよりはるかに膨大であり、多種多様であった。それもそのはずだ。マイナーなものは数えることが不可能な無限の襞のなかに、無限の潜勢力のなかに、それ自身として巣くっているのだから。
その力を解放しなければならない。それは言語と意識による近代主義にとっては想定もできない何ものかの解放でありうるだろう。それと同時にそれは、どこまでも古くからそこにありつづけ、これからもそこに存在しつづけるであろうものの解放であるだろう。」
