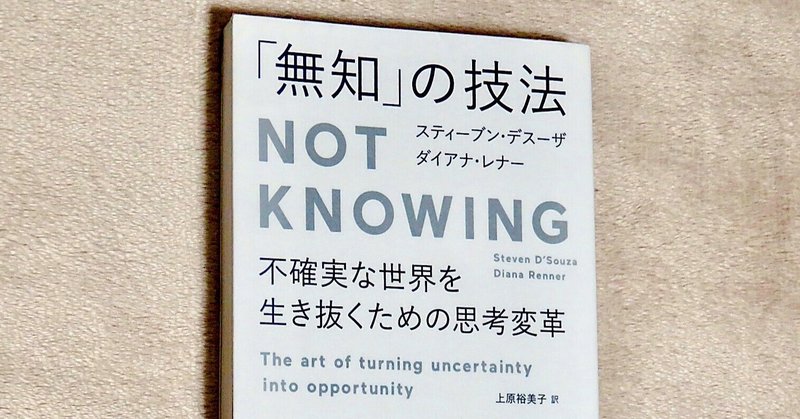
『「無知』の技法/不確実な世界を生き抜くための思考変革」』
☆mediopos-2297 2021.3.1
「仏に逢うては仏を殺し、
祖に逢うては祖を殺せ」
臨済録にある有名な言葉だ
仏や祖を
キリストやシュタイナーなどと
置き換えても意味は変わらない
殺すというのは
依存を去れ
自由であれ
という意だろう
知恵熱と信仰熱はコインの裏表で
知識への崇拝と権威への崇拝は
依存症のふたつの極だともいえる
知らないということ
寄るべき権威をもたないということ
このふたつの状態は
そうした依存症を生きる者とっては
かぎりない恐れとなるだろう
知らないことを恐れ
権威をもたないことを恐れるのは
「自分自身と向き合わざるを得なくなり、
自分の弱さ、不完全さをつきつけられるからだ」
しかし人は『ない』を受容する力
(ネガティブ・ケイパビリティ)によって
はじめて創造的であり自由であり得るといえる
そして『ない』がゆえに
変化ということに対して柔軟でいられる
多くの場合
知らないということ
寄るべき権威をもたないということは
「愚者」であることを意味する
しかし愚者であるがゆえに
仏を祖を真に受容することができる
権威化し信仰の対象にして
その庇護のもとに安住することは
むしろ仏を祖を否定することになるのだ
それらが真の権威であるならば
その権威はみずからこう言うはずだ
「私を権威としてはならない」
「私の言葉を鵜呑みにして信仰し従ってはならない」
「私の言葉があなたの真実の言葉として発されるときだけ
その言葉はほんらいの意味となり
あなた自身こそがみずからの権威となる」
■スティーブン・デスーザ/ダイナー・レナー(上原裕美子 訳)
『「無知』の技法/不確実な世界を生き抜くための思考変革」』
(日本実業出版 2015.11)
「何かを知りたいとき、それを「知らない(not knowing)」ままでいる状態はつらい。つらい状態は避けたいが、人として生きる以上、すべてを知ることは不可能だ。だから私たちは答えをする人のほうを向く。専門家、リーダー、その他の知っていそうな人。一方で、自分に多少なりとも知識があるときは、その知識が自分の手から消えていくことを恐れる。私たちは神経学的に、予測のつかないものを避け、確実なものを好むようにできているのだ。曖昧な状況、不透明な状況は、私たちに無力感を抱かせる。恥ずかしくうしろめたい気持ちにさせる。
だが、私たちが住むこの世界は不確実だ。複雑で、不安定だ。直面している複雑な問題を解決するどころか、はっきりととらえることすらできない。自分の知識がおよぶ範囲ぎりぎりの境界線に立たされると、私たちは既存の知識にしがみつくか、手っ取り早い系かつを試みるか、あるいは状況そのものをそっくり投げだそうとする。」
「本書はハウツーガイドではない。よって、はっきりした答えも提示しない。かわりに、科学、アート、文学、心理学、ビジネス、信仰、伝統的な知恵など、幅広いレンズを通じて、知らないということについて考察していく。」
「リサーチと執筆のプロセスを通じて、私たちは知らないということに向き合った。今の私たちは既存の知識に依存しない。確実だと断言する声には疑いのまなざしを向ける。そして、知らないことに対して、以前より安心して接するようになった。あなたにも同じ変化が訪れることを、私たちは願ってやまない。」
「深い知識と専門的研究への注力があるからこそ、専門家になれる。専門領域に貢献することができる。だが、逆に、深い知識と専門的研究への注力があるからこそ、視界が狭くなることがある。専門性を評価されている人間は、往々にして、その領域の外をしっかり見ようとしない。そうしようというインセンティブがない。また、専門性が高くなればなるほど、視野が狭くなる場合もある。「知っていること」に焦点を置くあまり、知っていることを疑ったり、知らないと認めたりすることができなくなるのだ。」
「私たちは周囲からのプレッシャーを敏感に察知して、自分の力不足や無能ぶりを隠そうとする。たとえ答えを知らないときでも知っているふりをしたがるーーーーあるいは反対に、ほかの人は知っていると信じたがる。専門家を探し、すべてを知っていると思いこむ。証拠が正反対を示しているときでさえ、他人の確信を疑って自分で判断するよりも、偽りの確信に依存するほうを選ぶのだ。特に、自分より上に立つ者との関係において、この傾向は何より深刻に顕著となるのである。」
「どんな立場でも、どんな肩書きでも、人はものを知っているふりをしたがる。」
「権威に対して服従していれば、知らないという不安や苦しみを感じないですむ。だが、盲目的に服従することは、正しい判断をする力も、本当の能力を発揮する力も奪う。最悪の場合、それが悲惨な結果を招きかねないのである。」
「私たちが未知を恐れる理由のひとつは、自分自身と向き合わざるを得なくなり、自分の弱さ、不完全さをつきつけられるからだ。」
「人は、知らないという内面的体験と、有能という印象を維持したい外面的問題とのあいだで、葛藤を感じる。」
「既知と未知との境界線に立った私たちは、知らないことを恐れるのである。」
「既知と未知との境界線に立たされたとき、自分はとっさにどんな反応をしてしまうのか。それを心得ていれば、意識して境界線の向こうへ踏み込み、その先を探りながら、新しいスキルや能力を育てていくことができる。」
「「わからない」と認めるからこそ、ものを学べるのだ。知らないという闇は、新たな光を呼び込む自由と余白を差しだしている。」
「西欧の神学と哲学には、知らないという姿勢を「不可知の道」と表現する奥深い伝統がある。」
「不可知の道とは、単なる「ものを知らぬ無知」とは異なる。中世ではこれを「stulta sapientia」と呼んだ。「知ある無知」「愚者の知恵」という意味だ。」
「イギリスを代表する詩人、ジョン・キーツは、1817年12月21日に兄弟にあてて書いた書簡で、シェイクスピアがもつ資質について語っている。
「事実があるはず、理屈があるはずと追求するのではなく、不確かなこと、不可解なこと、よくわからないことの中に、ただすっくと立っている力」
キーツはシェイクスピアのその力を愛し、それを「『ない』を受容する力(ネガティブ・ケイパビリティ)」と呼んだ。」
「キーツの書簡から1世紀のちに、イギリスの学者ロバート・フレンチとピーター・シンプソンが、この「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念をビジネスとリーダーシップの分野に持ち込んでいる。知識、、技術、競争力のような「ある」を追求する能力(ポジティブ・ケイパビリティ)と、沈黙、忍耐、疑い、謙遜のような、「ない」を受容する能力(ネガティブ・ケイパビリティ)を組みあわせたときに、初めて新しい学びと創造の余地を生み出せるーーーーというのがフレンチとシンプソンの見解だ。」
「哲学者のジャン=ジャック・ルソーは『エミール』という作品で、こう書いた。
「『わからない』という言葉が、私たち自身になる」」
「変化を主導するのも、人を導くのも、即興の対応が求められるプロセスだ。それはジャズに似ている。予測のつかない展開と変化するメロディに身をまかせる。最初に立てた計画に固執せず、一瞬一瞬に起こりうる可能性に心を開くのだ。」
「知らないというのはスリリングだ。」
「何が重要かを気づくために、私たちはときに失敗する必要があるのだ。」
「答えを知らずに判断するのは、もちろん愚かなことだ。だが、私たちはときに愚者のふるまいをしなければならない。タロットカードには「愚者」と呼ばれる1枚が含まれている。たいていの場合、そのカードに描かれているのは、崖の先端で足を踏み出そうとする男の絵だ。小さな袋をもっていて。旅で必要となる能力のすべてがそこに入っている。片手にもった花が象徴するのは美しいものを愛でる心。そして彼の顔は北西をーーーー未知の方向を向いている。
愚者はあらゆる可能性を表している。流動性と柔軟性のイメージだ。愚者は落ち着きがないが、機知に富み、決してひとところにとどまることはない。性格があけっぴろげ、正直、そして気まぐれ。自由な精神の持ち主で、あらかじめ決められた道ではなく、流れるがままに進んでいく。」
「未知の世界に対して目と心を開くには、大胆さが求められる。」
「オーストリアの詩人リルケはこう言っているーーーー「大切なのは、すべてを胸に生きていくこと。その問いを人生として生きていくこと。そうしていれば、遠い未来のいつの日か、少しずつ、気づくこともなく、答えへと歩んでいるのかもしれないのだから。」」
「「問う」という行為は、新たな可能性を切り拓く強い力だ。自分自身がもつ知恵を活かしながら、好奇心をもって生きる後押しになる。未知に対して前向きな姿勢でいさせてくれる。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
