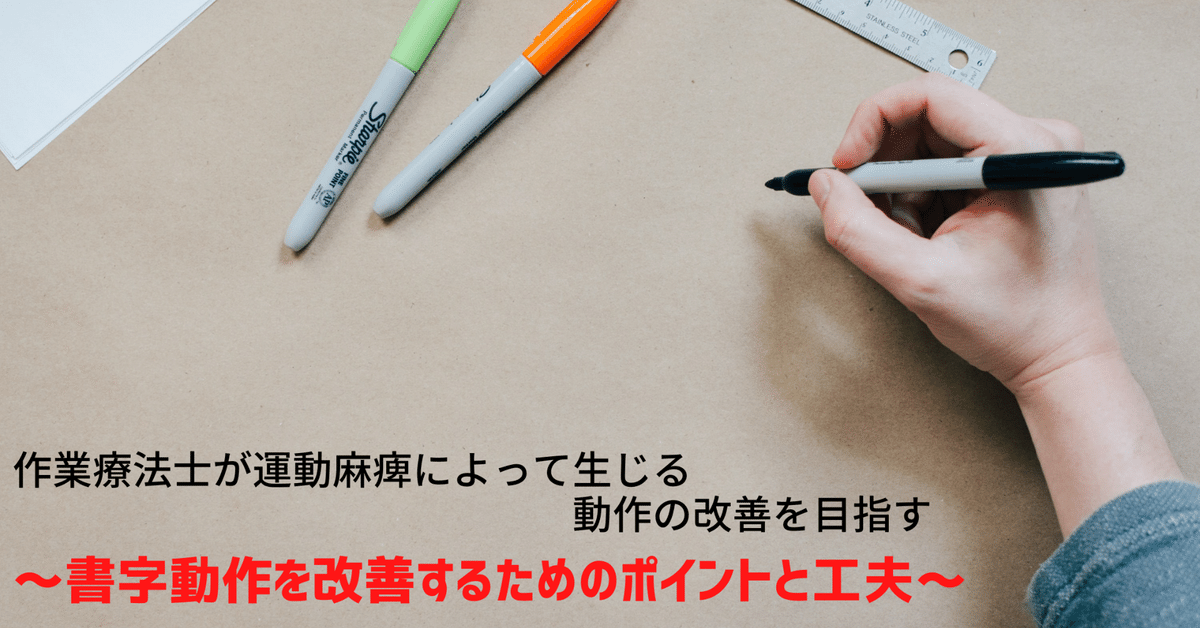
作業療法士が運動麻痺によって生じる動作の改善を目指す ~書字動作を改善するためのポイントと工夫~
皆さん、おはようございます!
本日も臨床BATONへお越しいただき、ありがとうございます!!!
回復期リハ病棟で働いている作業療法士の『よっしー』です。
まず皆さんへの感謝の言葉をさせて頂きます!!

これからも宜しくお願いします!!
☆はじめに
僕のブログでは、臨床で出会った患者様を通して『環境』・『行動』での視点から介入したことを中心にお伝えさせて頂いています!
少しでも、ブログを読んで頂いているセラピストの皆さんやその先の担当患者様への介入のきっかけになってもらえると嬉しいです😆
前回の僕のブログでは、『包丁動作』について、いくつかのアイデアを提案させてもらっているので、良かったら是非見てください!!
今回は『書字動作の再獲得に向けたリハビリ内容の動作指導や工夫』についてお伝えしたいと思います!!
僕は回復期リハ病棟で働いていて、入棟されてきた患者様より『運動麻痺』による影響で利き手の動かしにくさを主訴として聴くことがありますが、皆さんも同じではないでしょうか??
そして、利き手の動かしにくさを訴えられる具体的な動作として、『書字動作』『箸動作』『包丁動作』などが挙げられると思います!
作業療法士として『書字動作』獲得に向けて、どのようなActivity活動を実施したり、どのような介入や工夫を行いながら臨床にあたっているのかを提案したいと思います!
また、書字動作に必要となる手の機能が『箸動作』と関連することもあるため、『箸動作』の獲得にも繋がるヒントにも応用出来る内容になっています!
是非、書字動作獲得に悩んでいる皆さんや作業療法士として治療プログラムの引き出しを増やしたい皆さんにお届けしたい内容となっています!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

