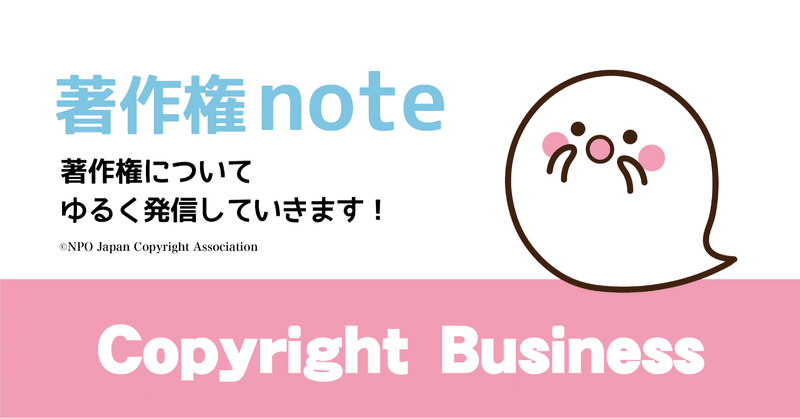
8.自分の書いたnote記事を勝手に修正して公表されています、これって著作権侵害ですよね!
質問⑤私のまとめたnote記事(文章)が勝手に使われていました!その一部に手を加えてあり、まるでその人が書いたnote記事のように扱われています。これって、著作権侵害にはならないのですか?とても嫌な気分です…
どんなに身近な言葉でも、創作性のあるものには著作権があります。ツィッターやフェイスブック、もちろんブログやメール、ラインなども著作権のあるものですから、著作者の許可なく勝手に使用することはできません。
ましてや、元の文章を勝手に改変してしまうなど、著作者を著しく傷つける行為、著作権侵害および著作者人格権侵害となります。
もちろん、法律に従ってクレームをつけることもできますし、裁判に持ち込むことも可能です。
例えば、本の出版などは編集者がより分かりやすく修正したり、大幅に改変する場合もありますが、必ず校正時に著作者の承諾(確認)をしてから発行しています。その原稿がへたくそであっても、誤字脱字があっても、間違いがあったとしても、著作者との確認作業が必要となります。このように編集の方々は常に著作権を意識していますからまずこのようなことはないと考えられますが、一般的なネット上内ではこのようなことは日常茶飯事です。
信じられないかもしれませんが、コピペなども簡単にできる時代で、人の文章でも制作をしていると自分が書いたと錯覚する者もいます。
また、このような言い訳をする人もいます。それは、「引用」として利用したというのです。確かに「引用」であれば「引用の定義・条件」を守っているのならば著作者に許可を得なくとも、著作権法上何も問題はないのですが、創作した人の名前等が記載されていなければ、その人が書いたという誤解も受けます。引用の定義に当てはまらないものはすべて「盗作」になります。
札幌市でこんなことが起こりました。
札幌市による広報誌「広報さっぽろ」6月号の特集
「公共マナーって何かしら?」より

札幌市による広報誌「広報さっぽろ」6月号の特集「公共マナーって何かしら?」が、漫画『ベルサイユのばら』に似ているとして、作者の池田理代子さんの事務所から抗議をさっぽろ市は受けた。
こちらは『ベルばら』の主人公、オスカルをもじった「オシカル」というキャラクターが、マリー・アントワネットをもじった「マナー・シラントワネット」に公共マナーを教える、という内容でした。
内容的には「公共マナー」のことなのですが、残念ながら、著作権のマナーを忘れていたようです。
作者からの抗議を受け、札幌市側はすぐに「誤解を招く表現でした」として謝罪。事務所側も謝罪を受け入れましたが、現在も札幌市のホームページで閲覧でき、PDFファイルでプリントも可能となっています。一般的には面白がってプリントをしている人がたくさんいるようですが、まだ、このまま放置しておくのでしょうか?
疑問がたくさん残りますね。
■「ベルサイユのばら」とは?

集英社「ベルサイユのばら」第13巻の表紙(マーガレットコミックス)
発表から40年以上経っても根強い人気を誇り、「少女マンガの金字塔」とも言われています。1972年~73年まで連載「週刊マーガレット」(集英社)より

特非)著作権協会です。少しずつですが読んでくれる人が次々と増えてきて、とても感謝しています。
著作権とは、法律用語でいえばむずかしい言葉と捉えがち。それをとても簡単の要約すると「優しさ」「思いやり」「気遣い」「配慮」ともいえる。つまり、「他人を傷つけない、傷つけてはならない、悲しませてはならない」という人格や人権にもつながるもの。
たとえば、あなたが気に入った写真を撮影した。それを勝手にトリミングされたり加工されたら、あなたは悲しくはありませんか?
一生懸命に書いた文章を下手だと言って勝手に変えられるのも嫌なことですよね。絵やイラストも同じ。勝手に改変されたり、いじられたら傷つく場合もある。
また、自分の知らないところで勝手に公表されても嫌ですよね。
これらはすべて、「優しさ」「思いやり」「気遣い」「配慮」のない礼儀知らず、マナー違反、いや、プライバシー権侵害でもあり、著作権侵害、著作者人格権侵害になる。
でも、創作者、製作者、著作者に一言でも確認があれば大きな事件やトラブルにはならないはず。そこに、せめて「配慮」があればむずかしいことではない。
人は簡単に傷ついてしまうし、簡単に傷つけることができてしまう。ネット、スマホの世界も同じ。フェイスブック、ツイッター、インスタグラムなどのSNS投稿のすべても同じ。このnoteも同じ。言葉は人を救う場合もあるが、深く傷つける場合もある。
このように他人のものを使用する、利用するときには要注意ですね。
ここまで読んでくれてありがとう!
では、また次回、おつきあい、お願い申し上げます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
