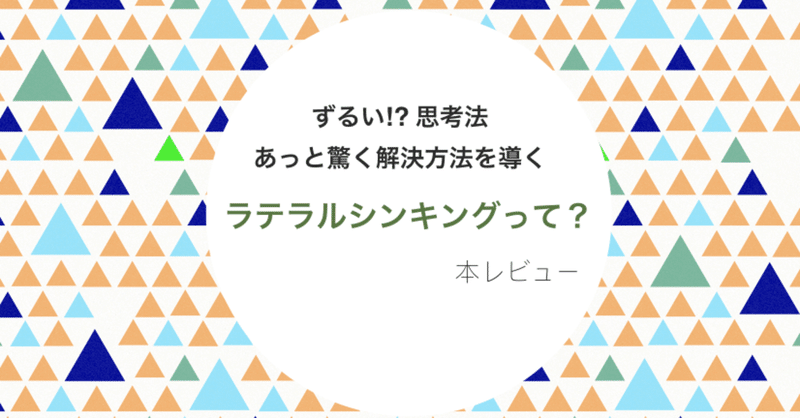
ずるい思考法?あっと驚く解決方法を導く「ラテラルシンキング」とは
はじめに
今回は、「ずるい考え方 ゼロから始めるラテラルシンキング入門」という本をもとに
ラテラルシンキングについて学びました。
この聞き慣れないラテラルシンキングという考え方、
ずるいとは一体どういうことなのか?
ラテラルシンキングとは????
本書から学んだことを共有します!
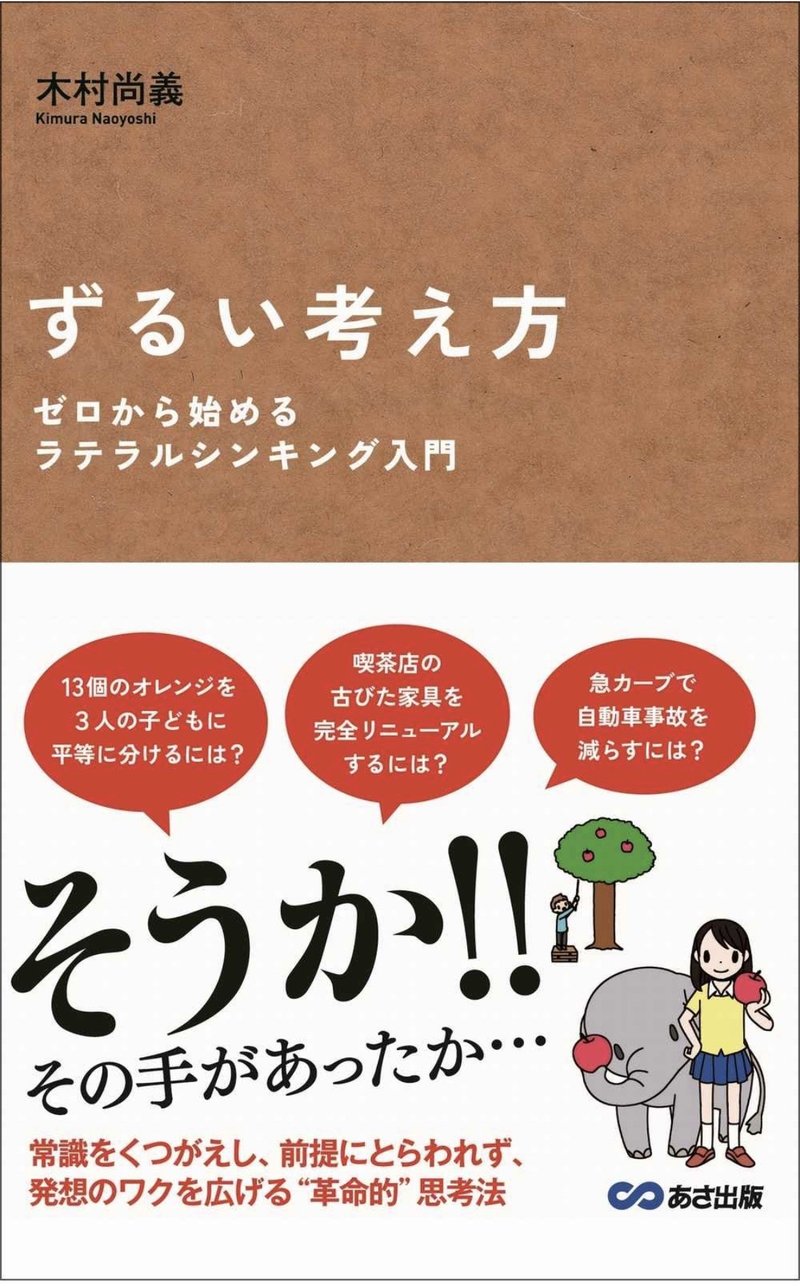
ラテラルシンキングとは
ラテラルシンキングのラテラルとは、「水平」という意味。
ロジカルシンキングが、垂直方向に思考を掘り下げていく考え方なのに対し、
ラテラルシンキングでは、水平方向に思考を広げていきます。
例えば、筆者は例として、
「アーチェリーの的に矢を当てるにはどうしたらいいか?」という課題を挙げています。
的中率を上げるための方法を掘り下げていくのがロジカルシンキングなのに対し、
的自体を大きくする、歩いて矢を射しにいく…などルール度外視の方法を考えたり、なぜ的に矢を当てないといけないのか?と前提を疑ったりするのがラレラルシンキングだと紹介しています。
もちろん、アーチェリーのルール的に今回の課題は解決できませんが、
こういった前提を疑うことにより、発明や開発の場において課題解決に繋がることもあるのだとか。
ラテラルシンキングの活用方法
では、このラテラルシンキング。
実際に役に立つものなのでしょうか。
ここでは、実際に紹介されていた大阪万博の例を紹介します。
■ 大阪万博の例
課題: 開場と同時に、多くの客が走って入場してしまって危険。
どうやってこの課題を解決するか?
→ロジカルシンキングなら…
・警備員の増員
・ゲートを大きくする
・入場者を制限するための柵を作る
→ラテラルシンキングなら…
・入場を待つ客に、小さな案内地図を配布
⇒走りながらでは文字が読めないため、走る人が大幅に減った。
この例は、ラテラルシンキングの成功例と言えるでしょう。
まさに、自由な発想で考えられた鮮やかな解決方法です。
本書の感想
本書では、このようなラテラルシンキングについて、
身近な具体例をもとに多数紹介されていました。
どれも、「その手があったか…!」と思わされる驚きの解決方法ばかり。
それらを読むことはとても面白かったです。
一方で、この考え方を実際に仕事で活かすというのは中々難しいな…とも考えさせられました。
なぜなら、問題の解決のためには、どうしても現実的な方法を考えてしまうからです。
(もちろん現実的なのは悪いことではないのですが…)
しかし、本書でも、
ラテラルシンキングは、ロジカルシンキングと対にあるものではなく、
どちらの考え方も活かして思考していくことが重要であると説かれていました。
そのため、いきなりラテラルな解決方法を考えるのは難しくても、
問題解決の中でふと思いついたアイデアがあれば、
それが実現できるかどうかをロジカルに考えて取捨選択していく…というのが現実的だと考えました!
また、本書を読んで感じたのは、
前提や固定概念を疑えば、解決できることがあるということ。
ロジカルな思考法では、なかなか前提覆す考え方は難しい。
だからこそ、双方の良いところを踏まえて考えてみるのが大事だと思いました。
さいごに
「その手があったか!」という奥の手を発見するラテラルシンキング。
今回は、その思考法について学びました。
日本テレビの番組で、
「THE 突破ファイル」ってありますよね。
(ウッチャンナンチャンのウッチャンが「突破!!!」って言うやつ…)
絶体絶命のピンチでも決して諦めなかった人々の実話をもとにしたクイズ番組で、
追い詰められた人達が思いついた、驚きのアイデアによる突破劇を紹介しているものです。
この本で紹介されていた事例は、まさにこの番組で紹介されていたような突破劇を見ているようで、
THE 突破ファイルは、ラテラルシンキングをもとにした番組だったのだと気づかされました。
新しい思考法について知ることができ、とても面白かった反面、
なかなか応用するのは難しいな…とも感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
