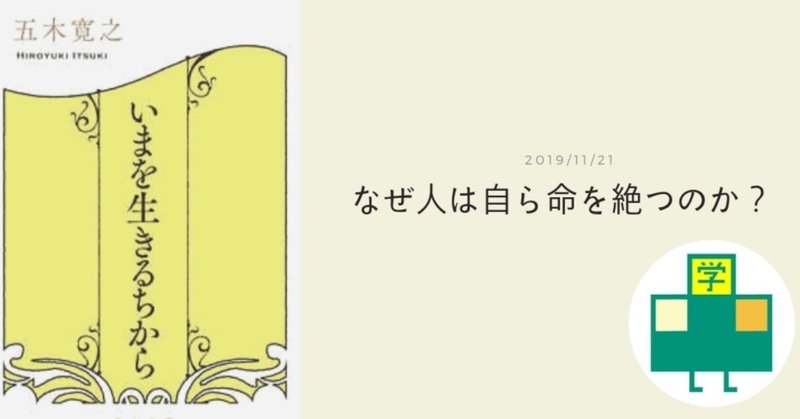
「いまを生きるちから」から考えるなぜ人は自ら命を絶つのか?
今は、昔よりも遥かに豊かになっている。
それなのに、なぜ自ら命を絶つ人があとを絶たないのか?
この図を見てもらうと、2017年には21140人と下がっているものの
2003年のピーク時には34427人と3万人を超えている。
1970年代は20000人前後となっているので、一気に増えていったものの
最近になって減りつつあるという兆しが見える。
だが、世界は冠たる長寿大国を作り上げたと同時にかつてなかった自殺大国を作り上げてしまったのだ。
また、 日本は世界一「若者自殺者」を量産しているのだ。

少子高齢化なのに、なぜ日本の若者は自ら命を絶つという選択をしてしまうのだろうか…
昔は、ものに恵まれず大変な思いをしているのではないか?
今の時代は、ものに恵まれすぎているほど沢山のものがあって贅沢な暮らしをしているのではないか?
それなのに、なぜ自殺者が多いのだろう…
戦争もなく平和な時代の陰で「見えないこころの戦争」が続いているのではないか?
ちょっとしたヒントが五木寛之(著)の「いまを生きるちから」に書かれているので、紹介していきます。
私たち日本人は、いまを生き抜くちからが希薄になっている。
どうすれば、命の重さをとりもどすことができるのだろうか。
この著書の中では、色々な例を元に「こころの乾き」について説明しています。
建築の世界では、むかし家を建てるときはコンクリートを水で溶いて、漆喰を作って…というように水が必要である「湿式工法」で建てられていました。
しかし、現代では作られたものを現地で組み立てられて水を必要としない「乾式工法」が用いられるようになったのです。
医療の現場でも、昔は体の調子を見るためには内診をすることが多かったものの、今では検査の数字を見ることが重要視されています。
また、雇用の面でも昔は終身雇用・年功序列が一般的で、途中で亡くなってしまった場合も面倒を会社が負担したりする生涯雇用が一般だったものの、
今ではリストラも当たり前の乾ききった人間関係になってしまったのです。
戦争前のジメジメした人間関係によって辛い思いをしてきた人たちにとっては乾いた社会を目指しました。
戦後は明るさ、笑い、ユーモアなどの知性の働きを重視して、悲しむ、嘆く、惑う、泣くなどの感情を捨ててきました。
しかし、物事には中庸が大事です。
現代の自殺者が多いのは、カラカラに乾ききった日本人のこころが、命の重さを考えることを失ってしまっているのではないでしょうか?
つまり心が乾いていて、日本人のいのちが軽くなったからだということです。
そのためにはオアシスつまり水が必要です。
その水に当たるものは、人間の<情>であり、また<悲>という感覚ではないか?
この人間の<情>であり、また<悲>という感覚という表現
人間には「明るさ」「笑い」「ユーモア」といった知性の働きであるプラス思考だけが大事なのでしょうか?
「悲しむ」「嘆く」「惑う」「泣く」といった感情の働きであるマイナスの思考も必要ですし、2つの感情に寄り添えるような居場所が必要なように感じています。
これから私たちは「#学校に行かないパターン」を通じて人間の感情を育むオアシスのような居場所を作りたいと思います!
インタビュイー・ライターを募集しています。
今、現在Twitterのほうで掲載していて合わせて10名ほど集まっています。
とても個性豊かな方々にインタビュー出来ており、正直期待しかないです!
しかし、これからも記事数を増やしていきたいと思っているので
人数がまだまだ足りておりません。
ぜひ、ご応募ください!
【インタビュー/ライティング記者募集対象】
•学校教育に、課題や問題意識を持っている学生
【インタビューを受けて下さる方募集対象】
• 過去に学校に行かなかった期間がある方
• 学校にも家庭にも居場所を感じられなかった方
• 学校に通っていないお子さんをお持ちの保護者の方
• ホームスクールを実践されている方
• 新しい教育を提案されている方
• 居場所づくりに関わっている方
【インタビュー/ライティング概要】
• 学校に行かなかった過去について(お話出来る範囲で構いません)
• 親や学校など周りの反応について
• ホームスクールを実践されてみての感想について
• 新しい教育を提案されている内容について
• 居場所づくりにどう関わっているのかについて
インタビュイー募集
ライター募集
ライター @kobayashinitya
現在、高校2年
大阪大学SEEDS3期生
ココトモ相談員
きっとみつかるカフェライター
「学校に行かないパターン」で活動中
興味のある方は、DMください!
これからのサイトの運営費に使わせていただきます! よろしくお願いします!
