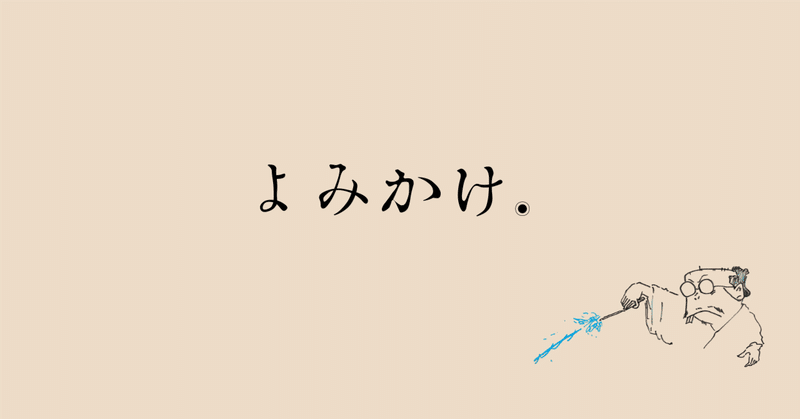
そんなことよりも、
過去を知り、現在を眺めて、未来を想えば、社会というものは虹色のしゃぼん玉のように面白いものである。
ラフカディオ・ハーン『心』
この書には、明治期日本で暮らしたハーンが観察した日本人および彼らの身に起こった出来事が、その出来事の奥底にある日本人の心——価値観、精神とともに描き出されている。
93ページまで読んだ。
いい本である。文章も美麗で優しく、描かれる情景もどこか懐かしく悲しみをおびていて静かである。
つい最近、岩波書店が出してる『思想』を年間購読した。
六月号「追悼 ルジャンドル」が気になってついに手を出してしまった。
六月も終わるころ、その本が届いた。
年間購読の料金を郵便局で払う。
社会的な手続きにまだ疎いのり子に郵便局員のお姉さんは丁寧に説明をしてくれた。彼女の指示のもと紙に色々書いて、お金を渡す。安心安心。
手続きの終わったあと、「ゆうちょのアプリはお持ちですか?」と聞かれた。
アイフォンを見ると、入ってる。今回必要なわけではないが、もし入金などしたい場合アプリを使うと便利で、郵便局が開いてなくても手数料なしで行えるらしい。
その説明を聞きながらアプリを開いてみると利用規約、電話番号入力——けれどのり子がゆうちょで登録した電話番号は今使ってるアイフォンの番号ではなかったので、変更手続きをしなければならなかった。
手続き、手続き、登録、手続き。
……なら優しいお姉さんにやってもらう。
そう思った。
いろいろ見てみると。登録やら何やら面倒だ。
はじめて老人の意見を身に沁みて理解したのである。
同時にのり子は考えた。老人のデジタル嫌いは、もしや生まれた時代に原因するのではなくて、生活と環境がそうさせるのではなかろうか。
確かに自分のこれまでを鑑みると、面倒くさいからアプリ済ませたい、と思う時というのはあまりに疲れて家を出たくない時か、精神的に疲れてしまって人と話したくない時である。
対して老人の生活には時間があり、家を出ることも人と話すことも苦でない時間が多いと考える(偏見)。そういう生活のなかではアプリの方がよっぽど面倒で、人に聞いて接客してもらうほうが楽なのである(それはそう)。
「デジタル嫌い」はデジタル化社会のずいぶん前に生まれてしまったが故に、新しい世界にコミットできないからなってしまうのではなく、年齢と生活からなるもの。
そう仮定すると、今はデジタル化を受け入れている40代50代が反デジタル主義に転じるのも時間の問題で、デジタルと共に育ってきた我々でさえ最後にはそうなるのである。
だとしたら隅から隅までデジタル化を進めねばならないという意見のある現代——その先がどうなるか考えたい。
我々は、我々の首を、日に日に締めているのかもしれない。
ロバート・L ・ハイルブローナー『入門経済思想史 世俗の思想家たち』を読んだ後、のり子は「先進国オワコン説」を考えるようになった。
それというのは、以下の通りだ。
高度経済成長がある。この時代——去年より今年、今年より来年と経済が発展する時代に、国はさまざまなインフラ、施設などを作り国を発展させる。新幹線や高速道路が日本を速くする。
それができるのは、来年はもっと儲かるという幻想に支えられてのことだ。しかしこの経済成長もどこかで頭打ちになる。
インフラを整えたはいいが、整備や修理に金がかかる。イケイケの時代はそれを補って余りある元気があるし、今後もあるものだと疑ってなかった。
さてしかし現実は、経済は止まるどころか、一度止まったら落ち始める。しかし新幹線や高速道路は以前としてある。水道もガスも先進国的なシステムもあり続ける。これが次には負債と転じる、とのり子は考えたのだ。
経済が落ちて、我々はこれを維持するのに悲しいかな全力を注ぐのでいっぱいで、余力がないのである。
「先進国オワコン説」とは、インフラや先進性に金が吸われて国民に渡らない。というイメージである。
もしのり子が総理大臣か大統領にでもなれば、高速や新幹線は捨てる。廃止するのである。このまま維持すると、発展はない。泣いて馬謖を斬って、成長の余地を無理くりつくりだす。
この説が正しいかどうかはわからない。ど素人の妄想であるが、デジタル化ものり子は同じイメージで見てしまう。
今はいい、それはまだデジタル化する余地も、それを享受する人の余地もあるからだ。けれどこのまま進んでも、若者の人数は増えずかつての若者も老人になる。そのとき民の心労は無視できなくなるのではなかろうか。
多分今の日本の状態くらいがちょうどいいデジタル度合いである。
店員がコンビニに立っていることや、住民票を取るために十数分歩くことはちょうどいい文化だと思う。郵便局員さんに手取り足取りしてもらうのは文化である。
今、文明が文化に終わらない戦いを挑んでいるのだ。
そしてこのままゆくと、文明の比重が高くなり、以前変わらない人数いる(あるいは増えた)老人たちは疲弊する。最後には怒る。そのうち、文明だけになった街を、老人が壊して回る。人が文明に牙を向く瞬間である。
のり子はそれが見たい。
そして、荒れ狂う革命老人家を見て、——その暴徒を生み出したのは自分たちだと気づかない人々が、その老人を叩くのを見たい。
三島由紀夫よ、日本も面白くなったやろ。
とほほ。
民衆がこぞって個人を叩くという、2ch、Twitter的な文化。
これには流石ののり子も慣れない。
ハーンの『心』を読むと、昔はそうではなかったと知れる。
この書の一番頭に「停車場で」という短い随筆が置かれている。
・・・
熊本で捕まった重罪犯罪人が、警官を殺し逃亡した。
それから四年後、熊本のある探偵はたまたま福岡の監獄署を訪れていた。探偵はそこに見つけたある男を指差して「あれは誰だ?」と聞いた。看守は「草部という名の窃盗犯だ」と答えたが、探偵は草部の前まで歩み寄り言った。
「おい、草部というのは、きさまの本名じゃないな。野村貞一、きさまは殺人犯で、熊本で御用だ。」
草部は四年前に、警官を殺した野村貞一だったのだ。
野村は一切を白状した。
ハーンは、それほどの犯罪者が停車場へつくというのを聞いて熊本まで見に行った。意外にも駅周辺の様子は普段と変わらない。
しかし、罪人が警官に後ろ手にくくりあげられた姿で出てくると、水を打ったように静かになる。駅の前にはすでに観衆が罪人を見ようと密集している。
警部が大きな声を上げた。「杉原さん! 杉原おきびさん! ここにおられますか?」
ハーンの斜め前にいた背中に子を負ぶる女性が「はい!」と答えて前へ出た。そして殺人犯の前に向かい合って立った。
警部はうなだれる罪人の顔を掴んで、杉原さんの背にいる子どもに向けて、
「坊や、彼が君のお父さんを殺した男だ。怖がらなくていい、よく見るんだ、それが君の務めだからね」
子どもは目をぱっちりひらいて、こわごわ相手を見ていたが、やがて涙をぽろぽろこぼした。そして睨んで、睨んで、睨みつけるのだった。
ハーンはそのとき、罪人の顔が歪むのを見た。
すると罪人はその場にへたへたとくず折れて、
「堪忍してくんなせえ。坊ちゃん、あっしゃァ、なにも怨みつらみがあってやったんじゃねんでござんす。ただもう、逃げたいばっかりに、ついこわくなって、無我夢中ででやった仕事なんで。……あっしゃァ悪い野郎でござんす。極道人でござんす。あっしゃァ坊ちゃんに申訳のねえ、大それたことをしちめえやした。ですが、こうやって今、うぬの犯した罪のかどで、これから死にに行くところでござんす。あっしゃァ死にてえんです。よろこんで死にます。だから、坊ちゃん、……どうか可哀そうな野郎だとおぼしめしなすって、あっしのこたァ、勘弁してやっておくんなせえまし。お願えでござんす。……}
子どもはやはり黙って泣いていた。
それとどうじに周囲からもすすり泣く音が聞こえる。
このときハーンは今まで見たことないもの——この先も見ることがないだろうものを見たという。それは、警官の涙であった。
・・・
以上、のり子による要約である。
野村貞一の最後のセリフだけ全文写した。
この出来事に続いて、ハーンはこう書く。
そこには人間の犯した罪科の当然の結果を、一場の終端場で目のあたりにほうふつと見せてやり、それによって罪科の何たるかを思い知らせてやろうという、じつに勘どこをはずさぬ、しかも慈悲に富んだ、正しい裁きがあった。
しかもその上、そこには大衆が——おそらく、ひとたびこれが怒ったら、この国でもっとも手のつけられない危険な存在となるかわりには、万事に物分かりがよく、どんなことにもすぐホロリとして、ああ、すまなかった、ああ、小ッ恥ずかしいの一念で、何ごともさらりと水に流してしまい、しかも、浮世のままならなさと人間の本性の弱さとは、骨の髄まで経験で知りぬいているから、肚のなかには一片の憤りもなく、ただ罪にたいする大きな嘆きだけを持っている——そういう大衆がいたのである。
「浮世のままならなさと人間の本性の弱さとは、骨の髄まで経験で知りぬいているから、肚のなかには一片の憤りもなく、ただ罪にたいする大きな嘆きだけを持っている——そういう大衆」
これがかつての日本人の賢さかと思う。
かわいそうな子どもと、ある種の悲運な運命を持った加害者ともどもに涙を流すのである。
もし、老人がデジタル化のいきすぎた街に怒り狂って暴徒と化しても、のり子は涙を流そう。そして社会のままならなさと、あまりに過ちの多い人間の弱さを、じっと思うのである。
ただ、
ただ、そんなことより、気になる存在があるのだ。探偵が、——
探偵が、のり子はずっと探偵が気になるのである。
あまりに格好良すぎる。
最後のセリフは全文書き写したと書いたが、探偵のセリフもそのまま引用している。
「おい、草部というのは、きさまの本名じゃないな。野村貞一、きさまは殺人犯で、熊本で御用だ。」
熊本で御用だ!
浮気調査でない現実の探偵を始めてみた。
そして監獄署を訪れていたらしいが、どんな事件を追っていたのだろうか。気になる。
筆のすさびで日本の未来など書いてみたが、その間中もずっと頭の中には探偵が居座ってならないのだ。
この野村貞一の事件は、調べても調べてもみつけられなかった。当時の新聞を探すしかないのだろが、それも相当の手間が必要なことは想像に難くない。できない。
誰か教えてくれ、この事件と、探偵の名前を。
のり子の読書は始終これである。
細かな部分が気になって、最終的に印象に残るのは本題に無関係な部分。
うしろに「あみだ寺の比丘尼」というやはり素晴らしい随筆があるが、ここでも、子どもを亡くした女性が死者を呼び戻す儀式をしたあと、
今日では、こうした儀式は法律で禁じられている。
とある。
儀式も、それを禁じたという法律も、こっちの方が気になって本筋などそっちのけだ。
しかしそれこそ読書の意義であり本分である。
と言っておこう。
根拠はない。
読書と執筆のカテにさせていただきます。 さすれば、noteで一番面白い記事を書きましょう。
