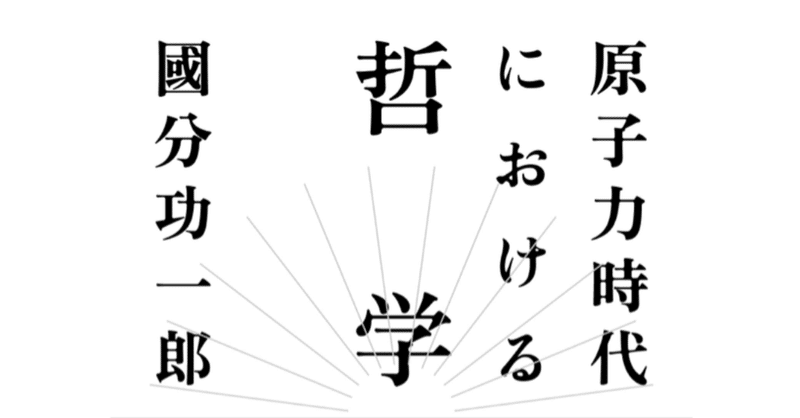
「原子力における哲学」國分功一郎著 読書メモ
國分さんのファンなんです
個人的に國分功一郎さんの本は好きで、有名な「暇と退屈の倫理学」や、大変勉強になった「近代政治哲学」、ご自身のアクティビストとしての活動も描かれている「僕らの社会主義」、少しマニアックな所だと先日の読書会で松永さんにご紹介頂いた訳書「基礎づけるとは何か」、そして最近だと「中動態の世界」、など、いつも楽しく拝読させて頂いている。
その國分さんが、私の専門にも関わる原子力について論じている本を出されたということで、つい気になってしまい一気に読ませて頂いた。この投稿は、その際の私の一連の読書ツイートをベースにして書いたものである。
出版まで6年の歳月
この本の発売日は2019年9月25日だが、2013年7月12日、19日、26日、8月2日に行われた連続講義の記録が元になっている。正直、國分さんがこんなに早く?から原子力問題に取り組まれていたとは存じ上げなかった。(ご本人は福島原発事故が起きるまで「原発のことを真剣に考えてこなかったことを悔やみ」(p.19)とあるので早くとは言えないのかもしれないが)
しかし、講義から6年の歳月を経ての出版ということで、形になるまでには相当のご苦労があったようだ。國分さんはあとがきで「これほどまでに完成が遅れたのはその責任を担うだけの勇気を筆者が持ちえなかったからである」(p.316)と弁明されている。私も専門家としてどうしてもハレーションが大きくなりがちなで、あまりにも根深く責任重大な原子力問題に対して、必ずしもまとまった形の明確な意見表明を避けてきた面がある。その心中は理解できるものがある。
これだと原発というより再エネも全部駄目じゃね?
さて、内容に関してだが、様々興味深い指摘はあるものの、結論としては、早くから脱原発を主張したハイデッガーに着目してしまったために、脱原発というよりは脱技術論に陥ってしまい、日本の実際上の原発論争にとっては残念ながら無意味なものになってしまっている、という印象を持った。
ハイデッガーが核兵器よりも原発をむしろ問題と捉えていた(p.82)ことは興味深い。彼は人間の自然への対峙のありかたとして技術論を捉えていた。そのため、たとえばある環境保護活動が「ディープエコロジー」か否か、といったような自然への畏怖の持ち方(つまりは思想)の問題に帰着してしまう。
そして、その原因を、「イデアという本質こそが実在で自然はその現れとしての仮像に過ぎない」としたプラトンのイデア論を源流とする西洋哲学にもとめる。つまり、西洋哲学は、ソクラテス以前にあった「知を愛すること(フィレイン・ト・ソフォン)」からある種の堕落をすることによって、自然は蔑ろにされた。そして、その結果原子力が生まれたというのである。
しかし、この論に立ってしまうと、原子力以外の殆どすべての技術も自然を弄んで人間のために使おうとしているという意味で批判することが出来てしまう。もちろん、そのような立場でも構わないのだが、例えば太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーも駄目ということになる。実際、本書の中で哲学者の加藤尚武先生が風車はよくて原子力はダメというのは理屈に合わないという趣旨の指摘をされている(p.160)。
ハイデッガーは原発を念頭に「自然が巨大なガソリンスタンドと化している」と指摘(p.83)しているが、これは現代を生きる我々にはむしろ再エネ開発を想起させる表現だと思う。
また、現代人や現代の科学者(の多く)が、果たしてプラトンのように自然の背後にイデアという本質的な実在があると考えているかと言えば甚だ疑問である。むしろ「新しい実在論」を展開するマルクス・ガブリエルのように、現代は自然以外に実在などないという様な自然科学主義が横行しているので、もっと目に見えないものを大事にしろという主張の方が強いという印象がある。
「放下」・・・ですか
とはいえ、現代社会において技術をすべて否定することはできないからか、ハイデッガーの結論は「放下(Gelassenheit)」という古いドイツ語を持ってきて、これを「然りとも否とも同時に言う態度」という意味として打ち出している。これは、私に言わせれば、「考えないやつにはわからない」と言って、小難しい単語を使ってさも新しい概念を創出したかのようにして、神秘化させ煙に巻いているようにしか思えない。
ちなみに、この"Gelassenheit"とは、原義には「委ねられた状態」(という意味で、中世ドイツ神秘主義思想家のエックハルトの使い方だと「神にすべてを委ねている」というような意味らしい(p.198)。
國分氏は、「意志の領域にも属さない」というこの「放下」という概念を、別の文脈からも強い関心を持ちっている「中動態」にも絡めて執着しているように見える。しかし、ハイデッガーに対して余程強い関心や信仰がない限り、この概念が一般国民や原発政策論争の当事者に國分氏のように響くかと言えば、甚だ疑問である。
そして、ハイデッガーの議論に立脚すると、原子力技術と原子力以外のエネルギー技術とを分ける何かがないと、脱原発ではなくただの脱技術論になってしまう。そこで、中沢新一氏による「原子力は化石燃料や太陽光・風力とは違って大元が太陽光エネルギーじゃないからダメ」という意見を採用する。しかし、それでは地熱エネルギーは天然放射性元素の崩壊熱なので、地熱発電も温泉もダメということになってしまう(p.264)。
原発は外部からの贈与に依存しないというナルシズムか
そして、人々が原子力を求めるのは、外部からの贈与に依存しない自立したシステムを作り出そうとする強い欲求(p.271)であり、その自立したいという願望はフロイトのいう所の大人が幼児期の頃の全能感に戻りたいという二次ナルシズムで、それは外界への関心からの離反や誇大妄想であるとして批判している(p.275)。
そうなると、やはり再エネを普及させて原発や化石燃料を置き換え、エネルギー自給率向上というという考えもまた、同じ病理を抱えているためダメということになってしまう。確かにそういう考え方は成立するかも知れないが、その運動を展開するには現代的な生活をすべて否定する他無くなってしまうだろう。
現代の論争と哲学と
國分氏は、原子力に反対する理由としては廃棄物や事故のリスクとコストで「ほとんどよい」(p.267)と言っているが、それだけでは推進派を論破・説得できないと考え、よりラディカルな理由を求めてハイデッガーにたどり着いたのだと思われる。しかし、このように、結論ありきで論拠を求める営みこそ、まさに本書が原発推進派を批判する「思惟からの逃走」(p.262)ではないかと思えてしまうが、いみじくも「原子力信仰と戦っていたはずなのに自分たちが信仰に陥ってしまう」(p.284)とも書かれていて、自らの議論の危険性を自覚しているかのようにも思える。
単語の原義に還ったり、過去の哲学者の議論にヒントを得たり、そこに論を立脚することは、時として興味深いものである。しかし、そうした過去からの哲学的論創の系譜のなかにも、どこかに普遍的ものがあるはずだと思いたい一方で、時代も想定されているものも、単語の使い方も違うなかで、過去の哲学論を現代の社会問題論争に当てはめようとすることに無理を感じてしまう。むしろ、現代の哲学者としては、同じ人間社会である過去を参照点としつつも、現代の論争の中にこそその問題性の本質を見いださなければ、当事者にとって響く議論とはならないのではないかと感じた。
私にとっては、原子力の問題はその廃棄物や事故のリスクという側面もあるが、政治哲学的には関与する人間と得られる利益の大きさの比が大きいこととと技術的に核兵器転用が可能である以上国際的に国家管理が必須であることに原発のエネルギー問題としての本質があるのだと思う。前者の点に関して、他のエネルギー技術と比べると利益分配の難しさから権力的な腐敗を生みやすいという違いが一番大きいように思う。それは、石油メジャーや産油国が抱える問題(=「石油の呪い」)と同じだったりするが、資源のない日本には幸いにもそちら(資源が多過ぎる故の問題)の心配をする必要はあまりない。
また、後者の点に関して言えば、核兵器より原発を問題視したハイデッガーをメインに据えた為に、あえて触れていないのかも知れないが、核兵器転用の恐れがあることから国際的に国家管理が必要な原発を、政治主導で民間事業者に保有させたことの政治的意味(あるいは隠された意図)は、國分氏が注目した1950年代の日本の議論を見ても、1980年代の日米原子力協定を巡る交渉をみても、やはり潜在的核保有国であることである。そして、それは明示的に言わないことで戦略的意味を為しているため、実証的な議論をしづらいという問題が内在している。
いつかお話してみたいとは思っていますが、私のような小物じゃまだ早いか。頑張ってオファーが来るくらいもう少し有名になります。
参考図書リンク
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
