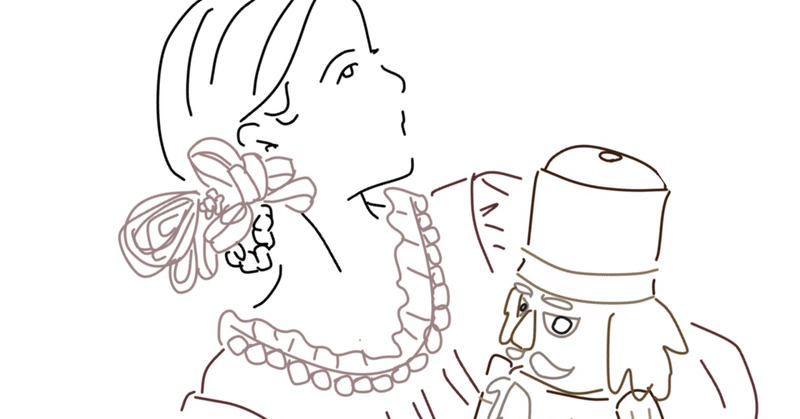
世間とは何か
阿部謹也さんの同タイトルの本があるが、改めて考えてみよう。
安冨歩さんが「立場主義」という考えを提唱している。立場主義のアルゴリズムは、安冨歩によれば以下のように説明される。
日本は、実のところ民主主義の国ではありません。基本的人権に基づいて、国民一人ひとりが尊重されることはなく、代わりに尊重されるのは「立場」です。日本の「民主主義」が意味するところは、「すべての立場は尊重されねばならない」です。この、日本立場主義人民共和国の憲法は、以下です。
前文:立場には役が付随し、役を果たせば立場は守られる
第一条:役を果たすためには、何でもやらなければならない(国民の義務)
第二条:立場を守るためだったら、何をしても許される(国民の権利)
第三条:人の立場を脅かしてはならない(国民の倫理)
「立場」とは、辞書的には「その人の置かれている地位や境遇。また、面目」という意味だ。「苦しい立場に追い込まれる」「負けたら立場がない」などのように使われる。
ここで「立場≒面目」という表現が出てきた。面目とは「世間や周囲に対する体面・立場・名誉。また、世間からの評価」のことだ。
では「世間からの評価」とはなんだろう?「世間」を辞書で引くと、「世の中」とか「社会」みたいなことになってしまう。ひとまずここでは、「一人ひとりの他人の集まり」というように仮定してみよう。
すると「世間からの評価」とは、「個々人が他人に要請することの総和」といえる。私たちは、人々から、何らかの立場、役割を要請されながら、生きているということだ。
ところで、安冨歩の提唱する立場主義憲法の前文では「立場には役が付随し、役を果たせば立場は守られる」と記されているわけだから、翻れば「役を果たせず、立場を守らなかった人には、立場は認めない」と解釈ができる。私達の生きる立場主義の世間では、立場に伴う役割をまっとうしない人には人権はなく、攻撃を受け、排除されることから、守られない。
私たちは、その攻撃と排除を恐れて、必死で立場を守ろうとする。そのような社会にあっては、立場とは、他人の暴力を回避するための数少ない方法なのだ。必死で立場を守りたくなる。
さて、立場主義社会では、世間という「他人」は、立場を守れない人を攻撃できる。「攻撃できる」とは、すなわち、「攻撃能力を有する」ということで、身も蓋もなく言えば「武装している」ということなのだ。つまり、世間とは「武装した他人の集まり」なのだ。いわば私たちは、つまり武装した集団に取り囲まれて生きているということなのだといえる。まじかよこえー。
ところで、「DDR」って言葉がある
これはDisarmament, Demobilization, Reintegrationのイニシャルで、日本語では「武装解除・動員解除・社会復帰」という意味だ。国連などが、紛争後の国家における復興と平和構築の促進を目的に行う国際平和活動の一種で。世界各地の紛争地で実施されてきた平和構築プロセスとされる。翻れば私達の生きる「世間」というのは、まだこのDDRが行われておらず、「非合法武装集団の解体」が未達な集団なのだ。
「世間」を構成する周囲の他人が武装しているために、個々人の人権が守られていない。「世間」の人は、相手に攻撃の可能性を突きつけて、「依頼」をする。もっとも、それは攻撃の可能性をちらつかせる依頼なわけだから、「脅迫」や「命令」というべきだろう。そして、その脅迫や命令を受け付けない場合、つまり、要請した立場に伴う役割を果たせない場合、攻撃が実行される。
ところで、そういう私達もまた、世間を構成しているとすると、私達もまた攻撃の可能性を有している。とすると、世間における立場とはなにかといえば、つまるところ「彼我戦力差」によって作られるパワーバランスなわけだ。
彼我戦力差が相対的に「立場」と「役割」を作り出す。彼我戦力差のバランスは、日々様々な要因で微妙に移り変わっており、その都度求められる役割も変わる。それはもはや言語で説明できるものではなく、身体的な肌感覚で感じ取るものになる。そういうのをきっと私たちは「空気」と呼ぶのだろう。言葉で説明できず、肌で感じるもの、まさに空気だ。
私たちはよく色んな習い事を勉強する。例えば語学だったり、クラフトだったり、資格試験だったりするが、案外この世間で生きていくために最優先で学ぶべきは、軍事学だったり、外交交渉技術だったりするのかもしれないよね。
ところで「立場」には「その状況から生じる考え方。観点。立脚点」という意味もあり、「医者の立場からの発言」「賛成の立場をとる」「第三者の立場」というように使われる。
この点について面白いのが雨宮処凛のインパール作戦に関するコメントだ。ここまでの「立場主義」から始まる一連の説明は、インパール作戦での牟田口の振る舞いをある程度合理的に説明できるように思える。とりわけ、雨宮が以下のように憤慨する箇所などは注目に値する。
彼自身、4月終わり頃には作戦の失敗がわかっていたというのだ。しかし、どうしても「やめる」と言えなかった。自分がゴリ押しして始めた作戦。それを「途中でやめる」だなんて、「男の沽券」にかかわるとでも思ったのだろうか。そのことについて、牟田口司令官は「顔色で察してほしかった」と甘え腐ったことを抜かしている。「忖度しろ」ってことか? 4月の時点で中止を決めていさえすれば、救われた命はどれほどあっただろう
(略)
あまりにも、あまりにもひどい話である。牟田口司令官という一人の人間の勝手すぎる「男のロマン」によって、膨大な命が奪われた。天皇誕生日までにインパールを攻略、という一人よがりな熱意。現実を無視したなんの計画もない作戦。成功したら、勲章でも貰えて出世できるという思惑があったのだろう。そうして途中で失敗だと気づいても、自分が言い出した手前、「メンツ」が潰れるから言い出せなかったのだろう。
このように雨宮は憤慨するが、この記述は、牟田口がメンツを守るために正しい選択をできなかったというが、じゃあこのメンツ、つまり立場に期待される役割をまっとうできなかったら、どうなっていただろう。世間から攻撃され、排除されたのではなかったろうか。とすると、牟田口自身も、上官や部下といった世間からの暴力に怯え、とるべき選択をできなかった、暴力の被害者としての自己認識があったものとして説明できそうだ。
ここまでの記述を読んで「やっぱり暴力はだめだ!ガンジーばりの非暴力をこころがけよう!」と思った人もいるかもしれない。一方で、「とはいえなあ…」という足踏みもされているのではないだろうか。
これは核抑止と同じようなもので、自分だけ武装解除して、相手が武装解除しなければ、あなたはボコボコにされてしまう。その相手への不安があるから、私たちは自分の暴力を制限することをためらう。
「私は暴力に対して一つの武器しか持っていなかった。それは暴力だ。」ジャン・ポール・サルトル『歯車』
「もし黒人がこの国で人権を獲得するために暴力が必要ならば、私は暴力の味方だ。」マルコム・X
だから、やるならティール組織みたいに「いっせーのーせ!」でやらないといけない。
とはいえ、そんなティール型組織なんて導入できないよって場合が大半だろう。そういう状況で、そもそも、利害衝突をどうやって解決するのかって話になる。近代国家の考え方に従えば、その地域で暴力を独占する国家による裁定が行われることになる。例えば兄弟ケンカなら、お父さんが裁定するのと同じだ。しかし、そういう公的主体による暴力の独占がなされず、人々に暴力が分有されている場合、「万人の万人に対する戦い」のカオスが発生し、社会が維持できない。
しかし、にも関わらず、私達の社会はどうにかこうにか攻撃力を行使し合う万人バトル状態を回避し、維持されているように見える。なぜだろう?そもそもやっぱり攻撃の実行って、集団にとっては破壊的に働くので、何らかの方法で攻撃は制御されているはずだ。
ここで山岸俊男のいう「集団主義的秩序」を召喚してみたい。
確かに、「立場に期待される役割をまっとうしなければ、暴力が行使される」かもしれないが、安冨歩憲法にも言うように、<役を果たせば立場は守られる>、つまり、暴力の行使は行われない。だからこそ、<立場を守るためだったら、何をしても許される>のだ。暴力が行使されることは、やはり社会にとってもまずい。
核軍縮にまつわる言葉で「相互確証破壊」ってものがある。これは核兵器を保有して対立する2か国のどちらか一方が、相手に対し核兵器を使用した場合、もう一方の国が先制核攻撃を受けても核戦力を生残させ核攻撃による報復を行うわけで、それはお互いまずいよねと。だから、一方が核兵器を先制的に使えば、最終的に双方が必ず核兵器により完全に破壊し合うことを互いに確証する。これが相互確証破壊だっていうんだね。
つまり、「立場を絶対裏切らない」という相互確証を約束した人々が閉じることで、集団主義的秩序に基づく安心社会が維持できるかもしれない。私達の世間は、そのようにして成り立っているのかもしれない。
身近なところでは、諸外国ではいい加減に許される電車の遅れなんかが、日本ではものすごく怒られる、みたいなことも、この論理で説明できるかもしれない。「時間通り電車を間に合わせろ」という強い立場の顧客から要請された役割をまっとうできなかったために、相互確証破壊の約束が破られたから、攻撃力が行使されてしまった、ということだと説明できるかもしれない。
さて、良い悪いは別として、私達の社会がそういう構造でなりたっていると仮定するならば、前にも書いたけど、立場の強い依頼者が、自分の行使する(しうる)攻撃(可能性)をどう取り扱うか、ということがやっぱり重要になって来そうだなあ、と思う。
よくいうように、私たちは「主権者」だ。主権者とは「主に権力を持つ者」という意味だ。「権」とは「他人に望まない行為を強制する力」のことだ。私たちは、パワフルな存在だ。だからこそ、そのパワーの使い方に対する、責任と哲学が必要ということかもしれない。
「暴力とは、無能者にとっての最後の拠り所である。」アイザック・アシモフ
「非暴力は臆病をごまかす隠れみのではなく、勇者の最高の美徳である。非暴力を行うには、剣士よりはるかに大きな勇気がいる。」マハトマ・ガンジー
「暴力が障害物を速やかに一掃してしまうことはある。しかし、暴力そのものが創造的であると証明されたことは一度もない。」アルベルト・アインシュタイン
「人間の中に、暴力・攻撃的な衝動というものが、あるんだと思うんです。それをなくす事は出来ないので、むしろどういうふうにコントロールするかという事が、人間や人類に課せられた大きな課題だと思うのですけども。」宮崎駿
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

