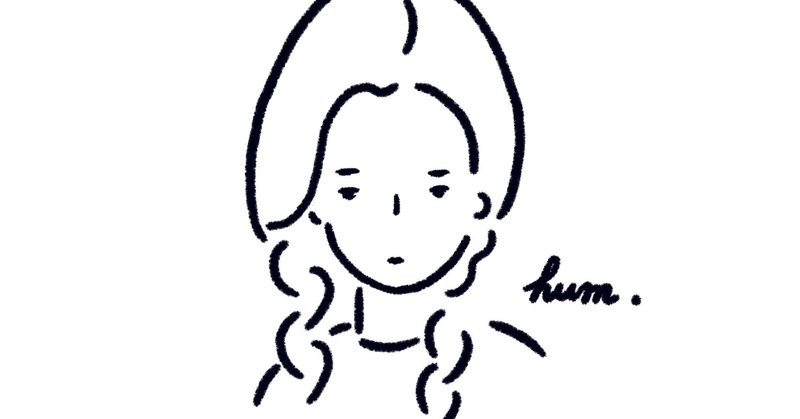
非リア充の声を聞くためのパッシブ参加のコストをどこまで下げられるのか − 東浩紀『一般意志2.0』講談社文庫、2011
本書で著者は、「萌えキャラとしてのルソー」を描いているように私には読めた。キレキレなんだけど、キラキラした人たちのサロンが鼻持ちならないと感じる、一人が好きな哲学者。本書は、そんなルソーの人となりや哲学を、現代の技術を利用することで徹底できるのではないか、という話を通じて、現在の民主主義や対話の限界を指摘している。
市民社会的世界観や、まちづくり分野では、「言葉での話し合い」とか「コミュニケーション」が尊ばれるが、現場にいればいるほど、その理想論性というか、無理っぽさを感じずにいられない。なんか、「こども食堂」やったら、キラキラ世帯が押し寄せて、逆に本来食事を届けたい、生活困難世帯が入りにくい雰囲気になったという話を思い出す。コミュ力やお金やハビトゥスなどの資本に恵まれたリア充が、競合性のあるこども食堂の空間を独占してしまうのだ。そうなると、相対的に貧しい人は行きにくくなる。本気で自信喪失しているリクルーターほど就職相談会に行けないし、本気でお金に困ってる人ほど役所に相談にいけない。だから、子育て世代や高齢者のサロンを開いて、そこに「来れる」人は、実はそもそもコミュニケーションの場という「レッドオーシャン」に臨める程度に元気なのだという逆説があるわけだ。
そういう出会い、対話する場に出られない人へどうサービスを届けるか、というのは、福祉領域ではずっと課題となっていることだが、どうしても政治でも福祉でもまちづくりでもなんでも、コミュ力の高いリア充目線で物事が進められてしまいがちだ。この点を思い出させるルソーの「非モテ」哲学から学ぶことは大きい。
例えばこんな調子。
<ルソーはじつは、部分的結社の存在を否定する箇所で次のように記している。(略)ここでのルソーの主張は、よみまごうことなくはっきりとしている。一般意志が適切に抽出されるためには、市民は「情報を与えられてinforme」いるだけで、たがいにコミュニケーションを取っていない状態のほうが好ましい。彼はそう明確に述べている。つまりは、ルソーは結社を認めないだけではない。直接民主主義を支持するために政党を認めないというだけでもない。彼は、一般意志の成立過程において、そもそも市民館の闘技や意見調整の必要性を認めていないのである。
なんということだろうか。一般意志を導き出すためには、市民は意見を交換しないほうが良い。これはいかにも奇妙な主張である。集団での合意形成に際しては、みなでじっくり話し合うのが世の中の常識だし、それはルソーの時代お変わらなかったはずだ。実際に今箇所については役者も戸惑ったようで、(略)カッコを使って意味が補足されている。こちらもカッコ内の文章は訳者の創作である。ルソーの文章は、同呼んでも「コミュニケーションがなければ」としか言っていない。(PP59-61)
<長い討論や紛糾や喧騒は、特殊な利益の台頭と国家の衰退を告げている」とルソーは記す。そのような思想を持つ彼にとって、結社や政党が肯定的に捉えられないのは必然である。(略)それ以前に政治的な議論の場、コミュニケーションの場そのものが、一般意志の出現のためには障害になると考えていたのだ。(略)ルソーはむしろ、一般意志の成立のためにはそもそも政治からコミュニケーションを追い出すべきだと主張した、とそう要約してもいい。(略)一般意志は、人民が集まり、会議を開き、喧々諤々の議論を重ねてたがいの差異を乗り越え練り上げる、わたしたちが一般に想像するような「合意」とはまったく異なる存在である。>(PP62-63)
<ルソーは結局は、そのサロン文化に馴染むことができなかった。(略)ルソーは都会の「おしゃべり」を嫌った。そして自然を愛した(略)死後に出版された『告白』には、ルソーがどう時代のサロン知識人に抱いていた、被害妄想めいた不信感が赤裸々に記録されている。(略)つまりルソーは一般に政治思想家や社会思想家といった言葉で想像されるものとはかなり書け離れた、現代風にいえばじつに「オタク」くさい性格の書き手だったのである。彼は、人間嫌いで、ひきこもりで、ロマンティックで繊細で、いさあか被害妄想気味で、そして楽譜を写したり恋愛小説を書いたりして生活をしていた。『社会契約論』は、そのような実に弱い人間が記した理想社会論だったのだ。>(PP68-69)
<例えばハーバーマスは、(略)「コミュニケーションの参加者は、相互主観的に同一の意味を認めうるという条件のもとでのみコミュニケーション的行為を行うことが出来る」と断言している。(略)けれども現実には、わたしたちはいま、その前提こそが成立しない時代に生き始めていないだろうか。(略)テロとは要は、議論において異なった意見を提示するのではなく、議論に参加しない、議論の場そのものを破壊するという極端なかたちの「意見表明」だからだ。>(PP106-107)
<現代社会はあまりに複雑で、すべてを見渡せる視線はもはや存在しない。それはすなわち、古典的な選良が存在しないことを意味している。いま「選良」と呼ばれる人々は、現実には特定の「業界」の専門家でしかない。彼らはその業界を離れれば、平凡な消費者、無見識な大衆の一員にすぎない。(略)つまり現代においては、選良と大衆という人間集団の対立があるというよりは、ひとりの人間が、あるときは選良として、またあるときは大衆として社会と関わっていると理解したほうが良い。>(P170)
<熟議民主主義の支持者は、しばしば弱点として「熟議に参加するコスト」を掲げる。けれども、この弱点は、単に弱点の一つとして片付けられるようなものではない。むしろ彼らの理論の致命的な血管を示してしまっている。人間は確かに理性の動物だが、つねに理性の動物であるわけではない。他人の話にきちんと耳を傾け、合理的な判断を下し、その結論に従って行動することは実際にはかなりの精神的なコストを要求する。
人間は普段は理性的に行動しないし、行動したいとも思わない。だから、議論のテーブルにつきたくないひと、あるいはつくことのできないひとの意志は、いかに開かれた制度を構築したとしても、熟議を政治参加の前提として考えるかぎり、どうしようもなく零れ落ちる。>(PP191-192)
<政治の危機の本質は、社会が複雑になりすぎて、熟議への参加コストが跳ね上がってしまったことにある。
年金改革でも景気対策でも外交問題でも、いま日本が直面する課題のいずれもが、専門家や当事者にしかわからない膨大なディテールに覆われている。そもそも事実認識の段階で、専門家の意見そのものが割れていて、どちらが正しいのかわからないことも多い。震災後の放射能汚染の問題はその典型だ。福島周辺の低線量被曝に由る健康被害について、どの情報が正しいのか、一般市民はほとんど何も判断することができない。
では市民は「勉強」すべきだろうか。すでにネトには、あらゆる問題についてーとりわけ放射能汚染についてー、そのように「勉強」して書かれたと思われるアマチュアのブログが無数解説されている。そして侃々諤々の「議論」を交わしている。しかし残念ながら、そのほとんどは素人のケンカでしか無く、あまり役に立たない。そもそもたいていのひとはそれほど暇ではないし、通勤時間胃新書に目を通すのが関の山だ。国民のほとんどは、時間的にも能力的にも熟議に参加することができない。>(PP206-207)
<宇野:ルソーは、他人に理解されたいという気持ちがすごくあるひとですよね。社交界、サロンみたいなところにも一生懸命出かけていく。でも、そこですぐ傷ついてしまう。自分をわかってほしいのに、どこかできっと絶対わかってもらえないと思っている。>(P288)
<東:投票って、ボイス、声ですよね。声をあげないひとというのは、スタンダードの政治思想ではどうしても周縁化される。ぼくは、やはり、オタクというか引きこもりの方から考えてしまうんですよ
宇野:たしかに政治において明確な発言をするひと、できる人のほうが例外的でしょう。それに対し、多くのひとの、言葉にならない思いにこそ、大切なメッセージがあるのかもしれない。その部分をひろいあげなくてはいけないというのは、そのとおりだと思います。熟議民主主義などという場合も、やはりきちんとした言葉で理性的にしゃべることができるひとを想定してしまう。ある程度知識や情報を持ち、議論をすることにも慣れているようなひとですよね。(略)リア充のひとたちだけの民主主義ではだめだというわけですね。引きこもりの人にもボイスの機会を、というのはわかります。>(PP313−324)
社会学の参加論には「アクティブ参加」と「パッシブ参加」って言葉がある。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

