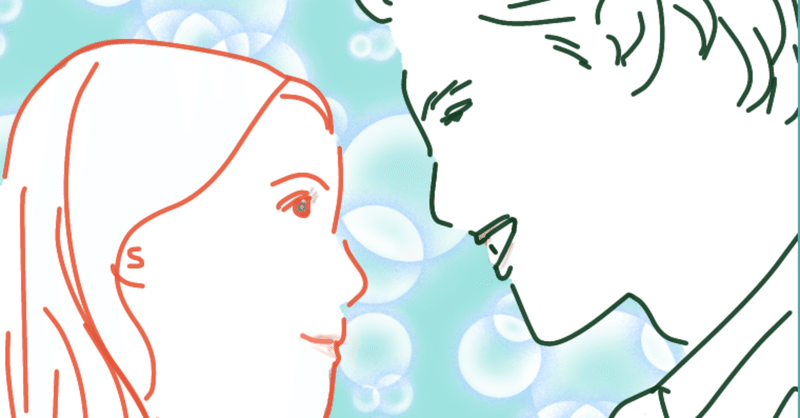
集まることのポイントは「習慣の再配分」
こないだね、子ども食堂について人の話を聞いていて、「ああ、なるほど」と思った事があって。それは、子ども食堂なり、学校なりが、「集まる」ことをなぜ大事にするのか、っていうことで。
例えば、僕が講義をさせてもらっている大学なんかでは、オンライン講義、オンデマンド講義は当たり前のサービスになった。京都では小学校の全生徒にパソコンを配布してオンラインで授業参加ができるインフラを整えていっている。これだけ見ると、わざわざ一箇所に集まって授業を行わなくても良さそうに見える。
子ども食堂でも同じで、本当に食事を届けたいだけなら、ボランティア宅食サービスでもいいわけだし、クーポンにしてウーバーイーツなどの民間事業者を使ってもいいわけで。しかし、そうはならない。子ども食堂では、食事を届けるだけでは不十分だという人たちが一定数いるんだね。
で、それはたぶん、学校でも同じことが言えて。講義内容というコンテンツはいくらでも遠隔で送り届ける事ができる状況になってきた。しかし、それでは不十分だといいたい人たちは一定数いるだろう。
じゃあ、そういう人たちは、宅食なりオンライン講義だと何が足りないのかっていうと、僕が最近理解したところでは、どうも「習慣の再配分」のようなんだね。
習慣の再配分とはなにか。例えば、子は親の習慣を見て学ぶ。だから、よくも悪くも、親の習慣は子に受け継がれる。少なくとも習慣という部分について「鳶は鷹を産まない」ってことになる。いわゆる「生活習慣病」みたいな病気をもたらすような悪習慣だって継承されていく。その逆もまた然りで、健康的な習慣もまた親から子へと継承されていくわけだ。するとどうなるかっていうと、「親ガチャ」によって習慣の格差が開いてしまうわけだ。それはひいては収入や心身の健康の格差につながっていくことになる。
つまり、親や身近な人間以外の、他人の習慣を見て学ぶ機会がないと、貧しい生活習慣が再生産される場合があるわけだ。とすると、必要なのは「多様な生活習慣を見て学ぶ機会を分配する」ってことになる。しかし、習慣っていうのは、その人が実際に生活している姿を見て学ぶしかない。つまり、「習慣の再配分」の機会として「集まる」必要があるということになる。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

