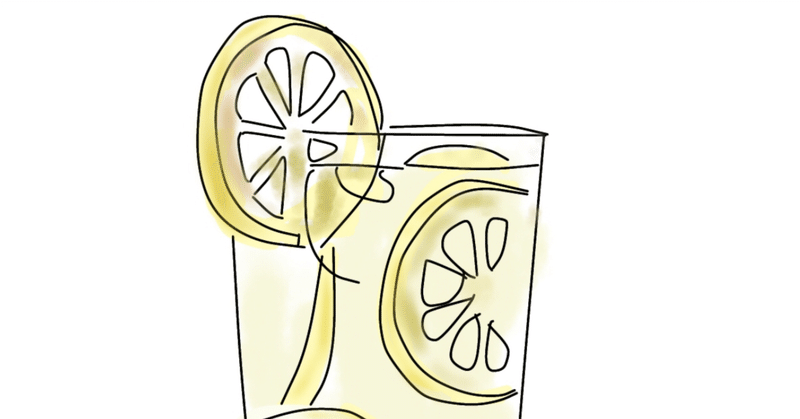
共・縁・電・孤、あなたはどれが好き?
こないだ読んだ、エリック・クリネンバーグ『集まる場所が必要だ孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学』の好きな記述でこんなのがあった。
<シャロン・マーカスは、クイーンズ区(訳注:ニューヨーク市の5つの区の1つで民族的多様性に富む地域)の労働者階級の家庭に育った。一家の生活は苦しく、誰もが忙しそうだった。「平穏な家庭ではなかった」と、彼女は振り返る。「公園で多くの時間を過ごしたけれど、そこはそこで荒れていた。落ちついて座れる場所はどこにもなかった。私は内向的だったから、誰とも話さない時間が必要だった。好きなだけ本を読んでいたかった。自分の時間やエネルギーを自分だけのために使いたかった。何にどのくらい注目するかを自分で決めたかった。図書館は、周囲の人を無視しつつ、ひとりぼっちではないと感じられる場所だった。うちは夏休みに旅行に行ったりしなかったから、図書館は、すべてから逃れて、よりよい現実を垣間見られる場所だった」>
「図書館は、周囲の人を無視しつつ、ひとりぼっちではないと感じられる場所」。この微妙な塩梅。
本書は、この有り様を可能とする社会的インフラが、人を外出させ、死ににくくさせるということを説得的に論じてくる。
例えば郊外のショッピングモールとかに平日に日中に行くと、ベンチコーナーに高齢者が一人で何をするともなく座っていたりするが、あれは思うに、この環境を求めていたのだといえる。あれ、やってみるとわかるけど、意外なほど快適だし、寂しさや不安を忘れられちゃうんだよな。人生経験豊かなご高齢の皆様がこぞってやるのもわかる。
この有り様、うまい名前がついているのかどうか知らなくて、それゆえに上手に扱えない概念だったのだけど、こないだ人から教えてもらって知った話で。
京都大学の藤原辰史さんが『縁食論――孤食と共食のあいだ』という本を書いていて、そこでこんな整理をしている。
例えば子ども食堂や高齢者サロンなどは、人が集まるが、参加者同士の言語的なコミュニケーションを強く期待する場だ。こういう場で行われる営みを「共食」という。
それゆえ共食の場には、言語的コミュニケーションを強く好む特定層は参加するが、そうではない一般層にとっては敬遠される場としてあった。
だから例えば高齢者サロンなんかは、コミュニケーションが達者なおばあちゃんが席巻して、口数少ないおじいさんが出てこない、なんてことはよく言われて生きた。誰でも参加できる、といっても、それはカッコ書きで、「ただし、一定以上達者な言語的なコミュニケーション能力を要する」わけだけど、そのカッコ書きは明示されない。
で、そういうのはちょっと、となると、途端に一人ぼっちで部屋に閉じこもってご飯を食べる、みたいなことになる。そういう食事のあり方を「孤食」といって、あんまりよくないよね、と言われてきた。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

