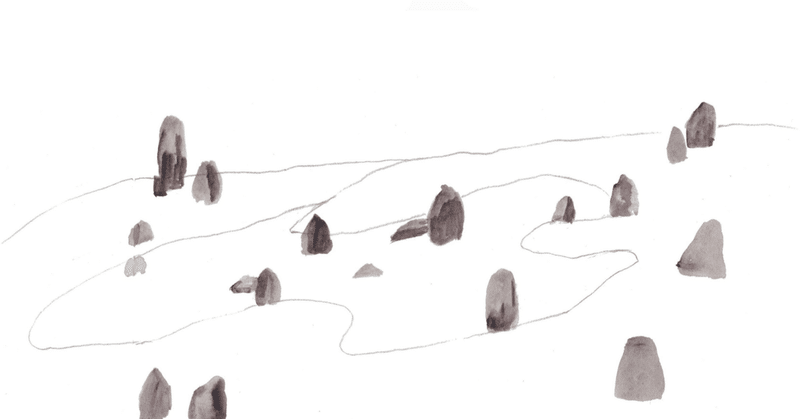
言葉のもつ可能性と絶望について 2024/04/01 -4
この本は、何度、そしてどれだけの深度でわたしのことを抉るのだろう。頭がパンクしそうになる。でも、読んでしまう。久しぶりに、所謂「頁を捲る手が止まらない」という状態になっている。といいつつ、どうしても同時に言葉が(想いが、の方が適切かもしれない)溢れて止まらなくて、勝手に頁を捲る手を止めて、スマホを手に取りアプリをひらき、気がつけばフリック入力をしている自分がいる。このふたりのわたしが、今わたしの目の前に創造されている現実だ。
言葉についてのこのくだりに、頭が真っ白になるくらいの衝撃を受けたので記録として残しておきたい、というか何とかして頭を整理したいと思い、今これを書いている。実は引用部分より下のひと段落(ひとかたまり?)は、それより上に書いたものよりも先に書いた。出てくるものを止めることが出来なかった。どう繋げるのが最適なのかを考える余裕もなく、頭が真っ白になったわたしはひたすらに手を動かしていた。
自分の親と、直接、込み入った話が出来ないというのは、どんな感じなのだろうかと想像した。ミャンマー語だけでなく、日本語も不得手だとすると、彼女は、この世界の誰とも、本心でやりとりすることが出来ないのだろうか?
こんな風に、独りで考えようとした時に、言葉が手許にないということは?僕が学校で習った程度の英語で、自分の気持ちを説明しようとするようなもどかしさだろうか?その場合でも、僕は日本語では、自分の言いたいことを理解しているのだが。・・・・・・
自分の話している言葉が完璧だなんて、どうして思えたのだろうと心底不思議に思った。ただ、感覚としては言い切ったときは言い切ったという感覚があって、それも疑うのはナンセンスだし、何よりお門違いというか、過剰反応な気がした。ただ、この過剰反応は、わたしの心を守るための防御反応でもあり、自分の心を自分の気付きから守りたくなるくらいに、わたし自身が驚き傷付いたのだということをなかったことにしてはいけないと思った。そうだ、わたしは、急に自分の不完全さを目の前に突きつけられて、ショックを受けて固まっているのだ。
'上' に戻って何とか "格好" をつけ、今またここから言葉を紡ごうとしているわたしがいる。だが、ここから紡いでいく言葉たちは果たして(そしてこれまでに紡いできた言葉たちは果たして)、わたしが今感じていることを全て網羅しているのだろうか?そもそも、ここに並べている言葉とその文体は最早、平野さんの小説「本心」の主人公の語る言葉と瓜二つになっているのではないか。だからこそ、それも相まって、わたしは今、このような気持ちになっているのかもしれない。ここにいるわたしね本当にわたしなのか?疑問視しているということはそうなのだろうか?それとも、そうせざるを得ないくらい、実は混ざってしまっているのだろうか?きっとそうなのだろう。わたしは本を読むと、その本に思考を乗っ取られるきらいがある。・・・・・・
言葉については散々といっていいほど考えてきたし、きっと死ぬまで散々以上に散々に考えていくのだと思う。恐らくわたしは、"言葉というものの存在" に取り憑かれている。言葉にならないことも含めて、言葉にするというその矛盾を愛しているといってもいい。だが、今回この小説のこの部分を読んでいてわたしが受けた衝撃は、そもそも「なぜその言葉/表現でいいと思っているのか、思えていたのか」という、言語化の根幹というか、源ともいえる部分に土足で踏み込まれてしまったような感覚になったということなのだと思う。
つまり、わたしは自分の扱っている "日本語というもの" に対して、そしてその自分の感覚に対して「信頼しすぎていた」という盲点を突かれた感覚になった、ということ。日本語(日本語という存在そのもの、言語という存在そのもの)に、甘えているといってもいい。たとえば、「日本語は話せる」「日本語の文章は書ける」「感覚には自信がある」という自負が自分の中にあったとして(あったのだ、恥ずかしいことに)、それが全てだなんて誰が決めた?ということに気付かされてしまったのである。・・・言語化し切れているのか?ということに気付いて絶望しているのにも関わらず、わたしは今ここに自分の中で起こっていることを馴染み深い日本語を集めた言葉で綴っていて、ホッとするという皮肉でしかない状況に陥っている。気付きたくない自分がいるのはわかっているが、気付かざるを得ない。それはここにそれを書いたからであって、またまた皮肉だなぁと感じる。嘲笑する、といった感じだ。メロスを嘲笑した暴君はこんな気持ちだったかもしれない。
このnoteにはきっとオチはない。なぜなら、わたしが今感じているこの感覚については、一朝一夕に答えが出るものではないと感じるからだ。と同時に、そんなに早く答えが出ては困ると思っている自分がいるからだ。こんなにショックを受けているのに、こうやって文章を綴りながら、その感覚がまるで霞が空気に溶けていくかのように、溶けてしまったほうが自然なように、感覚がぼやけていってしまう。そもそも、そんなところ疑う必要があるのかすら疑わしい。でも、わたしは感じてしまったのだから、無かったことにはできない。
むしろ、そのくらい微かで消えてしまうのが当たり前のような感覚だからこそ、支離滅裂なことは承知の上で、ここに記録しているのだと思う。掴んでいるのが難しいくらいなのだ。そのくらい、日常の中で当たり前になってしまっている感覚に、わたしは歪みを見付けたのだと思う。そんなに拘る必要が無いことなのではないか、という声も同時に聴こえてはいる(もちろん、自分から)。でも、それは検証の結果、或いは後日或いは数時間後或いはどのタイミングでもいい、このnoteを読み返したわたしが、「取るに足らない」と思えばそのときそう判断すればいいと思う。今のわたしは、そう言い切ることを拒絶している。なぜなら、今まで終ぞ感じたことのない感覚に出逢ったということが、何にも替え難い価値を持ってわたしの中に留まっているからだ。
ということで、答えは出ないまま、疑問のあるまま(そして疑問のないまま)、このnoteは終わりにしようと思う。わたしは小説を最後まで読みたい。読み終わるまでにあと何回こうやってnoteをひらくのかは分からないが、それも含めて今この本を読むことの意味なのだと思う。
2024/04/01 -4 (91/366)
よろしければサポートお願いします!!!いただいたサポートは、必ず循環させていきます!!!
