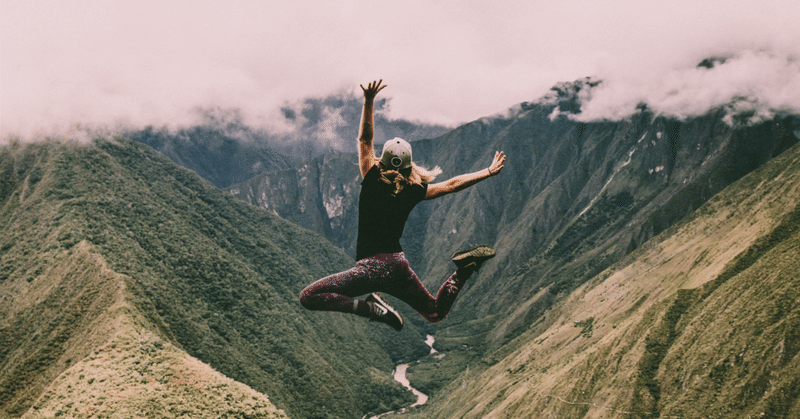
若気の至り
多文化共生社会における現状の移民(在日外国人)問題
1.はじめに
このレポートでは日本への移民に関する現状の課題を3つ述べたのち、それぞれの解決策を提示したうえで、多文化共生社会への実現の術を論じる。
2-1. 移民の受け入れや定住に関する法的・制度的な枠組みの不備や不十分さ
まず1つ目の課題として日本社会に移民の受け入れや定住に関する法的・制度的な枠組みが不十分であることが挙げられる。そのなかでも特筆すべきなのは在日外国人と日本人がもつ権利の質がかなり異なっていることだ。移民社会学者の駒井は次のように述べている。
「生存権:非正規滞在者は所得税を徴収されているにもかかわらず、法的保護をほとんど受けることができない。その好例が、重症の病気やけがにより生命の危機が生じる場合である。そのようなときでさえかれらの人権は無視される。…ところで1990年10月厚生省は「不当滞在者にたいする生活保護の適用は適当でない」という指示を出した。…この指示により、医療機関は外国人患者から徴収不可能であるのに生活保護費による補てんもされない未払い医療費の問題を抱え込むことになった。未払いをおそれ、重症であればあるほど医療機関による非正規外国人にたいする診療拒否が頻発し、治療から見はなされる者が多く生まれている。居住権:現在(1999)非正規滞在者が日本での滞在を正当化される唯一の道は、法務大臣から在留特別許可を得ることに限られている。ただし、近年在留特別許可が与えられている件数が若干増大していることには注目に値する。社会権:外国人労働者の就労する場が主として労働条件の劣悪な中小零細企業であるため、突然解雇、賃金未払い、内国人との賃金格差、労働災害保険の不適用などの事例が多発している。」 (駒井、1999、165-171頁)
社会権に関しては2-2で、居住権に関しては2-3でかかわってくるため、この節では生存権の問題の解決策を提示する。まずもって不当滞在者であっても所得税を払っている者に対しては法的保護を執り行うべきであると考えた。具体的には少なくとも教育扶助、医療扶助、出産扶助を日本人と同じように彼らに対しても行うべきだと考えた。そうでなければ何のために税金を払っているかがはっきりせず、彼らは日本国の産業を支えてくれている大切な人員であるため、十分な保護を受ける権利を有していると考えたからだ。
2-2.移民が定住した後の支援不足
まず、自分は、子をもって日本に移住してきた人の子に対する教育が適切に行われているのかどうかを調査した。文部科学省外国人児童生徒数等教育アドバイザーの海老原は「日本語指導が必要な高校生の中退・進路状況について、全国公立高校生等と比較した場合、中途退学率で7倍以上、就職者における非正規就職率で約9倍となり、進学も就職もしていない者の率では約3倍高くなった。また、進学率では全公立高校生等の6割程度となっている。」 (海老原、2021、48頁)と述べている。これは日本語の教育を受ける機会が必要な人に行き届いていないことを示している。また、外国人労働者に対する政策についても調べた。自由人権協会理事である旗手は「技能実習生や「技術・人文知識・国際業務」などの就労目的の在留資格で就労していたものに対する「雇用維持支援策」として特定技能に誘導する政策は、技能実習で取得した技術・技能等との整合性を欠くことになるとともに、専門的・技術分野の在留資格から熟練度の低い「特定技能」に導くもので、在留資格間の整合性を崩してしまうことも指摘できよう。」 (旗手、2022、173-174頁)この記述から外国人労働の面でも様々な対応は実行しているもののところどころに不十分な点が散見される。ではこの問題を解決するためにはどのような策を講じればよいのだろうか。自分はまず教育の面に関しては、日本語指導が必要な中高生に対しては、入学前や入学後に日本語能力テストを実施し、教師がどのくらい日本語を教えなくてはならないかを認識する。その後、必要に応じて学校側がオンラインの教材など教師側の負担を増やさない形で日本語を教える支援をしていくことが有効な解決策になると考えた。また、日本語以外の教科でも、外国人児童生徒の学習状況やニーズに応じて、補習やサポートを週1回以上は行い、他の生徒についていけるような支援を十分にする。また学校以外の教育団体に日本語教育を依頼するのも一つの手だと考えた。労働面に関しては、技能実習生や「技術・人文知識・国際業務」などの就労目的の在留資格で就労していた者のキャリアやポテンシャルを無視するようなことへ誘導することを防ぐために、これらの在留資格を有する外国人に彼らの高度な専門性や技術性を生かすことのできる分野における再就職を政府が支援するべきだと考えた。
2-3. 移民と日本人との間の言語や文化の違いによるコミュニケーションや理解の困難さ
第3の課題として言語や文化の違いによる理解の不足が挙げられる。その問題を表す、具体的な事例を発見したためここで紹介しておきたい。これは移民社会学者の駒井が著書の中で述べたものだ。
「…外国人も日本人も、硬直化し制度疲労を起こしている日本企業・経済や国家・政治の共通の犠牲者となっていることをあきらかにした。…日本人の中に非西欧系の外国人に対する差別や偏見がないとは言えない…差別がもっとも象徴的にあらわれるのは入居差別であり、原則として「外国人お断り」と掲げる家主や不動産業者が多数を占めるなかで、外国人が住居を見つけることはむずかしい。」Ⅰ(駒井、1999、165-171頁)
この問題の解決策としては教育の場や地域での交流の場で、互いの文化を理解する機会を設けることが考えられる。そこではお互いの文化を紹介し合い、価値観の相違を認めあう活動を行う。さらには自治体などに協力してもらい実際に対面し交流をするだけでもそれまでもっていた多少の偏見がうすれていき、何度もその活動を地域全体で行うことで少しずつだが理解の困難さといったものが消えていくと考えた。
3.総括
今回提示した3つの課題は日本の移民(在日外国人)問題のほんの一部にすぎず、他の問題に関しても早急な解決を要するものである。また日本の不法移民に対する攻撃的な意識の表れもネット上では散見され、その意識も払拭していく必要があると考えた。今後も日本の移民についてより詳しく知るため、様々な文献にあたって研究を進めたいと考えた。
Ⅰ 駒井洋(1999)「日本の外国人移民」東京:明石書店
Ⅱ 海老原周子(2021)「外国ルーツの若者と歩いた10年」東京:公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京
Ⅲ 旗手明、編者:鈴木江理子(2022)「アンダーコロナの移民たち 日本社会の脆弱性があらわれた場所」東京:明石書店
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
