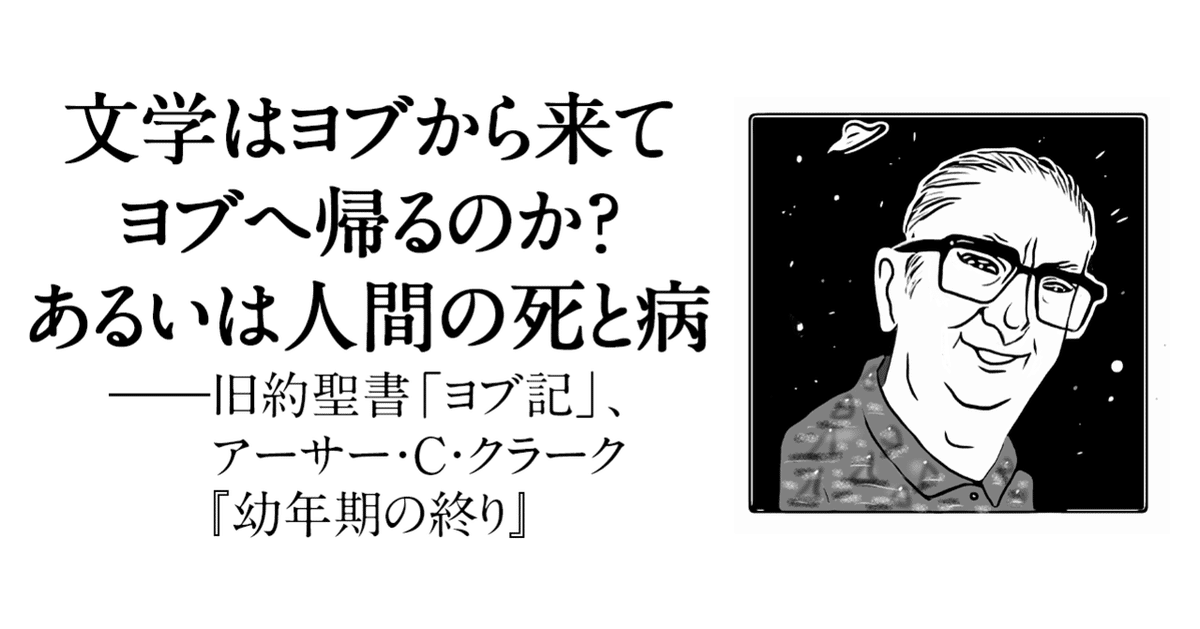
文学はヨブから来てヨブへ帰るのか? あるいは人間の死と病──旧約聖書「ヨブ記」、アーサー・C・クラーク『幼年期の終り』
「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト編 第10回
内藤理恵子(哲学者、宗教学者)
『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』著者、内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」。いよいよ第10回、最終回となってしまいました。
最終回では、「人間であるとはどういうことか」という究極の問いに対する答えを、旧約聖書「ヨブ記」と、SFの名作『幼年期の終わり』から探ります。
この連載はマガジン「内藤理恵子『死』の文学入門」でお読みいただけます。
西洋人よりも日本人の方が「ヨブ記」がわかる⁈
今回は旧約聖書「ヨブ記」を取り上げます。これは実存的文学のルーツといえるものです。しかし、一般には“文学”とはされておらず、そこをどう考えるべきなのか……。そこで、日本のある思想家の言葉を挙げたいと思います。キリスト教思想家の内村鑑三の言葉です。
「ヨブ記は文学書にあらずしてしかも世界最大の文学書である」
(内村鑑三『ヨブ記講演』岩波書店、2018年、Kindle版)
「ヨブ記」はユダヤ教・キリスト教の聖典であるため文学とは見なされないけれども、実際には、どのような文学作品をも凌駕する文学だということです。内村は、ゲーテの『ファウスト』、ダンテの『神曲』、シェークスピアの『ハムレット』もまた、「ヨブ記」から生まれたとも述べています。「ヨブ記」を知らずして、文学を語ることなかれ、なのです。
とはいえ、私たち日本人には「ヨブ記」はあまり馴染みがないかと思います。「ヨブ記」はおおよそ紀元前5〜3年にパレスチナで成立した、という説が有力ですが、実のところ、書かれた時代も作者も物語の舞台もはっきりしていません。いずれにしても、日本の文化とは関係のない土地で大昔に書かれたものなのですが、内村は異邦人の私たちのほうが、「ヨブ記」を読むのに適していると主張しているのです。
というのも、そもそも「ヨブ記」の主人公ヨブはパレスチナから見て異国の人であった、という説を内村は支持します。そして、ヨブが異国の人であるからこそ、民族を超えた聖書の普遍性をそこに見出しうるのではないかと考えたわけです。つまり、私たち異邦人と主人公ヨブの立場は同じ異邦人という立場にあります。ここで「ヨブ記」のあらすじを見てみましょう。
<内村鑑三(1861〜1930)>

イラスト:内藤理恵子(以下同)
「ヨブ記」のあらすじ
ヨブは7人の息子と3人の娘を持つ富豪で、神への信仰も篤い義人でした。自らのふるまいに神への対応に欠けた点はないのか、念には念を入れて生活しています。彼の少し強迫的ともいえる信仰スタイルは以下のようなものでした。
――息子たちはそれぞれ順番に、自分の家で宴会の用意をし、三人の姉妹も招いて食事をすることにしていた。この宴会が一巡りするごとに、ヨブは息子たちを呼び寄せて聖別し、朝早くから彼らの数に相当するいけにえをささげた。「息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない」と思ったからである。ヨブはいつもこのようにした。
(『聖書 共同新訳−旧約聖書続編つき』共同訳聖書実行委員会、1987年)
「聖別」とは俗な領域から切り離して神に捧げるということです。もしかしたら息子たちが犯したかもしれない罪の可能性にすら怯えるのが、ヨブの信仰スタイルです。
このような信仰生活を送るヨブに神は疑問を持ちませんでした。しかし、サタンは疑問を持ったのです。ヨブの信仰は自分の財産を守るためではないか、というのです。こんなことをすれば、神は自分の財産を守ってくれるだろう、という予測の下でヨブは動いているだけで、それを奪ってしまえば神を呪うに違いない、とサタンは予想します。そこで神に、ヨブの所有物を自由にしてよい(奪ってもいい)という許可を得ます。つまり、ヨブを試してみてもよい、という許可です。
サタンはまずヨブの牛、羊、ラクダ、雇っていた牧童たち、羊飼いたち、息子、娘たちを奪います。ヨブは、それでも信仰を捨てませんでした。そこで、サタンはさらに試練を与えようと、ヨブの全身を皮膚病にしてしまいます。それに対してヨブの妻は「どこまでも無垢でいるのですか。神を呪って、死ぬ方がましでしょう」と、信仰を捨てないヨブをなじります。しかし、ヨブは「わたしたちは、神から幸福をいただいたのだから、不幸もいただいておこうではないか」と苦難を受け入れようとするのです。
その後、ヨブの皮膚病が重篤であると聞いたエリファズ、ビルダト、ツォファルの三人の友人がヨブのもとに駆けつけて、それぞれがヨブに語りかけます。エリファズは「ヨブは最終的には天寿をまっとうすることになる」と励まし、ビルダトは「ヨブの子どもたちが神に対して過ちを犯した」という憶測でヨブを責め、三人目のツォファルは、「ヨブの現状は因果応報だ」と語ります。ヨブは「そんなことを聞くのはもうたくさんだ、あなたたちは皆、慰めるふりをして苦しめる」と腹を立てるのでした。
満身創痍のヨブの前にようやく神が登場し「腰に帯をせよ」(「シャキッとしろ」という意味)と語りかけます。そして人間がいかに無知な存在であるのかをヨブに語りかけるのです。一神教では、神の被造物にすぎない人間が、創造神に疑問を投げかけること自体、不敬だと考えられ、神もそのことをとうとうと語ります。最終的にヨブは神の忠告を受け入れ、苦難から解放されます。さらには神の恩寵によって財産が二倍に増え、子孫も栄えて、長寿も得ることになります。
(参考・『聖書 共同新訳−旧約聖書続編つき』共同訳聖書実行委員会、1987年)
ヨブの以前の信仰スタイル(いけにえを捧げて現世利益を守ろうとする姿勢)は誰からも後ろ指をさされるものではありませんでしたが、通り一遍ともいえるものでした。しかし、このような数多の苦難を経て、ようやく自らが選んで神への信仰を持つことになったのです。主体的な意思による選択(決断)という点で、これは実存主義の始まりといえるかもしれません。

気になるサタンの性質
「ヨブ記」に登場するサタンは、文学作品でよく見かけるような、人間を誘惑し、そそのかしたりするイメージとは少し異なります。「ヨブ記」のサタンは、神に従属する姿勢を見せつつも反対意見を述べる、という微妙な立ち位置にいます。サタンはヘブライ語の「(神に)敵対するもの」という言葉を語源としています。つまり、悪そのものではなく、堕天使(天から堕ちた天使)であって、善悪二元論の“悪”ではなく、“善の欠如”といった方がしっくりきます。優等生だった中学一年生が二年生になったとたんに傲慢になり、教師の手に負えないような問題児になってしまった……そんな光景を思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。
とはいえ、人はどうしても死や死を連想させるものを悪とみなし、サタンもそのような存在に見られがちです。旧約聖書「イザヤ書」14章においては、サタンは神に反逆し、天上から追放され「陰府(よみ)」「墓穴の底」に落とされたとされていますから、死者の国が彼の住処ということになります。
また、「創世記」では、サタンは蛇の姿になってイブをそそのかし、「善悪の知識の木の実」をアダムとイブに食べさせます。それが神の逆鱗に触れたことはよく知られています。
しかし、神がアダムとイブを楽園から追放したのは「善悪の知識の木の実を食べたから」ではありません。楽園には、もう1本その実を食べると不死になるとされる「命の木」が生えていて、それを食べたら人間が不死になってしまうという恐れ(実際には食べてはいない)によって、神は人間を追放したのです。
主なる神は言われた。
「人は我々の一人のように、善悪を知る者となった。今は、手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きる者となるおそれがある」
主なる神は、彼をエデンの園から追い出し、彼に、自分がそこから取られた土を耕させることにされた。
こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムと、きらめく剣の炎を置かれた。
(『聖書 共同新訳−旧約聖書続編つき』共同訳聖書実行委員会、1987年)
神は人間が「不死になる」恐れから楽園追放した――それはなぜなのか? 神の口からは語られません。おそらく、善悪を知り、さらに不死となってしまった人間は何らかの脅威になりかねないと判断したためでしょう。このエピソードの初動をたどれば、「善悪の木の実」を食べるようにサタンがアダムとイブをそそのかしたことが、きっかけになったわけですから、人間の死生の問題とサタンは関係していることになります。
ここまでの旧約聖書のサタンに関する記述をまとめると、サタンは死者の国に住んでおり(イザヤ書)、人間の死生に関わり(創世記)、ヨブの病(ヨブ記)にも関わることによって、後代に病や死の表象を抱かせるようになった、ということになるでしょう。
よく知られているサタンの外見についても特記すべきことがあります。私たちがサタンのイメージとして共有している「短い角」や「尻尾」といった特徴は、ギリシャ神話のヘルメスの息子パン(牧神、「パニック」の語源でもある)の特徴でもありました。つまりサタンの表象はギリシャ神話からの借り物なのです(J・B・ラッセル『悪魔 古代から原始キリスト教まで』野村美紀子訳、教文館、1984年、p127)。多神教の世界における神が、ひるがえってキリスト教世界ではサタンになっているわけですから、そのイメージはやはり絶対的な悪ではなく相対的なものなのです。
キルケゴールへの影響
キルケゴールの主著『死にいたる病』(1849年)では、ゲーテの『ファウスト』(1808年、1833年)のサタンに関する言葉が引用されていて、自分自身の罪の“自覚の強さ”にサタンを見出しています。キルケゴールにとって、サタンは、自省のための一要素と認識されているのです。ここでのキルケゴールの罪とは何か。彼が放蕩生活を送った過去と、肉親の性的放逸さ、そして彼自身の婚約破棄など複数の要因があるでしょう。
19世紀のキルケゴールは、「ヨブ記」から受けた強い影響について、偽名で公表した著書『反復』のなかで克明に記しています。キルケゴールのヨブへののめり込みは常軌を逸しており、彼が起こした婚約破棄事件も、もしかするとヨブへの傾倒が原因ではないかと思われるほどです。
『反復』は、架空の詩人と青年の往復書簡の体裁を採っていますが、単なる創作ではありません。実際に婚約破棄した恋人(レギーネ)に自分の本心を明かそうと書かれたものなのですから、本作の主人公である若い詩人は、キルケゴール自身とも考えてよいでしょう。詩人は、次のような手紙を文通相手の青年にしたためます。
もしぼくにヨブがいなかったら! 彼がぼくにとってどんな意味を持っているか、どんなにさまざまな意味を持っているか、それを書きあらわし、そのニュアンスを表現することは不可能です。ぼくは彼をほかの書物を読む時のように目で読まないで、ぼくはこの書物をいわばぼくの心臓の上にのせるのです。そして心の目でそれを読みながら、一種の透視力でぼくは細かな点まで実にさまざまに理解します。朝になって目を覚ましたらせっかく勉強したことを忘れてしまっていたということのないように、子供が教科書を机の下に入れておくのと同じに、ぼくは夜ヨブの書をベッドにもってはいります。彼の一語一語が、ぼくの惨めな魂にとって栄養であり、衣服であり、医薬であります。彼の一言がぼくを昏睡状態からよび覚まして新たな不安に駆り立てることもあれば、ぼくの内部のむなしい狂乱をおし鎮め、激情の無言の苦悩から生まれる兇猛なものに止めを刺すこともあります。あなたはきっとヨブをお読みになったことがあるでしょう。彼をお読みなさい。幾度でも繰り返してお読みなさい。
(キルケゴール『反復』桝田啓三郎訳、岩波文庫、1956年、p152〜153)
「やがて沈黙が破られて、ヨブの苦しみ苛まれた魂が力強い叫びとなってほとばしり出ます、それがぼくにはわかるのです。この言葉をぼくはぼくの言葉にします。その瞬間にぼくは矛盾を感じ、そしてまるで子供が父の着物を着ているのを見るとおかしくて笑わずにいられぬように、ぼく自身をあざわらいます」(同p156〜157)
物語の登場人物に感情移入することは誰しも経験があるでしょうが、キルケゴールの「ヨブ記」への心酔は並大抵ではなく、まるでヨブという男がキルケゴールに憑依したようです。実存主義の祖とされているキルケゴールの思想的ルーツに、ヨブの存在があったことは間違いないでしょう。キルケゴールは放蕩生活を経て絶望したのち、自ら選択して信仰生活に戻り、『反復』を執筆しました。彼は恋人との幸せな生活よりも、神への信仰を選択したのです。とはいえ、キルケゴールは相変わらず恋人を愛したままでしたから、相当苦しかったのでしょう。自らの葛藤を恋人(元婚約者)に理解して欲しいという気持ちが抑えられず、行間から彼の思いがほとばしるようです。
しかし、ヨブの絶望と、キルケゴールの絶望は同じものなのか、という疑問もあります。ヨブはすべてを奪われて絶望に陥りましたが、キルケゴールの目の前には輝かしい未来(恋人との新婚生活)があったはずなのです。キルケゴールは自分が幸福になりつつあるのを自覚していたからこそ、恐れおののいて、あらかじめ大切な婚約者を棄ててしまうことで、それを失うことを防ぐ倒錯的行動に走った可能性が高いと思います。キルケゴールの恐れの原因はやはり「ヨブ記」にあると思います。入念に罪を犯さぬようにしていたヨブですら、悪魔によって試練が与えられたのですから、罪の自覚のあったキルケゴールには脅迫のように感じられたことでしょう。「ヨブ記」は、信仰を持たない者にとっては文学的エピソードとして読むことができますが、信仰を持つものにとっては劇薬にもなり、キルケゴールにはそれが効きすぎたのです。
文学史の中のサタン
文学史の中には、サタンが旧約聖書に登場するような確固たるキャラクターではなく、人間の“影”になっている作品があります。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』(1880年)です。ここでは、サタンは三兄弟に次男イワンの白昼夢の幻覚……人の心の外部でもあり、なおかつ内部でもある形で登場します。人の心の影として登場しながらも、『カラマーゾフの兄弟』のサタンはやけに個性が強く、健康に気を使ってワクチンを接種した、などユニークな小噺まで披露します。
しかし、カフカの『変身』(1915年)、カミュの『ペスト』(1947年)などの不条理小説においては、神もサタンも、人の心の鏡のような存在としてほのかに顔を覗かせるだけで、明確なキャラクターとしては示されません。『ペスト』のパヌルー神父は、ぺストでパンデミックに陥った街で人々を励まし、信仰を守りながら死に至ります。『変身』のグレーゴルは、ある朝、突然虫に変身し、父の暴力で身体にダメージを受け、挙句の果てには、家族に忌み嫌われていることを自覚しつつ自死に近い形で死んでしまいます。虫に変身することを何らかの病だと解釈することも可能でしょう。
『変身』や『ペスト』には、「ヨブ記」に見られたような一神教の神との邂逅や恩寵などは出てきません。それは、20世紀の小説においては、明確なわかりやすい形での悪が存在しないということでもあります。『変身』における悪は、確固たるキャラクター(サタン)としてではなく、人の心に巣食うという形、たとえばグレーゴルの家族の残酷な性質として顔を覗かせることになります。それだけではありません。解釈次第では、健康であり、かつ金銭を稼がねば存在意義が認められない(異常なものは排除される)社会や経済のシステムにサタンが巣食っていることも示唆していると思います。
20世紀文学における善悪の問題には、「絶対的な善としての神」の死(ニーチェ)や、それ以前から一定の浸透を見せていた無神論的な懐疑主義の影響もあるかもしれません。明確に善と悪が明示されるのは、いまではエンターティンメント小説と呼ばれるジャンルだけでしょう。
『幼年期の終り』は未来形「ヨブ記」
そうしたなかで、19世紀ごろから現れたのが、サイエンスフィクション(SF)というジャンルです。なかでもアーサー・C・クラークの『幼年期の終り』(1952)は善・悪の問題をテーマに、「ヨブ記」を再考するヒントを提示しているように思います。
『幼年期の終り』のあらすじは以下のようなものです。
大きな宇宙船に乗って宇宙人が地球にやってきます。彼らのリーダー(カレルレン)は姿を表しませんが、音声のみで人類にメッセージを伝えます。彼は完璧な英語でスピーチし、圧倒的な知性を見せつけます。あらゆる都市の上空に宇宙船が出現し、ミサイルで攻撃しようとする国もありますが、まったく効果がありません。人類は完全に制服されてしまい、宇宙人は、次第に人間の倫理観にまで干渉するようになり、人種差別のある国に対し太陽を30分の間、遮断するなどという威圧的な警告を発するほどです。
時が経ち、いよいよ宇宙人のリーダー(カレルレン)が人類の前に姿を表します。その姿は意外なことにサタンの姿をしていたのです(これには本作の重要なメッセージが隠されています。詳細は後述します)。
カレルレンはじめ、宇宙人たちの力を借りて、すべての農作物や必要物資をオートメーションで生産できる技術を手に入れた人類は、働かなくても生命を維持できるようになります。宇宙人の高い医療技術のおかげで疾病の不安からも解放されます。病、貧困問題、戦争などの解消により、いわば“ユートピア”と呼べるものが地上に実現することになります。しかし、不安を手放した人類は、創造性までも失ってしまうのです。文学は何十年も生まれず、芸術的な活動も停滞することになります。暇つぶしの娯楽番組だけが膨大に制作され、人はそれを観ることに人生を浪費するようになります。
疾病や貧困からの解放のメリットを享受することが優先され、文化的堕落に警鐘を鳴らす人間はほとんどいませんでした。しかし、少数の哲学者のみが、それが危機的状況であると気づくのです。ある哲学者を中心に、芸術家たちのコロニー「ニュー・アテネ」が形成されます。
以下は本文からの引用です。
あらゆる種類の不知や相剋が姿を消したことは、同時に、創造的芸術の事実上の壊滅を意味していた。素人たると玄人たるとを問わず 、俳優と名乗るものは世に充満していたが、いっぽう、真に傑出した新しい文学、音楽、絵画、彫刻作品は、ここ二、三十年というものまったく出現していなかった。世界はいまだに、二度と還ることのない過去の栄光の中に生きつづけていたのだ。
だが、この事態を憂えるものは少数の哲学者以外にいなかった 。人類は手にいれたばかりの自由を貪ることに急で、現在の快楽の先にあるものを見通していなかった。ユートピアがついにここに実現したのだ。その目新しさは、まだあらゆるユートピアの最大の敵──退屈──に侵されるまでには至っていなかった。(アーサー・C・クラーク『幼年期の終り』福島正実訳、早川書房、2010年、Kindle版)
物語の中で人類が病や貧困の心配から解放されたことは、明らかに人類史的な達成です。現実の世界はいまだにこれをまったくなし遂げていません。しかし、そうした課題が地球外から来た宇宙人の力によって達成されてしまったこのSFのユートピアは、哲学者の目から見れば、人類の家畜化に他ならなかったのです。作中では、チャールズ・ヤン・センという哲学者がコロニーの理事長になります。
理事会の現議長は、チャールズ・ヤン・センという哲学者だった。皮肉っぽい。だが根は陽気な男で、まだ六十歳にはなっておらず、したがってまだ壮年というわけだった。プラトンが彼を見たら、おそらく、哲学者政治家の好例とみたことだろう 。もっともセン自身は 、必ずしもプラトンを買ってはいなかった。ソクラテスをはなはだしく誤り伝えたのではないかという疑問を抱いていたのである。彼は、この訪問(宇宙人の訪問)を最大限に活用してやろうと決心した島民(コロニーは二つの島で形成されている)の一人だった。オーバーロード(宇宙人)たちに、人類がまだ多くの主体性を持っていること、そして、まだ──彼の表現にしたがえば──〝完全に飼い馴らされ ” てはいないことを見せつけてやるのだ。
(同)注・カッコ内は筆者
この「コロニーの形成」こそが、物語のターニングポイントになります。コロニー内の子どもたちに超常現象が起こるようになり、外見がだんだん廃人のようになっていくのです。心が宇宙や精神世界とつながってしまった子どもたちは、内面が完璧に満たされているけれども、肉体的にはゾンビのような状態である、ということです。
この変化は、人類が物質である肉体を棄てて精神的な存在になる過程であることを示していて、子どもたちは、最終的には神のような存在(オーバーマインド)に召されることになります。精神的な存在となった人間がオーバーマインドと一体化するのです。それは同時に人類の終焉を意味します。このような展開が、良いことであるのか、そうではないのか……。その判断は読者に委ねられることになります。
この作品は、ニーチェが覆したはずの善悪の価値基準を、地球の終末期という舞台に物語を設定し直して、もう一度問い直す作品としても読むことが可能です。ニーチェは、キリスト教社会に蔓延するルサンチマンによる善悪の価値判断(天国に行くことを善として、地上的な強さを否定する)をひっくり返すために、地上的な強さをあえて力強く肯定(超人思想)しました。しかし地上的な豊かさなど、宇宙規模で考えれば吹けば飛ぶようなものであることにクラークは気づいており、それをもう一度問い直したのではないでしょうか。何が正義で、何が悪なのか? クラークは判断を下さず、ただ淡々と人類の終焉を描写します。そんな状況下にあって、サタンの顔をした宇宙人は、滅亡に向かう人類に惜別の念を抱いているようにも読めますし、もしかすると人類に愛情のようなものを抱いているようにも思えるのです。『幼年期の終り』に登場するサタンの顔を持つ宇宙人は、私たちが一般的に持つサタンのイメージを覆します。
(宇宙人のセリフ)「かつてその謎を解いたものはいない 。そして、いまはあなたにも、われわれ(宇宙人)が話さなかった理由がわかってもらえるだろう。じつは、そのような衝撃が人類に与えられたことは、ただ一回しかないのだ。そしてその出来事は、歴史の夜明けにではなく、まさしくその終末にあったのだ 」
「どういう意味です?」ジャン(天文学者)は訊ねた 。
(宇宙人のセリフ)「一世紀半前 、われわれの宇宙船が地球の領空に侵入したときが、われわれ両種族(宇宙人と人間)のはじめての出会いだった。もちろんわれわれのほうではそれ以前から地球人を観察してはいたが、実際の出会いはそのときがはじめてだったのだ。ところが地球人は、われわれがひそかに予想していたとおり、われわれの姿からあることを思い出し、われわれを恐れた。だがそれは厳密にいえば記憶ではなかったのだ。あなたは、時間というものが地球人の科学の類推よりはるかに複雑なものであるという証拠を、すでに充分もっている。つまり、その記憶とは、過去の記憶ではなく未来の記憶──地球人類がすべての終焉を知らされる、その最後の年月のそれだったのだ。われわれはできるだけのことはした、が、それは安易な終熄ではなかった 。そしてその終熄のときにいあわせたがために、われわれは地球人類の死と同一視されることになったのだ。そうだ、まだそれが一万年も先のことだった時代からだ!それはちょうど 、時という閉ざされた輪の内側を、未来から過去へと反響するひずんだ木霊のようなものだったのだ」
(同)注・カッコ内の補注、下線は筆者
これはつまり、未来(宇宙人と人類の滅亡)のヴィジョンを、古代の人類が第六感でキャッチし、サタン(宇宙人)のイメージを旧約聖書に取り入れていたというクラークのSF的想像力によるアイデアなのです。
重要なのは、このオカルトめいたアイデアに感心することではありません。サタンが象徴する悪とは何か、ということについて、私たちに揺さぶりをかけてくる作品がこの『幼年期の終り』という作品である、ということなのです。

音楽こそが人間の存在証明
ここで、「創世記」の楽園の中心に「善悪の知識の木」「生命の木」という2本の木があったことを思い出してください。これは『幼年期の終り』の二つのテーマ、①善悪の問題、②人間の死生の問題になっているのです。
まず、①善悪の問題について。
宇宙規模で考えるとすれば、絶対的な悪は存在しないのではないか、ということをクラークは伝えていると思います。サタンの顔を持つ宇宙人のリーダーカレルレンは時にとてつもない悪に見えます。が、物語の全体を見渡せば、人間の良き理解者という側面が見えてきます。それはどういう意味を持つのかといえば、善悪の判断自体を止揚せざるをえない場面を読者にイメージさせるということなのです。これまでの善悪の価値判断が通用しないような特殊な舞台を想定させることで、読者の持つ善悪の価値基準を破壊してしまう。この物語は、読者にそのような作用をもたらします。
次に、②人間の死生の問題について。
人間の死、人間に死をもたらす病が存在するのはなぜか? 人間はなぜそれに苦しまなくてはならないのか? それに対し、むしろ死への不安や苦しみこそが人間の人間たるゆえんであって、それは芸術の源泉だということを、クラークは伝えたかったのではないでしょうか。本作には、不老不死である宇宙人が音楽を持っていないという興味深いエピソードも描かれています。それに対して、人間の存在意義は、音楽を創造することにある……このエピソードは、当連載第9回で取り上げた哲学者ベルクソンの音楽論に通じるものです。
音楽それ自体が完璧な存在としてある不思議――人間の不完全さは、むしろ音楽を生み出すための前段としてあるようにも思えます。クラークは音楽こそが人間の存在証明だということを、『幼年期の終り』の中で、もう一度示唆しています。極めて印象的なシーンとして、地上最後の人間となった天文学者が、ピアノでバッハを演奏して残りの日々を過ごすというくだりがあるのです。
1977年にNASAによって打ち上げられた2機の無人惑星探査機ボイジャー号には、アナログレコードが搭載されました。そのレコードには、天文学者カール・セーガンが選曲したさまざまな音楽が収録されています。いつか宇宙人に発見されて、彼らの耳に届くかもしれないという期待を背負ってボイジャー号とレコードは宇宙を放浪しているのです。
NASAの公式サイトには、そのレコードの収録曲が公開されていて、バッハのブランデンブルク協奏曲第2番、モーツァルトのオペラ《魔笛》の「夜の女王」のアリア、ベートーヴェンの交響曲第5番といった名曲中の名曲が並びます。収録曲を聴きながら原稿を書いていると、宇宙人がバッハを聴きながら首を傾げている姿が目に浮かんで、愉快な気持ちになります。人間が創造した音楽を聴いた宇宙人は、きっと高い評価を下すことでしょう。音楽、文学を含めすべての芸術は、「人間が死すべき存在であること」「死の不安」から生まれます。それを受け止め、美の力で克服すること、それが文学的偉業を成し遂げるパワーになるのです。詩人ジョン・キーツはこのような力のことを「ネガティブ・ケイパビリティ」と定義しています。
『幼年期の終り』のサタンの顔をした奇妙な宇宙人は、人間に与えられた死と病という運命、そして、そこから生まれる芸術の意味を再考するための有効なモチーフなのだと思います。ヨブが病に苦しみながら発した「人間とは何か」という問いに、クラークは一つの答を出したのです。
ヨブが発した言葉は、実存的文学の“さきがけ“だといえます。いつか人類滅亡の危機に瀕した時――それは案外近いかもしれせんし、ものすごく遠い未来のことかもしれません――人々はまた「ヨブ記」の問いに戻るはずです。文学はヨブから出てヨブへ帰るのです。
<アーサー・C・クラーク(1917〜2008)、イギリス出身のSF作家>

著者プロフィール
内藤理恵子
1979年愛知県生まれ。
南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。
南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。
現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。
日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。
