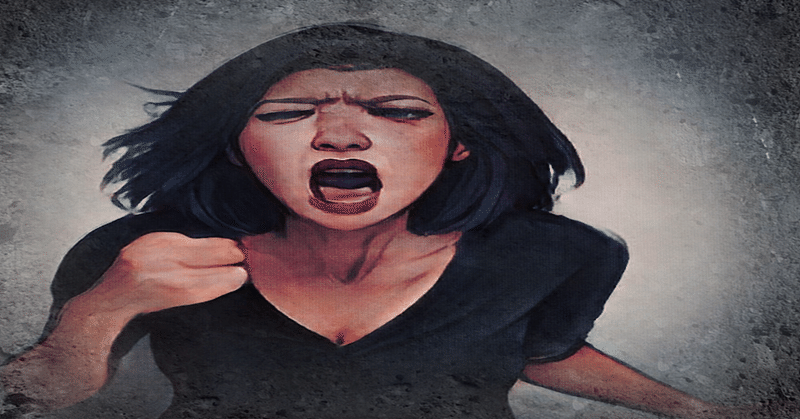
ルールだから守れよ!
どうする家康、リターンズ
私の記事を今年の始めから読んでくださっている方からすると、またかという記事の始まりです。あらかじめご了承ください笑
大河ドラマ「どうする家康」です。天下人秀吉が亡くなったあとの政治運営をどうするかというところです。社会の授業を思い出していただければと思いますが、そのとき五奉行という5人の実行部隊と五大老というご意見番的な存在がいました。
五奉行筆頭の石田三成の名前は聞き覚えはあるかと思います。そうです。天下分け目の関ヶ原で家康と戦った人として覚えさせられたはずです笑。
前回の放送では、五奉行筆頭の石田三成が秀吉時代のルールを重んじ義を貫き通すがあまり、周りからの反感を買い失脚していく様子が描かれました。
石田三成が何度も繰り返すセリフ「私は何も間違ったことをしておりません」がその象徴ともいえます。確かに私が見ても、石田三成は変なことは言っていません。ただ白黒はっきりさせすぎだなとも思いました。
石田三成の義を貫く態度が行き過ぎることを心配した、前田利家が放ったセリフに私は心打たれます。
「道理で政(まつりごと)はできぬ」
道理とは、物事の筋。今風に言えば、ルールとかマナーでしょう。政とは政治のこと。ざっくり言うと、集団を動かすこと。つまり、ルールで集団は動かせぬということです。さあ、私の記事分野である、教育の言葉のおでましです。
学校現場
石田三成は自分を取り立ててくれた秀吉へ恩義を感じ、秀吉に尽くしました。人への感謝を忘れない。一生懸命働く。周りが認める頭の良さ。人に流されず、違うものは違うと言える心の強さもあります。
小学校の道徳で教える内容をすべて吸収したかのような存在ですね。非常に優秀です。実際、秀吉に認められ五奉行まで上り詰めています。
でもですね、これは部下として優秀という話なのです。秀吉という圧倒的な後ろ盾がある中で力を発揮するのです。
私は11年間の小学校担任の経験があります。担任をしていると、クラスに2、3人ですが、石田三成のような子に出会います。学級委員タイプと言いますか、真面目な子と言いますか。みなさんも一人や二人ほど思い浮かぶのではないでしょうか。仮に石田君と呼ぶことにします。
一見すると、すごくしっかりしてそうに見えます。先生側からすると非常によく見える。なんせクラスのルールを守り、一生懸命勉強し、悪いことをしている人に躊躇なく注意をするんですから。まるでその姿は教師の分身かのごとしです。先生からの評判もいいもんだから、親も満足する。そこが落とし穴でもあるのです。
石田君は先生・世間のルールやマナーが正義で、それに反するものは悪と判断してしまいます。白か黒かしかなく、グレーがないのです。
小学生なんて悪さやいたずらの一つや二つはするじゃないですか。良い悪いの話ではなく、やるかどうかの話です。授業中だけど隣の子としゃべったり、廊下を走ったり、宿題をやらなかったり。そんなとき、先生は叱りますよね。その姿を石田君は見ています。
石田君も許せないわけです。学校のルール、クラスのルールを破ることは悪だからです。だから先生と同じように、平気で強い口調で注意をします。注意ってなんか上下関係みたいなものを想像させるのか、同級生に注意されるとむかつくものです。
でも、注意された相手は、強い口調だけど正論だけに反論できません。それに先生という後ろ盾があるので、露骨に嫌な態度を出すことはできません。しぶしぶ注意に従います。
とわいえ何度もされると我慢も限界に近づきます。反論はできないので、「うるせー」という言葉になり、石田君と距離を置くこととなります。特に先生が教室にいないときの注意は意味をなさなくなります。
その結果、石田君は友達が少ないか、クラスの中だけの友達づきあいとなることが考えられます(もちろん絶対ではないですよ)。石田君としては間違ったことをしていないと思っているけど、人の心は離れていきます。
そして、実は先生も同じです。道理だけで通そうとする先生に子どもはついていきません。学校のルールだからとか、先生だからとかでマウントを取り子どもを叱る人がいますが、そんな注意を子どもは聞いちゃいません。
そう。人は正論だけではダメなのです。
家庭
さあ、クライマックスです。私の記事のメイン、小学生の子育てです。幼児のうち(小学校1年くらいまで)は、親の言うことは聞こうという気持ちが強いです。だから早い話、強めに言えば子どもは言うことを聞くでしょう。
ただ、中学年になってくると、ギャングエイジという言葉もあるように、友達同士の結びつきを重視するようになります。また、自分という存在を認識でき始めるので自我が強くなり始めます。つまり、自分の意見が出てきて、それを認めれくれる人とつながりたくなる時期ということです。そう、正しいことを言ってくる人ではないのです。
「勉強しなさい」「宿題しなさい」「早く寝なさい」「ゲームをやめなさい」といった言葉を多く言うようになるのもこの頃ではないでしょうか。なぜ多く言うようになるかというと・・・当然、子どもが素直にやらなくなるからですよね。
「勉強はした方がいい」「睡眠はした方がよい」「ゲームをやりすぎるとよくない」ということは子どももすり込まれて知っています。つまり、言われることが正論であることは知っているのです。
その一方で、興味ないことは勉強したくない。宿題も同じ。寝るよりも起きてしたいことがある。ゲームをもっと進めたい。そんな気持ちがあるのです。だから、正論が分かっているけどできないのです。
そんな時、親はどうするか。
宿題は家に帰ってきてからすぐにやる。9時には寝る。ゲームは1日1時間。そういったルールを決めて子どもに習慣を身に付けさせようとします。が、冒頭のセリフ。「道理で政はできぬ」です。細かく言うと、道理だけではダメなのです。
じゃあ、道理だけではダメならどうすればよいのか。ヒントは家康に頂けばいいのです。信長には、宴会を用意し、信長をもてなしました。秀吉には、秀吉が平和な世の中をすると信じ、配下になり協力しました。諸国大名とは、酒を酌み交わし話を聞きました。
つまりは、相手をねぎらったり、信じて協力したり、話を聞いたりする。こうして人の心は開いていくのです。心を開いた人の言葉は多少なりとも、届くようになります。これは大人でも子どもでも同じだと思います。
子どもをねぎらい、子どもを信じ、子どもに協力し、子どもの話を聞く。その上で、道理を通す。
どうしても立場でマウントをとりにいきがちですが、あくまでも人と人との関わりなのだということを忘れないようにしたいものです。
最後までお読みいただきありがとうございました。何かの参考になれば幸いです。素敵な一日をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
