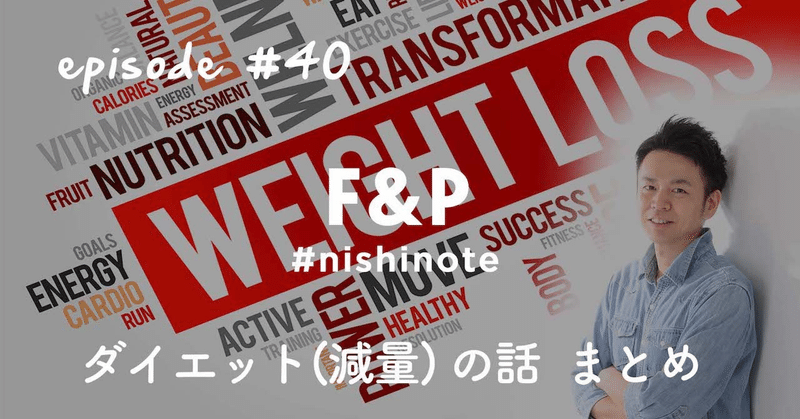
ダイエット(減量) の話 まとめ
今日は「食選び」、特に「ダイエット中の食べ物の選びかた」についてレポートしてみたいと思います。
自分に適した食べ物を自分で選ぶことができる能力を僕は「食選力」と言っていますが、「人は食べるものでできている」という欧米の言い回しの通り、食選力を高めることはまさに食意識を上げ、日々を健康的に暮らす素養を高めることに直結すると考えます。
ここで書くのは、あくまで僕自身が「減量」というテーマに絞って、減量期間中に食べるものを選ぶときにどういうところを見ているか、ということのサンプル紹介であって、「これが正解」ということではありません。
大事なのは、1つの参考にしてもらった上でそれぞれが「自分ルール」を作って「自分で選べるようになる」ということだと思います。
[著者 (西野) の人物サンプル]
・健康維持・向上のためのフィットネス習慣
・格闘技の大会出場を目的とした減量経験 (カロリー栄養学ベース)
・分子栄養学を勉強中
・アメリカのオーガニックスーパーとかを巡るのが好き
(かなり健康オタク寄りですね・・)

※以下、便宜上「ダイエット≒減量」というニュアンスで綴ることにします。
ダイエットをはじめる前に
「増量」と「減量」をコントロールする
フィットネスやボディメイキングをする人にとって、筋肉を増やしながら体脂肪を落とすことはできないので、増量期と減量期をきちんと意識して分けた方がいいとされています。 これは、ざっくり言うと
・筋肉は「摂取カロリー > 消費カロリー」という「オーバーカロリー状態」になっていると成長する
・体脂肪は「摂取カロリー < 消費カロリー」の「アンダーカロリー状態」になっていると燃焼する
という「体のルール」があるからです。からだは食べるものでできているので、このルールに従って科学的に変化します。よく言われるペースとしては、2ヶ月増量期、1ヶ月減量期を交互に繰り返していくようなイメージです。
(とは言っても正直なかなか難しいんですよね。。)
減量を開始して最初の3週間は、なかなか変化が出ません。
「頑張っても結果が出ない」、という一番精神的に辛い時期があります。
でもそこを超えると、急に変化が見えるようになります。ここまででたいてい1ヶ月強かかっています。
ちなみに、減量から増量に切り替えるときもなかなか辛い心境です。
努力の食事制限のもとに減量モードで生活していて一定の成果が出ているときに、急に今日から増量に切り替えて食べ始める、というのはやはり勇気がいるのです。「せっかく苦労して落としたのに、、また増やすの・・」
「失敗して太ってしまったらどうしよう・・・」
そんな感じです。やれやれ。
ダイエットは不健康?
さて、最初にお断りなんですが、、、
今減量中の僕は、ダイエット自体は不健康な行為だと思っています。
やっぱり、もりもり食べている状態がちゃんと栄養もしっかり摂れて精神的にも満たされ、一番健康的ですよね。
ダイエットとは、体づくりのために一時的に栄養やメンタルを犠牲にしているような状態だと考えています。
実際、僕も試合前の減量では風邪をひきやすい状態になりました。なので、だらだらやってもしかたありません。
予め決めた短期間でしっかりと結果を出して、あとはさっさと「しっかり食べる君」に切り替えられるように集中してやるのが吉じゃないでしょうか!
ダイエットは必ず成功できる
基礎となる考え方さえ押さえておけば、減量は確実に成功できます。
なぜなら、からだは食べるものでできているからです。
楽して儲かる方法がないのと同じで、
食事を正しく理解せずに健康になる道も痩せる道もありません。
「楽して儲かる」「飲むだけで痩せる」といった商材に踊らされて手を出してしまう人がいますが、正しく情報を取ってよく考えれば、そんなことあるはずがないことは判断がつきます。
からだは、身体の法則に従って科学的に変化します。
これはカロリー栄養学の考え方を使って説明ができます。
ここでは、カロリー栄養学に基づいてダイエットの設計をしていきます。
(※個人差があります)
目標を設定する
たとえば、「半年で6kg 痩せたい」という目標があったとします。
この場合、1ヶ月あたりに落とす体重は 1kg となります。
次に、体脂肪 1kg を燃やすのに 何kcal必要か?を計算します。
脂質 1g をカロリーに換算すると = 9kcal
1kg の目標 ですから 1000g の脂質を落とす。
脂質から水分を除去すると約80%になります。
9 kcal × 1000 g × 80% = 7200 kcal
7200 kcal ÷ 30日 = 240 kcal / 日
つまり、1日あたりの摂取カロリーが、消費カロリーに対して
240kcal 下回れば、この目標を達成できることになります。
自分の消費カロリーを知る
1日あたり消費カロリー = 基礎代謝量 + 活動代謝量
基礎代謝とは、「生命活動を維持するために自動的に行われている活動における必要最低限のエネルギー」のことです。
基礎代謝量は机上計算で想定値を出すことができますが、最近の体重計は乗るだけで基礎代謝量を教えてくれます。
最近はスマートウォッチの登場で、基礎代謝量も活動代謝量もさらに便利に計ってもらえるようになりました。
残念ながら年齢を追うごとに基礎代謝量は下がっていきます。
1日あたりの基礎代謝量
20代 24kcal / kg
30代 23kcal / kg
40代 22kcal / kg
[20代で体重50kgの人の場合の 1日あたりの基礎代謝量]
24 x 50 kg = 1200 kcal / 日
よく歩いたり運動したりする人であれば、基礎代謝に対して半分くらいは活動で消費できています。
[1日の消費カロリー]
1200kcal + 600 kcal = 1800 kcal / 日
1日あたり摂取カロリー目標を計算する
ここまでくれば、引き算で出せますね。
消費カロリー > 摂取カロリー ですから、
消費 - 減量目標 = 摂取目標
1800 kcal - 240 kcal = 1560 kcal / 日
摂取カロリーをPFCバランスに割り振る
1日あたりの摂取カロリー目標を 三大栄養素(PFC) に割り振って、それぞれの摂取量の目標値を設定していきます。
P = たんぱく質 (1g=4kcal)
F = 脂質 (1g = 9kcal)
C = 炭水化物 (1g = 4kcal)
理想のPFCバランスを仮設定します。
P (たんぱく質): 30%
F (脂質): 20%
C (炭水化物): 50%
割り戻して計算すると以下のようになります。
P (たんぱく質): 1560 × 30% ÷ 4kcal = 117g
F (脂質): 1560 × 20% ÷ 9kcal = 35g
C (炭水化物): 1560 × 50% ÷ 4kcal = 195g
これで、「1日に何をどれくらい食べていいのか?」の基準ができました!
[CASE 1] コンビニフードの選び方 : プロテインバーの功罪
さあ、それでは早速コンビニに行って、食品を選んでみます。
まず、気になる「プロテインバー」を評価してみたいと思います。

・見ての通り、高タンパク20g をウリにしている商品ですが、たんぱく質20g摂るために脂質が14.5g。 プロテインバーをおやつとして考えるとすると、間食に脂質14を摂ってしまうのは効率が悪い印象です。
たんぱく質20gはだいたいプロテイン1杯分なので、確かに甘いものを食べたくはありますが、それならプロテインをドリンク飲んだ方がいいかな、という感想。
たんぱく質20gなら、おおよそ糖質は5〜10g、脂質は5g以下には収まっていてほしいところですね。
・あと、合成甘味料としてスクラロースを使っているのも気が引けます。海外ではオーガニックなプロテインスナックが増えていますが、日本のコンビニで売っているプロテインおやつはこういうところでまだまだだと思います。
・右側の表中、ビタミン B群がいっぱい摂れるように見せていますが、これらは自然由来ではなく化学的なものを足しているだけなのであまりうれしくはないです。
・酵素処理ルチンはよくわからなかったのですが、調べてみたらメーカーさん側は力を入れているみたいです。あまり悪い噂は見つかりませんでした。
以上から、これは減量中には食べない。という判断になります。
ダイエットの心がまえ
ダイエットのメリット
ビッグボス新庄さんが言っていました。
「ダイエットは、精神的にも鍛えられる」
「体が重いよりもキレがあった方が打球は飛ぶし、選手がかっこいい方がファンは喜んでくれる」
また、とある腹筋女子は言いました。
「なんかちょっと嫌なことあっても「いいや、割れてるし」で片付く」つまるところ、自己肯定力が上がる。・・・これめっちゃメリットでかくないですか。
苦労して手にしたものは自信になります。そしてそれは、誰でも平等に手にできるチャンスがあります。
食べながら痩せる
僕は、初めての減量経験のとき、正しい知識を身に付けずにスタートしました。
トレーナーである師範から「西野さん、今度アマキックボクシングのトーナメント、申し込んでおきましたので、○月△日までに体重をXXkgにしてくださいね」と告げられます。
その後、「西野さん、減量生活の調子はどうですか?」とLINEで聞かれ、
「はい。しんどいですが頑張ってます。お腹が減ったらとにかく水を飲んで凌いでいます」と返したら、
「西野さん、減量の仕方を間違っています」と怒られました。
「西野さん。減量の基本的な考え方は「食べながら痩せる」です。食べ物についてもっと勉強してください」
筋肉を落とさずに体脂肪だけを落とす。
そのために、カロリー と PFC の関係を学び、増量と減量のメリハリをつけて食事管理をする。
僕の場合は、この10年前の体験が一生使える知識になっています。
最初に「食べてはダメなもの」を決める
減量に入るときに最初にやるのは、自分で「食べてはだめなものを決める」ということです。
基本的には、まず脂質をカットしていきます。揚げ物、チョコレート、パン、ピザ、マヨネーズを使ったもの。
あと僕はふだんからあまり食べませんが、チップス系菓子、ケーキ、ラーメンもしばらくおあずけですね。。
あ、僕のルールでは、お酒はOKにしてます! (ウイスキーなど蒸留酒のみ)
ケーキやラーメンを食べることと「減量する」ことは理屈上相反するので、基本的に食べたら減量にはなりません。
人と一緒の時など、どうしても食べなくてはいけない場面に直面した時は、少しでもさりげなく避けることも有効です。
マックに行ったらポテトをやめる、ステーキが出てきたら脂身を除ける、揚げ物の衣を外す、鶏肉の皮を外す ・・・などは数字的にもマインドキープの面でもだいぶ効果があります。
今までOKだったものが急に食べられなくなる、というのは、何回経験していてもなかなかマインドの切り替えがスムーズにいかないものです。
ですので、僕の場合はモードチェンジのための準備期間を置いています。
だいたい1週間くらいかかって、ようやく「あ、揚げ物だめなんだった!」というのを脊髄で判断できるようになります。
「OKなもの」を選んでいく
選定基準はやはり、「高たんぱく 低脂質」。
また、増量の時と違って糖質 (炭水化物) もしっかりコントロールしていきます。
これらの条件に当てはまるものは・・・鶏肉 (もも肉より胸肉、ささみがベスト)
野菜 (ブロッコリー 、ほうれん草、白菜、レタス)
海藻 (ひじき、もずく、わかめ)
豆 (豆腐、納豆、その他の豆)
魚 (さんま、いわし、かつお)
プロテイン入りスムージー
10年前の西野「夜に食べていいのはなんですか?」
師範「白菜とかブロッコリーがいいですね」
西野「押忍、・・・それって料理じゃなくて・・・食材・・・」
師範「西野さん。料理で言ったら、鍋! 鍋がおすすめです!」
[CASE 2] コンビニフードの選び方 : 最強のツナ缶とは
僕が試合前の減量をしていたときに、一番最初に心強い味方になってくれたのは「ツナ缶」でした。当時は、それしか食べられるものがなかったんです。
以来、コンビニでは「サラダチキン」が登場していろんな味バリも出たので、ダイエッターにとってなんといい時代になったことか(泣) と思います。
さて、ツナ缶も色々あるんですがわかりますか。
減量したい人が「減量にツナ缶は優秀だよ」と言われて、一番やっちゃいけないことを言います。それは「水煮」ではなく「オイル漬け」のタイプを選ぶことです。さっそく、「ラベルチェッカーを起動(※)」して、2つのツナ缶を比較してみましょう。
(※裏面の一括表示ラベルを見てPFCや原材料を分析する行動を、こう呼
ぶことにしています)

左: 油漬タイプ (140gあたり)
たんぱく質: 26.5 脂質: 26.9 炭水化物: 0.1
たんぱく質量が多いのはありがたいんですが、カットしたいはずの脂質もたっぷり入ってきてしまっていますよね。
脂質26.9摂ったら減量になりませんから、このツナ缶は食べられません。
右: 水煮タイプ (70gあたり)
たんぱく質: 12.5 脂質: 0.3 炭水化物: 0.2
優秀です!! これです。まさしく、たんぱく質だけを確実にコントロールしながら摂取できる理想の食品です。
あと、どうしてもオイル漬けしか家にないような時は、三角コーナーネットを使って油切りをしたりするのも実は有効です。
1日のうちの「時間帯別」で気をつけること
朝:しっかり食べて代謝を上げる
食事とは、それ自体が消化酵素を使ってエネルギーを消費する行為です。食べないと、痩せづらくなります。
パンは脂質が多いので、米中心に切り替えます。玄米などの精製していない米の方がベターです。
プロテイン入りスムージーをかけたグラノーラボウルは、忙しい朝に最適です。
夜は制限が多いので、たくさん食べられる朝は楽しいですね!
昼: コンビニフードをうまく利用
きちんと食選できる目を持っていれば、コンビニフードほど手軽で豊富で選びやすいことに気づきます。
会社の周りのランチは、中華屋さんとかとんかつ屋さんとか、食べられないものが多いです。その中で、寿司屋はたんぱく質が補給できてご飯にお酢がかかっているのでありがたいです。
夜: 食材ごとにしっかり見極め
炭水化物(糖質)はすぐにエネルギーに変わってくれますが、消費しきれなかった分は体脂肪に変わるので、食後の活動が少ない夜は摂らないようにします。
(体に摂り入れてから体脂肪に変わるまでの時間は諸説あり)
食べないものは、白米、パスタ、うどん、果物、芋・とうもろこし。
夜は1日のうちで最もコントロールしなければいけないので、料理ではなく食材ベースで考える癖をつけた方がいいかもしれません。
脂質は悪なのか?
さて、まるでヴィランズのように扱われている脂質ですが、れっきとした三大栄養素の1つです。
大事なエネルギー源であり、内蔵を護ったりビタミンを効率よく体に摂り入れるのをサポートしたりします。
(ストイックな減量期が続くと、明らかに肌が乾燥したり便が硬くなったり風邪を引きやすくなったりします)
ですが、糖質も脂質も現代人は摂取過多になりがちなので、意識してカットしてもよほど必要量は摂れています。
ドレッシングの選び方
例えば、サラダがヘルシーだと思って食べていると、気をつけるべくはドレッシングですね。ラベルチェッカーを起動してみてください。
大さじ15g または100g で脂質何g 熱量 何kcalか?
牛めしの松屋さんに行って生野菜サラダ頼むと、ドレッシングはフレンチと胡麻の2択ですが、テイクアウト用のポーション小袋を見てみてください。

[脂質量] フレンチ: 16.4g 胡麻: 5.1g
これで、松屋さんに行ったときは「胡麻1択」が確定ですね!
ちなみに僕のおすすめドレッシングは、イエローマスタード + バルサミコビネガー! ノンオイルよりもおいしくて、最強です。
ダイエットを持続するためのTIPS
周りの理解と協力を得る
ダイエットをしている人は、していない人から見ると「自分と違う食事」の方法や内容を実践している人が奇特に映ってしまうことがあります。ダイエットの中と外では、そもそも見え方が違います。
例えば親戚の家に集まったときや、同僚とのランチ、ビジネス上の会食の際などに、一人だけ食事の摂り方が違うことは後ろめたいことのように思うかもしれません。どうしても付き合い上の問題があるので、徹底することが難しくなってしまうこともあります。
ただ、特に普段食生活を共にする家族に対しては、この辺りの理解を求めることは減量を成功させる上でも避けて通れない大事なことのように思います。
減量するのに、自粛巣篭もりムードほど良い環境はないと思いました。 減量中のために人からの誘いを断らなきゃいけなかったり、人と違うものを食べなきゃいけなかったり、それらを説明するストレスが一切ありませんから。笑
食べ過ぎたら、前後の食事で調整する
どうしても食べることが避けられない場合は、前後の食事で調整します。
夜に会食があることがあらかじめわかっている場合は昼を軽めにしたり、食べ過ぎてしまった次の日は食事量を半分にするなどです。
体重を気にしすぎない方がいい
さて、僕の最近の減量には特徴があります。それは、「体重計には一切乗らない」ということです。なんのために体づくりに励むのか?
おそらくほとんどの場合は、「健康的で美しい身体を手に入れたい」的なことだと思うんですよね。決して数字をよくすることじゃないと思います。
(僕の場合は年甲斐のない挑戦をし続けたいとか、世間に発しているメッセージを自分で実践して正しいと証明したいとかですが)
僕が昔、格闘技の試合に出た時は、100%数字のために減量していました。
計量をパスしないと、試合に出られなくてサポートしてくれている皆さんに迷惑がかかるからです。
・数字は本来の目的ではない
・見た目と数字はリンクしない
・現れている数字だけでは正確に計れない
・ストレスの原因になる
などなどの理由から、数字を追って一喜一憂するのは無駄だなと思い、体重計に乗るのをやめました。なので、鏡と写真だけで進捗を管理しています。
(ただし、ゴール付近まで来るとゴールがわからなくなります笑)
「数字で測らなくては、成功か失敗かわからないじゃないか」という人もいますが、別にその人のために頑張るわけでもありません。 数字が気になる人はもう一度、「何のために減量するのか」を自身に問うてみるのが良いのではないかと思います。
[CASE 3] コンビニフードの選び方 : 乾きものの意外な活躍
減量の食事制限によって食べられなくなってしまうものは多いのですが、その中でも数値上優秀なカテゴリーに入るのが「乾きもの」です。
代表的なのが、あたりめ、鮭とば。
同じ乾きものだからといって、ドライサラミやビーフジャーキーを選んではダメです。くんさき・かわはぎは、脂質は少ないのですが糖質が多いので減量中は使い所に注意です。
(できる限りたんぱく質だけ高い方が何かとコントロールしやすいのでベター)

鮭とばのラベルをチェックします。
たんぱく質: 12.9 脂質: 1.1 炭水化物: 2.5
優秀ですね。気になる塩分も1.6に収まります。が、何袋も食べると塩分過多になってしまいます。
また、ラベルには出てきませんが、鮭から摂れる栄養素としてはビタミンDやビタミンB群があります。ここはうれしいところです。
さらにこの少ない脂質とは鮭のフィッシュオイルですから、つまりDHAやEPAなどのオメガ3系脂肪酸を摂れることが期待できます。
ソルビトール、pH調整剤、酸化防止剤
この辺は少し不安はありますが、やはりどうしても入ってきてしまいますね。
以上、まとめとしては「鮭とば」は減量中の食品として優秀。 体にうれしい栄養素も補える。
ただし、塩分・添加物が入っているので、食べ過ぎは禁物なのかなと。
「塩っけのあるおやつが好きな人のための代替品」として使うのが良さそうですかね。
自分ルールを決めて、楽しもう
・・・はい、結局これに尽きるのではないかと思います。
ここまではダイエットの話を中心に書きましたが、食選びの知識を磨くことは終わりがありませんし、減量に限ったことではありません。
食選力を磨くことは、自分自身の食スタイルを確立することにつながります。
そして、社会全体として個々が食スタイルを確立した文化を創っていくことは、僕たち F&Pジャパン が掲げるミッションでもあります。
長らく食べものの話が続きましたが、あくまで減量人サンプルとしての紹介です。
僕は国家資格を持っていないので栄養指導もできませんし、単に体験をつづるのみに過ぎません。
僕が伝えたいことは、たった1つのシンプルな考えです。
・・・「人は、食べたものでできている」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
