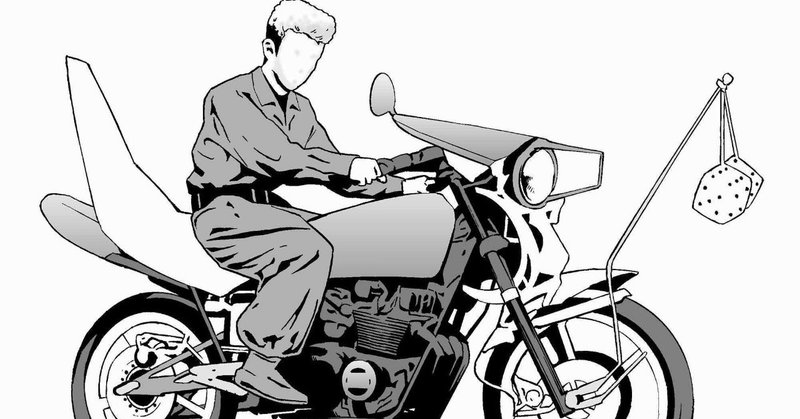
「みんなワルに憧れていた」熱風2012年11月号 特集「ヤンキー」
スタジオジブリは、毎月10日に「熱風」という無料の文芸誌を発行しています。今月の特集は「ヤンキー」。
先月の特集が「電子書籍」ですから、全く関連性がないように思えますが、この自由なテーマ設定がスタジオジブリの魅力のような気がします。(ちなみに「熱風」のサブタイトルは「スタジオジブリの好奇心」。ジブリの好奇心が社会のさまざまな点に着目しているのが、このサブタイトルからもわかります。)
ヤンキー特集のラインナップは、以下の通りです。
・私にとっての「ヤンキー」 (難波功士)
・本宮ひろ志 インタビュー :いまは強いリーダーがいなくて描きづらい時代
・ヤンキー女性はなぜモテるのか? (倉田真由美)
・ヴィジュアル系とはなにか--ポピュラー音楽とヤンキー文化 (市川哲史)
・斎藤環 インタビュー [聞き手]川上量生ヤンキーはファンタジーに生きていて、オタクのほうがリアリストなんです。
今、日本で「ヤンキー」について、ここまで真剣に語っている雑誌も珍しいですが、興味深い内容だったので、自分が感じたことをまとめてみました。
「オレは昔はワルかった」
この特集を読んで思い出したのは、糸井重里さんの「今日のダーリン」で語られていた、こんなお話です。
「『あらゆるお父さんは、昔、ワルだった』
と、なにかに書いた憶えがあります。
このことばが、中崎タツヤさんの
『じみへん』というマンガに出てきて、
妙にうれしかった思い出もあります。
ほんとうに、
ある程度の年齢の男たちは、
皆、口を揃えて、
『オレは昔はワルだった』と言います。
しっかりスーツ着込んで、
会社のバッジ付けている人が、
『ワルだったからなぁ、オレも』
と言います。
たまに、ほんとうの場合もありますが、
ほとんどウソです。
若いときには、
ワルに憧れたりするものですが、
そのときの気持ちを肯定したくて、
ウソを言っています。
お父さんが「オレは昔はワルだった」と言いたい理由は何か、丁寧に説明しているのが、今月号の「ヤンキー」特集です。
よく考えてみると、織田信長、坂本竜馬、白洲次郎、勝新太郎、田中角栄、矢沢永吉、EXILE、橋下徹など、大衆が憧れる人物は、どこか「ヤンキー」の香りがします。また、沢尻エリカの人気の秘密は、彼女の持つ「ヤンキー」純度の高さが要因なのではないかと考えると、どこか説明がつく気がします。
女性なら中森明菜、工藤静香、安室奈美恵、最近だとAKB48の板野友美といった人物も、「ヤンキー」の香りがします。お父さんが憧れる「ワル」というのは、日本人が共通して憧れている部分なのではないか?という点を、本書ではさまざまな視点から丁寧に説明しています。
個人的には、倉田真由美さんが、女性の「ヤンキー体質か否か」を見分ける方法として、「ネイル」に興味があるかどうか、と書いてあるのには、なるほど、と膝を打ちました。
今の世の中にはヤンキーが少ない
印象に残ったのは、本宮ひろ志さんのインタビューと市川哲史(過去にX JAPANやLUNA SEAなどビジュアル系ロックに関する書籍を多数執筆)さんの記事に共通して書かれていた言葉、「今の世の中にはヤンキーが少ない」です。
本宮ひろ志さんはインタビューでこのように語っています。
編集部
いまのヤンキーマンガって、昔にくらべてスケールが小さくなっているように思えますが。
本宮
日本人がみんなそうでしょ。成熟しちゃってるんだと思う。中国みたいに暴れるのってやっぱり未成熟だよね。
編集部
確かに、金太郎みたいなパワーはないですね。最近連載再開した「男樹」でも大きく立ち上がらないんですか。
本宮
難しいね、正直言って敵を作りづらい。今は政治の世界を見ても、何もまとまらず決められない。これって社会が女性化しているせいなのかなと思うね。
(中略)
「男樹」描いてて思いますよ。「描きづらい時代だ」って・・・・・・。こんな時代はヤンキーも自己満足するしかないね。
思い返すと、最近地元で暴走族を見る機会は減りましたし、コンビニの前でたむろする高校生を見る機会もほとんどなくなった気がします(そんな時間に家に帰ってないからかもしれませんが)。そう考えると、現代はヤンキーにとって、「住みにくい時代」なのかもしれません。
それが、幸福な時代なのかどうか、僕にはわかりません。しかし、この特集で書かれているように、「ヤンキー」パワーの減退が、社会全体のパワー不足の要因のひとつと言える気がします。実際、勝新太郎のような俳優も、矢沢永吉のようなシンガーも、新たに現れてはいません。
そういう意味では、斎藤環さんがインタビューの最後に語っていましたが、現代のヤンキーの象徴として橋下さんの今後には注目です。斎藤環さんがおっしゃるように、そこには「ヤンキー」の未来を考える上で、ヒントとなる要素がある気がするのです。
「オタクがつくって、ヤンキーが売る」会社。スタジオジブリ。
この特集の最後に川上量生さんがスタジオジブリのことを「オタクがつくって、ヤンキーが売る」会社。と定義したのは、面白いと思いました。
ここでいう「オタク」とは、もちろん宮崎駿さん、高畑勲さんのことで、「ヤンキー」というのは、ジブリのプロデューサーである鈴木敏夫さんのことだ、というわけです。確かに、鈴木敏夫さんは「ヤンキー」っぽい部分があるなぁ、と「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」を通勤中に毎日聴いている人間としては、妙に納得してしまいました。
※この記事は2012年11月にnishi19 breaking newsに公開した記事を再編集して掲載しています。
サポートと激励や感想メッセージありがとうございます! サポートで得た収入は、書籍の購入や他の人へのサポート、次回の旅の費用に使わせて頂きます!
