
一年を振り返る 後半編(7月から) at UC Berkeley(2022)
(誤字脱字スペルミスは触れないでください笑)
この記事は下記の記事の後編です。
もう数日でアメリカから出国するということでめちゃ忙しくしている感じの今日この頃ですが、振り返ってみると公私ともに学びや成長があった一年だったと思います。ということで日本に帰りますが、次のステージはもう始まりつつあるので、すでにワクワクしております。
僕はこの2022年は一年間UC Berkeleyという日本では知名度が低い、最強のパブリックユニバーシティに留学していました。それについてまとめたtipsは下記のものが少しまとめたものになるのでもし気になる人は読んでみてください。
7月
まずいもんくうのものむのも人生の無駄
だいぶ思想が強いですが、こんな言葉で七月は始まりました。
親孝行について
まず母親がアメリカに来たので一緒に旅行をしました。行ったのはYosemite National ParkというところでNorth Faceのロゴになっている場所があるところに行きました。というのも母親がとても登山が好きなのもあり、Yosemite旅行はとても楽しんでくれたと思います。

22歳にもなると、自分で働いて自立するのが目の前にきています。そうするとまとまった時間が取れないのは見えていました。ですので、こういった形で母のしたかったことを叶えてあげられたのはとても嬉しかったです。こうやって長い時間を過ごすことももうどのくらいあるのだろうと思うと自分の中で少し生き方が変わってきた気も最近します。家族というかけがえのない存在に対しての行動は家族のためだけでなく、自分にも大きな幸福をもたらすような気がしました。

不易流行そして、自己理解ついて
また半年アメリカにいたので、久しぶりに16personality を実施したところ、変化があったことに気づきました。
実は元々は下記のものだったのですが、上記のものに変わりました。
というか、ずっと起業家型にならないかな~っておもっているけど一生なりそうにない
現状は下の人をみることがおおいから主人公、
自分がもっと逆説的だけど、主人公になったら討論者にパーソナリティがかわりそう
ぼくがかんきょうで依存しているのがFJかTPかってところかな
とても面白い仮説だわ、
そうすると、自分がゆずれる部分がわかるし、譲れない部分がわかったということか
つまり、自分の中で環境で変わる部分と変わらない部分があると仮定するということですね。人との議論で変わらないコアの部分で対立した時に無駄な言い合いを避けるという意味ではいい気がしました。
自分の将来像に対してのロールモデルも下記のような考えを持っていました。
したいことは商鞅
出世の仕方はカエサル、
商鞅とは中国の秦の時代に活躍した歴史上の偉人で、法律制度などを整備して秦を強国にしたと言われています。またカエサルは誰もが知るローマの政治家です。なぜこの2人を引き合いに出しているのかというと、僕がしたいことが周りやこれまでの蓄積を生かしながら、システムを構築していきたいという自分の生き方を表現できる2人であるからと考えているからです。そのためにもそれを肝に銘じつつ活動をしているつもりです。
また大学の先輩起業家の方がベイエリアに来る予定があったのでお会いすることが出来ました。とても刺激的な話をさせていただく中で、自分に対してこのような理解が出来ました。
僕は必要に迫られているから思考するわけではなく、むしろ観察による疑問ベースだから多分タイプがちがうんだな~っておもた
(先輩)さんは実験の途中に疑問を見つけていくタイプ(実践の中で鍛えるタイプ)
僕はもっと座学のイメージで疑問を見つけるタイプ、だったっていうちがいかな
そんな自分への理解が進むとともに、自分のキャリアについてもこのように考えていました。
正直就職したくないので、アカデミックで人の金で海外に出るのが1番つよいきがしあ
にほんでしたくないのではなくて、僕は外に出るべき人間なきがする、
日本にいる意味がよわい
単純に僕の性格や思考が日本にマッチしていないのではないかという疑問ベースの話でした。日本を無自覚・無思考で批判したいようなことではないのでご理解ください。なんなら日本は好きです。
メンタルについて
前半でも涙を流してしまったという話がある(6月”Co-founder 永田くんと自分自身への解像度について”を参照)ように、自分の中で心が少し弱くなった気がしていました。そんな中で見つけたこんなツイート。
人生には意識して気をつけるべきことがいくつかありますが、忘れられているけれども重要なことに「鬱」があります。鬱病になり社会復帰をすることももちろんできますが、心は以前のようにはおそらくなりません。むしろ以前に戻れると思ってしまうこと自体が復帰を阻むと私は考えています。
— Dai Tamesue 爲末大 (@daijapan) July 20, 2022
心は戻らない、すごくわかる
実は致命的に、、、精神とは不可逆なものであり、その永続性に頼ることは、砂上の城に期待をすることと同じで、、、しかし僕らはーまるで成長を一生するということと同じでー自分を無条件に信じてしまうのです
心の守り方はシンプルで、自分を観察することに尽きると思います。なぜ今、自分は皮肉を言ったのか。なぜ今、笑ったときに少し顔が引き攣ったのか。なぜ今日は歩くスピードが遅いのか。なぜ、今足を組み替えたのか。全ては心の表れです。そこから自らの心を推測することが可能です。
— Dai Tamesue 爲末大 (@daijapan) July 21, 2022
自分を理解し続ける、これは無意識にやっていたので自分の圧倒的な崩壊を防げているのかも知れないです。
民主主義と政治
民主主義への挑戦か、
何かの衝動へと動かないといいけど
まさに激動の時代を象徴するかのように、日本の元内閣総理大臣である安倍晋三氏が銃撃され、死亡しました。
このことは日本では宗教の問題に発展するなど様々な余波を生みました。それ以上に暴力によって死をもたらすことで主張を通そうとすることに関しては反対の意を示すとともに、安倍氏の死には哀悼の意を表します。
またここで議論をしたいのは政治的な主張に対する激化への不安です。やはり民主主義を標榜する国として私たちは議論によって、口によって一つにまとまるべきです。ですから暴力による変更は避けるべきです、少なくともまだ機能不全とまでいうことのできないこの国においては。このことは11月の"政治・権利の主張について"で少し掘り下げていきます。
チャレンジしたさきに面白さがあるよなぁ
結局自分を理解してチャレンジし続ける。僕は変わらず前に進むことを選んでいるのでした。
8月
僕頑張っていない?
こんなだるいことをしてしまう時があるのですが、Co-founderである永田くんが下記のように答えてくれました。
頑張ってる、おつ
いい人ですね。
永田くんのTwitter
女性のキャリアと日本の関係性とアメリカで働くについて
8月は前半に中高の同級生が来ていて、一緒にベイエリアを探検したり色々な人に会っていたりました(僕はどちらかというと金魚のフンでしたが。)その一環でPlug and Play というインキュベーションをおこなっている会社のオフィスへ行来ました。そのほかにもVCとしてこちらで働いている人と話す機会も多くありました。個人的に感じたのは、アメリカで働くということの女性へのリターンはめちゃでかいということです。同級生が女性ということもあり、女性の方に話を聞くことが多かったのですが、日本でのリターンの文化的な問題はいまだに根深いようです。僕も3年以内にはアメリカに戻る予定ですが、できるだけ日本を変えるための努力をしたいと思いました。さらに思ったこととしてアメリカにいる人は自分の性格や考えにマッチしている人が多いと感じました。例えばアカデミアとして来るのが一つの手でありそうだと考えています。ただ少しの葛藤をしつつ。
アメリカでも頑張りたい!でも日本では一番を取りたい!
っていう葛藤



世界になにで戦う?
日本人としてまずbloombergに取り上げられているのがすごいなと思った動画。そんなことを見ていたら下記のツイートが流れてきました。
起業家として色々なプロダクト立ち上げをやってきた人間として、起業相談をされた時に最もよくするアドバイスは「リリースするのが遅すぎる」です。多くの起業家はしっかりプロダクトを作り込んでからリリースしたがりますが、これは完全に間違い。なぜか?スレッドで解説していきます👇
— Shin丨PM Schoolリリース準備中 (@shin_sasaki19) August 9, 2022
これを見てから僕はこんな決意をしました。
DeSciを作ろう作ろう作ろう
来週はなんかプロダクトの概案を出そう
DeSciの分野で何かしようと思っていましたが、前述のとおり実行までに落とし込んでいる訳ではありませんでした。なのでこれをきっかけにしてアイディアとしては下記のような形を考えました。
エンジェル投資家の研究投資gitcoin
仮想通貨型の研究と、それを支援するような仮想通貨長者をつなげるやつ
審査員を研究者にして、投資家を仮想通貨の人たちにする
まずはイベントベースでやる
ただし下記のツイートも頭に叩き込んでいました。
僕はまさにこれ。独立時代は3年くらい受託してた。それからUSを経て前の会社(ウノウ)を株式会社化。個人的にはすごくよかったと思ってます。
— 山田 進太郎 / Mercari, Inc. CEO (@suadd) August 13, 2022
けれども今はいろいろなエコシステムもあって、すっ飛ばす人も多いし、それでうまくいってるひとも多いような気もしますね https://t.co/npXuRUiLfP
こうして始まったのがMitsubachi DAO(Founding)プロジェクトです。このプロジェクトは最初は”クリプトで大成された人たちのお金を研究に流れ込むように作ることで研究システムを支える新たなDAOを作る”という形で始めました。前半でも述べているDeSciの一環となっています。
現在は”市井の人々が研究を支援できるようなスキームを提供するようなfoundingシステム”を提供するための最初の実験として研究コンテストの実施をすることで最終的に落ち着きました。日程は2023年の3月18日、渋谷駅近くの100banchで実施予定です!
続報が入り次第お伝えをする予定なので、ぜひ下記のTwitterをフォローしてください!
今後は日本で実証実験をしつつ、3年以内に国際大会として研究を支援できるスキームと大会を完成させる予定です。もし興味や一緒にやってみたいという方はご連絡をください。
そんな感じでアイディアを固めつつあった時、一度お話をさせていただいていたLabBaseの加茂さんがビルゲイツと会っていた。マジで加茂さんに勝ちたいと思ったし、ビルゲイツと会えるのが見えていると思うと嬉しかったです。絶対にイーロンかジャックにあってやる。
政治体制について
参院選が報じられる中で、私の中で少し疑念というか少し気になる点があり、友人とSlackでディスカッションをしていました。
根本
「民主主義って、悪くないだけで
別に良くもないんだよな〜」
友人
「この世の中完璧なものなんてないんです
独裁も悪い人が上に立つから悪いだけで良い人が立てば別に悪くはないんです。ただ絶対いつかは悪い人が立つのでやめてほしいですけど」
根本
「そうね、基本的に独裁にならないように政治は設計されがち。でもそのシステムも完璧ではないから大体独裁して〜〜民主化〜〜みたいな循環している。これは元々古代ローマ人が言っていた発想だけど、的を得ているような気もします。
最新の研究は知らん。」
〜〜中略〜〜
友人
「火星に全員移住させてみんな重力とかで馬鹿じゃなくなる奇跡に賭けますかぁー
」
根本
「でも、馬鹿なのが人間らしさで、それが美しさとも思うよね。むずい。火星に行くのは知性だけど、火星を楽しむのは馬鹿な心な気がする。」
参考資料
人を理解することについて
「親が子を思う気持ちも、子の努力を考えても涙出そう。」こんな発言をSlackにしました。
佑樹さんが小さかったころ、範子さんはダウン症のダンサーのステージを見て心を動かされた。「希望だ」と感じ、佑樹さんをダンススクールに何年も通わせたが、あのダンサーのような腕前にはなれなかった。 範子さんは「ダウン症だからこそ、何か特別に秀でたものがあったらいいなと思い、幼少期はいろいろな習い事をさせた。だけど、飛び抜けて『できる』ものは見つからなかった」と振り返る。でも、そんな息子が今、周囲の高校生と分け隔てなくアルバイトをしている。障害者の就労を考える上で意味があると感じている。
やはり前半で考えていた”人間の生きる意味”という命題には自分の中で解がうまく出来ていない気がした。だからこそ、人を理解するための一環としてMitsubachiの運営しているミツバチコミュニティの中でメンバーを理解するためのネットラジオを始めた。
参考例
まずは人の話を聞く。僕には足りていなかった部分を補完するような努力を続けた結果、ミツバチコミュニティ自体の理解も深まりましたし、自分の人への傾聴力も勝手に深められたのかも知れません。
9月
異常気象と共に去りぬ
バークレー暑すぎて集中ができない
僕にとっての二学期目が始まったのですが、いきなり日本並みの暑さにさらされました。
Yowza. It’s almost 8 pm in Berkeley and there’s a 30 deg F temperature gradient from the bay to the top of the hill. The high pressure of the heat dome is compressing the marine layer to the lowest elevations. #heatwave pic.twitter.com/cQw1PexoWa
— Josh Apte (@joshapte) September 6, 2022
アメリカあるあるなのか知らないですが冷房機能がうちの寮や大学の建物にはないことが多くて、爆暑い中で殺されるかと思いました。ただこちらのアメリカでも異常気象を感じることが増えているのではないかと思いました。やはりアメリカ人の消費特性とかってどう見ても世界をぶっ壊している気がするので、これらの異常気象をモロに感じる機会が増えて、彼らが日本人のような消費特性になったら気候もいくぶんか良くなる気もしますが、そこらへんは定量的なデータがあるわけではなく、あくまでも私感です。
今日ははじめてのラボミーティング、緊張します、そのあとしかも飯っていう、、。
今学期からこっちの教授について研究の手伝いをするようなURAPという枠組みを参加していたためそれの最初のMTGでめちゃ緊張しました。。。僕は基本的には初めての人とか基本無理タイプなので本当にナーバスでしたが、意外と難なく乗り越えることが出来ました。この場を借りてメンバー(日本語読める人ほぼいないけど)やSteven先生には感謝を申し上げます。URAPについては下記の記事を参考にしてください。
愛するということ①
この頃は自分の家族について考える時間が増えました。そんな中流れてきたのがこのツイート。
トーマツ時代にお世話になった大先輩が当時時短契約で働いていた。その理由を聞いた時に「ずっと不妊でやっと授かれた娘だから今後は娘を中心に生きることにしたから昇進とかどうでもよくて時間が1番大切なんだよね。」と。当時20代の自分は正直、理解できなくて、逃げのための理由なのかな、と(続)
— HAT | 会計士だった気がするけど未上場ベンチャー沼に生息10年、陸に上がるぞ (@HatKaz1983) September 10, 2022
感じてしまい、正直、その先輩に対してキャリア面においては憧れ、尊敬の対象からは外れた。
— HAT | 会計士だった気がするけど未上場ベンチャー沼に生息10年、陸に上がるぞ (@HatKaz1983) September 10, 2022
いま子ども2人授かって、あの時の自分の未熟さを痛感していて、とにかく子ども中心に時間を確保したい自分がいるw
子どもだけではないけど、経験しないと見えない視野、というものが確実にあるな、と。
人生を誰と過ごしたいのか、誰と時間を使いたいのか、
か
結婚式してみたくなった
自分はこの一年間も自分がやっているプロジェクトを、事業をどうしようかと考えることが多々ありましたが、自分自身の私生活についてはほとんど気にしてきませんでした。自分が結婚や子供が生まれるようなステップをー考えていない訳ではないですがー一つの直近や短期的な戦略として見ていなかったのは、振り返ってみると個人的には意外でした。僕自身は子どもと犬がすきなので、その二つがあるような家庭を築きたいと自然と思っていたからです。ただ、よくよく考えてみるとそれ以上の解像度はほとんどないことに気づいたのです。だからこそ、この1ヶ月はそれについて個人的なビジネス的な理想年表と比較しながら、検討を始めました。子どもは養子や特別養子縁組など自分の血のつながっていない子でも全く構わないと思いました。理由は否定する理由がないからです。また結婚(形は問わない)は30代までにしておきたいなって思いました。理由は自分のパワーポジションが一番良いのがパートナーがいるときだと仮定しているからです。それに互いに支え合うような存在がいる時が一番僕は楽しいので。もうちょっと色々とありますが、考えたということだけお伝えします。基本的にはパートナーとでっかい犬が一緒にいてくれる人生を考えています。
満足の中の変化について
気づいた、僕らって自然と成長しよう、上に行こうより、より良くしようって思っている気がする。(ここからはちょっと胡散臭いけど)戦後の成長と復興からなっていた経済圏から、僕らみたいに(日本やアメリカなど)生活に不自由ないけどこの世の中はより良い状態があると実感できる(戦争や不平等など)に対しての自然的な使命感を持っている気がする、、、自由人としての最終形態な気がする
僕の好きな藤井風(あえて敬称略させていただきます、Fujii Kazeってめちゃ聴き心地よくないですか?)がまた新曲を作ったみたいだったのですが、それを聞いた時に感じた感想が上記でした。自分達が生まれてきた世界は満足のある世界であるからこそ見方を変えなければならないということです。これは僕が大学一年生で擦るほど見た馬田さんの資料にありますね。
シリコンバレーの強さと世界の狭さ
たまたま友人からの紹介でスタートアップワールドカップなるものに参加しました。コンペティションに参加している企業はまさに世界中から集まったシリーズBくらいまでの企業でみんなめちゃ面白いことをしている。その前座から僕は見ていたのですが、前座にはGithubのCEOがきたりと日本には会えない人がばんばかきました。「べイエリアマジでチャンスと刺激が多い。」これをマジで実感しました。実際に何を一緒にできるか以上にどれだけ刺激を得て頑張れるのかってすごく大切だと思っているので、ベイエリアに来ない手はないなって確信しました。さらに一緒に行ったインドネシアの親友がベイエリアインターン3ヶ月で200万くらいもらえるっていう話を聞いて、やっぱり僕ら来るしかないんじゃないのっていう直感レベルの何かを感じました。

また、本ちゃんのコンペティションは日本人チームが英語が渋くて、正直これでは日本ダメだなって思っていました。ちょっとこれでグローバルで戦うとか言っている人が多数なら僕らの船は本当に泥舟じゃんって。ただ、その後Berkeleyの卒業生のOishiiのCEO Kogaさんを見た時にちょっと安心しました。僕は彼みたいに本当のグローバルをガチガチに取りに行きたい。
そんな中で一番びっくりしたのはいとこにあったこと、マジで世界が狭すぎる。小学校の時の同級生に実はこれで2人会っていて、あれ僕の生まれた街って5万人しかいないめちゃちっちゃい街なんだけどなって思ったりして。本当にこの世の中は小さい、だからこそ世界に対して恐れを持つのは本当に無意味だと思う。思ったより世界は僕らを超えてこない。
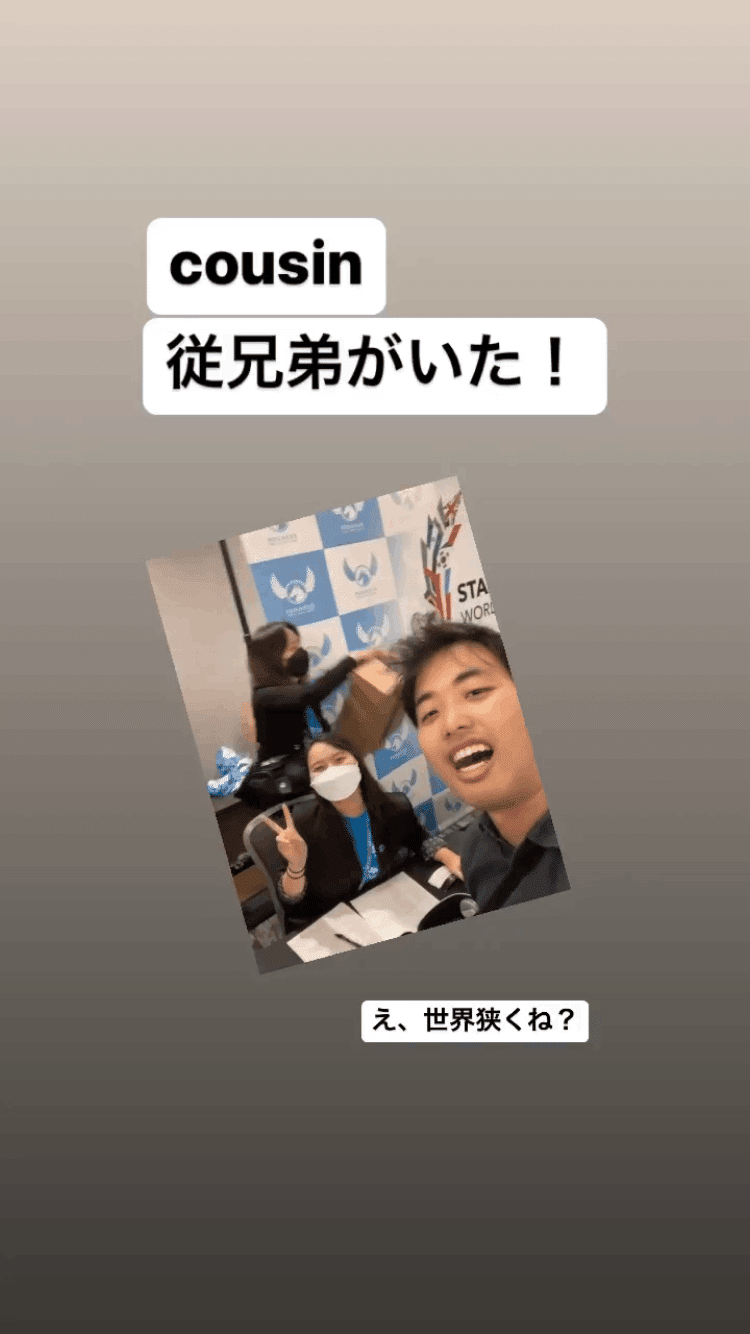
この頃読んだもの・気になったもの
確かに最近成田くんの顔テレビとかでたまに見るから、一瞬テレビが院生部屋かと錯覚する
— J.YAMASAKI (@J_YAMASAKI) September 20, 2022
We've trained a neural net called Whisper that approaches human-level robustness and accuracy on English speech recognition. It performs well even on diverse accents and technical language. Whisper is open source for all to use. https://t.co/ueVywYPEkK
— OpenAI (@OpenAI) September 21, 2022
10月
そら跳ねるわな〜 いい発表
そんなteenの若々しい発表で始まった10月です。残り2ヶ月をどう過ごすのかそんなことが耳に入りつつ、一番考えていたのは人間関係かもしれないです。
環境とそのシステム、そして比較と自信について
政治やねぇ
というか社会的に良いと思って作ったルールが逆に絶対視されちゃっている良い例よな
だから、フレキシブルなルール変更基準が必要よな
もちろん僕はどんなシステムにも欠陥があると思います。ただ、おそらく最初の始まりはどんなものも往々にして誰かのためになるためにシステムが作られています。それが年月を経ると、だんだんとその意味を失い、形骸化したルールのみが残ってしまいます。それはどんなシステムにもあることですが、この話も一つの最たる例とも見えます。
またアメリカのベンチャー系のキャリアフェアに参加した際に、バークレーのシード系のVCのポートフォリオを見る機会がありました。普通にY -com採択企業とかがあるんだぁ〜って思いました。でもそれは自分でもいけるなっていう確信に変わった時でもあります。バークレー生は優秀ですが、事業内容やそのシードの資料に多いな差があるように思ったことは一切ないですし、おそらく事業云々よりアメリカ社会のコネクションにどれだけアクセスしてそれ以上に進むのかが問題だと感じました。勝つためにはある程度の戦略も必要ですが、それ以上に変な確信と自信が得られるきっかけも大切な気がします。そしてそれが得られるのは良いシステムのある適切な環境に身を置くことだと思っています。ただ個人的な意見として、"confidence and accuracy are negatively correlated"な気もします。
僕は行動が足りていない
上記の論をさらに深めるために下記の投稿を添付します。
あなたは生きている。
あなたには時間がある。
あなたは行動を起こせる。
大丈夫。時は必ず訪れます。
最後にアメリカの詩人の言葉をご紹介します。
(寒さに震えた者ほど 太陽の暖かさを感じる
人生の悩みをくぐった者ほど 生命の尊さを知る
これから私は幸福を求めない 私自身が幸福だ)
自分は彼のようなうつの症状はないものの、やはり悩みを抱えることがあります。それが解決するきっかけは、彼の言葉を借りれば、時間と行動ときっかけです。僕にはまだ20代として時間があります、行動をするためのエネルギーがあります、そしてその先にはきっときっかけがあるはずです。僕は鬱ほどではないものの、僕は人生という迷路に入っていることは確かです。彼の力強くしなやかな言葉は僕に一種の爽快感と一種の前向きな指標を与えてくれた気がします。どんなに辛くても、それは考えすぎている僕のちょっとした気の迷いなのかもしれないです。幸せになるために、僕は少しでも多くの時間で行動し、きっかけを掴む必要があるみたいです。
自分がそんなふうに変な自信をつけていた時に下記の記事とともにこんな感想をいだきました。
これは僕はもうきにしてないなー
結局こころのおもむくままにいきればこうかいないもんねー
まぁもちろん悩むけど、でもひとと比べてないとはおもう、昔より
正直、僕はこの記事を読んだ時、これはどんなことを始める時にでも言えることだと思いました。前半の記事でも書いていましたが、最短経路とはただの歴史であり、自分がどう生きるべきかのコンパスであって、道を示しているわけではないと思います。だからこそ、この記事は比較の中で生まれた自分への思いの問題だと思います。それの思いは僕も大学一年生にありましたが、今では結局心の赴くままに生きる以上の何かでないという考えに至っています。
11月
世界から見た日本・自分について
Asian not asian っていうPodcastよく聞くんだけど、日本人って“日本人を主人公にせずに、違う世界の人間と思わしき生物をヒーローにするみたい“って言ってて確かに、アメリカのヒーローってみんな実在世界の人やな〜って思った
前半のものでも述べたのですが、Asian, not Asian というPodcastがあってそれが好きなのですが、その中で日本のヒーローって違う世界(Universe)での話が多くない?みたいな話がありました。そういう日本を世界から見る視点って面白いですよね。
自分の日本からのFBをもらうたびに自分のアメリカでの頑張りに失望してしまう
詳しくいうと、自分は日本語では最強の気分になってしまう、、、英語だと普通の第二言語くらい話せてそれを専門性や僕の知識や経験が補っている感じ
自分の専門性がなさすぎるからだろうか、それってよくないな経済の専門家になりたい
確かになぁ、日本語できるのすごいけど仕事ができんとあれやもんなぁ
日本で英語が強みだった人は英語圏に住んでネイティブに囲まれた途端それが弱みになってしまうことが多い。
— Masa 🇬🇧 (@MS08170) November 9, 2022
今働いてる英国系の会社も社員の9割がネイティブなので自分の言葉のレベルはまだ遠く及ばないと日々感じる。けど彼らのレベルまで高めればもう上ないぞと自分に言いきかせ明日も頑張ります。
2月の"母国語とその意味について"でも話しましたが、マルチリンガルでない限り母国語と第二言語などには必ず差分が生じてしまいます。そして僕のように母国語が得意であればあるほど、おそらくその落胆は厳しいものとなるものでしょう。それを補う・克服するためには専門性を磨くしかない気がします。経済学は僕の好きなことですし、磨き上げたいことです。僕はこの経済学を武器にすることについてキャリアの面からもこのきっかけに絶対に学ぶと心に決めたのです。
ただビジネスも必ず伸ばしたいと考えていました。その際に
must-do
SkyDeck
Y-com
登竜門
東大の院
こいつらを二十代で全クリする
常にグローバルをみて最高の社会を想像する
そして創造する
メラメラしてきました
でもなんか成長や経験したなって思えるのはSky DeckもY -comも言っても見えてるってことだと思う
バークレーに行って変わったことはいい意味でも悪い意味でもチャレンジしようと思えるようになることです。しかも周りはみんな上記のアクセラに出していて、受かっているし、むしろ自分がやらないのはなんでなのかと思うくらいです。確かにすぐには無理かも知れないです、ただ挑戦というのは”歓喜”を引き起こします。
ニブイ人間だけが「しあわせ」なんだ。ぼくは幸福という言葉は大嫌いだ。ぼくはその代りに〝歓喜〟という言葉を使う。 危険なこと、辛いこと、つまり死と対面し対決するとき、人間は燃えあがる。それは生きがいであり、そのときわきおこるのがしあわせでなくて〝歓喜〟なんだ。
「しあわせ」というのは”点”でしか無い。極論ではあるが、我々が「しあわせ」なとき、地球の何処かでは誰かが飢餓に苦しんでいる。その事実に気づいたとき、簡単には「しあわせ」という言葉を使いたくなくなるだろう。
そんな現状を知りながら、己の使命を見出し、それに燃える瞬間沸き起こる感情を「歓喜」という。「歓喜」は生まれた環境、置かれた環境に関係なく、誰でも持つことができる。使命をみつけ、命を賭そう。
僕は常に歓喜の中にいたいです。だからこそ日本からだと考えもしなかった選択肢をバークレーに行ったことで見えるようになると、それが歓喜へのチケットへの変わっているのです。歓喜は0%の可能性にはありません。1%の狂気によって成り立っている気がします。そしてその歓喜をもとに僕は社畜精神を片手に突き進むのです。
コラボメーカーで養ったどこでも働ける精神(名付けて社畜精神、もしくは古谷マインド)によって私はメキシコにいようと、私生活が死んでいようと幸せに生きていける!努力・友情・勝利!
自分って本当にゲームも映画もドラマも見ないから、お笑いが好きなんだなって思う
ただ一番頭を常に使っているのは事業で、事業のことはマジで毎日考えているし、そういえば学部一年生の時に言われた、起業家とは常に自分の事業を考えている人だって言ってたことを思い出して、納得した、
覚悟やろなぁ
Yamottyさんの記事を読んだ後、こんなコメントを残していました。
僕たちが次のGoogleを作っているかもしれないからな
ボストン、MIT・ハーバードについて
UC Berkeleyが常に上位ということで、やっぱりこの大学に来てよかったと思いつつ、学生のアイディアがすごいというよりかはこのエコシステムが最強なんだろうなっていう確信を持っています。またそれ以外の上位校として同じベイエリアのStanfordもありますが、東海岸にはMITとハーバードがあります。実はこの月はボスキャリというキャリアフォーラムに参加するために訪れました。
てかハーバードで迷ってたら普通に話しかけた人がMBAの人だった
世界、、、
(ボストンの二校の)学生はレベルが違かった
ボスキャリ自体は、僕にとっては楽しいものでした。社会人の方の方が自分が悩んでいることに対しての答えを持っていることが多い上に、やはりその分野に通じている方が多いので含蓄のあるエピソードを展開してもらえるので知的好奇心をくすぐられました。その意味で、もし学生起業をしたいという変な覚悟を持った人でも、ぜひ就活はちょっとだけしてみてもいいかもしれません。さらにボスキャリは短期的なので時間を長くかける必要もないためさらにおすすめです。また普通の学生にとっても選考が簡略化されているため、内定を取りに行くっていのもめちゃありな気がします。
また僕自身は出店と言う観点から見てみると一区画(おそらく10m四方の正方形くらい?)がおそらく数百万で借りられているため、そこへの出店費用+出張費用や諸々を考えると1500万位の予算感(担当者全員5人ほど区画は一区画想定)でやっているのかなって思いました。そうすると結局5人くらい採用できたとして、一人頭300万で、相場が100万くらいだと考えるとちょっと割高だが、英語ができると言うことでペイするのかなって言った感じ。ベンチャーは何社かあったが、留学している学生はどちらかというとミーハーや現金な学生が多い印象でネームバリューが先行しているイメージ。そうすると実際にネームバリューのないベンチャーがそこで出店する意味がどこまであるかと言うような感想でした。ただ実際出店をしてみたいなって思ったので(学生は優秀な子が多いとは思うので)、もうちょっと思考した上で実施できるならしたいと思いました。
詳しいビジネスや就職に関するものは下記でまとめたのでご覧ください。
Mitsubachi PJとDAOについて
Mitsubachi PJは度々言葉として出てきましたが、ここで少し説明しようと思います。Mitsubachi PJとは「研究が好きな人誰もが、研究者を目指せる世界を。」をビジョンに掲げている事業全体のプロジェクトの総称です。私はその中の一環として「研究者コミュニティミツバチ」と「Mitsubachi DAO(Founding) PJ」をおこなっています。
ミツバチコミュニティにはこんな仮説を持っています。
写真と年月、、これを積み重ねると強いコミュニティになる一個の形になる
正直コミュニティは有象無象に存在していて、その中で自分達が生き残る方法はただただ続けることなのではないかと思っています。それは僕が住んでいたUC BerkeleyのI-Houseという場所から得た発想でした。I-Houseは約100年前からある国際学生寮です。この歴史を感じたり、そのシステムを見ていると、生き残りそして場所を提供し続けるということがコミュニティとして偉大なことなのだと確信しました。場所がいい、飯がうまい、テストが難しい、そんな側ではなく人は歴史や時間の流れに対して一番心が動くのではないかと。そのためにもコミュニティは何よりも続けることを大切にしていきたいと思います。
Mitsubachi DAO(Founding) PJは何よりも世界に対してMitsubachiが何をできるのかということを目線に立てているプロジェクトです。私たちは研究社会全体の変革に向けて活動をしています。その中でボーダーレスな研究社会を日本だけ解決していい顔するのは全くもって意味がないことだと考えてます。だからこそ最初から世界的に展開ができるDeSci PJとして出発しています。私たちのビジョンは、研究者を社会で応援して、支援するようなリサーチャーエコノミーを作り出すことです。Youtubeで投げ銭をする感覚で社会がクリエーターであるリサーチャーを支援する、そんな社会を作り出すための事業です。ぜひ興味のある方、賛同してくださる方は私にご連絡をください!
最後にうちの大学の先輩でグローバルに頑張っている小林さんがこんな感じでめちゃやっていて失礼ながらイライラしているので、彼を越えられるように頑張ります!世界、変えます。
Seraphim Spaceのアクセラレーターに選ばれました!
— 小林稜平@ElevationSpace CEO (@k_ryohei58) November 11, 2022
グローバル展開本格化させます。
ちなみに来週からアメリカです! https://t.co/JWJ2i5HlpF
愛するということ②
僕の大好きなYamottyさんのこの記事を読みました。エーリッヒフロムの”愛するということ”という本に関しての文章。僕のこの章題もこの文章の訳からきています。この文章を読むまで愛ついて深く考えたことなんてなくて、基本的にはギブアンドテイクじゃね?みたいな感じのことを考えていた気がします。ただこの文章を読んだ後、愛とは何かって考えたときに下記の点から自分なりの結論と自分の改善点を見つけました。
愛とは、愛する者の生命と成長を積極的に気にかけることである。この積極的な配慮のないところに愛はない。
愛するということは、なんの保証もないのに行動を起こすことであり、こちらが愛せばきっと相手の心にも愛が生まれるだろうにという希望に、全面的に自分をゆだねることである。愛とは信念の行為であり、わずかな信念しかもっていない人は、わずかしか愛することができない。
「愛する」というのは、この態度を実践する「技術」であり、誰もが簡単に浸る「感情」ではない。
愛とは無条件に相手の成長と生命を積極的に気にかけることで、それは信念によって全面的に委ねる行為である、と。これまでの短い人生の中で、何人かと付き合ったりした中で、いつも自分は同じような形で振られていた。それに関して僕はいつも不審を抱いていたから生まれた行動が原因な気がする。相手をどこかで不審に思うということ。それは自分の幼少期が影響を受けているとは思うが、変わらなければいけないところとして確信した。相手に自分を無条件に委ねること、そこが僕に足りない”技術”なんだろう。
ただ訳書はartを技術と訳しているみたいだけどちょっとしっくりこない感じがしました。僕的にはなんだかもっと個性が含まれている気がする(the art of practice and theories って書いてあったりしたので)ので個人的には愛するという表現という方があっていそうな気がします。
もし愛するということが点であるとしたらそれに付け加えて話すべきことが長く付き合うという技術です。つまり二者を引きつけ合う引力を愛の実践とするならば、おそらく付き合うというのはベクトルを合わせる行為を指す気がします。Yamottyさんはこの付き合うことについて、このように記載していました。
長期的なパートナーシップを念頭に置く
相手や自分や環境の変化、許容をゆっくりと待つことができる
曖昧さも許容する
自分は自分が正しいことを強要する癖がありました。このために喧嘩をした数は数知れません。ただ、自分が正しいことより、それを許容していく自分の姿勢が足りてないのかも知れないです。信頼と許容。僕に足りてない二つの言葉が分かった気がします。
結局自分がダメなのに、いつも人のせいとか環境のせいにしてる、いい仲間とか人に囲まれてるのに、活かせてる気がしない
まず周りを信頼して、許容しよう。そうしたら自ずと感謝ができるはず。
雑談的に、
どうでもいけど自由恋愛によって移動の数があがったっていう指摘おもろい
YamottyさんのPodcastで言ってたけどどれか忘れちゃいました。
参考資料
政治・権利の主張について
政治に向けてそういうロビイングしていきたいな
若者* 研究者 *政治で政治家と繋がりたいなちょっとそこらへんをしたいな
今年のアメリカの中間選挙では今まで以上に政治家がコンテンツクリエイターにならないといけないのが明らかになっている。
— Tetsuro Miyatake (@tmiyatake1) November 9, 2022
18歳になって投票できるようになった800万人の若者層を取り入れるためにFacebookの広告予算を削減してBeRealやTikTokにかなり投資している。pic.twitter.com/BSd0dn9MSa
政治とは何か物事を疑問に思ったり変革させたいときに行き着く終着点の名前だと思っている。民主主義においては、多数決などの方式をとって選挙や決議が行われている。多くの場合はそれらの投票には誰かの意見を反映されていることが多い。
ストライキだねぇ、来週から
普通にワシントンポストに載ってたわ
https://www.washingtonpost.com/business/2022/11/14/university-california-strike-academic-workers-union/
11月の中旬より院生らがTAに関する給与に関して不満をもちUC(系列校全てにおいて)全体の大規模なストライキへと入った。結局僕の最後の学期中は決着がつかず、来学期へと持ち越しになる可能性があるようだ。うちの教授の話によると予算の配分などを考えると結構根深く複雑な問題らしく、解決はだいぶ時間がかかりそうとの話だ。

なんか、権利の主張って大切よな
最近お勉強や事業と称して自分の時間を作って向き合っている(ボッチとかいうな!)からか、めちゃ心に動きがある、、、やはり政治な気がする
いわゆるシルバー政治と言われて久しい日本政治に関して日本なのかでも若者が色々と活動することが増えているが、日本での闘い方を考えたときにプロテストなどが本質的な解決に大きく貢献しているということは弱いと思う。ただもちろんそいう活動が意味がないかというと嘘で、ただ近年の国会を囲んだプロテストが法案の決定を覆したことは少ない。であるからこそ僕はまず最初に政治的な若者のつながりを作りたいと思っています。事業領域や仕事を超えて、この日本という国を良くするための議論をもっとしませんか?っていうのが僕の提案です。そして最終的にはきちんと政治に働きかけられるような組織にしていきたいと考えています。もし協力してくださるということであれば是非ご連絡をください。
いつも変わらない言葉として、何が起こっても自分に刻んでいる言葉があります。
大義のためにいき、大義のために死ぬ
12月
普通に感動したんだけど
カタールワールドカップのスペイン戦は自分の中で、日本人であることを強く意識させたとともに同時に自分も彼らのように人を感動させ、動かしたいという思いがありました。振り返ってみるとオリンピックの歩夢くん、野球の大谷選手、そしてワールドカップの日本代表。いつだって人を動かすのは、世界を舞台に活躍している人々で、彼らのようになるためにもやはり僕も世界を舞台にした事業をしたいと確信しました。そんな12月の初め。
自分の良さについて
多分、普段がいつも変な感じだからギャップがあるかもしれないけど、比較的に言葉を力にできるタイプなんだと思う
スピーチとか、変に狙おうとするときはそれは面白さ重視しちゃうけど、それを狙わないと本当に気持ちを全力でぶつける文章が書けるってことが気づいた
この前自分が書いた文章で友達が泣いてた、なんかそんなことがあったからこそ、自信が生まれてきた
自分ができることってなんだろうって常々考えているのですが、最近確信を持っていえることが三つだけあります。組織への理解、人の理解、そして言葉の表現力です。最後の三つ目はまだ発展途中ですが、他の人よりかは優れているような気がしてきました。この文章で、誰かに興味を持ってもらって世界を一緒によくできる仲間が集まると嬉しいです。それが今回の文章の一個の趣旨でもあります。
最近思ったけど自分がUC Berkeleyで作った関係性や自信って本当に強い、自分が引っ張ればまじで世界取れる自信がある
アメリカに留学して自分が少しマシになった点として挙げられるのは、理由のない自信です。UC Berkeleyってほんとに周りの人がみんな優秀なので自分がちっぽけに見えるのですが、実は外の世界に出ると自分が鍛えられていることに気づきます。だからこそ、でたら「俺どこでもやっていけんじゃね」っていう変な自信と共にいろんなチャレンジができます。実はそんなこと言いながらも十個くらい今年に入っていろんなものに落ちているのですが、それも自分の中の起業家マインドである「5万回の失敗も一回の成功によって癒える」が全てすっ飛ばしたので結局今も頑張れています。それまで持っていた謎の起業家マインドがバークレーに来て加速したのが僕のいいとことしてあるのかもっていう話です。
最近思ったけど、アメリカ来てから笑顔が上手くなったかも、写真で
これは最近言われて思ったことですが、確かに僕はアメリカに来てから笑うことが増えました。特に写真を撮るときに笑うことが増えました。それが最終的に笑うことへの上手さにつながった気がします。笑うことが上手くなると自然とみんなが助けてくれることが増えた気がします。とりあえず辛かったら、わかんなかったら笑う、そうすると周りの人はなんだか楽しくなって助けてくれるみたいです。とりあえず明日も笑って過ごします。
事業について
もっと深い課題をみよう、現状の課題ってなんだか、そりゃ金がいっぱいあった方が幸せだろって問題ではないか?
それって本質的ではないのがわかる、、、、もっと本質的な問いとは何か
たぶん自分が考えている解像度は、低いのではなくて、包括的ではない、もっと深い課題にフォーカスすべき、そこは何か、もっと執着したい
僕らが変えようとしている事業は科学という人間の営みに立脚をしています。だからこそ科学の営みは、もっと多様でさらに世界中が行なっている生産の集合体の概念であるべきだという強い僕の考えがあります。それはつまり浅い理解ではお金があれば世の中うまくいくけど、多様で平べったい科学という中にある本質的な課題をもっと見つめていきたいと考えました。その時コミュニティの中で考えたのが次のような考えでした。
commynityをMUst to haveに持ち上げるのは、研究という孤独な行為への単なる恐怖への救済ということな気がしてきた
研究とは最後は孤独な知的生産の営みです。私たちはその孤独に少しでも寄り添い支援するのが一番抽象度を上げた状態であるのではないかと僕の中では合点がいきました。僕らは孤独に対してのソリューションを提案する、ということです。
利益は追求したい、なぜなら夢の追求には金がいる、ただ、利益変調にはなりたくない、といことです。
ただそんな世の中を抽象度高く見ても、金がなければ全てが始まりません、ただお金だけをしていることは美しさがありません。僕のそんな直観は下記の記事で少しバックアップされました。
本当に世界を変えたいと思っているなら、自然と周りが支援してくれる、そんなことがわかった気がする
世界は僕たちが思っている以上に狭くて、そして世界は思っている以上に僕らに優しいです。それはただしそうしたいと思わせる人間である必要はあります。僕は少しずつですが、そういうふうになっていっているような気がします。僕たちの中での価値観や言葉によっていろんな人が賛同してくださっていることがあるからです。
そして科学というアウトプットに対しての全面的な支援と新しい社会への最強の状態を作り出す
僕の作り出したリサーチャーエコノミーってめちゃいい言葉な気がしてきた
新しい社会を創造する、そのために僕はリサーチャーエコノミーを作り出し、研究を新たなステージに引き上げていきます。
During that time, Musk was also going through a very public divorce. Altogether, Musk says, “I was just getting pistol-whipped.” A lot of that seems to be related to his ex-wife “torturing” him in the press, but the near-failures of Musk’s two biggest ventures clearly made the situation much worse. “You have these huge doubts that your life is not working, your car is not working, you’re going through a divorce, and all of those things,” he says. “I felt like a pile of shit. I didn’t think we would overcome it. I thought things were probably fucking doomed.”
僕は人間関係など色々なことで悩む時期もありましたが、イーロンも悩んでいた(大きさは全く異なるが)時期があったということで自分も乗り越えられた気がします。というのも、イーロン自身が、その時乗り越えることができると思っていなかったと言っているのが、とても救いでした。うまくいくかわかっていなくてもやり切る、生き残ることの大切さを教えてくれました。
あと、ミツバチholdingsで超越テックを全部持っているおもしろカンパニーを持ちたいな
わしも負けてられない、僕はトヨタ作るよ、次の
別にシリアルになるつもりだから、これで終わりとかはないけど、とりまやるならでっかく、宇宙までも世界をよくしたい
次のトヨタを作るときに本当にこのような研究開発支援というサービス領域でいいのかという疑問を持たれる方もいるかもしれないです。ただ、僕はこの領域でやることを決めましたし、これをやり切る気持ちです。ただその派生はいくらでもできると思っていて、そこからTeslaとかSpeceXみたいなおもしろ超絶テックを作り出すことができると確信しています。何よりも僕は科学を支えて、次の新しい社会を作りたいんです。
覚悟って直ぐにはつかないけど段々と生まれてくるもんだよね、
大学一年生の時は自分が会社を立てるなんて学生の楽しみくらいかなって思ったけど、今は人生かけてするつもりやし、なんならそれで死んでもそれでいいかなって思てる
最後は僕の覚悟を表したもので、今年を締めくくりたいと思います。来年はこの事業で起業を行い、本格的にコミットするのでぜひ応援やご支援をお願いいたします。
後半の終わりにかえて
ということで、僕のうっすい人生の2022年の後半が終わりました。本当は例年通り一つの記事に終わらせる予定だったのですが、ちょっと多くなりました。最後までお読みいただき本当にありがとうございます。結局3万字くらいある長文になってしまいました。ここまでやったのも僕のよくスラックで言っていることで表現することができます。
辛い後には必ず良いことや満足なことが起きる、全力で生きることしか意味がない
全力で生きてれば後悔は残らない、勉強も事業も恋愛も友人関係も
僕は全力で生きる
全体の最後として
そんなことでうっすい人生の一年が終わりました。薄いので書き切れました。最後に関わってくださった全ての人に感謝したいです。ありがとうございます。感謝したいので名前をあげたいのですが、順番が生まれてしまいそうなので、根本にお力を貸してくださった方に感謝していることを書き記します。永田くんと前川さんはお疲れ様です。来年もよろしくお願いします。
今年の目標は「自分を強強にすることです。いい意味で他人に頼らない。」でした。確かに、弱い自分もわかってもしかしたらある意味で強くなれたのかもしれないです。ただ基本的にはもっと強くなれる気もします。あと他人は頼っていいです。なので目標としてあまり良くないかもしれないですね。達成度は40%くらいでしょうか。
来年の目標は「有言実行・日本をハックする」です。アメリカ帰りの”かぶれ”として日本社会に起業・事業経営という形でコミットして、数字を出すこととと関わる人が幸せになるように頑張りたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
お願い
もしMitsubachiPJについて気になった方はご連絡をください!お待ちしています。URLは下記になります。
もし僕に興味を持ったや応援をしたいという際にはぜひTwitterのフォローやNoteの好き、いいねよろしくお願いします。励みになります。そしてご連絡はいつでもください。一緒に次の社会を作りましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
根本
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
