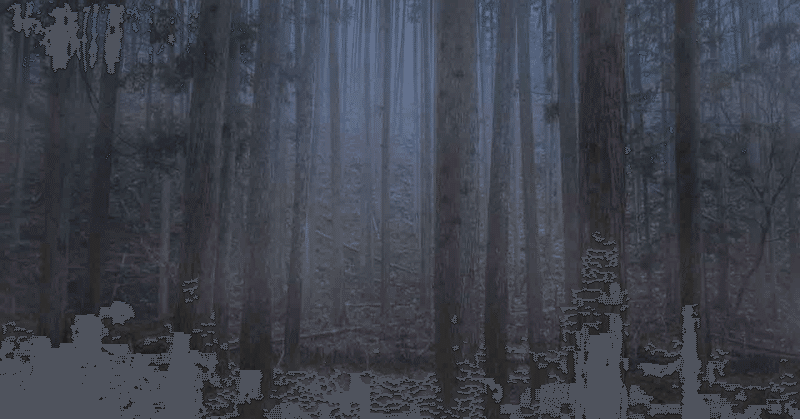
【読んだ】夜と霧
おすすめ度 ★★★★☆
落合陽一さんの「忘れる読書」で紹介されていて、読んでみた。
実体験に基づき、ナチスでの収容所生活を描いた超ロングセラー。
世界史に疎いのと、重くて難しそうだったので手を出せずにいたが、結論、読んでよかった。
意外にも読みやすい。初版は昭和に翻訳されたものなので骨太で難解だったらしいが、新版は2002年。文体も新しく、柔らかい。
収容初期
収容されてすぐに、収容者は全ての価値を奪われる。
全裸にされ、全ての携帯品を取り上げられ、全身の毛を剃られ、名前も肩書もなくし番号で呼ばれる。
「みっともない裸の身体の他には失うものはなにもない」
数週間もすると、被収容者は感情も失っていく。
はじめのうち他の収容者が何度も殴り倒されているのを見て、耐えられず目をそらす。
しかしすぐに、何も感じずに眺めていられるようになる。
十二歳の少年が、裸足で雪の中に何時間も立たされ、凍傷になった足指をピンセットで付け根から抜かれる…
こんな痛々しい出来事が次々に起こる。
嫌悪も恐怖も同情も憤りも、見つめる被収容者からは一切感じられなかった。苦しむ人間、病人、瀕死の人間、死者。これらは全て数週間を収容所で生きたものには見慣れた光景になってしまい、心が麻痺してしまったのだ。
死んだほうがマシ と思う安直さ
こんなに苦しい思いをしてでも、生きていたいものだろうか、と最初思ってしまった。
でも私がこんな疑問を持つのは、それだけ「自分の死」が遠く現実離れしているからなんだろう。
本当の死が想像できないから「死んだほうがマシ」なんて安直に思ってしまうのかも知れない。
加害も被害も単純ではない
どうしてこんな酷いことができるんだろう、とも感じる。
相手を人間として扱ったらこんな事できない、酷い人たちだと。
でも、その一面的な考えにも著者は疑問を投げる。
とある収容所長は人間らしいふるまいや善意を収容者に見せた。所長は解放後、アメリカ軍に引き渡されるとき、唯一収容者がかばった存在だったそうだ。
人間らしい善意はだれにでもあり、全体として断罪される可能性の高い集団にも、善意の人はいる。境界線は集団を超えて引かれるのだ。したがって、一方は天使で、いっぽうは悪魔だった、という単純化は慎むべきだ。事実はそうではなかった。
この逸話をフランクルが入れた理由について、新版の翻訳者である池田香代子さんがあとがきで推測している。
あいにくなことに、十七ヵ国語に訳された「夜と霧」はアンネ・フランクの「アンネの日記」とならんで、作者たちの思いとは別に独り歩きし、世界の人々に対してイスラエル建国神話をイデオロギーないし心情の面から支えていた、という事情をフランクルは複雑な思いで見ていたのではないだろうか。
(中略)
受難の民は度を越して攻撃的になることがあるという。それを地で行くのが、21世紀初頭のイスラエルであるような気がしてならない。フランクルの世代が断ち切ろうとして果たせなかった悪の連鎖に終わりをもたらす叡智が、今、わたしたちに求められている。
2002年に書かれたこのあとがきから20年、「フランクルの世代が断ち切ろうとして果たせなかった悪の連鎖」は、今も続いている。悪化している。
私達はいつになったら、夜と霧から抜け出すことができるんだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
