
社会人の学びなおし!【学び合い、発信する技術】読書感想
こんにちはにどです。
読了した本
2022年10月20日発売の
岩波ジュニア新書 林 直亨著
学び合い、発信する技術 ~アカデミックスキルの基礎~
の感想を書いてみようと思います。
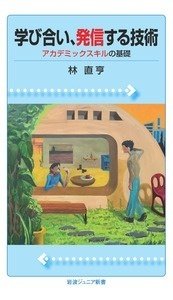
なぜこの本を読んだか
岩波ジュニア新書と言えば、
中学~大学生までを対象にした新書ですよね。
でも、社会人の学び直しとしても有用な印象です。
特に「空気」を読んでも従わない
という本は一時期凄い流行りましたよね。
そんな岩波ジュニア新書ですが、
毎回、新刊はチェックしていて、
気になっていたので、
目次を立ち読みしてみました。
すると
本書では、対話、プレゼンテーション、ライティング、リーディング等に
ついて分かり易く解説します。
大学や研究、探求活動やビジネスの場など広く社会で必要な技術を
身に着けるための入門書です。
裏表紙
とありました。
もう、範囲広すぎて
社会で生きてく必須スキルじゃないか!
なんて思ってわけです。
でも、改めて、話すスキルや書く技術、
ましてやプレゼンの方法なんて勉強したことない・・
そう思って、読みやすそうなジュニア新書を
選んで、入門してみました。
はじめに
まず、一言感想を・・
「学生時代勉強してなくても、まだ取り返せる!」
でした。
昨今、インフルエンサーたちが動画やSNSで
自分の意見を雄弁に語る様子を見る機会が多いです。
その影響なのか、実社会でもしっかり自分の意見を伝える技術を求められたり、考えを表現する方法を求められる事が多い気がしていました。
そんな中、僕は
「話すの得意な方ではないしな・・」
とか
「文章や発表苦手なんだよなぁ・・」
と逃げてしまっていました。
この本は新書170頁ほどで
アカデミックスキル全般を網羅しているため、
この本からスタートして学んでいける気がしました。
感想
対話、発信、書き、読みを端的にまとめて
方法論を提示してくれています。
対話であれば、基本的な心得から始まり、
質問(聞く事)の大切さも述べています。
その質問方法も
自分の立場や主張と比較する
意見の賛成点を探す
意見の欠点、反論を考えながら聞く
といったように具体的で
今まで人の話を聞く時どうだったかな・・
なんて考えながら読むことが出来ました。
また書きに関しては
アメリカの小中学の作文の時間に扱われている
「5段落エッセーの基本構成」が紹介されていました。
序論
(問題提起、なぜその問題を取り扱うか
論文なら背景や先行研究、その問題点等)
↓
段落①
↓
段落②
↓
段落③
(段落は序論に対する主張や根拠等)
↓
結論・まとめ
とこの形式で例文があり解説されています。
印象に残った項目は
読みの項目です。
著者は読むものに困ったら古典を読もう
と述べています。
なぜか
古典は多くの批判に長年耐えてきて
現在でも高く評価されている。
つまり、価値があるという事だと思います。
これについては
ショウペンハウエルの「読書について」
を引用しながら説明しています。
さらに興味深い視点があって、
ドストエフスキーの「罪と罰」を
例にして、普通では体験できない
殺人や罪悪感を追体験できる。こういった
"読む"楽しさも書かれていて、
とても共感しました。
他にもピアレビューやプレゼンテーションの
方法論も簡潔に書かれており、
通勤時にとても読みやすい内容になっていました。
おわりに
生活している中で、
アカデミックスキルの必要性は感じてはいましたが苦手意識はありました。
でも、この本を読んで、
簡潔に方法論が書かれているので、
「学生時代勉強してなくても、まだ取り返せる!」と思う事ができました。
noteでも(本を)読んだ後に書いてみて
その内容を誰かと話したり、発信を続けて
アカデミックスキルを磨いていこうと思います!
稚拙な文ですが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
次回も更新したら読んでみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
