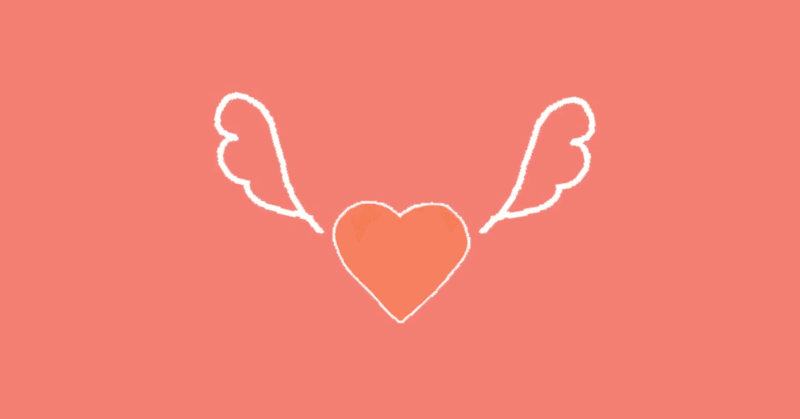
「友達という関係。」/ショートストーリー
冬特有のどこまでも高く高く青い晴れた空。
わたしは公園で散歩するといつものようにベンチに座った。
わたしが散歩すると言うよりは、うちの愛犬のため。
うちの犬の名前は『シロ』。
保護団体からきた子だ。
雑種だが、とてもお利巧さんの可愛い、わたしの犬。
シロと散歩するのはリモートワークばかりのわたしにとっても気晴らしになるし、何よりシロは散歩が大好きだ。
ベンチに座って一息つく。
わたしとシロの息は白かったが、身体と心は温かかった。
冬生まれのわたしは暑い方が苦手で、冬の凛とした空気の方が好きだ。
それはシロも同じようで似た者同士だなと思うとますますシロが可愛くなるわたしだった。
「お隣。いいかしら?」
その声で視線を上げると背の高い女性がベンチの傍らにいた。
彼女が愛犬と一緒に散歩する時間がわたしたちと同じようで大体毎日見かけたものだ。
もう、何年も見かけるのだが声をかけたりしたことは一度もない。
モデルのような体形で颯爽と大型犬と散歩する彼女とは住む世界が違うと感じていたからだ。
それなのに、彼女から声をかけてくるなんて。
わたしの胸はドキドキするとかではなくて、何故かざわついた。
「どうぞ。」
わたしはベンチの真ん中から一人分身体を移動した。
「ワンちゃん。可愛いですね。お利巧さんでしょう。他の犬に吠えたのを見たことがないもの。」
住む世界が違うと思い込んでいた彼女はわたしたちには興味がないと思っていた。
それに、犬と散歩するひと達はたくさんいた。
彼女の方は目立つ存在だが、わたしたちの方はその他大勢のほうだ。
「今日はワンちゃんと一緒じゃないんですか?」
「そうなの。ちび。。うちの子はちびと言うのよ。昨日の夜、ちびは虹の橋を渡ってしまったの。」
わたしはなんと言っていいのか、頭にはなにひとつ言葉が浮かんでこなかった。
「もう、年だったから。保護団体からきたときは10歳過ぎでしょうと言われて5年はたっていたの。幸せな5年だったな。ちびも私と同じだったら良いのだけれど。」
「きっと、同じです。」
わたしはなぐさめで言ったわけではない。
彼女と彼女の犬がいつも楽しそうに散歩しているのを遠くから眺めていたのだから。
「私ね。友達がいなくて。ちびが唯一の友達だった。」
わたしはその言葉に驚いた。
彼女に友達がいないなんて信じられない。
どうみても、周りから人が寄っていくようなそんな彼女に友達が愛犬しかいないなんて。
「友達関係って私には難しい。こちらが友達だと思っていても、相手が同じだとは限らない。同じ熱量とは限らない。まあ。恋愛でも同じだけど。片思いばっかり。」
そういうと彼女はとても淋しく笑った。
わたしの胸が痛くなるほどの淋しそうな笑顔。
「だって。きがついたの。いつも私的な連絡するのは私のほうばかり。それは友達じゃないわよね。同級生とか仕事相手とか、そんなジャンルに私はいつもいるの。」
「だから。人間の友達は諦めた。だけど。ちびはね、本当に親友だった。」
「あの。失礼ですが。ご結婚とかは。」
「友達もできないのに、恋人なんて無理。あなたは?」
「わたしは。実はバツイチです。」
「ごめんなさい。これだから、友達が出来ないのよね。」
「そんなことはないと思いますけど。」
「ありがとう。私ばっかり話しちゃって。」
彼女はゆっくりと立ち上がった。
「これから、ちびの骨をもらいにいくの。」
「あの。お身体大切にしてください。」
わたしにはそれしか言えなかった。
彼女はまた笑った。
今度は淋しい笑顔ではなかった。
「ちびったらえらいのよ。私がひとりにならないように、この公園で捨て猫を見つけて。あんまり小さくてびっくりした。ちびは大型犬なのにちびって名前がついてて。そのちびが本当に猫のおちびさんを見つけてさ。」
「それじゃあ。」
「そうなの。次は猫のちびが私の親友になると思うの。やっと、獣医さんから引き取ることが出来るようになったから。」
「公園には?」
「そうねえ。公園にはもう来ないかも。猫は散歩しないから。」
彼女はいつも見るように颯爽と歩いて行った。
彼女にわたしが友達になりますとは言えなかった。
大体、友達ってなるものだろうか。
わたしも彼女と同じ。
人間の友達もパートナーも諦めている。
シロだけだ。
わたし、シロがいなくなったらどうするのだろう。
友達がいなくても生きてはいけるだろう。
だけど。
シロがワンと珍しく吠えた。
シロの足元に何かが落ちている。
拾ってみると、彼女の身分証だった。
会社用みたいだから、なかったら困るだろう。
直接連絡した方が良いのか、交番に届けた方が良いのか?
「シロ。どうしたらいい?」
シロは嬉しそうにしっぽをふっている。
不思議なことにその身分証は光って見えた。
「わかった。シロ、今は何も考えずに連絡してみるよ。それでいいんでしょう。」
シロのしっぽはますます大きくふれていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
