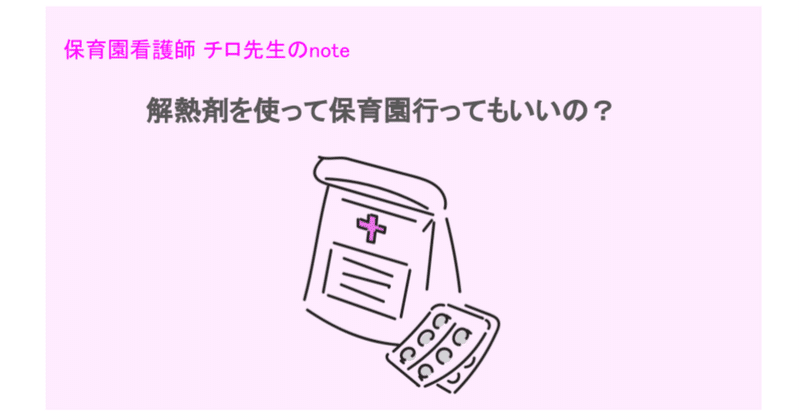
解熱剤を使って保育園行ってもいいの?
こんにちは!現役保育園看護師のチロです。
今回のテーマは、ずばり「解熱剤」です。
解熱剤は、小児科で処方されることが多いお薬の一つです。おそらく、どんな人でも人生で1回は使ったことがあると思います。
新型コロナウイルスの流行により、発熱した状態で働いたり登園したりすることのリスクが世間的にも認知されたように思います。しかし、一昔前までは、大人も子どもも解熱剤を使って出勤したり登園させたりしていたという話をよく耳にしていました。
そこで今回は、改めて解熱剤を使用した状態で保育園に登園してもよいのかどうかについて、保育園看護師としての見解をまとめてみました。
結論としては、解熱剤を使用した状態で保育園に登園することはNGです。なぜ解熱剤使用中の登園がNGなのか、解熱剤というお薬の特徴や解熱剤使用時の留意点等について、解説していきたいと思います。
この記事を通じて、保育現場で働かれている保育士さんや保育園看護師さんが、保護者の方に簡潔に説明する際の一助になれたら嬉しいです!よろしくお願いいたします。
「発熱」とはどういう症状か
まずは、発熱という症状について整理しておきましょう。
子どもの場合、発熱の原因の多くは風邪(感染症)によるものです。他にも発熱する原因は多々ありますが、今回は風邪に絞って考えていきます。
風邪の原因は、8~9割がなんらかのウイルスによるものと言われています。ウイルスが体内に侵入すると、身体は自分を守るために様々な反応を示します。咳や鼻水などの症状は、ウイルスを身体の外に出そうとした結果の反応です。中でも体温を上げることでウイルスをやっつけようとする反応があります。これが、発熱の正体です。
特に乳幼児期は、様々な種類のウイルスに生まれて初めて出会います。出会う度に風邪をひき、治ることで少しずつ免疫力を培っていきます。風邪をひいては熱を出してウイルスをやっつけるため、大人と比較すると発熱する頻度が高いのです。
そして、体温を上げると身体はたくさんのエネルギーを消費します。ウイルスをやっつけるために無理やり体温を上げて頑張るため、だるくなったりつかれやすくなったりします。
また、体温が上がりすぎると今度は身体が高温に耐えられなくなることもあります。頭が痛くなったり、眠れなくなったり、乳幼児期には熱性けいれんを起こすこともあります。
要するに、発熱という症状は、身体がリスクを冒してウイルスと戦うための戦闘手段であり、身体が頑張っている証拠でもあります。
解熱剤使用時に登園してはいけない3つの理由
解熱剤を使用しているときに保育園を利用してはいけない理由は、一言でいうと『治っていないから』です。もう少し詳しく説明すると、大きく分けて以下の3つの理由があります。
身体への負担が大きいから
感染リスクがあるから
解熱剤は治療薬ではないから
それぞれについて、解説していきます。
①身体への負担が大きい
発熱している状態の身体は、前述した通りとても頑張っています。頑張っている身体に解熱剤を使用して体温を下げたとしても、身体が頑張っているという事実は変わりません。
解熱剤を使用すると、身体は急激に汗をかくことで体温を調節します。ただでさえ熱でだるいのに、一気に汗をかくためかなり疲れます。そんな状態で保育園に登園すると、どうなるでしょうか?
お子さんは、ただでさえ疲れている身体を酷使して集団生活を送らなくてはいけません。いつもより元気がなく、なかなか遊びに集中できないでしょう。仮に、普段通り走って遊べたとしても、それは身体に鞭を打っているようなものです。解熱剤の効果が切れたら、再び熱が上がってくる可能性もあります。
要するに、解熱剤で体温を下げている状態で集団生活を送ることは、身体への負担度が大きいということです。無理をすれば、風邪をこじらせたり、熱が長引いたりする要因にもなりえます。
②感染リスクがある
二つ目の理由は、コロナ渦でも繰り返し言われてきた通り、発熱している状態は感染リスクが高いからです。
風邪の原因はほとんどがウイルスによるものです。保育園では様々な風邪が流行しますが、流行するということは園内でお子さんが「感染している」ということです。
保育園内で感染が広がる要因は多々ありますが、一番の理由は「子どもだから」です。感染対策を自律して行うことはまだまだ難しい年齢ですし、咳や鼻水を出しながら大声で泣いて笑ってと忙しく、なにより子ども同士の距離がとても近いです。要するに、保育園内は3密不可避だということです。
そんな中、解熱剤を使用して熱は下げたとしても、身体の中にはまだたくさんのウイルスがいる状態のお子さんが登園したとします。ただの風邪ならまだしも、インフルエンザやRSウイルスなどの感染力の強いウイルスだったら、一気に感染が広がる可能性があります。
保育園は集団生活の場です。他のお子さんを守るために、感染リスクの高い状態のお子さんをお預かりすることはできません。これが二つ目の理由です。
③解熱剤は治療薬ではない
三つ目の理由は、解熱剤は治療薬ではないということです。
これまでの話からも分かるように、解熱剤という薬は一時的に体温を下げるための薬です。発熱の原因であるウイルスを直接やっつける効果はありません。あくまで対症療法としての薬なので、風邪そのものを治すものではないということです。
体温が高くなりすぎて眠れなかったり、身体がだるくて苦しい時などは解熱剤の出番です。医師や薬剤師の指示をよく確認して、用量用法を守って正しく使うことで、その効果が最大限発揮されます。つまり、解熱剤を使用する場面というのは案外限定的だということです。なんでもかんでも熱が出たら解熱剤を使う、というのは間違いです。
解熱剤を使用しても風邪が治っているわけではないため、保育園に登園してよいという判断には至りません。
解熱剤使用時の留意点と登園の目安
解熱剤を使用しているときは、少しでも早く風邪の原因であるウイルスをやっつけられるように、ゆっくり身体を休めるようにしてあげましょう。
リラックスできる環境で、胃に負担にならないものを食べさせてあげることは、身体の回復力を高めます。無理して保育園に来てもいいことはなにもありません。ご自宅等で、ゆっくり休んでくださいね。
時間で言うと、解熱剤を使用した場合は最低でも24時間は経過を見ていただきたいです。これは、お子さんがちゃんと治っているかどうかを見極めるためと、感染リスクがないかを見極めるために必要な時間です。
子どもの発熱は、朝起きたときは下がっていても、日中再び熱が上がってくるというケースが多くみられます。保育園でも、お昼寝前後くらいの時間帯に発熱することが多い印象があります。特に解熱剤を使用している場合は、薬の効果で熱が下がっているのか、ウイルスをやっつけたから熱が下がっているのかが、すぐには判断できません。その判断をするために、平熱に戻ってから(=解熱してから)24時間経過をみて、その間に再度熱が上がってこないことを確認してほしいのです。
特に感染症にかかった場合、保育園には感染症ごとに細かく登園基準というものが設定されています。そのほとんどは、解熱後24時間経過しているということが大前提として設定されています。
熱が再び上がってくるということは、まだ感染リスクがあるということです。24時間経過を見ることで、感染リスクが低減しているかどうかを客観的に判断する必要があるのです。
まとめ
解熱剤を使用しているときは、身体への負担度も大きく、感染リスクもあるため保育園に登園することは避けてほしいという話でした。
無理をしてほしくないというのは、子どもだけでなく大人も同じです。感染リスクが高いからというだけでなく、単純に自分の身体を大切にしてあげてくださいね。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
