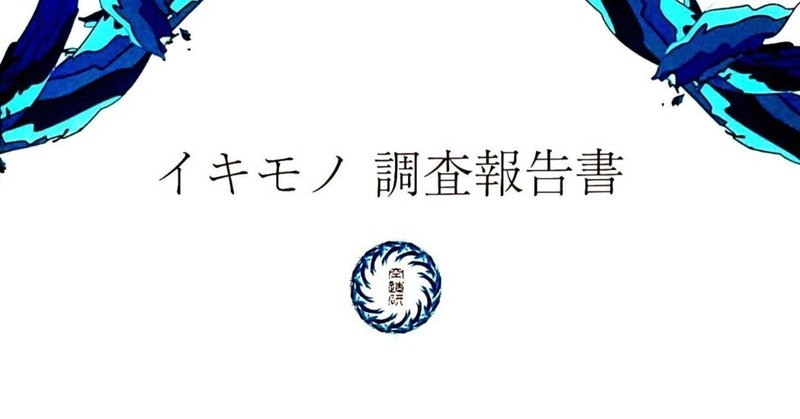
主にはその世界観について|武蔵野美術大学 空想造形會『イキモノ 調査報告書』
ムサビにて、趣味の合いそうなサークルを見つける
2022年10月末、武蔵野美術大学の大学祭に赴き、これからさらに高尾山に登ろうとしていた。芸祭の見落としがないか入念にパンフレットに目を凝らすと、空想生物の創作をやっているサークルがあることを発見したので急いで向かった。
ブースを認めてすぐに、冊子を販売しているのがわかった。当然創作された空想生物の紹介である。表紙には「イキモノ 調査報告書」とあった。即決で購入した。
ちなみに私は以前に生物創作について記事を書いたが、あくまで個人の好みと方針の範疇を出ない、と言っておく。
ただまあ、やはり環境の中で一見不自然な結集が生物である。結集であるからには、とにかく何か寄り集まっているわけだ。それは摂取して吸収される分子のような物理的な側面のみならず、概念的な問題も含む場合がある。今回はあまりこれについて言及することはない。
以下、当該冊子の個人的な感想である。
冊子内容
当然冊子の中身は作品だらけなのでおいそれと無断転載するわけにはいかない。文字だけでご勘弁願いたい。
形式
全体として、書名のとおり調査報告書の体裁を持っている。また、海外の創作怪奇投稿サイトで、日本でも有名な「SCP財団」の作風からの強い影響を感じさせる。
まず、見開きの左側頁に「ソウサクセイブツ」と呼称される作品=空想生物のイメージ絵や写真など画像的情報がタイトル=名称とともに大見出しにされ、次いで「発見研究員」「体長」「出現場所」そしてA>B>C>Dの四段階評価による「危険性」が示される。
次に、見開きの右側には「研究員報告書」と題された文章ベースの頁がある。所感・実験結果・推測・追加情報・生態情報・総括など、各「ソウサクセイブツ」ごとに形式は定まっておらず、文体も特に一致していない。それぞれが赴くままに報告書らしいものを書いたという印象を受ける。
「ソウサクセイブツ」
「ソウサクセイブツ」たちのコンセプトは多種多様で、日常にあって特に気にしたこともない部屋のシミのような何かしらの形象または現象に生物的な要素を見出す、ないしは付加することで空想生物たらしめているものもあれば、完全に新規の生物像を創り出して100%のフィクションに挑んでいるものもあって、バラエティ豊かだ。
私個人の生物創作の方針とは全く違うし、いくつかは真っ向から対立してしまうものがあるが、私の制限的な創作方針は発想を抑圧させるので、かなり刺激になった。
世界観
一読して直感的に、冊子には統合された世界観がないという印象を受けた。つまり、「作品としての冊子」ではなく、「作品がそれぞれ冊子に記入されている」だけに感じた。以下で検証する。
「空想造形會」像あるいは当該冊子のスタンスは、書名と「はじめに」の挨拶、それから作品部分の説明するものの立場で我々は読み取らなければならない。「はじめに」で空想生物を発表するサークルであることは明記されているから、冊子全体が、作品内の随所で言及されるところの研究員が所属する異界に存在する組織(これにあたるものは「サニー」においてはP20などで「造形會」と言及されている)の、その刊行物として扱うように我々に訴えかけてくるわけではないが、表紙とあいさつ、奥付は現実の規格で、コンテンツ部分は異界の産物として扱うように暗に示してくるタイプのものはある。
この冊子全体の世界観の問題について、私は読み進めるにあたって最初は今言ったタイプの、「コンテンツ部分は異界の産物」であるものだと思った。ひとつめの作品「ミツノジ」の報告書の文体が、現実的な報告用メモの体裁をとっていて、作者意図のようなものはそこに含有されていなかったからだ。まあ、作品名の上に毎回「ソウサクセイブツ」と書かれているので、没入感は薄れるが、これはコンテンツ外のものとギリギリ補正できる範囲の問題だった。
しかし、ふたつめの作品「S字フックの神」になると、事態は一変する。報告書の文中に「ソウサクセイブツ」という単語が断定的に使用されているのである。解釈の場合分けを行う。
1.「ソウサクセイブツ」がそのまま「創作生物」の意味なら、興ざめになる。「ミツノジ」はリアリティのある怪奇を提供していたからだ。自ら虚構だと主張する虚構は、目的が倒錯している。
2.あるいは、カタカナの表記に注目すれば、ここでの「ソウサクセイブツ」とは偶然我々の「創作生物」と音の似ている異界の語彙の可能性もある。たしかに「はじめに」でも末尾に「貴方の身の回りにはどんなソウサクセイブツがいるのでしょうか」と呼び掛けていて、その可能性は濃厚だ。各作品見開き左上に表記されているそれも、単に「哺乳類」のような分類項目名と考えてもいい。
ただし、この場合も問題点がある。それは、他の作品の説明文章中には「ソウサクセイブツ」という単語が1つも登場していないことだ。特に長編の報告書を携えていて会話ログなどもある「サニー」で「ソウサクセイブツ」という単語が出てこないあたり、当該の異界で「ソウサクセイブツ」という発音の分類項目が存在しているという説得力のある材料・描写が不足していて、却って「はじめに」の指定に沿って報告書内で「ソウサクセイブツ」と作品のことを呼称してしまった「S字フックの神」の文章が他の作品の中で浮いてしまう結果になっている。
今述べたように、どちらの場合でも、私には世界観の統合的に問題のあるスタンス的差異に思われる。仮に、先に書いたところの「作品がそれぞれ冊子に記入されている」だけのものをこの冊子の完成形としている場合、そもそも各作品で見開き左側のフォーマットのみを揃え、作者=「研究員」という同一的世界観を各作品に中途半端に与える必要さえなかったのではないか。つまりアンソロジーを「ソウサクセイブツ」という最低限の縛り=テーマでやっただけ、という程度の緩めな統制にしておいたほうが良かったのではないかと思う。冊子全体としてのスタンスが不明瞭である。
なおこの章で言及したのは主に最初の2作品だけだが、選出の理由はこの2つが普通に読み進めている場合に真っ先に比較対象にされるものというものであって、それ以降の作品も記述スタンスがそれぞれ異なっている。結論(=コンセプト)ありきな概論にとどめるタイプや、設定の一部あるいは断片的で間接的な情報しか提示しないタイプ、生態学的な記述を試みるタイプなどのばらつきはないでもなかったが、文体の問題以外は然程乖離というほどでもないように思う。
ただ、仮に「作品としての冊子」を作ろうとすれば、私ならもっと厳しいフォーマットを作品それぞれに課す。というのは、概念的には、各文書を報告書として提出する際には必要事項があるはず(例えば、「振る舞い」「対処法」「現在の状況」「実験記録」「インタビュー」など……)であり、これを埋めることだけは譲らないか、これを埋められないメモ書き程度ならば欄だけつけて無記入としたり、メモ書きしか残っていないことについて、この冊子を編纂している架空の異界人物に成り代わって断りの文言を入れるなどする。確かに、見開き左側の部分には「発見研究員」「体長」「出現場所」「危険性」とその説明があるが、それが必須項目ならば、右側はもっとラフなメモで問題ないはずだが、実際には左側の情報を簡単な説明と扱ってさらに詳しく右側で説明するものもいくつか存在する。フォーマットを統一することで、この書類が現実に存在するという画面的な説得力を感じられるからだ。編集者という、作品群を統括するこの世界観には必須の存在が、あまり感じられない。
「報告書」部分には硬質で実際的な文章もあれば、概念的で設定と創作コンセプトを報告する体裁に直したにすぎないものもある。特に、根拠が明白でないのに突飛な発想で結論に至るものなどは──それを全作品で行っていれば「そういう世界観」とすることで済んだものの──明らかに作者としての特権を行使した優越的な記述であって、「貴方の身の回り」にいると言われて色々想像している読者は、ここで突然おいて行かれる印象がある。「S字フックの神」における「天にいるナニか」などは、独自の世界観が他作品から乖離していて、書き手の立場もよくわからない。宗教的世界観の存在を事実の記録的に示した「サニー」のものと比較せざるを得ない。また、(これは最後尾の作品であって、おそらくはネタキャラ扱いを受けているであろう)「限界美大生お助けマン」の記述も、書き手が作者としての断定的解説と観察者としての報告や推測のあいだで行ったり来たりしている。
各論
「ミツノジ」
面白い。
3つの点の集合を生物的な存在者として画定しようとする試み。「研究員報告書」も所感と簡単な実験メモが付されていて、発見者のライブ感を楽しめる。
「S字フックの神」
S字フックに擬態している寄生生物だという。被害実態と研究員の推測が報告書欄には記述されているが、口頭での報告を文字に起こしたような文書となっており、事実と推測が同じ地平にあって、「説得力のある妄想」にまで十分至っているとは思えない。唐突な神的存在への言及、およびそれを前提にした推論は、上述した通り唐突な印象を避けられないと思われる。
S字フックという日常生活に埋没したモチーフを恐怖的存在に仕立て上げるコンセプトは、「貴方の身の回り」という部分に即していて良いと思った。
「メダマギノコ」
メインイメージ、および図解が詳細で素晴らしい。将来すこしでも目玉のようなできものができてしまった場合、この作品を連想して恐怖するだろう。
「世界観」の項目で言及した「ソウサクセイブツ」という呼称を用いず、「本生物」と呼称している点で、ひとつ前の「S字フック」とは異なった世界観という印象を受ける。
概説、形質や生態、危険性に関する情報、対処方法など新情報といった具合で完結に報告がまとめられており、強くリアリティを感じる。
なお、報告書文中に「胞子植物」とあるが、これが現実のものと同じ場合、根の有無ではそうであるかどうかは区別できないはずだ。また菌類は植物ではなく、植物的な根も張らない。また、普通キノコ類の名称として連濁した「~~ギノコ」というのは聞きなれないが、「~~ダケ」ではない理由が気になる。
「トラスチュウ(卵)」
実際にいそうで嫌悪感のあるコンセプトが良い。
文体は口頭説明の文字起こしに近く、所感(あるいは小説)と報告書のあいだを往復している印象がある。
「サニー」
長編ログ。特にSCPの潮流を感じる。こういう書体の小説ともいえる。
研究記録への書き込みを窓口にした異界描写。
所々で、記録というよりも「サニー」収容のための「職員」向けアナウンスが混ざっている部分が気になる。
「ガマミム」
バランス風呂釜における事故の原因を怪異に求めている。「カルシファー」の変種のように思える。実際に起こりえる事件や事故の不可解な原因を求める心の映し出す存在として現出する(ように見える)点で、妖怪的な性質を感じさせるが、実態はむしろSF的なもののようだ。
逆に言えば、今まで妖怪の仕業とされてきた現象が未確認生物によるものである可能性も否定できなくなる。
会話ログの文体は小説的。
「限界美大生お助けマン」
恐らく、マスコット。
むしろこの「セイブツ」は精神的に追い詰められた美大生の心内に表れる正負の両側面を持つある種のエネルギーやこだわり、あるいは別人格なのではないかと思う。
文体は前述のとおり作者と観察者とのどっちつかずだが、この作品に関しては紹介順やコンセプトから考えてむしろ妥当な扱いなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
