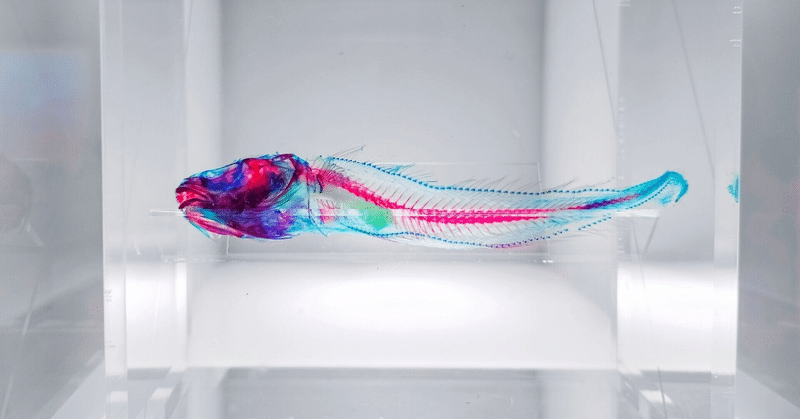
生物創作
「生物の創作」という作業において、私にはあるこだわりがある。つまり、生物とはエントロピー増大の法則を遡行する存在である、ということを守ることだ。世界を構成する要素の不自然な結集と呼んでもいい。とにかく、周囲に依存しながらしか存在することができない。
生物は通常環境の一部であって、独立した存在ではなく、所属する生態系の中の地位が必ずある。生物間でも影響しあう。だから、厳密な意味で創作生物を考える場合、先に考えるにせよ後付けにせよ、創作世界の地形や気候を加味し、一見無理のない嘘をつかねばならない。2つ以上の生物を同じ生態系内で描写する必要があれば、その2者の関係を意識せざるを得ない。
環境の一部ということへの配慮
実際の地球環境を、創作世界とみなして考えてみよう。地球は太陽から受け取るエネルギーと地球内部からのエネルギーによって、その表面は絶えず塑像と彫像を繰り返している(これを外的営力・内的営力という)。地軸の傾きは地球の公転をして地表のあらゆる地域それぞれを時期的に偏った太陽光に晒すことを可能にする(これを季節という)。さらに自転によって、大気は単なる対流ではない大循環を引き起こしており、これがいわゆる貿易風とか偏西風とかにもつながる。(プレートテクトニクスの理論に基づけば、)大地は常に地球内部から湧き上がる「大地の素」とでもいうべきマントルによって押し広げられ、それらが互いにぶつかったところに山脈ができたり、あるいは広がった溝に大きな谷や海溝ができたりする。あるいは日本近海のようにプレートは再びマントルへ沈んでいき、溶けたプレートの一部は地表に湧き上がって火山前線を描写する。沈み込みで生じる摩擦は地震を引き起こす。そういう地形と大気および海流が、その土地の気候条件を決定し、また植生を決めるというのが、現代社会の通説だ。動物はさらにその植生の上にしか寄る辺のない存在だ。
例えば、シカとクマは普通、直接的に被捕食者と捕食者の関係にある。しかし、クマは常にシカ、あるいは他の草食獣を捕食するのではなく、木の実や虫なども食べる。シカは植物ばかりを食べるから、シカの食べることのできる植物がある植生の地域にしかシカは住むことはできないし、該当する植物がなくなれば、違う食物に適応するか、あるいはそこから撤退するかしかない。そうなると、クマもまた食物が不足して、どこか別の場所に行くか、食べ物を変えざるを得ない。
キノコとシカを比べてみる。シカは普通キノコを常食にしないから、両者は一見関係がないように見える。しかし広く考えればキノコは植生の一部である。朽ち木に生えるキノコは、枯死した樹木の分解されづらい組織をばらばらにする。キノコがいなければ、シカの住む林はいずれ倒木に埋め尽くされ、次の草木が生えるための十分な土壌が育たず、結局枯ればかりの土地になるはずだ。彼らに直接的な関係はないものの、一定の近さで存在する2者には関連性がある。
もっと言えば、キノコが破壊した朽ち木をさらに土壌に住む微生物が分子レベルまで分解し、土壌が育ち、これが下草を生やしたり、種子を芽吹かせたりする。それをシカは食む。だから、「この林にはシカとキノコしかいません」と言うことはできない。そう見えるとき、それは我々の恣意的な焦点化が映す歪んだ写像でしかない。
突き詰めるとキリがないが、ある程度このような循環的な分子移動を前提にすることで、創作世界はより強く現実性を帯びるだろう。
進化への配慮
進化論を当然とする我々現代人においては、さらに通時的な変化も考えねばならない。つまり、これは私にとっては原則ありえない例を述べると、完全にイヌの顔をしているのに首から下はクモなどという創作生物の類である。
生物の形質はソフト・ハードを問わず、その所属する環境に基本的には適応している。イヌの頭は発達した嗅覚や鋭い犬歯、体温調節のための舌や体毛、方向を変えられる耳、獲物との距離を図る顔の前面についたふたつの眼球など、それぞれ地球の野山に住む中型哺乳類(恒温動物)の捕食者としての特徴を示している。一方首から下がクモということになると、実際はクモは昆虫のようには頭と胸が分かれていないので、頭胸部の下半分からということになるが、まず8本脚で、それからいわゆる肺による閉鎖血管系ではなく、気門から直接組織液に酸素を溶かす開放血管系だ。このタイプの呼吸法を採用している節足動物は、地球上では身体のサイズに厳しい上限が設けられていることは、身の回りの虫たちが軒並み小型であることを思えば難しくない。身体が大きくなればなるほど、体液に気体が溶け込むのを促しにくくなるためだ。だから酸素濃度が高かった大昔は今より大きい昆虫が化石として見つかっている。また、消化器官はもしかすると頭部から伸びて犬のものが流用されているかもしれないが、仮にクモのものならば哺乳類の消化管のように固形物を内部で消化吸収できる代物ではない可能性が高い。クモは獲物に牙を突き刺し消化液を注入したあと、ドロドロに溶けた中身を啜る体外消化の捕食者だ(主な獲物となる節足動物の外骨格が消化に向いていないことに関係している)。犬の口で獲物に噛みつき肉や骨を飲み込んでも、消化器官がそれを受け付けないはずだ。同じ肉食だから大丈夫なわけではない。他にもいろいろ問題はあるが、犬の頭部とそれ以外のクモというパーツの組み合わせは、生物としては土台無理のあるものだということが分かる。
これが、イヌのような顔つきと、クモのような身体つきの未知の生物として指し示すなら問題は無いし、他にも自然に生きている生物ではなく一時的に無理やり作り出された人工生物ということなら、可能不可能の度合いは創作世界の技術進度の問題になるから、存在させることは不可能ではない。ただ、単にイヌの頭とクモの身体の動物というのは、存在し得ない。あるいは「魔力」のような、我々には土台理解のできない体系があれば別だが、この世と地続きの感は薄まってしまう。下手にキメラを創るのは危険な行為だと言える。
この問題は、要するに現生する生物の進化の流れをある程度は追っていくと辻褄を合わせることが出来るだろう。例えば多くの昆虫が持つ翅だが、これは今までかなりその発生元が謎に包まれていた。翅のない昆虫からある昆虫への中間化石が見つかっていないからだ。だから化石を辿ると、昆虫はいきなり進化の途上で空中を舞うようになる。空を飛ぶ他の動物を見比べてみると、プテラノドンなどで有名な翼竜も、空を飛ぶ古生物のひとつだが、前肢の指の間に皮膜を発達させて上昇気流を掴んでいる。また、今に生きる鳥類は恐竜の中でも獣脚類(ティラノサウルスとか)の子孫であって、前脚がやはり発達した羽毛を携えて空力を生み出し、強靭な筋肉によって羽ばたいている。哺乳類のコウモリも、翼竜などとは様態が異なるものの、手の皮膜による空気抵抗と羽ばたきで宙を舞う。さて昆虫は、翅があってもなくても基本的に6本脚で、上記の飛ぶ脊椎動物たちのように、どこかの器官が徐々に飛翔機能をもつように変化した痕跡に乏しい。現在では研究が進み、水棲昆虫などが持つ腹部のエラと、胸部の側面部にある「側背板」という突起の複合した遺伝形質であるという見解がもたれている。
エラは翅を動かす関節や筋肉の説明に、側背板は翅のつく場所と形状の説明に、それぞれ適当なのだ。こうして昆虫は翅を手に入れているから、空飛ぶ脊椎動物たちとは全く飛翔機能の獲得経路が異なる。彼らは脚を1対犠牲にして飛んでいるのだ。だから、例えば翼を持つウマ「ペガサス」は、哺乳類としてはあまりにも不自然な身体の作りをしている。そもそもウマの体重を浮かせるのに必要な翼長と筋肉という問題も抱えるが、そもそも昆虫のように都合のいいエラも側背板もないウマがどうやって脚を失わずに翼を獲得できるだろうか。これが幻獣と、創作世界内のリアルな生物とを分ける好例であると思う。
どうやら、脊椎動物の系譜は一度失った関節を増やすのが不得意らしい。魚から考えて明らかに背鰭だった部位やしり鰭だった部位はなくなっていくわけで、脚を増やすなんてもっと難しいだろう。節足動物は体節を増やせばその側面に生える脚も増えたりして、どうも我々とは根底からルールが異なっているようだ。このあたりを踏まえながら、混ぜたり形を変化させて生物を創る。
勿論、そもそも進化の根源的な部分から現実のものとは異なった体系を考えることは不可能ではない。H2Oを全く使わない生物など、地球上にはいないが、H2Oを使用していなければ生物でないというわけでもない。ただ、かなり面倒くさい作業になるし、辻褄合わせに割く労力が過剰になるだろう。幻獣でも妖怪でも魔物でもないが全く新しい生物を描く必要がある場合、想像のつかない異界からの来訪者として描くか、あるいは現実の体系に沿って部分的な変化を施した似せ物を使うかした方が良いと思う。
モンハンの創作生物
この辺りをうまく説明したり、あるいは説明を避けているのは「モンスターハンター」シリーズの個性豊かなモンスターであろう。いわゆるワイバーン型のモンスターを「飛竜種」と呼ぶが、彼らは前脚が翼として特化した発達をしていたり、脚としても翼としても使える中間態であったり、あるいは完全にただの4脚生物だったりする(大きくて太いイグアナのようなものだ)。モンハン世界内にも不完全ながら進化系統を示すような「生態樹形図」があって、ほかにも獣脚類のような「獣竜種」や、哺乳類のような「牙獣種」などがいる。その中でもひと際目立つのは「古龍種」という区分だ。先ほど生態樹形図を「不完全な」と呼んだ最大の要因はこの区分にあって、これは実質的には生物学的分類の体裁を成していない。明らかに草食の動物から派生している「キリン」、頭足類のような身体をもつ「オストガロア」、巨大で前脚のある蛇「ダラアマデュラ」、そして4本脚を持ち背中に一対の完全な翼を持つ「クシャルダオラ」「テオ・テスカトル」「オオナズチ」など、そして4本脚と1対の「翼脚(=飛翔機能を持ちながら手足のように扱えるもの)」あるいはほぼ完全な脚をもつ「ゴア・マガラ」「ゴグマジオス」「ガイアデルム」……明らかに「飛竜種」と「獣竜種」のかけ離れ方よりも大きな違いが、同じ分類内に混在している。いわば分類困難な生物を放り込むごみ箱のような部分が「古龍種」の一側面である。
※生態樹形図の批判については以下の記事にも書いているので、モンハンプレイヤーはぜひご一読いただきたい。
各論は避けるが、結論から言えばモンハン世界には6本脚の進化をたどった陸生脊椎生物の系譜と、4本脚の進化をたどった陸生脊椎生物の系譜とがあるように思われる。なぜなら、4本脚のうち前脚2本が(現実の鳥類などのように)飛翔機能に特化した発達をしている飛竜種と、4本脚とは別に1対の翼、翼脚、あるいは完全な脚を持つ一部の古龍種とが併存しているからだ。関節を増やしにくい(であろう)ことを踏まえると、6本脚のグループから4本脚のグループが派生した可能性もあるが、とにかくこの2グループは根本的に違う生物である可能性が高い。あるいは、昆虫的なプロセスで翼を獲得した可能性も検討可能だが、例えばガイアデルムの3対目の脚の形態は他の対のそれとほとんど同じであって、独自に派生した部位と考えるのは直感には反する(ただ、虫を潜在的なモチーフにしていると思われる古龍種は多い)。
このように、現実にはあり得ない生物でありながらも、現実の法則に近しい流れで進化の流れを示されれば、そういう世界もあるのかと納得せざるを得ないのである。深く考えてある程度予測がつくような秩序のありそうな世界。こういう感覚のために、その世界の末端を示す生物は慎重に設定する必要がある。
余談
一度ファンタジーを書こうと思って、異世界の現地生物を創ろうとしたことがある。結局執筆開始までにも届かず、ただの創作生物図鑑にしかなっていない。
いや、本当は実在しない生物を考案する遊びのほうが目的であって、ただただその妄想に意義を与えるために、小説を持ってきたというほうが正確なところなのだろう。今公開することはできないが、そのうち何らかの形でお披露目したいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
