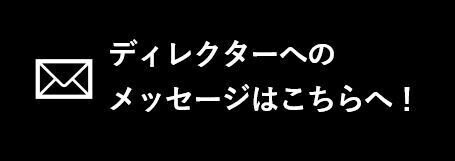新人が先輩全員をごぼう抜き ~餅ばあちゃん ギャラクシー賞 受賞の裏側~
<マケドニアに「蜂ばあちゃん」現る>
「ハニーランド」という映画を観た。ギリシャの北に位置する北マケドニアの大自然の中で暮らす、自然養蜂家に密着したドキュメンタリー映画だ。電気も水道もない谷に、寝たきりの盲目の母と暮らしながら、ミツバチを育て、ハチミツで生計を立てる女性。ヨーロッパで最後といわれる自然養蜂家に、カメラは3年間密着していた。
サンダンス国際映画祭ではグランプリを含む最多3冠。世界の賞を総ナメにし、92回アカデミー賞では、史上初、長編ドキュメンタリー部門を含む2部門でノミネートされた。
監督はなんと弱冠27歳のマケドニア出身の女性、タマラ・コテフスカ氏。今、世界が注目する若手ドキュメンタリー監督だ。

クセのようなものだろうか、映画を見ながら、ついついやってしまうのが「この映画に邦題をつけるとしたらなんだろうか」と考えること。この「一人配給会社ごっこ」は、時に迷宮入りするのだが、今回はすぐに出てきた。
「蜂ばあちゃん」。
これしかない。

そう、この映画を観る数ヶ月前に、僕は、「餅ばあちゃん」という衝撃作と出会っていた。
<「餅ばあちゃん」の衝撃>
「プロフェッショナル 仕事の流儀」で2020年6月に放送されたのが、「餅ばあちゃん」だった。舞台は、青森県五所川原。山に分け入り、笹の葉を採り、材料の小豆から全て手作りでお餅を作る、桑田ミサオさんの日々を、2019年夏から冬まで、移ろう季節とともに記録した。
桑田さん、通称「餅ばあちゃん」は、93歳という年齢ながら、颯爽と自転車に乗り、年間5万個の笹餅をたった一人で作る。地元に愛され、売店では、飛ぶように笹餅が売れる。美しい日本の原風景とともに、たんたんと「餅ばあちゃん」の日常が綴られていく。

コロナ禍の中で、移動を封じられてしまった僕たちが見るのは、都市の無機質な景色ばかりだった。人が生み出す音も温度も失った街の風景は、より一層、無力さを増幅させた。
そんなときに見た、人間の不安なんて気にも止めない津軽の山、雲、空、稲穂。そして、餅ばあちゃんの優しい笑顔に、心が震えた。
監督は、弱冠27歳の伊藤麻衣ディレクター。入局3年目だ。
恐るべきことだ。入局3年目といえば、僕はまだ、「のど自慢」で出場者と演歌歌手をステージに送り出すタイミングがわからず苦しんでいた。(タンタンターン、タタタタタタン、タタタ←たしかこのあたりなのだが、行進のスピードも考えねばならず、困難を極める。)
その伊藤Dが作り出した世界は、独特のリズムを刻んでいた。
ナレーションは、ギリギリまで排除され、山の音、草の音、そして「餅ばあちゃん」の声のみ。(ナレーションをしている橋本さとしさんの喉をだいぶ休ませるワークライフバランスな結果となった。)
ゆっくりと、でも着実に。祈るようにあんこを炊き、餅をこねる。
津軽の自然と、餅ばあちゃんの手。いつしかその世界に没入し、出られなくなる。出たくなくなる。

<蜂ばあちゃんと餅ばあちゃん>
「ハニーランド」に話を戻そう。僕は映画をみながら、内容どころではなくなってきた。「蜂ばあちゃん」と、「餅ばあちゃん」。もうこれは、マケドニアの27歳、タマラ・コテフスカ監督と、日本の27歳、伊藤麻衣監督との一騎打ちなのである!
マケドニア代表 対 日本代表。ブブゼラの音すら聞こえてきた。
<マケドニア 蜂ばあちゃん byタマラ監督>
北マケドニアで養蜂を営む「蜂ばあちゃん」の元に、ある日突然招かれざる客がやってくる。トルコ系の一家が移住してきて、自分たちも養蜂をやりたいという。蜂ばあちゃんは、彼らに、ある言葉を残し、養蜂を教える。「半分はわたしに、半分はあなたに」。できたハチミツを全て取らず、半分は蜂に残しなさいという、蜂ばあちゃんが自然界と交わした約束だ。だが、移住者はそれを破ってしまう。
カメラは移住者にも向けられ、崩壊していく生態系が映し出されていく。自然との調和、共生。もしかしたら、ヨーロッパが抱える「移民」というメタファーさえ入れ込んできた。3年間、400時間、谷にテントを張りながら撮影を続けてきたマケドニアの27歳、タマラ監督。伊達じゃない。
<日本 餅ばあちゃん by伊藤監督>
一方、青森は五所川原の「餅ばあちゃん」。100グラムのお餅は量りを使わずとも、体が覚えている。蒸した餅は、素手で触る。熱さで手は真っ赤だ。なぜ手袋を使わないのかと聞くと、粉の微妙な変化に気づくためだという。
「十本の指は黄金の山」と、餅ばあちゃんは愛おしそうに何度も言う。母が残したこの言葉が、餅ばあちゃんの原動力になっている。
貧しい中、4人の子どもを、女手一つで育ててくれた母。何もなくても、十本の指さえ動かしていれば、生きていけると、強く生きるための言葉と、動く手を残してくれた。
辛いときも、苦しいときも、助けてくれたのは十本の指。そして誰かを喜ばせることもできるのが、十本の指だった。
映画を観ながら、心の中で叫んでいた。
「伊藤麻衣いけ!頑張れ!」
「負けるな、ニッポン!」

<NHK3年目が令和の怪物に化けるまで>
この「餅ばあちゃん」、つい先日発表された「ギャラクシー賞」でテレビ部門賞を受賞。(2021年4月30日)
ギャラクシー賞は、1963年に創設され、数々の優秀な番組をたたえてきた。テレビ局に勤める人間なら誰もが知っている賞で、正直言って羨ましい。あぁ、羨ましい。
愛媛で育ち、大阪の大学院で生命科学を研究し、NHKにやってきた伊藤D。一体どうやって、3年目にして、この力を身につけたのか。
通常NHKのディレクターは、入社してすぐ地方局に配属される。そこで、様々な仕事を行う。
僕は最初、福岡放送局に配属され、漁や祭りの中継、スタジオを使った情報バラエティー番組、朝のニュースの5分企画、10分の紀行番組などを制作した。ドラマのサブのサブの助監督としてエキストラの方に芝居をつけたり、音楽番組で、ステージ周りをせっせと動きまわったこともある。
出演者の立ち位置の目印をつける「バミる」という行為も、地方局で初めてやった。
ビニールテープをスタジオの床に貼った瞬間、「あ、俺、今、バミった・・・。」と感動を覚えた。
東京に来てプロフェッショナルの担当になり、すっかりバミることもなくなってしまった。(バミってたら問題ですね・・・)
新人は基本的に地方局配属という方針なのだが、数名、東京配属になることがある。
それでも、いきなり1時間のドキュメンタリーを制作する班に新人が配属されることはない。
伊藤Dは、ある意味アクシデント的な形でプロフェッショナル班にやってきた。
伊藤Dを受け入れた、荒川プロデューサーと末次プロデューサーのダブルPは、こうつぶやいた。
「3年、いや2年で、一人前にする。」
瞳の奥は鋭く光っていた。
プロデューサーたちの命を受け、横山デスクが付きっきりの指導を始めた。横山デスクはディレクター時代にいくつも世界的な賞をとっている凄腕だ。横山デスクが本気を出し、前代未聞、新人にプロフェッショナルを作らせる大作戦が始まった。
ただ伊藤D、一筋縄ではいかないのである。

一度、伊藤Dの取材現場に横山デスクと僕でついていったことがある。
教育界で有名な数学の先生の取材だった。
このときは初対面で、撮影の前段階の挨拶を兼ねて話を聞いた。
教育の道に進んだきっかけ、仕事のおいて大切にしていることなどを聞いていく。
ずっと隣で黙って聞いていた伊藤Dだったが、先生からあるエピソードが出た瞬間、声を発した。
「先生それ、今日いちイイっすね!」
!
!!
!!!
初対面の取材相手に、「きょ、きょ、きょういち・・・。今日いちイイだと・・・。」
漫画やドラマであれば、テーブルの下で、見えないようにチョップが出るところだ。だが時は令和の現実。
「落ち着け、落ち着け、落ち着け自分。」
もしかしたら、「今日いちイイ」は、謙譲語の意味合いに変わっているかもしれない。まずは広辞苑だ。いやいや、僕が若者についていけないだけだ。TikTok界隈では、感謝と敬意を示す言葉で使われているのかもしれない。
いや、違う。たぶん、違う。
「キョウイチ」は、使っちゃダメなやつのはずだ。
どうすればいいんだ、令和。
正しく、正しく言い換えて、伝えるしかない。
「先生、今日いちイイっすね!」=「先生、本日、一番印象的なお言葉でした。」
で、どうだろうか・・・。
浮き彫りになったジェネレーションギャップという大きな課題。
そうだ、コミュニケーションだ、コミュニケーションが圧倒的に足りないのだ。
とある日、僕は、一緒に番組を見ながら構成の勉強をしようと、伊藤Dを誘った。
大切なのは、コミュニケーション。指導っぽくなるのもいやなので、楽しくしようと寿司の出前をとった。
ここは先輩の威厳。奮発して「上」を頼んだ。
打ち合わせ室にやってきた伊藤Dに「寿司でも食べながらやろうぜ!」というと、
伊藤D「あたし、寿司きらいっす!」
!
!!
!!!
もうダメだ。。。
立ち上がれない。。。
反省します。確認不足でした。いやいや、そもそも新人に媚びた僕が悪かった。
一人で食べる二人前の上寿司は、思いのほかヘビーだった。
その後、伊藤Dは「今日いちイイっすね!」をぶちかましてしまった数学教師と、とても良い関係を築き、先輩たちがみんな驚く見事なプロフェッショナルを放送した。
恐るべきスピードで、先輩達をごぼう抜きにしていったのだ。
スラムダンクで言えば、沢北栄治。山王工業に入る前の中学時代の沢北だ。「てんでつまんねぇ」って言われてたのかなぁ。
伊藤麻衣ディレクター、通称「タマちゃん」。真っさらな新人として僕たちの前に現れた伊藤Dは、サザエさんの磯野家の愛猫「タマ」のように、かわいがられた。わずか2年とそこらで、猛虎に化けるとも知らずに。

<驚異の新人に教わったドキュメンタリーの哲学>
餅ばあちゃんこと桑田さんと伊藤Dが出会ったのは、2019年夏。
初めて会ったとき、全く緊張しなかったという。おばあちゃんの家にいる感覚だったそうだ。
一体どうやって、あの自然な表情と言葉を引き出したのか。
先輩が後輩に極意を聞いたっていいじゃないか、恥を忍んで、聞いた。
僕「現場では、どういう感じで撮影してたのー?」
伊藤D「ただ、いただけなんです。」
えっ・・・ドント シンク、ジャスト フィールですか・・・。
NHKきってのドキュメンタリーの大巨匠がドキュメンタリー勉強会で言っていた「番組は、作っちゃだめなんです。」とほぼ同じことを言っている・・・。
むしろそのときは、コギト・エルゴ・スムぐらいわっかんないなぁと思いながらメモをとっていたが、伊藤Dの言葉と巨匠の言葉が重なり、0.0001%くらい分かってきた気がする。
「作為」が番組をダメにする。でも、番組を作るねらい=「作為」を持つことこそがディレクターの仕事。そのジレンマと闘いながら、結局最後は作為を捨てるということか。
撮影が進むにつれ、ああ、こんなインタビューが必要だ、こんなシーンが撮れてたらよかった、今からどうしようか、今日はどうしようかで頭がいっぱいになる。スケジュールが日に日になくなっていく中で、焦りと後悔、「作為」に支配される。
「ただ、いる」こと。「ただ、いる」を貫くこと。当たり前のようで、これができない。
うまくやりたい、良くしたい、あたりまえにある「作為」から解き放たれた瞬間に真実が見える、のか・・・?
恐ろしい・・・。入社3年目にして巨匠の世界観・・・。
バガボンドでいうならば、刀を置いてクワを持ち畑を耕しはじめた宮本武蔵の領域。武蔵第4形態。
「こんな番組にしよう」、「こんな狙いでいこう」、そんな作為を捨て、ときに笹餅作りを教えてもらいながら、ただただ、そばにいたという伊藤D。
そして、この言葉を引き出した。
「仕事、仕事さ教えてくれる。」
仕事の中に、仕事の答えがある。一生懸命やっていれば、いつか分かるときがくる。
この言葉が、沁みる。
僕も、仕事に悩むときは、餅ばあちゃんの言葉を思い出し、仕事に聞いてみようと思った。

一度だけ、伊藤Dが撮影をやめようと思ったことがあったそうだ。
餅ばあちゃんの家族に、病が見つかる。
家族の一大事に、これ以上の撮影は負担になる。もう、中断したほうがいいんじゃないか・・・。
だが、その後、伊藤Dは考え直す。
「今、自分が去ってしまえば、餅ばあちゃんは一人になってしまう。大変なときだからこそ、そばにいたい。」
再び青森に向かう。
人に向き合うピュアな姿勢が、澄み切ったドキュメンタリーを生み出した。
<憧れのカメラで撮る、美しいニッポンの風景>
映像美も素晴らしかった。カメラは、「AMIRA(アミーラ)」というめちゃくちゃ綺麗に撮れる機材を使い、4K撮影。僕も一度使ってみたい憧れの一品だが、テーマが合わなければそう簡単には使わせてもらえず、いまだ触れたことがない。
この「AMIRA」を操ったのは、阿部崇人カメラマンと、百崎満晴カメラマン。キラキラとしていて、温かくて、稲穂の間を走る一本の電車のワンカットだけで、心が洗われる。「ああ、日本人でよかった」と思う。

百崎さんは、NHKを代表する名カメラマン。18年間、秩父の山奥に暮らす女性に密着し続け、名作ドキュメンタリーを何本も世に出してきた。そして去年、映画化までもされた。その主人公は、「ムツばあさん」。
ん?「蜂ばあちゃん」、「餅ばあちゃん」、「ムツばあさん」。佐賀には、「がばいばあちゃん」もいる。一体世界にはどれだけの「スゴばあちゃん」がいるのだろうか・・・。

「餅ばあちゃん」をみごとに描ききった、伊藤麻衣ディレクターは、去年10月に東京を去り、熊本放送局へ異動した。転勤制度というやつだ。
拝啓
伊藤さん、元気にしてますか?
熊本はどうですか。同僚や街の人と仲良くなれましたか。
こちらは、ちょっとお騒がせだけど、楽しくて優秀な後輩がチームを離れ、寂しいです。
少しほっとしている先輩も、チラホラいそうです。
うそです。
ちょっとほんとです。
あまり無理せず、体に気をつけて元気に頑張って下さいね。
熊本で番組ができたら、教えて下さい。
「デコポンばあちゃん」、楽しみにしてます。

制作者:伊藤麻衣ディレクター
2018年入局。プロフェッショナル班には通常、地方局で4〜5年経験を積んだディレクターが「新人」として加入するが、彼女は新人研修後に直通でプロフェ班に加入。班史上初のスタイルでの「新人」となった。持ち前の明るさで先輩から貪欲に吸収し、1年目の終わりから1年半で「電器店主」「数学教師」「餅ばあちゃん」「魚仲買人」の4本を制作。「餅ばあちゃん」はギャラクシー賞テレビ部門賞(2020年度)を受賞。愛称、タマちゃん。プロフェッショナル班でこれほど可愛がられたディレクターはいない。

執筆者:奥翔太郎ディレクター
2010年入局。初任地は福岡。「生花店主・東信」「歌舞伎俳優・市川海老蔵」「納棺師・木村光希」、「プロのおうちごはん」などを制作。2020年8月に「石川佳純スペシャル」、2021年3月に「サンドウィッチマン スペシャル」を放送。後輩に対するジェラシーなnote記事を書きすぎて「ジェラ男」と呼ばれることも。