#3作家の時間を取り入れる
新評論から出ている「作家の時間」を読んでいる。海外での実践「ライティング・ワークショップ」をもとに、日本の先生たちが実践を重ね、本にまとめたもので、とても価値があると思っている。
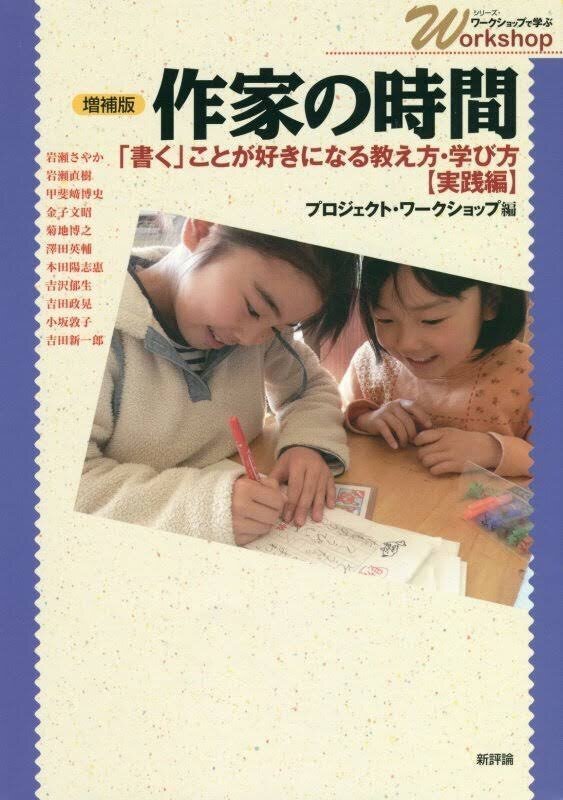
「作家の時間」が書くことを好きにする
作家の時間は、簡単に言うと、「子どもたちが書きたいことを、書きたいように書く」時間である。書かされる作文とは大きく違い、子どもたちは書くことが好きになっていく。本来「書く」ことは苦行ではないのだろう。学校の中で「書かされる」という経験を何度もすることで、書くことが「苦行」になってしまっているのかもしれない。何かを強制させられることは、それ自体が本来の能力を奪っていく。
私も「書く」ことは苦手だった。いや、いまも苦手かもしれない。それでもこうやって”誰かにやれと言われたわけではない”のに、noteに綴っているのは、”誰かにやれと言われたわけではない”からなのだろう。(それから、一方的に上から「良い」とか「悪い」とか○か×の評価を下される心配がないことも挙げられるかもしれない。)
作家の時間をどのように取り入れるか
正直、本書を読むまでは、作家の時間を取り入れることに対して「難しそう」と思っていた。しかし、第1章を読んだ段階でそれはかなり薄れた。実践の記録が具体的で、わかりやすいからだろう。
作家の時間を授業で取り入れるにあたって、その時間をどのように確保するかと言う問題がある。本書で紹介されているように週に1回行うと、年間35回時間を消費することになる。この確保が一番課題だろう。「教科書」がある学校では、これがネックになって、良い教育活動も広まらない現状がある。
しかし、作家の時間の「ミニレッスン」の時間のなかに、教科書に書かれている内容は自然と盛り込まれてくる。もちろん、学習指導要領に則った形で授業ができるのだ。「書く」単元での指導事項を「ミニレッスン」で取り入れていけば良い。(ただし、ミニレッスンは子どもたちの実態から内容を決めていく。事前にかっちり決めすぎていると、趣旨とずれてしまう。)また、「読む」領域の内容も入れることができそうだ。比喩表現や書き出し、副詞の使い方、段落…など、本物の「作家」から学ぶときにも使えるだろう。
来年度は「作家の時間」を取り入れたい。本書を読み進め、実践に繋げようと思う。もちろん、学年にも提案できる形で。子どもたちは本来「書くこと」が好きなのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
